- ニュース
- 「比較文学―文学的創造のプロセスを追究する」文化構想学部 菊池有希教授(新任教員紹介)
「比較文学―文学的創造のプロセスを追究する」文化構想学部 菊池有希教授(新任教員紹介)

- Posted
- Wed, 05 Jul 2023
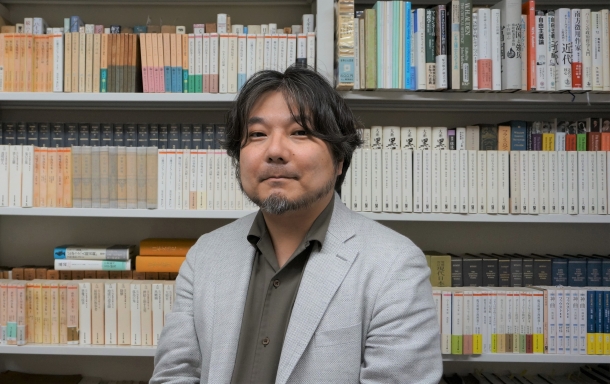
自己紹介
高校生の時に地下鉄サリン事件という社会を大きく揺るがす事件が起き、そこから社会評論や論壇誌などを背伸びして読むようになり、大学では社会学を専攻しようと考えていました。ですが、大学入学早々、生協の書籍部で手にしたドストエフスキーの『地下室の手記』という作品に衝撃を受けて以降、すっかり文学中心の読書生活となり、文学を専攻するのもいいかもしれないと考えるようになりました。学部後期課程の進学先を決める段では、当時愛読していた、ドストエフスキー論も書いている社会学者の作田啓一がフランス文学・思想に造詣が深い人だったこともあり、もともと志望していた社会学と文学とのあいだで随分迷いました。結局、文学熱に押し切られるかたちで仏文科を選びました。
詩というジャンル、特に日本の近現代詩に親しみ始めたのもこの頃です。仏文科でフランス文学を学ぶ傍ら、フランス象徴詩の影響を受けた蒲原有明や三木露風などの明治期・大正期の日本の象徴詩を読み、文語で書かれたその陰々とした詩風に魅了されました。そして、日本の近代詩を西洋の詩との比較の視点から研究したいと思うようになり、比較文学の大学院に進学しました。

福井県・三国にある三好達治の詩碑(於三好楼(三好達治仮寓跡))。「わが庭の秋のあはれはふと在りて 風に流るるくれなゐの花をとらへしあきつかな」
大学院では、北村透谷や島崎藤村などの近代日本の詩人・小説家が、19世紀前半のヨーロッパ・ロシアの文学・文化に大きな影響を与えたイギリス・ロマン派の詩人バイロンをどのように読み、自身の作品世界の中に消化していったのかというテーマで研究をしました。大学院を修了してからは、ヴィクトリア朝期のイギリスの文人カーライルの近代化・文明化を批判する思想が、日本の近代草創期の詩人透谷の詩作にどのような影響を与えたのかについて研究をおこなっています。カーライルが見据えていた近代化・文明化の問題点は、21世紀の現代文明の問題点にも直接通じるものがあり、カーライルに深く感化された透谷の詩と思想の意義を現代的視点から評価づけたいと考えているところです。

イギリス・ノッティンガムにあるニューステッド僧院。
歴代のバイロン家の住まいで、中世のゴシック建築の醸し出す雰囲気はバイロンの詩風に通じるものがあります。
私の専門分野、ここが面白い!
さまざまな紆余曲折の果てに私がようやく辿り着いた専門、それが比較文学という学問です。比較文学は非常に裾野が広い学問ですが、もともとはフランスにおいて、自国文学と外国文学のあいだの影響・受容関係を実証する学問として始められました。私自身も日本の近代詩を中心に扱いながら、オーソドックスな比較文学研究の方法としてある影響・受容研究を専らとしています。
影響・受容研究の面白いところは、文学的創造の現場に立ち会えるところです。ある作家が異国・異言語・異文化圏の作家・作品から影響を受ける。一見するとそれは受け身の営みのように思われますが、影響という現象が成立するためには、影響を受ける側の方にも、その異国・異言語・異文化圏の作家・作品に価値や意味を見出す積極性・内的必然性がなくてはなりません。そして影響を受けた後、その作家は、自身の内部に点ぜられた異国・異言語・異文化圏の作家・作品の〈影〉が奏でる〈響〉に耳を傾けながら、そこから得られた感動(反発の場合もあるでしょう)を自身の創作の中に主体的に落とし込んでゆくことになります。これが受容の営みということになるわけですが、その創作の原動力ともなる感動(反発)には、その作家の個人的な内的・外的事情だけではなく、当時の時代状況や文化的な背景といった歴史的な条件が大きく関係している場合があります。
こうしたことを包括的に踏まえながら、影響という現象を〈点〉ではなく、一定の時間をかけてなされる受容の営みという〈線〉として捉え、さらにその〈線〉を様々な歴史的条件との関わりという〈面〉において描き出す。すると、影響・受容の成果として作家が新たに生み出した作品が、立体感を伴った興味深い〈図柄〉として私たちの前に生き生きと立ち上がってくるということがしばしばあるのです。国・言語・文化圏を異にする複数のテクストが関連づけられる文脈を精査した上で、文学的創造の現場に立ち会い、創造のプロセスを追究しながら、そこに籠められた企みや秘められた謎を解明してゆく影響・受容の比較文学研究には、探偵が行う推理にも似た愉しみがあります。

ロンドンのチェルシーにあるカーライル博物館。
夏目漱石の「カーライル博物館」でもお馴染みです。奥のカーライルの胸像は21世紀をどう見ているでしょうか。
プロフィール
きくち ゆうき。1978年宇都宮生まれ。東京大学仏文科卒業。同大学大学院比較文学比較文化博士課程修了。博士(学術)。日本学術振興会特別研究員PD、聖学院大学助教、都留文科大学専任講師、同准教授、同教授を経て、2023年4月より現職。『近代日本におけるバイロン熱』(勉誠出版、2015年)により第21回日本比較文学会賞受賞。
- 新任教員紹介は、研究紹介・アウトリーチからご覧いただけます。


