- 受験生の方へ
- よくある質問
FAQ
よくある質問
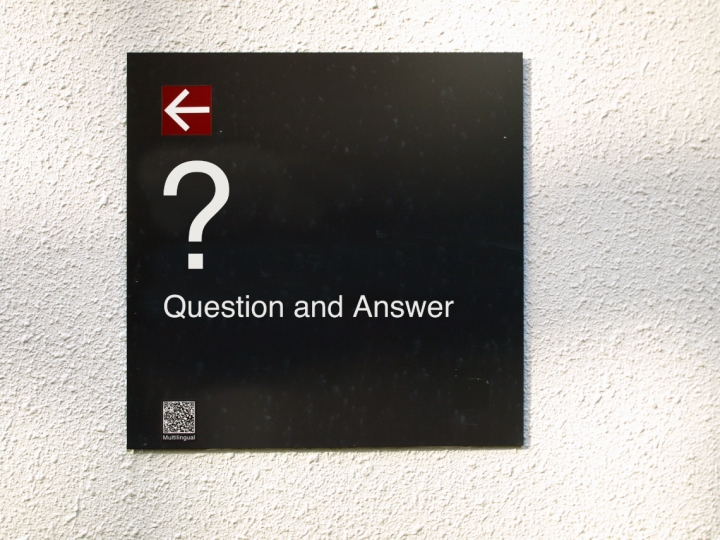
教育学研究科について、みなさまからよくご質問いただく項目を以下にまとめました。なお、入試に関する情報は、必ず「入試要項」にてご確認ください。
共通【①出願まで】
Q.入試要項はいつごろ、どこで入手できますか?
A.修士課程入試、博士後期課程入試、科目等履修生入試、修士課程推薦入試いずれの入試制度についても、ご自身で受験生の方へ > 入学試験情報より、入試要項をダウンロードしてください。事務所窓口での配布、販売等は一切行っておりません。また、入試要項公開の時期は、以下を予定していますが、前後する場合がございます。
| 修士課程推薦入試(学内) | 3月中旬 |
|---|---|
| 修士課程入試 | 5~6月 |
| 博士後期課程入試 | 6~7月 |
| 科目等履修生入試 | 10~11月 ただし時間割については、1月頃掲載予定 |
Q.入試要項は教育学研究科事務所で配布していますか?
A.事務所窓口での配付、販売等は一切行っておりません。
Q.自分の研究分野と合う先生を探したいのですがどうすればよいですか?
A.入試要項で、「研究指導の内容」を掲載していますのでご確認ください。また、教育学研究科教員紹介ページにアクセスしていただき、教員情報を検索することも可能です。授業内容の確認は、シラバス検索からでも可能です。
Q.入学前に、指導教員を決めておく必要がありますか?
A.はい。入学前に指導教員を決めていただく必要があります。ただし、科目等履修生は研究指導・演習を履修できませんので、指導教員を決める必要もありません。
Q.指導を希望する先生と事前に相談をする必要があるでしょうか?
A.指導教員との事前相談は必須条件ではありません。ただし、入学後に研究指導を開始してからご自身の研究分野とのミスマッチが発覚するという事態を避けるためにも、事前に相談されることをおすすめします。
Q.教員と事前にコンタクトをとりたい場合、どのようにすればよいですか?
A.入試係([email protected]) のメールアドレスに、コンタクトを希望する教員に宛てたメールをお送りください。事務所からメールを教員宛に転送いたしますので、その後は、教員から直接のお返事をお待ちください。なお、事務所を通じてのお返事となる場合もあります。
事務所までメールをお送りいただく際は、以下のページを必ずご確認ください。
Q.修士の学位を持っていないのですが、博士後期課程に出願できますか?
A.修士の学位を得た者、または取得見込みの者でなければ出願資格はありません。ただし、文部科学大臣の指定した者、修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認めた者等、入試要項に記載されている出願資格を満たしていれば出願可能です。詳細については受験生の方へ > 入学試験情報より入試要項をご確認ください。
Q.入試説明会はありますか?
A.早稲田大学入学センター主催の大学院合同説明会と、教育学研究科主催の教育学研究科入試説明会があります。各説明会の詳細は 受験生の方へ > 入試説明会よりご確認ください。
Q.英語能力証明書・スコアカードが出願締切日に間に合いません。どうすればよいですか?
A.英語能力試験の証明書・スコアカードが試験実施団体から出願締切日までに必ず大学へ直接送付されるように、志願者が早めに依頼してください。また、暫定的なス コア証明として、手許にあるスコア報告のコピー、またはネット上のスコア確認画面を印字したものの提出も必須です。ご不明な点がある場合は、入試係([email protected])までお問い合わせください。
Q.日本語能力証明書・スコアカードが出願締切日に間に合いません。どうすればよいですか?
A.日本語能力証明書・スコアカードは出願締切日までに必ず提出してください。
また、日本語能力試験・日本留学試験のスコアについてご不明な点がある場合は、入試要項を確認の上、入試係([email protected])までお問い合わせください。
Q.IELTS AcademicのスコアとはIELTS for UKVI Academicも含まれますか?
A.はい。IELTS for UKVI Academicのスコアも、IELTS Academicと同等のスコアとして利用することができます。
Q.過去の修士論文の閲覧は可能ですか?
A.修士論文の閲覧は、当研究科在学生が対象となります。当研究科の受験を希望する方で、修士論文の閲覧を強く希望される場合は、入試係([email protected])までお問合せください。
Q.編入学をしているものですが、編入前の学部の成績証明書は必要ですか?
A.必要です。必ず証明書の原本を提出してください。
Q.2つの大学を卒業しているものですが、入学前の学部の成績証明書はどちらの大学のものを提出すればよいですか?
A.最終学歴となる大学の成績証明書の原本を提出してください。
Q.出願書類が届いたら連絡をもらえますか?
A.当研究科から個別の連絡を行っておりません。簡易書留等の追跡ができる形でお送りください。
共通【②入試】
Q.筆記試験ではどのような対策をすればよいですか?
A.試験対策について具体的なアドバイスは行っておりません。過去問題を公開しておりますので参考にしてください。
Q.過去問題はどこで見られますか?
A.早稲田大学入学センターのホームページで、過去3年間にわたり、入試種類別に問題を掲載しています(教育学研究科入学試験情報からもアクセス可)。ただし、設問によっては著作権の利用許諾が得られないため、公開しているPDFファイルにマスクがかかっているものがございますのでご了承ください。教育学研究科事務所では、過去3年分の入試問題を公開しております。閲覧を希望される場合は、早稲田キャンパス16号館2階教育・総合科学学術院事務所までお越しください。(入試問題の持ち出し、コピー、写真撮影は厳禁です。)また、教育学研究科入試説明会でも、入試問題の閲覧が可能です。
Q.入学試験の倍率はどのくらいですか?
A.受験生の方へ > 入学試験情報に入試結果を公開していますので、ご確認ください。
Q.入学試験での辞書の利用は可能ですか?
A.修士課程入試では、辞書の利用を一切認めていません。博士後期課程入試では、一般入試・外国学生入試の筆記試験において、一部辞書の利用を認めています。詳細については必ず受験生の方へ > 入学試験情報より、入試要項をご確認ください。
Q.スマートウォッチを腕時計として使用することはできますか?
A.腕時計端末等の通信機能のある機器の使用は一切認めていません。試験時間中に使用を認めない物品については、入試要項で必ずご確認ください。
共通【③入学後】
Q.教職大学院(高度教職実践専攻)の科目は履修できますか?
A.教職大学院の「基本科目」「分野別選択科目」「学校臨床実習」を修士課程の学生が履修することはできませんが、修士課程の「共通選択科目」には高度教職実践専攻設置により加わった科目が含まれています。
Q.先取り履修制度で履修した科目や科目等履修生で履修した科目を、正規生として入学後に単位認定することはできますか?
A.先取り履修制度で履修した科目については、当研究科運営委員会が認めた場合に限り、16単位を限度として、該当する科目の科目区分に修了に必要な単位として充当することができます。詳しくは、早稲田キャンパス16号館2階教育学研究科事務所までお越しいただくか、入試係([email protected])までお問い合わせください。
また、科目等履修生で履修した科目については、当研究科運営委員会が認めた場合に限り、8単位を限度として該当する科目の科目区分に修了に必要な単位として充当することができます。詳しくは、合格者に配布する「教育学研究科要項」をご確認ください。
Q.一般教育訓練給付金の対象の講座はありますか?
A.教育学研究科修士課程「学校教育専攻」に所属の方が対象となります。受給資格や手続き等の詳細は、各ハローワークにお問い合わせください。「教育訓練給付金」の概要、申請資格、申請手続きなどの詳細は、厚生労働省のサイトでもご確認いただけます。
【教育訓練講座検索システム:早稲田大学大学院教育学研究科学校教育専攻】
https://www.kyufu.mhlw.go.jp/kensaku/SSR103Scr02M
Q.在学中に留学をされる方は例年どのくらいいますか?また、その場合の単位取得について教えてください。
A.例年、修士課程の学生が数名程度留学をしています。留学先等で修得した単位については、当研究科運営委員会が認めた場合に限り、10単位を限度として該当する科目の科目区分に修了に必要な単位として充当することができます。
Q.奨学金はどのようなものが用意されていますか?また、奨学金申請はどのように行うのでしょうか?
A.本大学独自の学内奨学金をはじめ、民間・地方公共団体奨学金や日本学生支援機構等の学外奨学金制度があり、多くの院生がこれらの奨学金を受けています。奨学金の申請は、入学手続時(在学生は成績発表時)に配布される「奨学金情報 Challenge」という冊子の要項に則して行われます。まずは3月上旬から3月下旬(在学生は2月上旬から3月中旬)の奨学金事前登録期間に、必要書類を完備し申し込みをすることが必要です。奨学金は選考がありますので、必ずしも希望の奨学金に採用されるとは限りません。その点ご留意頂き、奮ってご応募ください。詳細については学費・奨学金ページからも確認いただけます。
Q.学生寮はありますか?
A.早稲田大学の学生を対象とした学生寮があります。詳細は、早稲田大学学生生活課学生寮デスクにお問い合わせください。
Q.修士課程在学中に学校(小中高)の非常勤講師として働くことは可能ですか?
A.可能です。ただし、カリキュラムの関係上、第一年次は学業に専念することを強くお勧めします。
推薦入試
Q.出願資格のGPAの基準に少しだけ足りない場合、受験できませんか?
A.教育学研究科では推薦入試の出願資格として、GPAが2.5以上ない場合は、前年度終了時の専門科目(必修・選択)・外国語科目の平均値が基準を満たしていれば受験できます。これらの基準を満たしていない場合、出願資格はありません。なお、推薦入試の出願資格については専攻ごとに異なりますので、 必ず、受験生の方へ > 入学試験情報より入試要項をご確認ください。
Q.推薦入試ではどのような試験が行われますか?
A.指定の日時・場所で口述試験が行われます。英語英文学科については、状況により英語での口述試験が行われる場合もあります。
社会人入試
Q.社会人のための入試制度はありますか?
A.修士課程入試では、「特別選考制度入試」、博士後期課程入試では「専門職業人入試」の制度があります。出願資格等については、受験生の方へ > 入学試験情報より、入試要項をご確認ください。
Q.出願時は現職ですが、3月で退職し、4月から入学する予定です。この場合社会人入試の出願資格はありますか?
A.入学時に現職にあるかどうかは、出願資格とは関係ありません。特別選考制度入試は、修士課程入学までに、学校の専任教員、または社会教育機関・教育行政機関の専任の職(専任に準ずる職を含む)において継続して3年以上の職務経験を有する方が対象です。また、専門職業人入試は、博士後期課程入学までに、学校・官公庁・企業等の専任の職(専任に準ずる職)において継続して3年以上の職務経験を有する方が対象です。ご自身が出願資格を満たしているかどうかは、事前に確認されることをお勧めします。
Q.出願資格を満たしているかどうか確認できますか?
A.出願資格を満たしているかどうかを確認したい場合は、メールに「職歴(在職期間・勤務先名称)」や「職務内容」について詳細に記載し、入試係宛([email protected])までお送りください。メール内容を確認し、入試係より返信いたします。
Q.修士課程への入学を検討しているのですが、現職を続けながら在学することは可能ですか?
A.初年度は在職校等の勤務を離れて就学に専念していただきます。ただし、特例の適用を受けた学生の場合、第2年次は現職に復帰し、勤務しながら定期的に研究指導を受けることが可能です。
教育上特別に必要があると認められる場合には、特定の時間または時期において適当な方法により授業または研究指導を行っていますが、受講可能な期間・時間帯にご対応が可能かについては、教員により事情が異なります。研究指導を希望する教員と、事前にコンタクトをとり、ご相談ください。
また、この方法による履修を希望する場合、志願時にお申し出をいただくことになっておりますのでご留意ください。
Q.博士後期課程への入学を検討しているのですが、現職を続けながら在学することは可能ですか?
A.特例の適用を受けた学生は、指導教員の指示に従い、定期的に研究指導を受けることが可能です。
博士後期課程の修了要件に含まれる「指導教員の担当する演習科目4単位」は、なるべく第1年度に履修することになっています。
教育上特別に必要があると認められる場合には、特定の時間または時期において適当な方法により授業または研究指導を行っていますが、受講可能な期間・時間帯にご対応が可能かについては、教員により事情が異なります。研究指導を希望する教員と、事前にコンタクトをとり、ご相談ください。
また、この方法による履修を希望する場合、入学志願時にお申し出をいただくことになっておりますのでご留意ください。
Q.修士課程在学中に非常勤講師として働くことは可能ですか?
A.可能です。ただし、研究指導の関係上、第一年次は学業に専念することをお勧めします。
外国学生入試
Q.9月入学はありますか?
A.当研究科では、修士課程、博士後期課程ともに9月入学はありません。
Q.外国学生入試の対象となるのはどのような人ですか?
A.修士課程の場合、外国において正規の学校教育における16年目の課程を修了した方(見込み含む)は、外国学生入試で出願してください。外国籍の方でも、日本の大学を卒業した方は、修士一般入試への出願になります。(日本の大学と外国の大学両方を卒業された方も一般入試への出願となります。)
博士後期課程の場合、外国において修士もしくは修士(専門職)の学位またはこれに相当する学位を得た(見込み含む)方は、外国学生入試で出願してください。
Q.Online Verification Report of Higher Education Qualification Certificateはいつから送付依頼できますか?
A.該当年度の各入試要項公開後から手続可能です。
Q.中国で15年、教育を受けてきた場合、外国学生入試の出願資格はありますか?
A.
中国で15年の教育を受けてきた場合、その内訳により出願資格の有無が異なります。
・中国の3年制大学である「専科」を卒業した場合、出願資格はありません。
・4年制大学である「本科」を卒業した場合、本学で事前に学歴審査を行います。詳細は以下の入学センターHPをご確認ください。
・早稲田大学入学センター > 大学院入試情報 > FAQ
https://www.waseda.jp/inst/admission/graduate/faq/
Q.出願資格の日本留学試験「日本語」260点以上の中に、記述問題の点は含まれますか?
A.日本留学試験「日本語」は、聴解・聴読解(200点)、読解(200点)の計400点のうち、260点以上となります。記述問題はは含まれません。
Q.外国学生入試での出願を考えています。国外出願と国内出願はどのように違うのですか?
A.外国学生入試において、出願時の住所が国内にある方は国内出願、外国に居住している場合は、国外出願となります。国外出願の場合は出願期間も異なりますのでご注意ください。
詳細については、入学試験要項をご確認ください。
・教育学研究科入試要項掲載ページ
https://www.waseda.jp/fedu/gedu/applicants/admission/
Q.国外からの出願者です。入学検定料は日本国内の知人が納入してもいいですか?
A.日本国内の代理の方が納入することも可能です。その際は、必ず「志願者ご本人の情報を入力する」ようにしてください。
Q.短期間滞在証(ビザ)取得手続きの際に招へい人・身元引受人になってもらえますか?
A.早稲田大学が引受人になることはできません。ご自身でご手配いただくようお願いいたします。
Q.外国籍ですが、在留資格「留学」を取得するにはどうすればよいですか?
A.国外出願の場合、入学手続を完了した学生には、大学で「在留資格認定証明書」の代理申請を行います。国内出願の場合は、ご自身で手続きを行っていただくことになります。詳細は入試要項をご確認ください。また、在留資格申請についての詳細は、早稲田大学留学センターにお問い合わせください。
Q.研究生制度はありますか?
A.当研究科では、外部の方に公開している研究生制度はありません。代わりに、非正規生として当研究科の科目を履修できる「科目等履修生」の制度があります。
なお、科目等履修生では研究指導・演習科目を受講することはできません。
科目等履修生入試についての詳細は、受験生の方へ>入学試験情報より、入試要項をご確認ください。
科目等履修生
Q.9月入学はありますか?
A.当研究科では、科目等履修生の9月入学はありません。
Q.科目等履修生として履修できる科目の上限はありますか?
A.科目等履修生として、教育学研究科で履修できる単位上限は春学期6単位・秋学期6単位の年間計12単位となります。
Q.外国籍ですが、在留資格「留学」を取得するにはどうすればよいですか?
A.在留資格の有無により手続きが異なります。詳細は入試要項をご確認ください。また、在留資格申請についての詳細は、早稲田大学留学センターにお問い合わせください。
Q.在留資格「留学」を取得の要件は何ですか?
A.春学期6科目、秋学期6科目、年間12科目の履修が必要です。
※必要な履修授業時間10時間以上とは、本学の科目数に換算すると、6科目以上ということになります。
Q.外国人留学生の科目等履修生ですが、日本語科目を登録したい場合、どのように申請すればいいですか?
A.日本語教育研究センターでの日本語科目の登録および日本語科目聴講料の支払いが必要となります。詳細については日本語教育研究センターホームページをご確認ください(ページ下部 「各学部・大学院科目等履修生の日本語科目履修」の部分)。
Q.4月から科目等履修生になる場合、春学期に開講される科目だけを選択していても9月以降引き続き在籍することは可能ですか?
A.秋学期に当研究科科目を履修しない場合、9月15日をもって当研究科の在籍がなくなります。日本語教育研究センターの語学科目を履修することを考えていても、当研究科の科目を履修する予定がない場合、学籍を失いますので語学科目の履修も認められません。
Q.科目等履修生として履修したら、後ほど正規生になることはできますか?
A.科目等履修生として履修していても、正規生として入学し、学位取得を目指す場合は所定の入学試験に合格する必要があります。
Q.科目等履修生でも図書館などの施設は利用できますか?
A.図書館、コンピュータールームなどの学内施設は正規生と同様に利用可能です。
Q.科目等履修生になれば通学定期および学割はもらえますか?
A.通学定期および学割の利用はできません。
資格取得・就職
Q.どのような専修免許状が取得できますか?
A.教育学研究科で取得できる免許状の種類及び教科一覧は以下の通りです。
| 専攻名 | 免許状の種類 | 免許状の教科 |
|---|---|---|
| 学校教育専攻 | 小学校教諭専修免許状 | |
| 中学校教諭専修免許状 | 国語 社会 数学 理科 英語 ドイツ語 フランス語 中国語 スペイン語 | |
| 高等学校教諭専修免許状 | 国語 地理歴史 公民 数学 理科 書道 英語 ドイツ語 フランス語 中国語 スペイン語 情報 | |
| 国語教育専攻 | 中学校教諭専修免許状 | 国語 |
| 高等学校教諭専修免許状 | 国語 書道 | |
| 英語教育専攻 | 中学校教諭専修免許状 | 英語 |
| 高等学校教諭専修免許状 | 英語 | |
| 社会科教育専攻 | 中学校教諭専修免許状 | 社会 |
| 高等学校教諭専修免許状 | 地理歴史 公民 | |
| 数学教育専攻 | 中学校教諭専修免許状 | 数学 |
| 高等学校教諭専修免許状 | 数学 情報 |
Q.修士課程修了時に専修免許状(教育職員免許状)を取得できますか?
A.入学時に一種免許状を取得している場合と取得していない場合とで異なります。
・入学時に一種免許状を取得している場合
入学後に専修免許取得に必要な24単位を取得すれば、修了時に、取得済みの一種免許状と「同一学校種・教科」の専修免許状を取得することができます。なお、専攻により、取得できる免許状および履修可能な科目は異なるのでご注意ください。
・入学時に一種免許状を取得していない場合
入学後に学部の科目等履修生になることにより、教科・教職に関する必要科目を取得すれば、修了時に専修免許状を取得することが可能な場合もあります。ただし、学部時代に教科・教職に関する単位を全く取得していない場合は、3年以上の履修が必要になる場合があります。なお、取得できる教科には一定の条件があります。詳細は教育学部ホームページより、科目等履修生入学試験要項をご確認ください。
Q.一種免許状を一つも取得していないのですが、修士課程在学中に中学校・高等学校教諭専修免許状を取得することはできますか?
A.学部の科目等履修生になることにより一種免許状の必要単位を取得し、同時に研究科で専修免許状に必要な単位を取得することができれば可能な場合もあります。詳細は、教職支援センターまでお問合せください。
Q.中学校教諭(または高等学校教諭)一種免許状を取得済みです。修士課程在学中に小学校教諭免許状を取得することはできますか?
A.入学後、学部の科目等履修生になることにより、修了時に小学校教諭一種免許状を取得することが可能です。教育学研究科(高度教職実践専攻 1 年制コースを除く)の正規学生または修了者が小学校1種免許状を取得するためには、通常、2年間で教職科目約50単位(3週間の教育実習を含む)の修得が必要になります。在籍する研究科と当学部の時間割設定によっては、2年間で取得要件を満たすことができない可能性があります。大学院の正規授業との両立には、相当の困難が予想されますので、充分ご検討の上、出願してください。
Q.他大学で取得した教職関係の単位は、早稲田大学で単位として認定されますか?
A.単位の「認定」は行っていませんが、教員免許取得のための必要科目は、複数大学で組み合わせて修得することが可能です。当該学校種・教科の「学力に関する証明書」を他大学でご発行いただき、未取得のものを本学で履修することで要件を満たせます。ただし、本学で履修できる学校種・教科には特定の条件がありますのでご注意ください。
Q.図書館司書や博物館学芸員の資格は教育学研究科に在学しながら取得できますか?
A.教育学研究科修士課程在籍(予定を含む)で、指導教員の許可を得ることができれば「博物館学芸員のみ」科目等履修生として必要科目を履修することができます。教育学部に置かれている図書館司書資格関連科目を、大学院生が履修することはできません(科目等履修生としても受け入れていません)ので、在学中に図書館司書の資格取得を希望される方は、他大学で実施している通信課程や司書講習などをご利用ください。
詳細は教育学部ホームページ入学試験情報よりご確認ください。
Q.事前に教員免許状や資格について、取得可能か相談できますか?
A.教職課程への出願にあたり、履修が必要な科目等について、ご不安のある方を対象として、科目履修に関する相談を受け付けています。また、旧々法、旧法にて既に免許をお持ちの方で新たに別教科の教員免許状取得を希望される方、他大学で習得した単位を含めて、教員免許状取得を希望される方は、必ず事前履修相談を受けてください。詳細については、教育学部ホームページ > 受験生の方へ > 入学試験情報より、科目等履修生募集要項をダウンロードし、ご確認ください。不明な点は、教職支援センターまでお問い合わせください。
Q.修了後の進路(修士課程)について教えてください。
A.教員をはじめとする教育関係の職業はもちろんのこと、多岐にわたる分野で活躍しています。また、研究を深めるため、博士後期課程へ進学する人も多くみられます。
詳細は、受験生の方へ > 修了後の進路でも紹介しています。
Q.教育学研究科の修士課程を修了後、博士後期課程への進学を希望する場合に入学試験を受験する必要はありますか?
A.当研究科の修士課程を修了した場合でも、博士後期課程への進学を希望する場合は改めて入学試験を受験する必要があります。
ただし、一部の研究指導では当研究科修士課程修了者について筆記試験が免除されます。詳細は博士後期課程の入学試験要項をご確認ください。
| ※教員免許状や資格についての詳細・問合せ先
教育学部Webサイト入学試験情報 https://www.waseda.jp/fedu/edu/applicants/admission/#anc_15 教職支援センターHP お問い合わせ |
