- その他
- 2007年博士後期課程退学■池村 恵一■会計専修
2007年博士後期課程退学
■池村 恵一
■会計専修
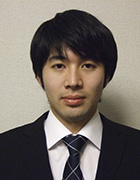
- Posted
- Fri, 06 Feb 2015
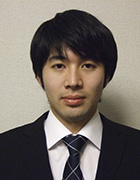 2007年3月博士後期課程退学
2007年3月博士後期課程退学
池村 恵一さん
(会計専修 財務会計研究指導/現職:広島経済大学経済学部経営学科 准教授)
博士後期課程進学の動機について、教えてください
私は、学部時代から公認会計士を目指していましたが、現役合格が叶わず、大学院の修士課程に進学してからも、資格取得のための勉強を続けていました。修士課程在籍中、私は、学部時代からの勉強スタイルを変えようと、資格試験の勉強をフォローするつもりで、専門的な学術書に触れる機会を増やしました。今思えば、このとき手にした学術書が、博士後期課程進学のきっかけだったのかもしれません。形式ばった資格試験の勉強ばかりしていたせいか、学術書を読み解く時間は、まさに至福のひとときでした。学術書は、私の学問に対する好奇心を煽りながら、私を斬新で柔軟な発想に誘ってくれました。気がつくと、一日の大部分は、資格試験の勉強というより、学術書を読み解く時間に費やしていました。私は、自分の中で感じた「学問に向かうことの喜び」を素直に受けとめ、修士課程1年目の秋に一念発起、研究者を目指すことにしました。そして、当時の指導教授から、「会計学者になるなら早稲田に挑戦してみては?」とアドバイスをうけ、早稲田(博士後期課程)への挑戦を決意しました。私は、当時他大学の修士課程に在籍していたため、外部からの受験ということで、リスクが大きいことを承知していましたが、その不安は、とにかく受験勉強に没頭することで払拭しました。
進学(入試)に向けて、どのような準備や試験対策をされましたか?
あくまで私が受験したときの対策なので、参考になるかわかりませんが、まず、過去の試験問題から出題の傾向を整理することからはじめました。つぎに、試験範囲となるいくつかの分野を絞って、その分野ごとに基本的なテキストを選びます。そのテキストの基本論点を理解できるようになるまで精読したら、今度は自分が傾注したい分野をさらに絞って、洋書の基本的なテキストを精読します。これらの作業を通じて各分野の基礎を学びます。基礎を学んだら、つぎに応用的な対策に入ります。まず、各分野の手頃な英語雑誌を見つけて、初見の英語論文を全訳することからはじめました(私が受験した当時は全訳の問題があったので)。一度全訳が終わったら倍以上の時間をかけて、その英語論文のフォローを行います。慣れてきたら、本番の試験時間と同じ時間で制限時間を設けるのもいいかもしれません。試験直前では、この応用的な対策にどれだけ時間を投入できるかがポイントになるかと思います。ちなみに、文法的に型にはまった直訳のみが正解とは限らないので、分からない単語が出てきても推定して、文章全体をまとめること、一定の訳し方を読みやすさの観点から定着させることなどに気をつけました。
実際に入学されて、いかがでしたか
早稲田の博士後期課程に進学して一番印象的だったことは、博士課程の学生は皆、一端の研究者という自覚をもって、高い意識で自身の研究に専念していたことでした。博士課程の学生が参加する授業は、議論のレベルも高く、授業のテーマに関連するいくつかの研究論文を事前に読み込んでいなければ参加することが不可能なものでした。正直、博士後期課程の1年目は、周囲のペースに付いていけず、自分自身の不甲斐なさを感じる毎日でした。
この苦い経験から、博士後期課程在籍中、私は一日の大半を、基本的に図書館で過ごすようにしました。そもそも「勉強すればするほど、分からないことが増え続ける」のは、ごく自然なことだと割り切り、図書館では専門分野の辞書を手元に置いて、「調べる」と「理解する」という基本的な作業を繰り返しました。もちろん、勉強ばかりではなく休憩とのバランスも大切です。早稲田キャンパスには、綺麗な銀杏並木があります。私はよくベンチに座って、この銀杏並木にいろいろな悩みを解決してもらいました。また、とにかく気の合う先輩・後輩に囲まれていたおかげで、ゼミやゼミ以外でも楽しく学生生活を送ることができました。ちなみに一番リラックスできた場所は、早稲田キャンパス界隈の居酒屋になります。
博士後期課程の学生生活はどのようなものですか?
私の専攻分野は、会計学のなかの財務会計(Financial Accounting)になります。日頃の研究活動は、文献研究が中心でした。私の場合、研究室のゼミメンバーで共通の関心事を扱った研究論文を輪読して、ゼミや授業以外では、自己の研究を練り上げるための文献研究を行いました。商学研究科では院生が自身の研究成果を報告できるように研究発表会が定期的に開催されます。博士後期課程在籍中、私の日々の目標は、文献研究を重ねたうえで、研究発表会で自身の研究報告を行い、商学研究科の雑誌『紀要』に研究論文を掲載することでした。
博士後期課程在籍2年目に商学部助手になってからは、指導教授や先輩に連れられて、学会や研究セミナーに参加しました。学会に参加することで、他大学の研究者によるさまざまな研究報告から、新鮮味のある学術的な刺激をたくさん受けることができました。また、自らが学会発表を行うことで、他大学の研究者との交流が、研究上、不可欠なものであるということも認識しました。私の研究活動は、とくに文献研究が中心となるので、私に限ってのことかもしれませんが、どうしても自分自身の頭の中だけで結論を導く傾向があります。他大学の研究者との交流は、自分自身の凝り固まった考え方をさまざまな観点から照らしてくれます。私は、いろいろな活動を通じてさまざまな研究者と出会うことが、自己の研究の質をより高めることができる有効な手段となることを実感しました。
現在はどういった研究をしていらっしゃいますか?
大学教員として現在の本務校に着任してからも、研究分野や研究スタイルに基本的な変更はありません。本務校では、授業や学内業務はもちろん、最近は社会人講座も担当するようになりました。その中で、研究に着手する時間は、大学院生のときよりもはかるかに少なくなってしまいましたが、いろいろな分野の先生方との交流も増え、自身の研究に対する世界観に学際的な視点を徐々に取り入れることができるようになりました。
また、母校を離れてとくに感じることですが、早稲田大学(商学研究科)の研究環境は、研究者の養成という観点から、全国でも屈指であるといえます。たとえば、図書館に所蔵されている貴重な文献が豊富であることや、研究設備や助手制度などを含めた研究支援体制の充実をあげることができます。とくに早稲田大学の助手制度は非常に充実した研究支援であり、他大学でこのような制度を実施している例はあまりみません。私が今教壇に立っているのも、早稲田大学の充実した研究支援のおかげです。
現在は、月に1度、博士論文の執筆のために、早稲田キャンパスを訪れて、指導教授にご教示いただいてます。当面は、教育活動にも従事しながら、気持ちの面で大学院生の時分を忘れることなく、博士論文を書き上げることが目標になります。
博士後期課程への進学を検討されている方へメッセージをお願いします
研究者の養成を目的とする博士後期課程は、少々閉鎖的なイメージもありますが、それは自身の取り組み方次第です。研究上の特定の問題に対して、1人で机に向かって何時間も格闘することもあれば、複数の研究者とチームを組んで問題解決に取り組むことも十分に考えられます。いずれにしろ、研究に取り組むことの魅力は、すべての問題を解決できなくても、研究のプロセスを通じて、また他の研究者と議論を交わすことで、一定の結論を導き出すことだと思います。私は、研究に取り組むことで、「学問に向かうことの喜び」を素直に感じることができます。博士後期課程に進学するかどうかで悩んでいる方は、試しに学術書などを読み込んでみて、「学問に向かうことの喜び」を見出せるか否か、自身に問うことをおすすめします。
もっとも、実業界から博士後期課程に挑戦される方は、一度実業界に出られて、ブランクができてしまったことを不利に思われるかもしれませんが、実学としての商業をすでに体感されているという点で優位性があることも忘れてはいけません。この優位性は、研究職に就いてから、さらなる強みを発揮します。実業界から博士後期課程に挑戦することを考えておられる方は、是非、その優位性を活かしてみてはいかがでしょうか。
略歴
2002年 明治大学経営学部経営学科卒業
2004年 国士舘大学大学院経営学研究科修士課程修了
2007年 早稲田大学大学院商学研究科博士後期課程単位取得退学
(2005年-2007年 早稲田大学商学部助手)
2007年 広島経済大学経済学部経営学科専任講師
2010年 広島経済大学経済学部経営学科准教授(現在に至る)
