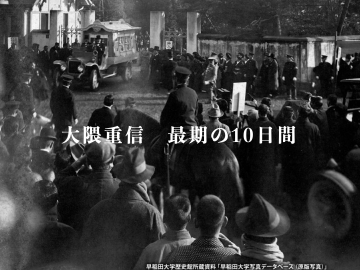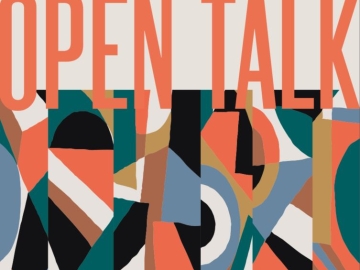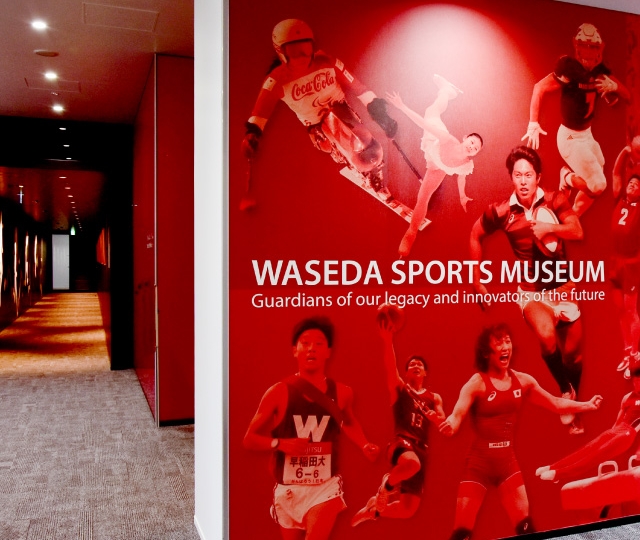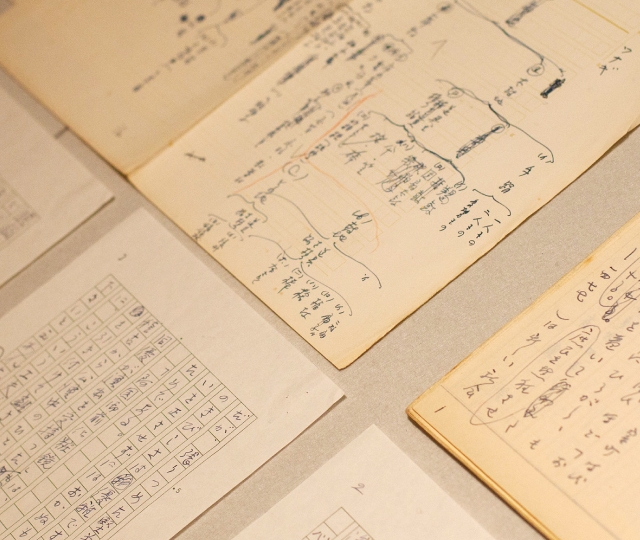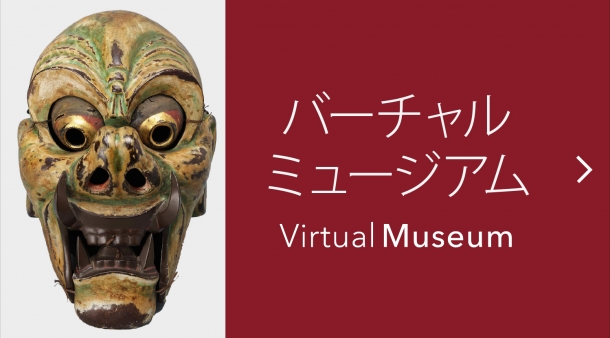Open Talk 日本の”生き物供養”と”何でも供養”
早稲田大学国際文学館を訪れる方々に、文学を読む面白さや文学研究の魅力を感じていただくための講演会を開催しております。今回は国文学研究資料館の相田満教授によるトークをお楽しみください。
何でも供養する日本人の習性と、その精神文化は世界的に珍しいのではないかと思われています。
たとえば、筆や紙や針、人形などの供養行事はよく知られているが、実状はさらに多様です。鯨や鯔(ボラ)、鰰(ハタハタ)などの海生生物のあれこれ、陸生生物では草木や馬や犬猫、鶏牛などの家畜、果てはシロアリやゴキブリなどの被駆除生物や、魚の餌になるユムシまでも供養しています。
加えて、橋や日食、庖丁のような器物や自動車のような工業製品までも供養して、それらを祀る供養の営みは、今なお続けられるどころか、新たな供養も生み出され続けています。このことを、海外の人に話すと、皆一様に驚き不思議がります。
もっとも、驚くのは日本人も同様です。とりわけ、日食や金属片のようなものまでが供養されて碑塔が造られていることを伝えた時には、伝えたこちらがうれしくなるような新鮮な反応が返ってくるのです。
このような日本人の心性は何に由来し、いかなる文化的な思考回路で営まれてきたのでしょう。本講演では、日本・中国・台湾や他の諸国における供養の動向と現状をふまえながら深掘りします。
詳細
- 開催日時:10月29日(火)14:00~15:00
- 会場:早稲田大学国際文学館(通称:村上春樹ライブラリー)2階ラボ
- 言語:日本語
- 参加:どなたでも無料で参加できます。
- 主催:柳井イニシアティブ グローバル・ジャパン・ヒューマニティーズ・プロジェクト
- 共催:国際文学館
講演者
相田満(Mitsuru Aida)
 国文学研究資料館准教授。和漢比較文学研究と人文情報学。特に、日本古代・中世文学、学問・注釈学、説話文学に関わる研究。
国文学研究資料館准教授。和漢比較文学研究と人文情報学。特に、日本古代・中世文学、学問・注釈学、説話文学に関わる研究。
人文情報学では、地理・時間・概念の情報に着目した応用研究を進めるほか、『古事類苑』データベースの構築と研究も進めている。
著書に『和漢古典学のオントロジ』(2007)、『時空間とオントロジで見る和漢古典学』(2016)、『元号の歴史大事典』(2019)、『観相の文化史』(2021)がある。
ファシリテーター
伊丹
柳井イニシアティブ研究員
イベントに関する問い合わせ
- 柳井イニシアティブ事務局email: yanai★list.waseda.jp(★部分を@に変更してください。)