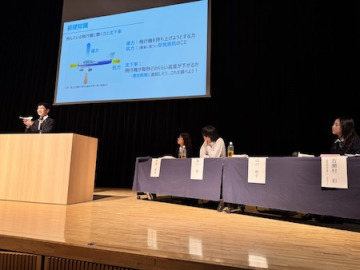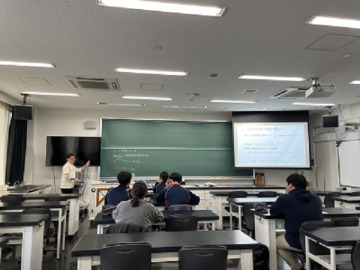韓国セロナム・クリスチャンスクール(セロナム高校)との間で継続している国際学術交流を、本年度は初めて対面で行いました。プログラムの中心は持続可能な開発目標を主題に探究するフォーラムです。共通言語は英語です。学院生10名が公民科羽田教諭、地歴科松田教諭の引率のもと7月17日~20日(3泊4日)の日程で韓国テジョン市を訪れました。
5月にオンラインにて初回ミーティングを行い、SDGsのテーマごとに5つのグループに分かれ、自己紹介や研究内容についての話し合いをしました。その後もGoogleチャットなどのツールを使用し、月1回のミーティングの時間以外も共同で準備を進めました。研修前最後となる7月のミーティングでは、グループ内で研究内容に関する中間発表とフォーラム本番に向けての最終確認を行いました。最初は緊張して上手く話せないこともありましたが、回数を重ねるごとに対面で会うことが待ち遠しくなりました。

(成田空港にて出発前)
韓国研修初日、私たちはセロナム高校を訪れました。多くの生徒が温かく迎えてくれて、学校のカフェでスイカジュースを頂きました。私たちは韓国研修を楽しみにしていましたが、慣れない国の文化に適応できるかどうか等多少の不安を抱えていました。しかし、韓国の方々の温かさにその不安や緊張もほぐれ、歓迎会での自己紹介でお互いの仲を深めることができました。小中学生によるパフォーマンスの披露のあと、セロナム高校の施設を見学しました。私はセロナム高校にカラオケルームがあることが非常に印象に残っており、是非私たちの高校にも取り入れてほしいと思いました。学校到着時にセロナム高校の生徒から「コンニチハ」と言われたのは今でも覚えており、韓国人の温かさに触れられる良い機会だったと思います。

(セロナム・クリスチャンスクール中等部生によるパフォーマンス)
本研修にはセロナム高校の生徒宅へのホームステイ(2泊)が組み込まれていました。ホームステイでは韓国生徒の放課後の遊びに交わりました。1日目の夜は、バスで10分ほど移動したところで買い物をし、フォトステッカーを撮りました。日本のキャラクターが韓国のお店にたくさんあり、日本文化の広がりを感じました。2日目の夜は、今回の韓国研修に参加した生徒達16人でボーリングをした後、夜道を散歩しました。テジョン市は理科系の都市であるため橋やタワーの構造に独創性がありました。セロナム高校は学校終了時刻が22:00と遅く、私達の学校と違い、遊びに制限が自動的にかけられていると感じました。
また、韓国の家庭では、テーブルマナーや、毎食必ずキムチが出ることなど、日本の食卓との違いを感じました。

(セロナム高校とバディと韓国の街並みを夜の散歩)
2日目、セロナム高校の礼拝に出席したあと、バスに乗ってフィールドワークに行きました。
最初に訪問した清州公共下水処理場では、沿革、施設の構造、処理プロセス、放流水水質基準、運転状況などを学びました。 運営事業では、改良・拡張事業について理解しました。
清州焼却施設では、施設の仕組みについて学びました。この施設は、清州市内の住宅地や商業地から家庭ごみを収集し、安全でクリーンな方法で処理する最新鋭の施設でした。職員の方の説明は韓国語で、セロナム高校のバディが英語で通訳する形で行われました。
施設を見学したあとに学校に戻って所感を発表する時間がありました。自身の英語力が向上したのと自分の思っていることを要約することができました。強い雨が降っていたため、屋外のリサイクル施設を見学することはできませんでしたが、日本の施設との違いを学ぶことができました。韓国でのフィールドワークはとてもいい経験になりました。

(ゴミ焼却処理施設の最先端技術を学ぶ)
2日目のメインイベントは学術発表会(フォーラム)でした。メンバーそれぞれがオンラインで練習したときよりも調査と発表の練習を重ね、非常に完成度の高い発表を行うことができました。もちろん練習の時と違って多くの聴衆の視線があり少々緊張しましたが、少し話し始めるといつもの調子を思い出し落ち着いて最後まで発表をすることができました。また、他のチームの発表も初めて聞きました。どのチームも入念なリサーチを行っており、聞き手側のSDGsや世界で起きている様々な問題についての興味が深まる説得力のある発表ばかりでした。質疑応答の際に出た質問はどれも鋭いものでしたが、それらに的確に回答する様子からは各グループの下調べの綿密さが伺えました。

(各チームによるアカデミック・プレゼンテーションとディスカッション)
フォーラム終了後の夜には各グループに分かれて、韓国伝統料理のプルコギを作りました。プルコギは日本でも食べられていますが自分たちで作って食べることは初めての体験でした。
初めに日本の学生のみに作り方が書かれた紙が配られ、その内容を韓国の学生に英語で説明しました。相手に分かりやすく伝えるために、使う言葉を工夫したり、身振りを使うなど、日本語で作り方を説明するよりもはるかに難しかったですが、自分の英語力や説明能力の向上に繋がりました。
料理をしている間は、今まで話したことがなかった韓国の学生と食材を入れるタイミングなどを相談することで仲を深めることが出来ました。完成したプルコギは今まで食べたプルコギの中で1番美味しかったように感じます。日本でも韓国でも、何かを共に作ることで楽しく相手とコミュニケーションがとれるのだなと思いました。2時間30分という短い時間でしたが、お互いの食文化への知識を深め、多くの学生と交流するという貴重な体験をすることが出来ました。

(セロナム高校の生徒と一緒にプルコギづくり)
研修3日目には、セロナム高校のメンバーと一緒に陶磁器作りと伝統家屋であるハノクマウルの見学を行いました。
陶磁器作りでは、ろくろを使うものと手で成形するものの2種類の体験を行いました。前者では、形を選び、職人の方に手伝っていただきながら器を作りました。後者では、それぞれ個性あふれるお皿を作りました。日本の陶磁器と似ている点もありましたが、お皿の分厚さや形、柄が韓国伝統のものであり、とても興味深かったです。
伝統家屋の見学では、建物と庭園を訪れました。松や竹があり、家屋に瓦が使われている点が日本と似ていると感じました。また、壁のない縁側のような場所が広くとられていて涼しく過ごせる工夫がされていると感じました。
実際に体験したり家屋に入らせていただいたことで韓国の文化を体感することができました。

(工房で陶磁器作り)
最終日はセロナム・クリスチャンスクールの初等部を見学しました。コンピューター室、職員室、図書室など日本の小学校と同じような部屋がある一方、テコンドーの練習室、遊具などがあり日本との違いを発見することができました。また、ミッションスクールということで、お祈りをするための部屋もありました。学校は全体的にカラフルで小学生に親しまれやすい校舎だと感じました。
セロナム高校の校長先生は残念ながら海外出張中とのことで、ビデオ講義を受講することになりました。講義ではチャック・フィーニーのお話を聞きました。億万長者となってもキリスト教の教えを忘れず、寄付や慈善事業に勤しんだと知り、私自身も思いやりや愛を忘れずに日々行動していきたいと感じました。

(キリスト教歴史館。初等部の英語の先生が解説して下さった)
全体の所感について日韓それぞれの代表者3名ずつが発表し、最後の交流として、”We are the World “を全員で歌いました。この曲で、日韓の間では政治や歴史など様々ないざこざがあるけれど、歌を歌う時はお互いに一体感を感じることができ、さらに肩を組むことによって愛を感じました。
その後に私たち早稲田チームは”紺碧の空”と”アイドル”を披露し、セロナム高校は複数の女子生徒がCCDというダンスを披露してくださいました。そのダンスは非常にハイレベルで、とても私たちのように前日の夜から始めて完成するような振り付けではありませんでした。来年受け入れ側となったときは、早稲田側も事前にたくさん練習し、より高度なパフォーマンスをできるように努めたいです。この文化交流・成果発表会は私たちによって一生の思い出となる発表となりました。

(参加生徒全員でWe are the Worldを合唱)
日本の若者にとって憧れの国のひとつである国、韓国。私がこの研修を受けて言えることがあります。このプログラムには一生の友、一生の思い出、唯一無二の経験が詰まっていると思います。学校の代表として韓国の高校に行くということや初めて行く国ということで不安な気持ちもありました。しかし、この不安はすぐに消えました。引率の先生をはじめ、現地の高校生や先生、ホームステイ先のご家族たちの厚いサポートがあったことでとても楽しく過ごすことができました。そして現地の高校生と深い絆を結ぶことができました。このことから私はこの研修で、ある重要なことを学びました。それは人と仲良くなるのに文化や言語の違いは関係ないということです。大切なのはその人の魅力を知り、深くコミュニケーションをとっていくことだと思います。

(閉講式でのプレゼンテーション)
2025年は本学院がホストとなってセロナム高校の訪問団を受けいれ、國際学術交流を行う計画です。