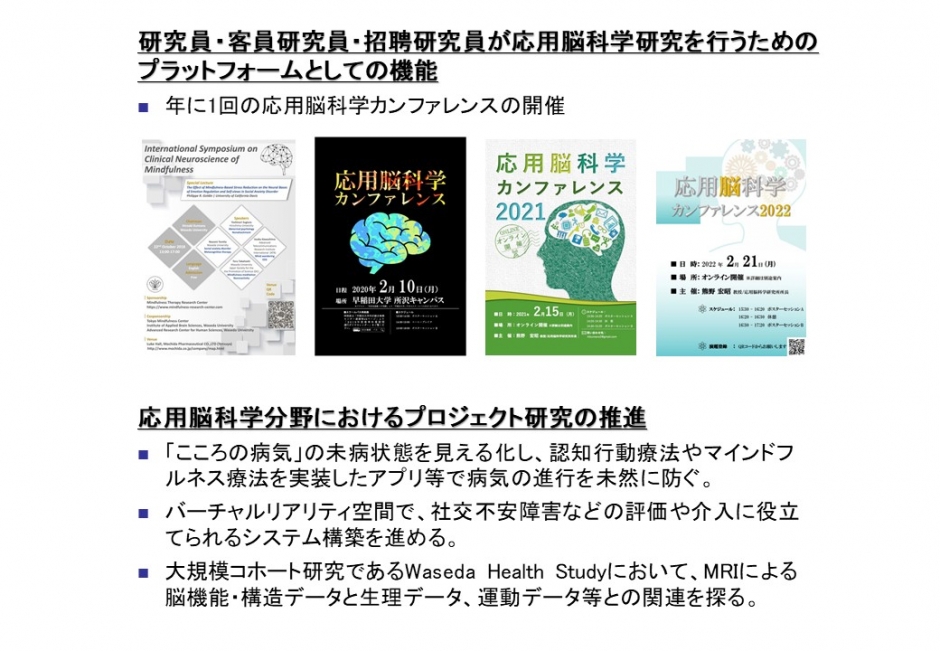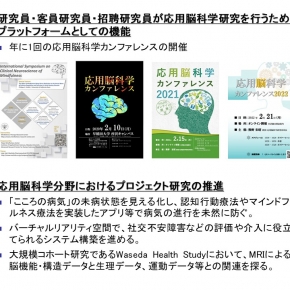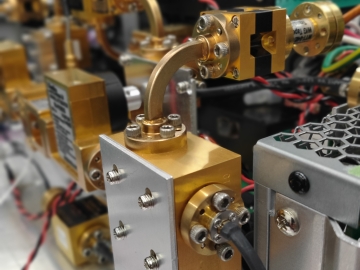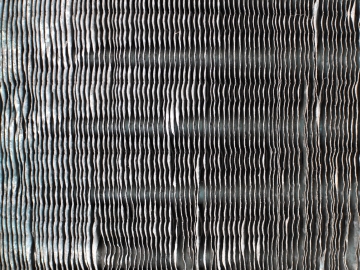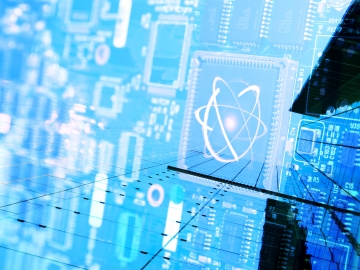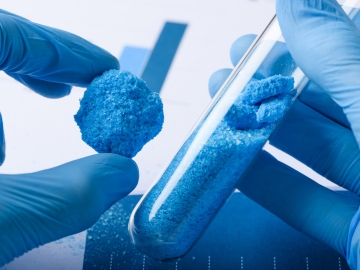Research Theme 研究テーマ
総合人間科学に基づく応用脳科学の展開 (①未病状態の見える化と病気の進行の防止、②VR を用いた社交不安症などの評価や介入に役立てるシステム構築、③大規模コホート研究Waseda Health Study での脳構造・機能データの取得とマインドフルネスの役割の検討)
Research Director 所長
Member メンバー
- 東 玲奈 国際学術院国際教養学部准教授
- 大須 理英子 人間科学学術院人間科学部教授
- 岡崎 善朗 人間科学学術院人間科学部准教授(テニュアトラック)
- 掛山 正心 人間科学学術院人間科学部教授
- 菊池 英明 人間科学学術院人間科学部教授
- 熊野 宏昭 人間科学学術院人間科学部教授
- 齋藤 順一 総合研究機構次席研究員(研究院講師)
- 嶋田 洋徳 人間科学学術院人間科学部教授
- 田山 淳 人間科学学術院人間科学部教授
- 千葉 卓哉 人間科学学術院人間科学部教授
- 辻内 琢也 人間科学学術院人間科学部教授
- 原 太一 人間科学学術院人間科学部教授
- 正木 宏明 スポーツ科学学術院スポーツ科学部教授
- 松居 辰則 人間科学学術院人間科学部教授
- 百瀬 桂子 人間科学学術院人間科学部准教授
- 臼井 香 総合研究機構客員次席研究員(研究院客員講師)
- 内海 智博 国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所 睡眠・覚醒障害研究部リサーチフェロー
- 池田 寛人 学習院大学学生相談室相談員
- 今井 正司 梅花女子大学心理学科教授
- 国里 愛彦 専修大学人間科学部教授
- 鄭 志誠 京都大学大学院医学研究科精神医学講座研究員
- 富田 望 総合研究機構客員主任研究員(研究院客員准教授)
- 長尾 賢太朗 国立精神・神経医療研究センター 精神保健研究所 睡眠・覚醒障害研究部リサーチフェロー
- 仁田 雄介 株式会社心の杜メディカルサービス心理師
- 野田 隆政 独立行政法人国立精神・神経医療研究センター病院神経科医長 脳病態統合イメージングセンター臨床脳画像研究部
- 羽澄 恵 日本医科大学医療心理学教室・准教授/国立精神・神経医療研究センター・客員研究員
- 藤島 雄磨 金町駅前心療内科かわせみクリニック心理師
- 守口 善也 ルンドベック・ジャパン開発本部メディカル・アフェアーズ部部長
- LEWKIS, Sheldon Vancouver Neuromodulation
研究キーワード
応用脳科学、認知行動療法、アプリ作成、バーチャルリアリティ、マインドフルネス
研究概要
応用脳科学研究所は、現代社会をめぐる様々な課題状況の下、重点領域研究機構(2009~ 2013 年度)、総合研究機構(2014~2023 年度)に所属する研究所として、人間科学学術院とスポーツ科学学術院が 35 来以上に渡って蓄積してきた「脳と心の科学」のポテンシャルを「応用脳科学」という軸に沿って有機的に結びつけながら発展させ、具体的な成果として社会に還元することを目的として活動してきた。その結果、500 件を超える論文や著書を発表し、統合データベースとして一覧できるようにするともに(http://opendb.iabs-waseda.net)、27 回を数える一般公開の主催・共催・後援シンポジウム、研究会などの開催を実現してきた。
3 期目に当たった 2019~2023 年度の活動に当たっては、応用脳科学に関する当初の啓発的な役割はほぼ終えた一方で、早稲田大学における応用脳科学研究基盤の活力を維持・発展させていくという大きな役割は今後も担う必要があると考え、まずは関係者間の協同作業を可能にするプラットフォームの機能を維持することとした。その実現のためには、毎年 1 回は必ず開催してきた研究成果発表会(応用脳科学カンファレンス)を、コロナ禍の状況下でもオンライン化することによって継続することにしたが、その結果、研究所員の研究室に所属する大学院生や若手研究者、さらには客員研究員や招聘研究員を中心に毎年 30 件近い発表があり、常時 45~50 名程度の参加者を得ることができた。さらに、このようなプラットフォーム機能を維持する一方で、一旦それまでの活動を終了し、新たに参加者を募ることによって、新しい研究テーマへの取り組みも始めることにした。具体的には、①うつ病などの「こころの病気」になる前の未病状態を判定して見える化し、その結果に基づいて病気の進行を未然に防ぐことを目指す、②情報科学の方法論を用いてバーチャルリアリティ(VR)空間を設定 し、社交不安症(極度のあがり症)などの評価や介入に役立てられるシステム構築を進めて行く、③早稲田大学同窓生を対象とした大規模コホート研究である Waseda Health Study(WMS) において、MRI による脳機能・構造データを収集し、生活習慣に関わる様々な指標、身体運動機能、血液生化学指標、マインドフルネスや精神的健康などとの関連を見るという 3 つの研究領域に取り組むことにしたが、仮評価事業報告書に記載した通り、いずれの研究領域においても大きな進展を見ることができた。
現在、これらの 3 つの研究領域では、複数の研究が進展しており、以下の研究計画の項に記載する通り、今後もこれらの研究を継続的に発展させ、英語論文等として国際的に情報発信も行うことで、科学技術の最先端に迫る活動を続けていきたいと考えている。