- プロジェクト研究
- 宇宙望遠鏡群による銀河とブラックホールの物理探求
宇宙望遠鏡群による銀河とブラックホールの物理探求

- Posted
- Tue, 01 Apr 2025
- 研究番号:25P04
- 研究分野:science
- 研究種別:プロジェクト研究
- 研究期間:2025年04月〜2028年03月
代表研究者
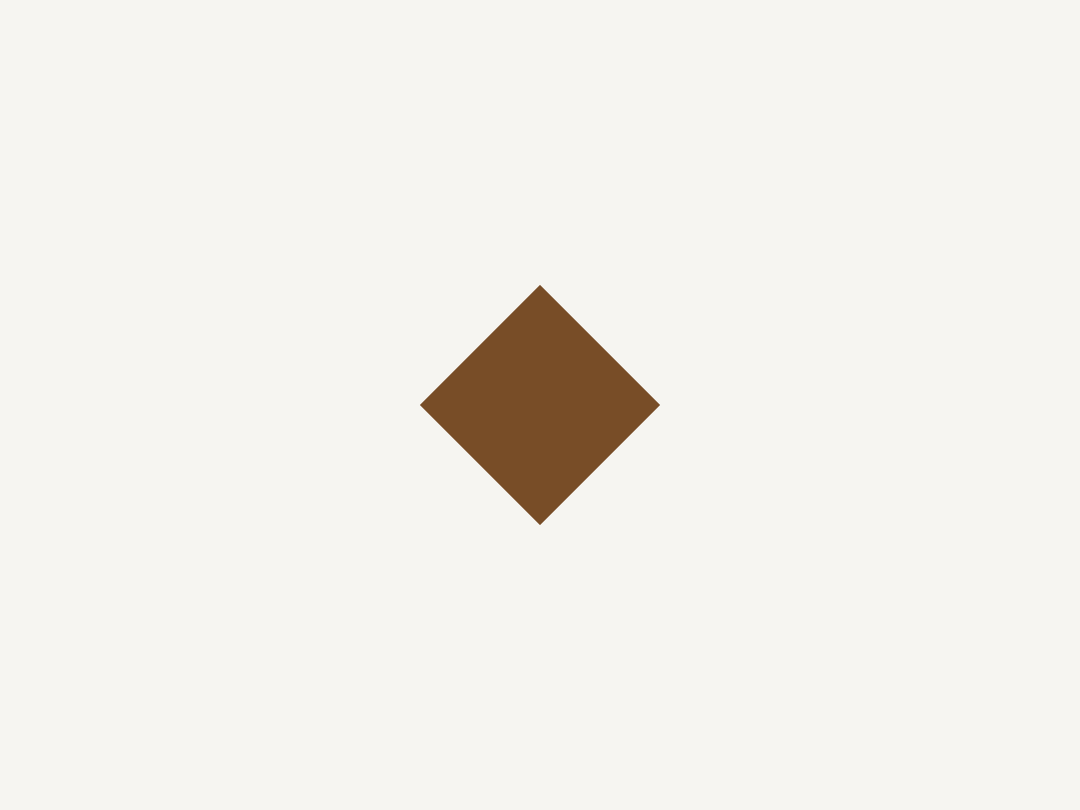
山田 章一 教授
YAMADA Shoichi Professor
先進理工学部 物理学科
Department of Physics
研究概要
銀河とその中心に存在する大質量ブラックホールは互いに影響しながら進化すると考えられている。この「共進化」の物理メカニズムを解明することが、宇宙物理学分野における現代的な一つの大目標となっている。米国によるジェームズウェッブ宇宙望遠鏡(JWST)の成功により、138億年の宇宙史ほぼ全体にわたる銀河とブラックホールの共進化研究が可能となった。また、昨年打上げに成功した欧州のEuclid衛星は、その超広視野の撮像探査能力を活かし、銀河とブラックホールの大統計サンプルの構築を進めている。
そこで本研究は、Euclid衛星の大統計サンプルで初めて見つかる極めて希少な、宇宙初期の「初代ブラックホール」を宿す明るい遠方銀河に注目し、それらをJWSTで観測することで、「共進化」の物理メカニズムを明らかにすることを第一の目的とする。また、JWSTのこれまでの観測により浮かび上がってきた、明るい銀河の数密度超過問題の解決を第二の目的とする。従来の定説である冷たいダークマターにもとづく宇宙の構造形成シナリオで予想される銀河の数密度に比べ、非常に大きな数密度が観測されたが、統計的有意性が十分ではない。Euclid衛星による超広域探査による初期宇宙の銀河の大統計サンプルにもとづけば、数密度超過問題の真偽をより高い統計的有意性をもって議論できる。もし数密度超過が確実となれば、初代ブラックホールの影響で明るく観測されている可能性を軸に、その物理的理由を明らかにする。さらに、2030年代に日本が打上げを目指す次世代超広域銀河探査を主目的としたGREX-PLUS計画の概念検討を第三の目的とする。
