- プロジェクト研究
- 安全安心な社会を実現し豊かな文化を創造するコンテンツ・映像処理技術研究(3期目)
安全安心な社会を実現し豊かな文化を創造するコンテンツ・映像処理技術研究(3期目)

- Posted
- Tue, 17 May 2022
- 研究番号:21P53
- 研究分野:technology
- 研究種別:プロジェクト研究
- 研究期間:2021年10月〜2024年09月
代表研究者
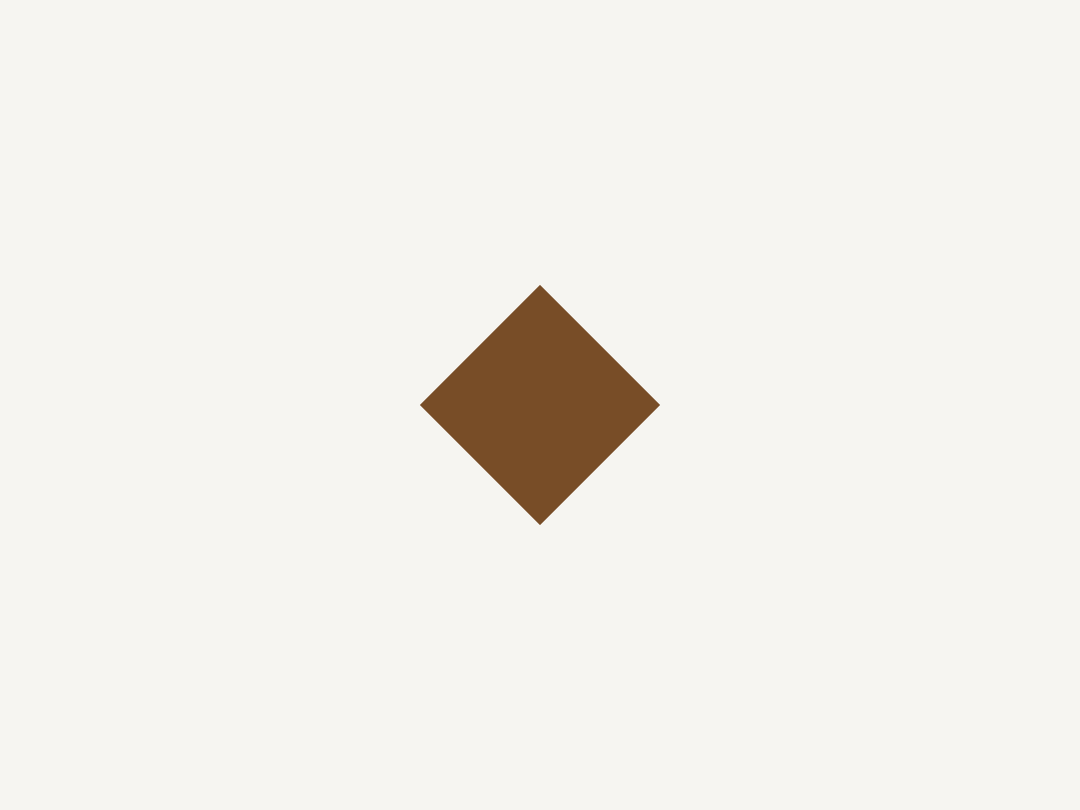
森島 繁生 教授
MORISHIMA Shigeo Professor
先進理工学部 応用物理学科
Department of Applied Physics
URL:http://www.mlab.phys.waseda.ac.jp/team/%E6%A3%AE%E5%B3%B6-%E7%B9%81%E7%94%9F/
研究概要
日本の食文化は,ユネスコ無形文化遺産にも登録された通り,食の多様性や新鮮な食材,栄養バランス,四季折々の自然の季節感の表現,正月など年中行事との関わりなど,様々な側面を有している.特に欧米の食文化と比較して最も大きな特徴は,料理を作ること(料理人の匠の技等)が食べることと対等な位置づけになっている点である.例えば茶室や寿司,小料理屋のカウンターなどでの,サービスを与える側と受ける側の対等なコミュニケーションが1つの特徴である.茶道ではお茶とお菓子というサービスの授受の中で,作法,茶器や茶室,庭の美しさなどの詫び寂びに古来から引き継がれる伝統の美しさを感じ,茶器や茶室の視聴覚的なリアリティだけではなく,サービスを提供する側の人々の立ち居振る舞いのパフォーマンスも1つの楽しみの要素となっている.寿司屋のカウンター,小料理屋の板前とのやりとり,鍋(すき焼き,焼肉,バーベキュー等)を囲む人々との弾む会話など,作って食べるという行為に含まれるコミュニケーションや出会い,発見,感動など,日本の食文化の特徴として列挙することができる.
現在,コロナ禍においてリモートでの会議や作業が必要不可欠となってきているが,定型的な会議や講義など一部の応用では効果的に機能している実例がある.しかし,懇親会や密な議論,会食などについては,現状の技術では場の雰囲気などの伝播,あるいは場の雰囲気を共有しているという実感が得られない.ZOOMを介しての飲食時間の共有が急速に下火になっていることは,改めて飲食場面などの場の空気の共有がオンラインでは困難であり,実際に対面する必要があることを浮き彫りにしている.このような環境下で,特に飲食業に目を向けてみると,時間短縮営業などによって,その経済状況が悪化しており,テイクアウト対応など行って対処しつつあるものの,そのお店独特な雰囲気や人間同士のコミュニケーションなど,本来飲食店に実際に足を運ぶことで満たされていた様々な要素が実現不可能となっており,業界は窮地に立たされている.よって,このままでは,孤立した空間での孤食がさらに進行し,ひいては日本の食文化の衰退を招きかねない状況にある.
そこで本研究では,遠隔地に存在する人物同志が,お互いの存在環境を共有したり,別の環境・空間にあたかも一緒に存在しているかのような空間共有感覚を実現しながら,さらに五感を駆使して共食できる環境を提供し,サービス提供者ともコミュニケーションを行いながら,日本の食文化そのものを継承可能な共食支援システムの実現のための要素技術研究とその実用化に向けてのプラットフォーム構築を行う.これによって,海外の人物にも日本の食文化を体験できる機会を提供することができるばかりではなく,過去や歴史的に著名な食イベントの追体験可能なアーカイビングも実現可能となり,時間と空間を越えて日本の食文化の伝承に大きく寄与することが期待できる.
1つめは共有する空間の雰囲気や気配を忠実にキャプチャ・モデル化し,低遅延伝送し,再現する技術である.遠隔地に存在する人物同志が,仮想環境を共有して対話したり,協調作業を行うことを支援するXR技術開発は活発に研究が行われてきたが,あくまで3次元的なオブジェクトや人物の表現方法等視覚的な側面に研究の焦点が置かれていた.本研究では,空間の壁を越えた食環境や時間の壁を越えた食文化の再現を目的としており,感性豊かにマルチモーダルな情報で五感を刺激して,雰囲気や気配を忠実にモデル化・再現すると同時に,現状では視聴覚だけでは伝わり切らない食感や感性情報を抽出,伝送することにより,食に関わる多様な物語体験・空間体験によってもたらされる感動を共有できる環境創出をめざすものである.
もう1つは,食に関わる生体・感性情報のモデル化とそのフィードバック技術である.食に関わる多様な物語体験は本来リアルタイムでしか体験できず,時と共に変容・拡散し失われてしまう.料理や空間は比較的記録可能性は高いが,その体験により参加者の内面状態がどのように変化していったか,という点については記録は難しく,また再現も困難である.例えば現実の食事場面では,自己の味覚・視聴覚を通じて得られる,食事そのものや周囲環境に関する情報から満足感を得る.さらには食事をともにする他者の行動や反応と,自身の行動・反応が相互に影響しあい,食事という場を共有する満足感を得ることとなる.このような状況を人工的に再現しようとする場合,身体外部の雰囲気や気配の抽出再現はもとより,どのような食品を食べ,どのような気分であるか,という身体内部の状態の相互共有を考慮することが必要となる.そこで必要な情報を視聴覚情報や生理センサ,ウェアラブルデバイスを通して取得し,それを多様な感覚デバイスで伝送する技術を開発する.この技術は,現状のオンライン食卓が欠いている共食者同士の味や満足感などの内受容的感覚の食体験の共有を,新たな形で実現することを目指すものである.
これらの二つの技術により,①:遠隔にいながら,料亭などの特別な環境の雰囲気を体験する,②:遠隔の他者が食べている食品の特長やそれによって他者が得られる生体的・心理的変化を抽出し,伝送可能な情報(視聴触)でそれを再現したり,強調して伝える,③:①②を融合し,新しい心が通う共食スタイルを実現する.
この研究と同時に,仮想空間の時間軸制御によるスポーツやトレーニングのモティベーション向上の研究や,医療分野における信頼できるAIの実現,さらには視覚障碍者をはじめとする社会的な弱者を支援するための,プライバシーやセキュリティを考慮したスマートデバイス上での支援システムの開発にも取り組んでいく.
