- プロジェクト研究
- 生物制御機構のモデリングと治療戦略確立への応用(2期目)
生物制御機構のモデリングと治療戦略確立への応用(2期目)

- Posted
- Tue, 19 May 2020
- 研究番号:16P11
- 研究分野:technology
- 研究種別:プロジェクト研究
- 研究期間:2016年04月〜2019年03月
代表研究者
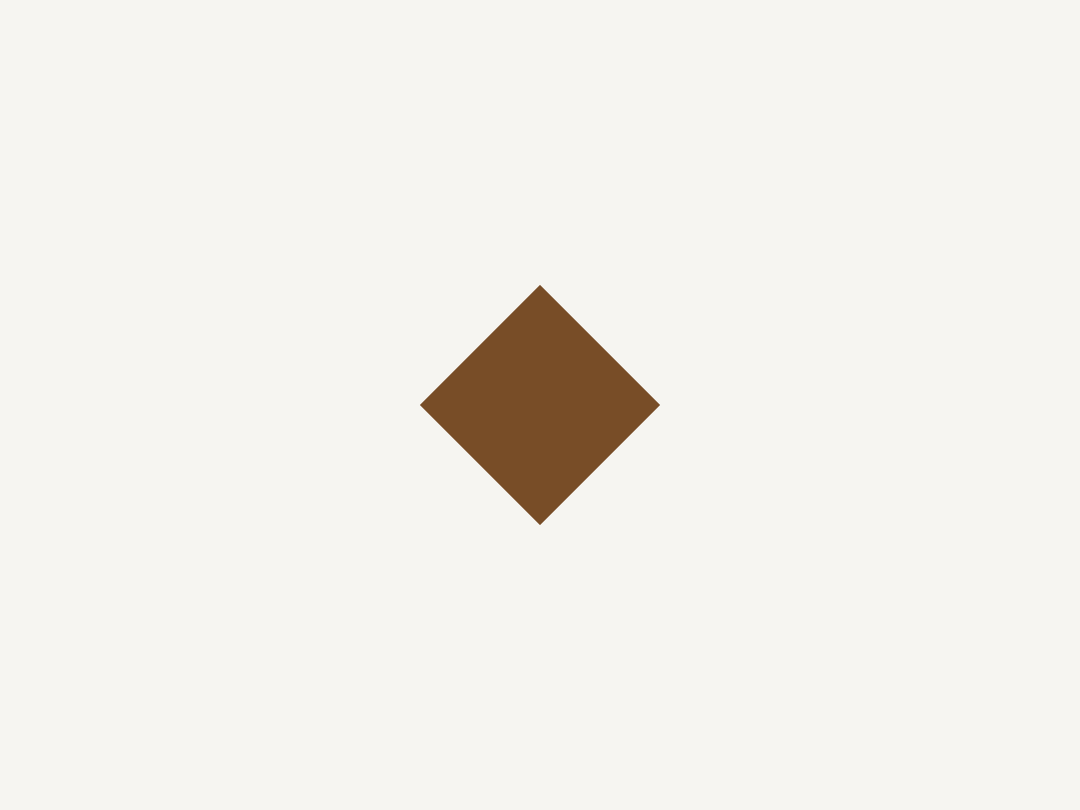
内田 健康 教授
UCHIDA Kenko Professor
先進理工学部 電気・情報生命工学科
Department of Electrical Engineering and Bioscience
研究概要
生物には様々な制御機構が働いている。①個体レベルの脳の運動制御、②臓器レベルのホメオスターシス、③細胞レベル遺伝子発現や代謝の制御など、生物のあらゆる種、あらゆるレベルでさまざまな生体機能を支えている。制御が機能を果たすことが出来なくなったときに人間は病気に犯され、場合によっては死の危機に直面する。従って、病気の発生、その重篤化、さらに死へのプロセスを解明し、それを防ぐ合理的な治療戦略を確立するには、生物の制御のメカニズムとダイナミックスを定量的に理解することが必要である。生物制御、特に人間の健康保持のための制御には、自律神経系、内分泌系、免疫系の三つのシステムがあり、これらが相補い合って活動している。これらの三つの制御系が機能を分担し適切な相互作用を通して作用機序が統合するネットワークを構成している。この制御のネットワークを定量的に解析するためには、人間の全体的な統合生理モデルを構築することが不可欠である。統合生理モデルは、検査の当否、投薬効果の予測や治療法の選択など個々の疾病へ治療戦略確立に極めて有用であるだけでなく、病態進行の遅い高齢者の場合は個人ごとのモデルを治療経験や検査データにもとづいて逐次時間をかけて更新し、遠隔治療への道を切り開くことが出来る。モデルの利用による診断と治療の高度化はシステム医療への重要な一里塚であり、「技」に頼ることの多い労働集約的な医療の現場を改変することを目標としている。本研究プロジェクトでは以下の課題に取り組む。
① 敗血症の動態解析モデルの投薬戦略確立への展開:すでに申請者らが確立した敗血症の動態解析モデルを用いて治療戦略を確立する。統合モデル構築のための具体例として検討する。
② 統合生理モデルの構築:従来の生理モデルは各臨床科別、疾病個々に対応した部分モデルのみしか存在せず、循環系、消化系、呼吸系、温熱系、血糖系などを結び付けた統合モデルは必要性が高いにも拘わらず存在しない。数理科学と臨床医学での循環系、消化系、呼吸系、温熱系、血糖系の各系融合による「人体統合モデル」を構築し、疾病の発生と進行メカニズム解明へ繋げる。
③ 自律神経系、内分泌系、免疫系の統合制御モデルを統合生理モデルの上に構築し、臨床データによるその実証を行う。
④ 高齢者の遠隔医療システムへの適用:高齢者の場合病気が急性でなく、慢性化して進行が穏やかである場合が多く、ケアに十分時間を掛ける余裕があり時間を掛けた日常的な生理状態の計測検査により、モデルを精密化できる。これにより要介護者の生理機能の変化に応じモデルを進化させる方法を検討する。
