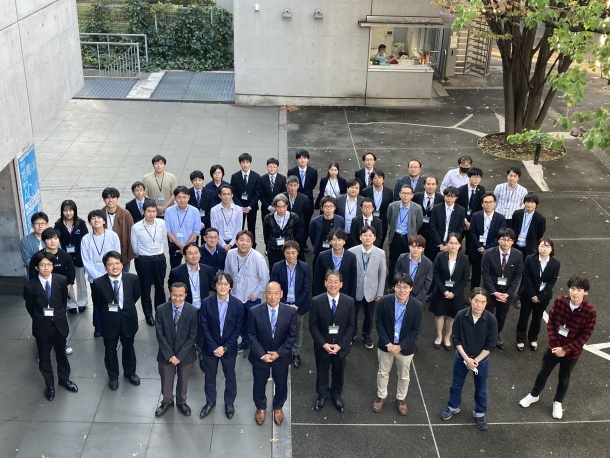- ニュース
- 【開催報告】2023年11月7日「第 9 回電子状態理論シンポジウム―説明可能人工知能 (XAI) 技術の化学研究への展開―」について
【開催報告】2023年11月7日「第 9 回電子状態理論シンポジウム―説明可能人工知能 (XAI) 技術の化学研究への展開―」について

Dates
カレンダーに追加1107
TUE 2023- Posted
- Thu, 14 Dec 2023
第 9 回電子状態理論シンポジウムを早稲田大学西早稲田キャンパスにて開催した。
本年は「説明可能人工知能 (XAI) 技術の化学研究への展開」という副題のもと、本大学から 2 名の講演者と 3 名の招待講演者により講演いただいた。学内からの参加者は 26 名、学外からの参加者は 28 名と盛況のもと行われた。私も講演者の一人として「人間知能による化学原理の発見と説明可能人工知能への期待」と題し、これまでの化学原理の発見と説明可能 AI が化学研究における概念的理解を導くことへの期待について発表した。髙橋氏(北海道大学)には「理解を伴ったインフォマティクス:ブラックボックスからホワイトボックスへ」と題し、ハイスループット実験による新規触媒の発見とオントロジーを用いたホワイトボックス化について発表いただいた。原氏(大阪大学)には「説明可能 AI と決定木」と題し、ブラックスモデルと決定木を併用した、説明可能かつ高精度な「部分的に可読なモデル」について発表いただいた。
金氏(大阪大学)には「説明可能な AI による分子シミュレーションデータ解析の高度化とメカニズムの解明」と題し、遷移状態を正確に記述する反応座標の抽出やガラス転移における構造の識別について発表いただいた。清野氏(早稲田大学)には「説明可能人工知能技術による化学原理・法則の自動創出」と題し、解釈可能な数式の形で現象をモデリングするシンボリック回帰手法の、反応速度論や材料探索分野への応用ついて発表いただいた。本シンポジウムは、XAI 技術を用いた化学研究に関する第一人者による講演により、参加者が XAI に対する理解を深め、新たな知見を得られる有意義なものとなった。本シンポジウムで得られた知見は、プロジェクト研究「計算化学の社会実装」を推進するうえで、大いに役立つものである。