- プロジェクト研究
- 三次元周期π共役化学の開拓を目指した共有結合性有機構造体の創製
三次元周期π共役化学の開拓を目指した共有結合性有機構造体の創製

- Posted
- Fri, 20 Oct 2023
- 研究番号:23C12
- 研究分野:science
- 研究種別:奨励研究
- 研究期間:2023年10月〜2024年03月
代表研究者
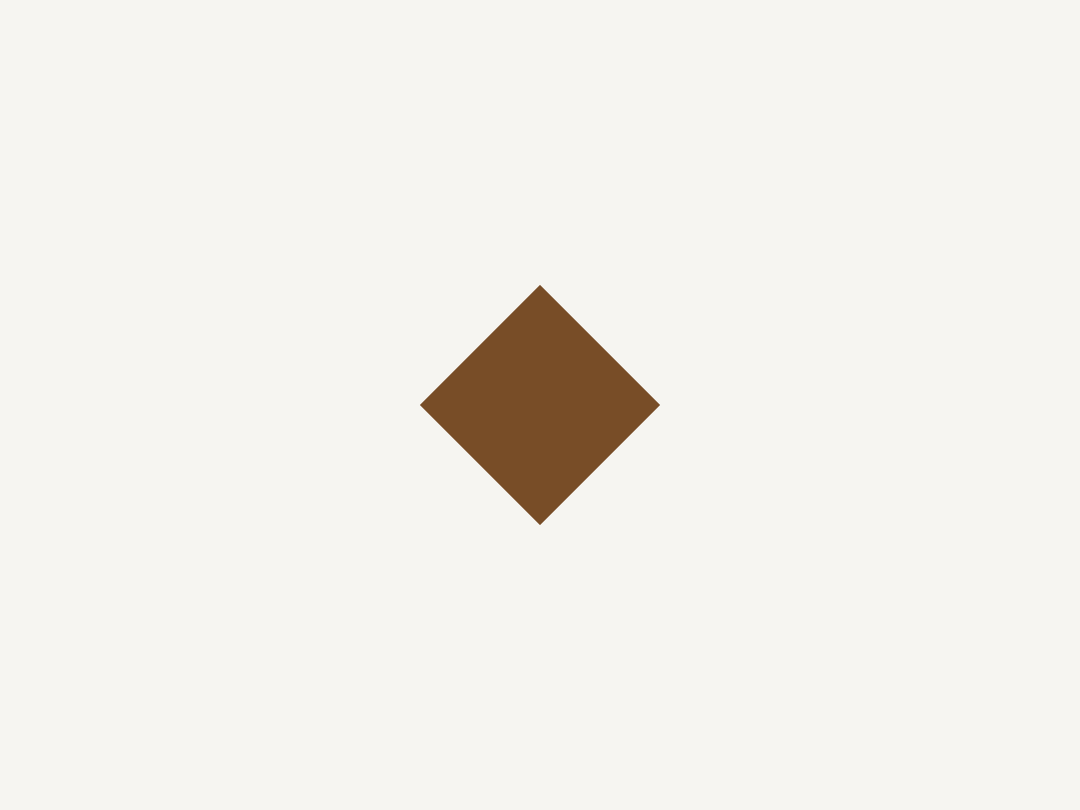
加藤 健太 理工総研が募集する次席研究員
KATO Kenta Junior Researcher
理工学術院総合研究所 山口潤一郎 研究室
Research Institute for Science and Engineering
研究概要
π共役材料の性質は、その繰り返し構造(周期性)に強く依存している。これまで、ナノカーボン類を中心に一次元および二次元の周期性を有するπ共役材料が研究されてきた。一方、三次元周期性を有するπ共役材料は、理論計算が行われているものの、未だ未開拓の研究分野である。そこで、本研究では三次元周期π共役化学の開拓を目的とする。実際には、鞍型アミンおよび平面ケトンから、三次元周期π共役有機構造体を創製し、徹底的な物性解明から三次元π共役系の特異な物性・現象の探索と追究を行う。革新的な基盤材料の創出を最終展開とし、起点となる三次元周期π共役結晶の創製に挑戦する。
三次元的な周期構造を有するπ共役系の構築には鞍型構造が必須であり、また、ユニット同士を最低二本以上の結合で連結させ、同一平面への固定化することが必要となる。そこで、サドル型構造として、すでに報告されている[8]circuleneを選定し、さらに、結合には強塩基条件で平衡反応となるフェナジン構造を用いる。ここで、共有結合性有機構造体(COF)は、他の構造体(分子結晶、金属有機構造体)と比較して結晶性が乏しいことが知られている。そこで、反応条件の際、溶媒や温度、時間のみならず、COFの結晶化が制御できるイオン性添加剤についても検討を行い、高効率での有機構造体の構築を目指す。計画どおりに進まない場合は、鞍型イミンを酸性条件で部分的/完全にアミンへと変換し、結晶化の速度を調節する。もしくは、構成部品のイミンとケトンの交代やもう一回り小さい鞍型イミンおよび平面ケトンの利用も視野に入れる。三次元周期π共役有機構造体の創製と構造解析が完了次第、物性解明を行い、三次元周期π共役のもつ特性の根本理解を進める。
研究が順調に進捗している場合、解明された特性をもとに、基礎物性複合化による高機能材料の創出を目指す。具体的には、遷移金属触媒の担持による担持触媒、フラーレン類との複合化による物性の調製、化学気相成長法(CVD)よる空孔の閉鎖(Mackay結晶と同様に空間を二分できる)による含窒素三次元ナノカーボンへの昇華などに挑戦する。
年次報告
- Tags
- 研究活動 理工総研が募集する次席研究員
