- ニュース
- 【開催報告】シンポジウム「グローバルヘルス法の観点から見たパンデミックに関する各国の法制度の比較検討:現状と課題」が開催されました
【開催報告】シンポジウム「グローバルヘルス法の観点から見たパンデミックに関する各国の法制度の比較検討:現状と課題」が開催されました

Dates
カレンダーに追加0617
SAT 2023- Place
- 早稲田キャンパス内 8号館B107教室 + オンライン(Zoom)
- Time
- 16:00~20:00(JST)
- Posted
- Tue, 11 Jul 2023
シンポジウム「グローバルヘルス法の観点から見たパンデミックに関する各国の法制度の比較検討:現状と課題」
主 催:早稲田大学比較法研究所
共 催:ジョージタウン大学オニール研究所、早稲田大学グローバルヘルス研究所(プロジェクト研究所)
日 時:2023年6月17日(土)16:00~20:00(JST)
場 所:早稲田キャンパス内 8号館B107教室 + オンライン(Zoom)
言 語:日本語、英語(同時通訳あり)
企画責任者:岡田正則教授(早稲田大学法学学術院、比較法研究所所長)、河野真理子教授(早稲田大学法学学術院、比較法研究所所員)
参加者:76名(うち学生23名)

左から河野教授、Dr. Constantin、Professor Ginsbach、棟居教授。
2023年6月17日(土)、早稲田大学比較法研究所は、ジョージタウン大学オニール研究所と早稲田大学グローバルヘルス研究所と共に、シンポジウム「グローバルヘルス法の観点から見たパンデミックに関する各国の法制度の比較検討:現状と課題」を開催しました。このシンポジウムは、新型コロナ感染症のパンデミックを受けて、今後あり得る更なるパンデミックへの対応のために必要な国内法制度及び国際的な制度のありようを検討するために、開催されました。
開会に当たって、岡田正則教授(比較法研究所所長)が開会の辞を述べた後、河野真理子教授(比較法研究所所員)が本シンポジウムの目的と意義を説明しました。
基調講演 Professor Lawrence GOSTIN

最初に、ローレンス・ゴスティン教授(ジョージタウン大学ナショナル/グローバルヘルス法オニール研究所所長)より基調講演をいただきました。ゴスティン教授は、人間の健康、動物の健康、そして環境保護が切っても切れない形で結びついているという認識をもとに、動物の安全・健康と地球環境の保護をも人間の健康を守るための戦略に組み入れるような「ワンヘルス戦略」、ないし「深い予防(deep prevention)」という観点から、将来のパンデミック等の保健上の危機に対処するためのグローバルな体制を作り上げなければならないと議論されました。それは、ひとつには動物由来の新型感染症の発生と蔓延を防止するという観点から動物の健康を守ることであり、また土地の保全や野生動物の違法な取引の規制、生物多様性の保護、気候変動への対応を含むものでもあります。そして、全ての人間の生命と健康を守るために新しい感染症をサーヴェイランスする国際的枠組みを構築するとともに、エクイティの原理に基づいてワクチンや治療薬を分配することも含みます。ゴスティン教授は、これらを実現するためには、グローバルヘルス機関、特にWHOの一層のエンパワメントが必要であると非常に強く強調されました。WHOの資源と能力は、その与えられた任務の大きさに比して明らかに小さ過ぎます(WHOの年間予算は米国CDCの4分の1程度しかありません)。現在の世界では、COVID-19パンデミックが終了したという認識のもと、明らかに慢心のパンデミックが起きています。しかし次なる危機の際に「もう少し健康に、もう少し衡平(equitable)に」対処できないのだとしたら、それはわたしたち全員にとって恥ずべきことです。最後にゴスティン教授は、今そのような十字路にわたしたちが立っていることを認識し、大変革を行う必要があると議論されました。
Session 1: COVID-19の経験とグローバルヘルス法の対応
棟居徳子教授
(早稲田大学社会科学総合学術院、比較法研究所所員)
法的備えを通じてグローバルヘルス・セキュリティを強化する:COVIC-19の教訓
Professor Katherine GINSBACH
(Senior Associate, O’Neill Institute for National and Global Health Law, Georgetown University)
 第1セッション「新型コロナの経験とグローバルヘルス法の対応」では、最初にKatherine Ginsbach教授(オニール研究所)より、「法的備えを通してグローバルヘルス・セキュリティを強化する:新型コロナの教訓」というタイトルでご講演いただきました。Ginsbach教授は、新柄コロナウイルス感染拡大以降、各国が採用した政策を振り返りつつ、パンデミックの最中に(予防ではなく)対応のための法案を作る国々が多かった――しかもその法が不十分なものであったため、変異株の出現に合わせて更に変更されなければならない事態になることさえあった――ため、本来避けられたはずの時間の無駄が発生してしまったという点を指摘されました。法律をつくることには一定の長い時間がかかってしまうものだからです。そして、パンデミックという危機に対応するための法的備えを平時から整えておくこと、しかもパンデミックの性質上その備えは全世界的な形で整備されなければならないということこそが、新型コロナから学ぶべき大きな教訓のひとつであると主張されました。
第1セッション「新型コロナの経験とグローバルヘルス法の対応」では、最初にKatherine Ginsbach教授(オニール研究所)より、「法的備えを通してグローバルヘルス・セキュリティを強化する:新型コロナの教訓」というタイトルでご講演いただきました。Ginsbach教授は、新柄コロナウイルス感染拡大以降、各国が採用した政策を振り返りつつ、パンデミックの最中に(予防ではなく)対応のための法案を作る国々が多かった――しかもその法が不十分なものであったため、変異株の出現に合わせて更に変更されなければならない事態になることさえあった――ため、本来避けられたはずの時間の無駄が発生してしまったという点を指摘されました。法律をつくることには一定の長い時間がかかってしまうものだからです。そして、パンデミックという危機に対応するための法的備えを平時から整えておくこと、しかもパンデミックの性質上その備えは全世界的な形で整備されなければならないということこそが、新型コロナから学ぶべき大きな教訓のひとつであると主張されました。
法的備えの中には、ワクチンや医薬品などの医療資源へのアクセス、迅速なサンプル共有、資金調達の持続可能性の確保、NPIの効果的な実施、機能的な緊急オペレーション、効果的なリスクコミュニケーションなど、多様なトピックがあります。グローバルヘルス・セキュリティを達成するためには、これら全てについて、法的な権限を運用可能な形で予め分配しておくことが必要です。そこでGinsbach教授は、ご自身が関与された「グローバルヘルス・セキュリティ・アジェンダ 法的備えのアクション・パッケージ」について詳細に説明されました。グローバルヘルス・セキュリティ・アジェンダ(GHSA)とは、グローバルヘルス・セキュリティの強化のために各国のパンデミック対応能力を向上させることを目的として、各国とWHO、FAO、OIE等の国際機関とが連携し、WHOの国際保健規則における感染症対策の枠組みを強化する取組みです。GHSAの「法的備えのアクション・パッケージ」は、公衆衛生に関する法的備えの強化に必要な事柄について強固な基盤と共通理解を構築するために、各国と主要専門家を結集させることを目的とするものであり、各国の法的備えの強化を指導・支援する技術的ツールを開発するものです。そこで、公衆衛生上の緊急事態に備えるための法制度、即ち感染症の脅威を予防・検出・対応する上で重要な要素となるような法的手段をマッピング、開発、改良、活用することに注力しています。Ginsbach教授はこの点について詳しく説明された後、特にリーガル・マッピングに各国がどの程度取り組んでいるかなど現在の状況についてご講演されました。
講演後の質疑応答では、特に国際保健規則の実施が国家主権によって阻まれ得るという点に絡めて、その実施の鍵となるものは何かという点について議論がなされました。Ginsbach教授は、国家主権によって本来是正できたはずのものが是正できない点に不満を持っているというご自身の思いを率直に述べつつ、ガイドラインの作成において各国の協力をどの程度確保できるかがひとつの鍵となると述べられました。
COVID-19 パンデミックにおける国際協力と国際的な規則のハーモナイゼーション:パンデミック後の安全な国際クルーズの運航に向けて
河野真理子教授
(早稲田大学法学部、比較法研究所所員)
次に、河野真理子教授(早稲田大学)が「COVID-19 パンデミックにおける国際協力と国際的な規則のハーモナイゼーション:パンデミック後の安全な国際クルーズの運航に向けて」というタイトルで講演しました。河野教授は最初に、新型コロナウィルスのパンデミックの初期の段階で新型コロナウィルスのクルーズ船内での爆発的な感染が問題となったダイヤモンドプリンセス号の事案が示す問題点を指摘しました。そして、感染症対策を十分にした上での国際クルーズの運航のために各国が構築してきたガイドラインやガイダンスの蓄積がもたらすようになっている、安全・安心なクルーズの実現のための国際的な規則のハーモナイゼーションの意義と課題を改めて検証すべきと述べました。
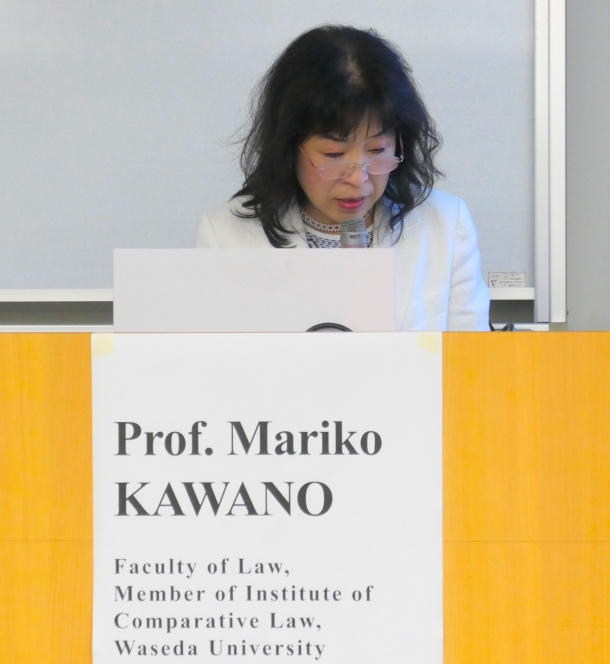 国際クルーズに関する法的対応を難しくしている主要な要因の一つとして河野教授が最初に指摘したのは、国際クルーズの多国籍性です。船主の多国籍性、便宜船籍の問題、船員・職員・部員(以下、クルー)の多国籍性、運航管理会社・代理店の多国籍性、乗客の多国籍性は、国際クルーズの法的な管理や規制において様々な問題を生みます。伝統的な国際法では旗国主義を原則としつつ、寄港国や沿岸国に一定の権限を認めてきましたが、国際クルーズの有効な法的管理や規制に十分な解決をもたらすものではないことが明らかになりました。日本政府はダイヤモンドプリンセス号に横浜港への寄港を認めましたが、政府の権限の範囲について限界や問題点がありました。現在、国際保健規則(IHR 2005)の改正の議論も行われています。また、他の国際機関も感染症のパンデミック時の船舶及び船員の保護についての対策を強化しています。しかし、これらはクルーズ船の安全・安心な運航を特に扱うものとはなっていません。
国際クルーズに関する法的対応を難しくしている主要な要因の一つとして河野教授が最初に指摘したのは、国際クルーズの多国籍性です。船主の多国籍性、便宜船籍の問題、船員・職員・部員(以下、クルー)の多国籍性、運航管理会社・代理店の多国籍性、乗客の多国籍性は、国際クルーズの法的な管理や規制において様々な問題を生みます。伝統的な国際法では旗国主義を原則としつつ、寄港国や沿岸国に一定の権限を認めてきましたが、国際クルーズの有効な法的管理や規制に十分な解決をもたらすものではないことが明らかになりました。日本政府はダイヤモンドプリンセス号に横浜港への寄港を認めましたが、政府の権限の範囲について限界や問題点がありました。現在、国際保健規則(IHR 2005)の改正の議論も行われています。また、他の国際機関も感染症のパンデミック時の船舶及び船員の保護についての対策を強化しています。しかし、これらはクルーズ船の安全・安心な運航を特に扱うものとはなっていません。
こうした中でより注目されるのは、クルーズ産業に関心を持つ主要な国や地域が設けてきた感染症対策のためのガイドラインやガイダンスです。これらは新型コロナ感染症に関する科学的知見の進歩とともに改訂され、呼吸器系の感染症への対策として、またクルーズ産業の特性にも配慮した、優れた内容になってきています。そして、注目されなければならないのは、ガイドラインやガイダンスの改訂の度に他の国や地域のガイドラインやガイダンスが参照されることによって、国際的な規則のハーモナイゼーションが生じているということです。個々の国と地域のガイドラインやガイダンスには一定の共通項を指摘できるようになっています。
第一に、感染症の蔓延を防止するために予防と管理の措置が採られるべきこと、第二に、有効な措置のために、最良の科学的知見とグッド・プラクティスに基づく合理的な対応が必要であること、船上の乗客とクルーだけでなく、寄港地の地域の居住者達も重要な保護の対象であること、安全・安心な運航の実現のためには、政府、地方公共団体、船舶の運航管理者、船舶の船長及びクルー、港湾・ターミナルの関係者、水先人、乗客の協力が不可欠であることを指摘することができます。また、感染症対策としては、クルーズ船の運航開始前に船舶に感染症が持ち込まれることを防止すること、感染者の出ていない通常の運航状態での対策、少数の感染者が出た場合の感染拡大の防止のための措置、そして爆発的な感染が生じた際の対応という段階を区別した対応が必要となります。
最後に、河野教授は、クルーズの安全・安心な国際運航のためには、今後、様々な場合への対応力の強化(preparedness)が鍵となること、クルーズ産業の信頼性と強靭性を高めていく必要があることと、及びこの分野での対応における国際協力が重要性であることが指摘されました。
Session 2: COVIC-19パンデミック後のグローバルヘルス法の新展開
Chair: Dr. Andrés CONSTANTIN
(Acting Director, O’Neill Institute for National and Global Health Law, Georgetown University)
感染症対策の人権影響評価
棟居徳子教授
(早稲田大学社会科学総合学術院、比較法研究所所員)
 第2セッション「新型コロナ・パンデミック後のグローバルヘルス法における新展開」では、最初に棟居徳子教授(早稲田大学)が「感染症対策の人権影響評価」というタイトルで講演しました。棟居教授は最初に、新型コロナ・パンデミックの重要な教訓のひとつは、感染症に対する不安や恐怖が、特定の脆弱な集団に対する暴力や差別、ヘイトスピーチを増長させるため、これに適切に対処する形で感染症対策が組まれなければならないという点にあると議論されました。実際日本においても、ドメスティック・バイオレンスや子どもへの虐待の相談件数が増加し、患者や医療従事者、その他感染リスクの高いと目された人々やその家族に対する偏見と差別が見受けられました。いわばパンデミック期には、それまで社会に存在してきた不平等が一層顕在化したり、悪化したりするわけです。新型コロナの感染率・死亡率は日本でも社会経済的要因に関係しているということも分かっています。非正規雇用者や自営業者、フリーランスの人々、シングル・マザー、低所得世帯、ホームレス、移民・移住者などの社会的弱者が、深刻な状況に陥りました。
第2セッション「新型コロナ・パンデミック後のグローバルヘルス法における新展開」では、最初に棟居徳子教授(早稲田大学)が「感染症対策の人権影響評価」というタイトルで講演しました。棟居教授は最初に、新型コロナ・パンデミックの重要な教訓のひとつは、感染症に対する不安や恐怖が、特定の脆弱な集団に対する暴力や差別、ヘイトスピーチを増長させるため、これに適切に対処する形で感染症対策が組まれなければならないという点にあると議論されました。実際日本においても、ドメスティック・バイオレンスや子どもへの虐待の相談件数が増加し、患者や医療従事者、その他感染リスクの高いと目された人々やその家族に対する偏見と差別が見受けられました。いわばパンデミック期には、それまで社会に存在してきた不平等が一層顕在化したり、悪化したりするわけです。新型コロナの感染率・死亡率は日本でも社会経済的要因に関係しているということも分かっています。非正規雇用者や自営業者、フリーランスの人々、シングル・マザー、低所得世帯、ホームレス、移民・移住者などの社会的弱者が、深刻な状況に陥りました。
棟居教授はこうした点に注目し、L. Gostin教授やJ. M. Mann教授の議論を参照しつつ、感染症対策を人権の観点から評価する枠組み、つまり人権影響評価(Human Rights Impact Assessment)を開発する必要があると議論され、ご自身で開発された日本の文脈での人権影響評価のためのチェックリストを報告しました。人権影響評価は、「その法律や政策、プロジェクトは人権にどのような影響を与えるか」という質問を投げかけるものです。日本でも、2021年2月に改正された新型インフルエンザ等対策特別措置法には、「国及び地方公共団体は、新型インフルエンザ等対策を実施するに当たっては、新型インフルエンザ等に起因する差別的取扱い等……及び他人に対して差別的取扱い等をすることを要求し、依頼し、又は唆す行為が行われるおそれが高いことを考慮して、新型インフルエンザ等の患者及び医療従事者並びにこれらの者の家族その他のこれらの者と同一の集団に属する者……の人権が尊重され、及び何人も差別的取扱い等を受けることのないようにするため、新型インフルエンザ等患者等に対する差別的取扱い等の実態の把握、新型インフルエンザ等患者等に対する相談支援並びに新型インフルエンザ等に関する情報の収集、整理、分析及び提供並びに広報その他の啓発活動を行うものとする」という規定(13条2項)が盛り込まれ、人権影響評価の実施が求められます。
棟居教授が人権影響評価のチェックリストは以下の通りです:1. 感染症対策、2. 健康管理、3. 社会保障、4. 十分な生活水準、5. 住宅・居住、6. 雇用と労働安全衛生、7. 教育、8. 情報へのアクセス、9. プライバシー、10. 差別、暴力、ハラスメント、11. 拘禁施設等での処遇、12. 緊急事態宣言および緊急措置。
1. 感染症対策においては、例えば以下のような質問が投げかけられ、法政策を評価するための論点が示されることになります:感染症対策の策定・実施過程において、脆弱な人々や取り残される危険性の高い人々が特定されているか。パンデミックに関連する匿名化され、細分化されたデータ(性別、年齢、民族、国籍、障害別など)が収集され、一般に公開されているか。対策の策定・実施過程において、ジェンダーに関する分析が行われているか。
講演の最後に棟居教授は、次のパンデミックに向けた課題として、人権影響評価の能力向上のために学際的なネットワークを構築する必要があること、また、人権影響評価の実施に向けた責任の明確化と体制強化が必要であることを述べられました。
人新世におけるプラネタリー・ヘルスへの道:人間の安全保障に基づいて
勝間靖教授
(早稲田大学大学院アジア太平洋研究科、グローバルヘルス研究所所長)
第2セッションの最後に、勝間靖教授(早稲田大学)が「人新世におけるプラネタリー・ヘルス(planetary health)への道と人間の安全保障」というタイトルで講演しました。勝間教授は、現在の地球は、人類の活動を原因とする、地球環境の限界(planetary boundalies)を超えるような大きな変化に直面していると主張しました。人新世の時代にあるという認識に基づき、こうした時代にあってヒトの健康、動物の健康、そしてそれらを支える生態系が脅かされており、健康上の危機は増大していると述べました。そして、将来世代への配慮を含め、プラネタリー・ヘルスという観点から人類の活動を検証しつつ、複合的な脅威にさらされる人間の安全保障を再構築することで、地球環境の変化がもたらすグローバルヘルス上の危機に対処していく必要があると議論されました。

Panel Discussion: 新しい感染症パンデミックへの対応に必要とされる法的システム
シンポジウムの最後に、登壇者全員で、「新しい感染症パンデミックに対応するために必要とされる法的システム」というタイトルでパネル・ディスカッションを催しました。その中で河野教授からは、特にダイアモンド・プリンセス号での出来事を踏まえつつ、科学的知見を実践的な指針に変えていく上で法学者が非常に重要な役割を果たしていなかければならないこと、Constantin博士からは、NCDsの予防についてソフトローの様々なツールを使用していく必要があること、そして棟居教授からは、人権影響評価のターゲット・グループには国や地方公共団体のみならず特にメディアなどの様々なグループが含まれていることが説明されました。またHalabi教授に対しては、ワンヘルス・アプローチには患者への直接的なアプローチが欠けているのではないかという質問がなされ、この点について議論がなされました。
ディスカッションの後、Constantin博士より閉会の辞が述べられ、早稲田大学比較法研究所とジョージタウン大学オニール研究所との間での今後の更なる学術的な協力への期待が述べられました。

(文:松田和樹・比較法研究所助手)

