【生物学専修】「植物形態学・実験」/ 受験生のみなさんへ

- Posted
- 2020年8月24日(月)
科目情報
- 科目名 :植物形態学・実験
- 科目区分:2年必修
- 執筆者 :佐藤 朱音(理学科生物学専修)
生物学の重要な分野「形態学」を、足元から学ぶ
私たちの身の回りにはたくさんの植物が存在しています。家の庭やベランダに生えている植物、よく通る道のアスファルトから顔を出す花。スーパーで売られている野菜だってもちろん植物です。ただし、特別に“植物”と意識することはないでしょう。特に道端の植物なんて素通りされてしまいます。今回紹介するこの「植物形態学・実験」という科目では、その一つ一つが大切な試料であり、履修後には面白さまで感じられるようになります。
生物の形態とそれが持つ機能は、密接に関係しているため、形態を知ることは生物学の様々な分野に繋がる重要な視点です。「形態学」は生物の外形や組織など、目視で確認できる形態の特徴を、記述・測定し比較する学問分野です。この「植物形態学・実験」では、植物の形態の観察を通して植物の生物学的な理解を深めること、並びに、道端の草木に“面白さ”を感じ、何が面白さにつながっているのかを理解することの2点を全体目標として、様々な実習が進められました。
「葉の外部形態」「花のつくり」を学ぶ実習では、近所の河川敷に生える植物やマンションの花壇の植物の葉・花のつくりを観察したり、「果実」の実習では、自分で試料を選択・購入し、市販のキウイフルーツ3種間で形態にどのような違いがあるのかを考察したりしました。最終回では、それまでに学んだテーマから各履修者が好きなものを選択してレポートを作成しました。私は「果実」をテーマに選び、グリーンキウイとゴールデンキウイについて、詳細な観察・統計的解析・複数個での比較といった定量的手法を用いてレポートを作成しました。(16個のキウイを観察して、各部分を計測して、種子を約1万1千個も数えたのは初めてでした…)
実習開始当初は、植物にあまり興味がなかったのですが、今では道端で「あの葉の構造、どうなっているのだろう」と思えるくらいに興味津々です。自分の元々の興味を超えて、幅広い視野で生物学をとらえることは、自分の興味関心を広げ、新たな知見を得るだけでなく、身近なものの見方まで変えてゆくのだと感じました。

計測結果はExcelだけでなく写真にも残しました
受験生の皆さんへ:焦っても仕方がない
困難な状況だとしても、焦ってしまっては今までの自分の頑張りがうまく発揮できません。実際、1年の浪人生活を経ても、本番ではもちろん緊張するし、焦りました。満足いかない部分が多く、試験が終わり、外に出た時に泣いてしまったこともあります。(ちなみに早大教育の本番でした…)受験生活を経て感じるのは、不安を感じて焦ってしまい、事前の準備を怠ってしまっては、本末転倒だということです。不安や焦りを感じているのならば、その分、事前準備を人一倍行って受験に挑みましょう。
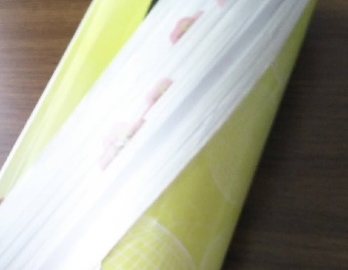
付箋を貼り何度も見返してボロボロにした予備校のテキスト
- Links
- オンラインオープンキャンパスに戻る

