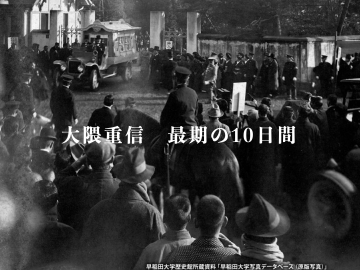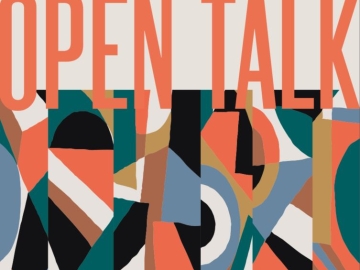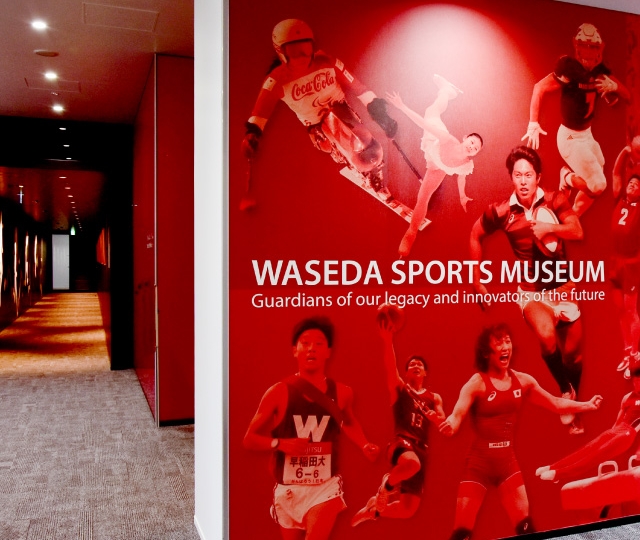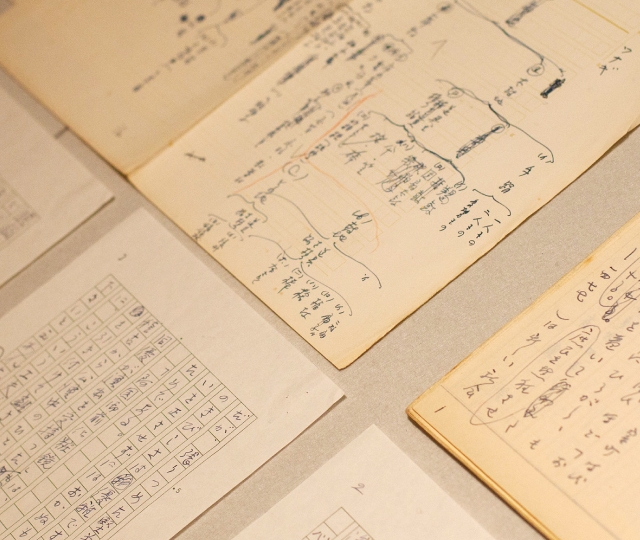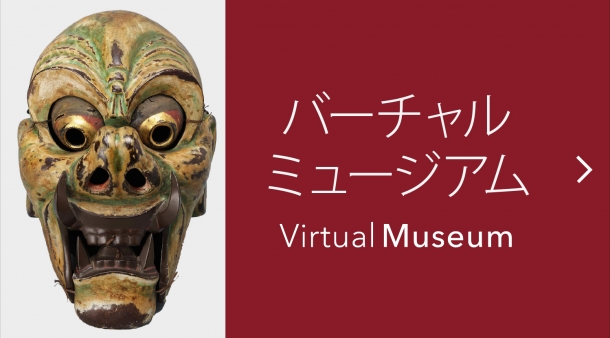本国際シンポジウムは、近世江戸・明治日本と中国明清の書物交流と博物書写に焦点を当て、蔵書、経学、デジタル歴史学の視点からアプローチし、異なる国々や文化が越境して交流し、書物や知識と文化が共有された過程を探求します。
近世江戸から明治以来、日中両国の知識人は異なる背景や言語を持ちながらも、漢籍の書物や知識の交流を通じて相互に学び合いました。このシンポジウムで、それらの過去の交流を振り返り、現代の学術研究にどのように影響を与えているかを深く理解し、未来への洞察を議論する場を築き上げたいと考えます。
また、蔵書、経学、デジタル歴史学の視点と手法を通じて、古典籍・歴史文献の保存とデジタル化、物質文化、及び歴史遺跡を考証することの重要性と価値を再評価し、デジタル技術を運用して歴史場景を再現します。学術的議論と交流を促進し、人文学の発展と新たな視野の拡大に貢献することを目指します。
内容
- 日時:11月18日(土) 13時20分~18時30分(開場12時30分)
- 会場:早稲田キャンパス14号館B101(正面階段を下りてください)
- 言語:日本語、英語
- 参加:学生、教職員、一般、どなたでも無料で参加できます。当日参加も可能ですが、事前登録をするとスムーズにご入場できます。
- 主催:柳井イニシアティブ グローバル・ジャパン・ヒューマニティーズ・プロジェクト
- 共催:早稲田大学総合人文科学研究センター
- 後援:中央研究院歴史語言研究所・中央研究院ASCDCデジタル文化センター
登壇者
陳熙遠
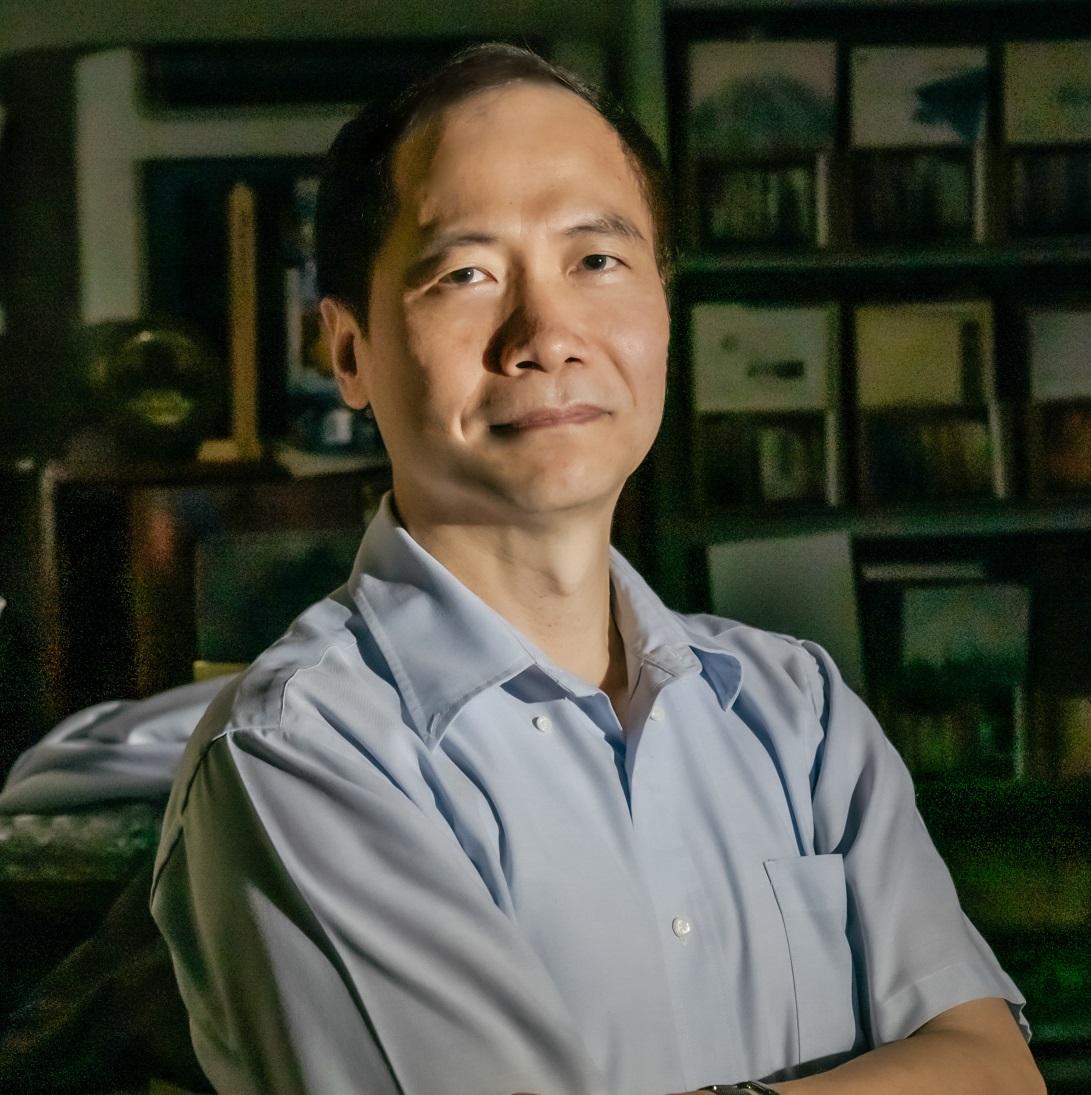
ハーバード大学で歴史と東アジア言語の博士号を取得。現在、台湾中央研究院歷史語言研究所の教授、および、台湾中央研究院デジタル文化センター(ASCDC)のセンター長を兼任。主な専門分野は歴史的な文献研究で、古文献を入念に調査し公文書と私文書を並べ立てて重要な歴史的洞察を明らかにしている。研究の中心は、国家の信仰と一般的な宗教との相互作用、地方と中央政府間の情報伝達の複雑なメカニズム、そして後期中国帝国時代のさまざまな文化変容のダイナミクスが含まれる。特に、中国明清時代における皇帝勅令の制定と普及、文化的景観の複雑な進化、長江の地理的な形成の変化、および明清時代の変換期における地方説教による儒教の大衆化に焦点を当てている。
陳捷

東京大学大学院人文社会系研究科教授。北京大学中国語言文学系修士課程を修了後、同大学で専任講師を務め、1994年に来日。慶應義塾大学附属研究所斯道文庫、東京大学東洋文化研究所で研究に従事し、1995年東京大学大学院人文社会系研究科アジア文化研究専攻(東アジア思想文化専門分野)博士課程に入学。2001年博士号取得。日本女子大学人間社会学部文化学科助教授や国文学研究資料館研究部教授などを歴任し、2017年より現職。日本と中国の書籍文化・学術交流史を研究している。
林玟君

早稻田大学柳井イニシアティブ研究員。2020年5月からは台湾中央研究院歴史言語研究所デジタル文化センターで博士後、研究員・学術出版編集・デジタル博物館学芸員を務め、同年、台湾師範大学中国古典文学(文献学)の博士号を取得。2021年から2023年3月までは日本独立行政法人国際交流基金(The Japan Foundation)の招聘研究員として、慶應義塾大学文学部で和漢書誌学の研究に従事。文献学・版本学・目録学・和漢書誌学、和漢古典文学、書道と写本文化、デジタル人文学を研究している。主な論文に「日本図書情報学と目録学における中国の「文」と「集」の位置—明清・江戸時代の出版物を例として」(2023年)、「Research and Construction of Ancient Bookstores: Examination of the Early Modern Ming-Qing and Edo Periods, Environmental Buffering Analysis, and Temporal-Spatial Scenes」(2023年)、「『李卓吾批点世説新語補』の版本系統ついて-補刻、覆刻、後印、彫版字様学の手掛かりから-」(2023年)などがある。
住吉朋彦
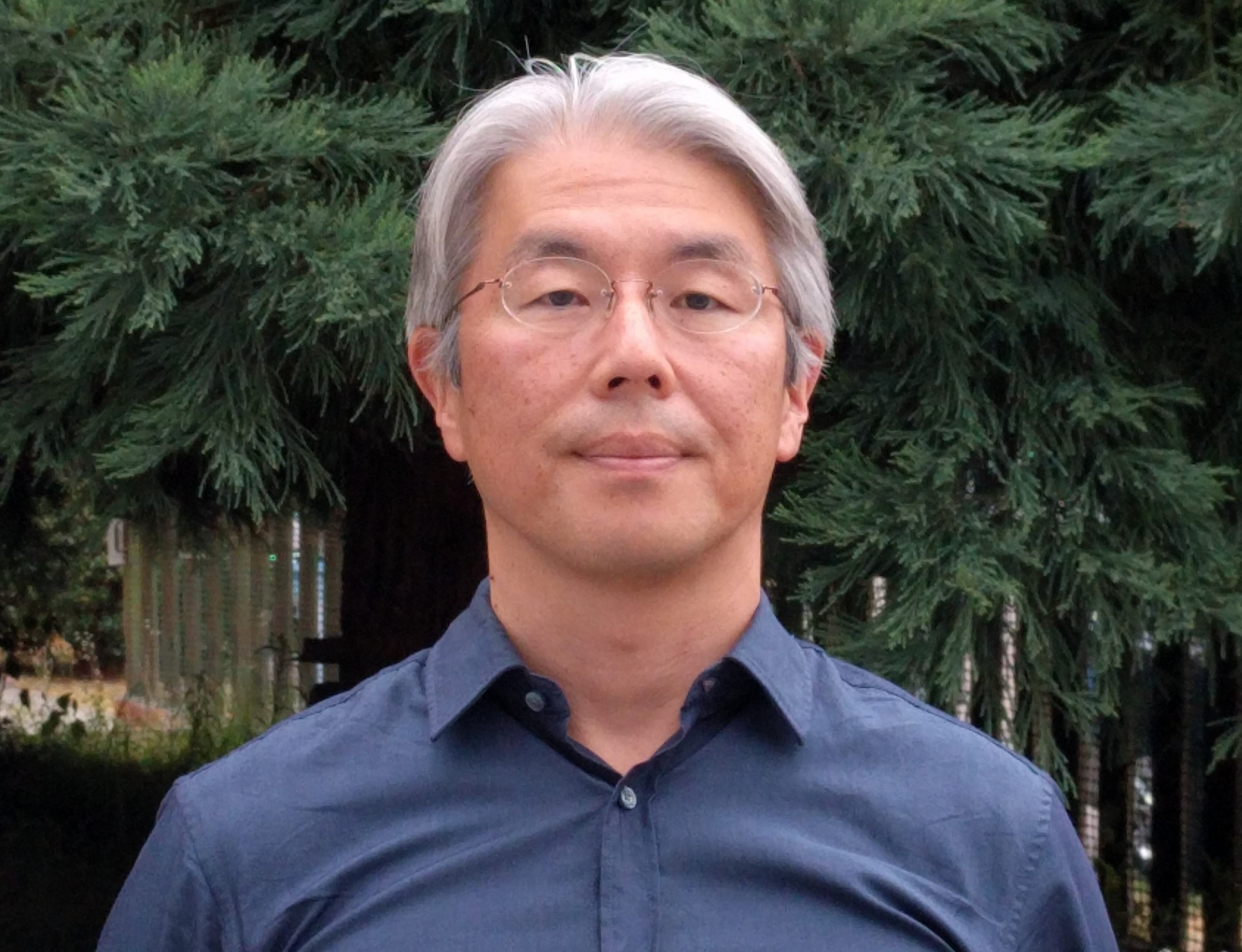
慶應義塾大学附属研究所斯道文庫教授。宮内庁書陵部図書調査室員を経て現職。東洋書誌学専攻。日本に数多くのこる典籍を、東洋文化の粹と捉え、時代とともに変化する姿や、国を越えて流通したいきさつを調べ、その背景を考えている。著書に『中世日本漢学の基礎研究 韻類編』(汲古書院)、編著に『図書寮漢籍叢考』(同)があり、現在、陳捷講師、矢島明希子講師とともに研究プロジェクト「在米日本漢籍の蔵書学―今関天彭蒐集書を事例として―」および「江戸幕府紅葉山文庫の再構と発信―宮内庁書陵部収蔵漢籍のデジタル化に基づく古典学―」を進めている。
矢島明希子

慶應義塾大学附属研究所斯道文庫専任講師。慶應義塾大学文学研究科東洋史学専攻博士課程で中国古代の文化史を研究し、2017年単位取得退学。同年、博士号取得(史学)。博士課程在籍中は古代史と平行して斯道文庫にて書誌学を学び、2014年から2年間同文庫の研究嘱託を務めた。2017年に同文庫の助教に就任、2021年より専任講師。専門分野は漢籍書誌学、中国古代文化史。主な論文に「日本における『毛詩草木鳥獣虫魚疏』の受容―国書中の引用に関する調査」(斯道文庫論集』第55輯、2021年)などがある。
工藤卓司

広島大学文学部人文学科卒、同大学大学院文学研究科博士課程修了。博士(文学)。国立台湾大学中国文学系、中央研究院中国文哲研究所、国立清華大学中国文学系の博士後、国立台湾師範大学等での非常勤講師、台湾・致理科技大学応用日語系副教授を経て、現在は県立広島大学地域創生学部准教授。専門は中国思想・経学・日本漢学。主著『近百年来日本学者《三礼》之研究』(2016年)、翻訳書として、黄俊傑著『徳川日本の論語解釈』(2014年)・『儒家思想と中国歴史思惟』(2016年、共訳)・『東アジア儒家仁学史論』(2022年、共訳)及び黄進興著『孔子廟と帝国―国家権力と宗教』(2020年)・『義理学から倫理学へ—清末民初の道徳意識の転化』(2023年)がある。
コメント・ディスカッション
河野貴美子
早稲田大学文学学術院
山本聡美
早稲田大学文学学術院
シンポジウム
13:20 開会挨拶・Michael Emmerich(柳井イニシアティブディレクター/文学学術院)
~第一セッション~
13:30 発表1・陳熙遠「“Learning of the Sages” as “Learning of the People”: A Newly Uncovered Text on the Community Covenant and Mass Confucianism during the Ming-Qing Transition」
14:00 発表2・矢島明希子「『詩経小識』の諸伝本について―写本に見る知的ネットワーク」
14:30 発表3・工藤卓司「日本徳川時代「三禮」研究概況序説」
15:00 休憩
15:15 コメントとディスカッション・河野貴美子
~第二セッション~
15:50 発表4・住吉朋彦「UCLA 東アジア図書館所蔵の今関天彭旧蔵漢籍について―旧蔵書研究の視点から―」
16:20 発表5・陳捷「清末における安井小太郎の北京体験について」
16:50 発表6・林玟君「江戸・明清の書誌データと蔵書文化の3次元図景の再現について」
17:20 休憩
17:45 コメントとディスカッション・山本聡美
18:15 閉会挨拶・十重田裕一(柳井イニシアティブディレクター/文学学術院)
18:30 閉会
注意事項
講演中、主催者側で記録のために写真を撮ります。
ウェブサイト等に掲載する可能性がありますので、気になる方がいらっしゃいましたらスタッフまでお声がけください。
お問合せ
早稲田大学柳井イニシアティブ:[email protected]