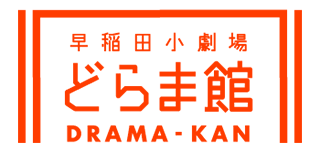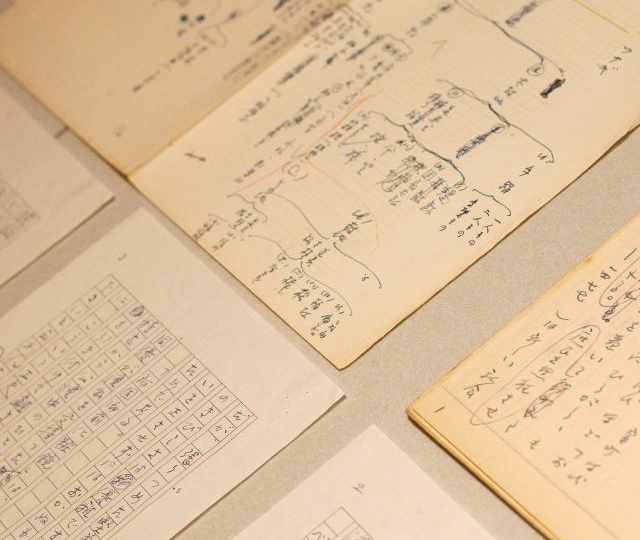3月2日(水)〜6日(日)の5日間にかけて、早大演劇サークルOBOGの方々を講師に迎えた5つのワークショップを開催予定でしたが、関係者から濃厚接触者が出てしまったため、WSは3日間のみの開催となりました。
今回は、開催した3日間の体験レポートを紹介します。
第三弾は、教育学部2年の清水美希さんのレポートです。
どらま館学生リポート 中島梓織「台詞を発することだけで「アクション」シーンをつくってみよう」
教育学部 2 年 清水美希
話し合って演劇を創り上げる楽しさ
今回私は、劇団献身の奥村徹也さんご提案のもと、早稲田小劇場どらま館が開催した「繋ぐ。OBOG ワークショップ」の「台詞を発することだけで『アクション』シーンをつくってみよう」に参加させていただきました。講師を務めてくださったのは、中島梓織さんです。演劇倶楽部出身で、現在演劇団体「いいへんじ」で劇作家、演出家、俳優として活動されています。私自身、演劇サークルに所属していませんでした。しかしながら昨年から演技を習い始めていたため、実践的で勉強になると思い、参加することにしました。
今回のワークショップでは、キャラクターから演技ができるのではなく、演技からキャラクターがつくられる、ということを実感することを目的に、「アクショニング」を用いながら台本を使用したお芝居をしました。「アクショニング」とは、具体的なイメージが掴みにくい台詞を、誰に何をするかを明確にした動詞に置き換えて読むことです。印象に残っているお話は、「コーヒーいかがですか。」には何通りもの意味を持たせられるということ。素直に読めば店員が客に勧める場合になりそうだが、男性が女性を誘う場合、上司が部下に休憩を促す暗示の場合など、台詞の裏には様々な状況が想定される、というお話を聴きました。何となく言うだけでは、当然ながら観客に伝わるリアルな演技にはならない。対象とより具体的な動詞を使って表す「アクショニング」は、想像を膨らませるための良いツールになる、という中島さんの考えを深く理解することができました。
後半ではこれを踏まえて、参加者全員で一つの戯曲台本を使ってお芝居をやりました。一人一役担当し、最初に何もしない状態で読み合わせました。その後各々が「アクショニング」したい台詞を選んで話し合いながら練習しました。私が選んだ台詞は「なに」。とても短い台詞ですが、それゆえに安易に発するべきではないと思ったからです。文脈上は喧嘩を買うように感じた、ここまでの展開もよく整理しなければならない、相手との関係性はどうか、などと様々なことを話し合いました。直接絡む相手はもちろん、あまり接点がない役の方とも意見交換しました。議論を重ねていく中で、段々とイメージが定まってくる過程がとても
面白かったです。話し合いの結果、相手に返事をする、に決定。最後に全員で通してやってみて、読み合わせと比べて人物同士の距離感や関係性が具体的になったように感じました。
大切なのは、とにかく話し合ってイメージを固めること。これが、演技からキャラクターをつくる過程であり、「台詞を発するだけで『アクション』シーンをつくる」ことになるのだと思いました。これまで私は、台詞を独りよがりな解釈で読みがちでした。しかしワークショップを通して、色々な人と考えをすり合わせる中で表現は自然と決まってくるものだ
と思いました。「アクショニング」を学んだだけでなく、一つのものをみんなで創り上げることの楽しさを実感することができました。
また、私は今まで早稲田演劇にはあまり触れることはありませんでした。しかし今回、早稲田演劇サークル出身の卒業生、現在在籍中の参加者とも楽しく交流でき、早稲田演劇への興味も湧いてきました。これを機に、演劇の公演を見に行ったり、今後のどらま館の活動にも参加したり、などしてみたいと思います。