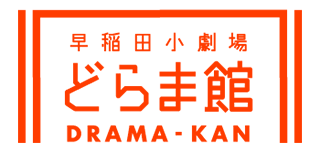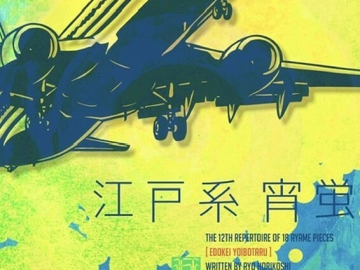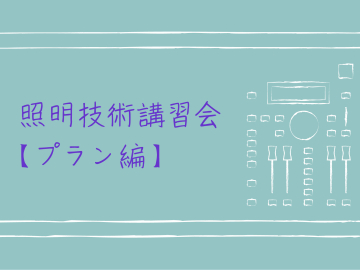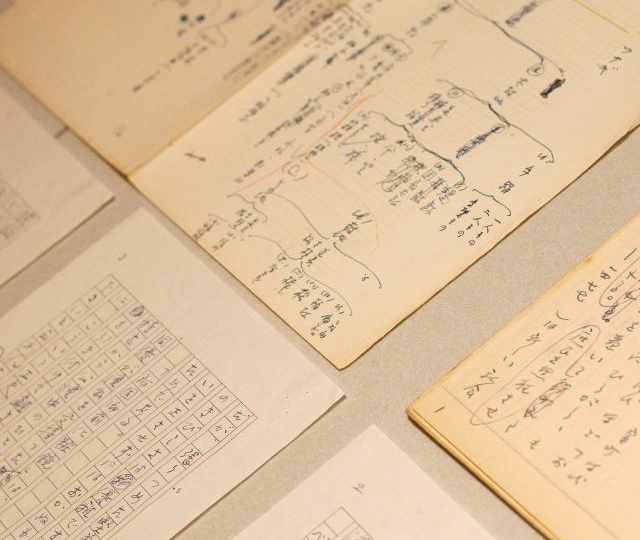企画概要
12/19に「演劇におけるジェンダー・セクシュアリティ研修会 〜安全な稽古場運営のために〜」を開催しました。
当日は、早稲田大学GS(ジェンダー&セクシュアリティ)センター監修のもとGSセンター専門職員の向坂あかねさんに解説いただき、8名の参加者とともに、演劇の文脈でジェンダー・セクシュアリティについて話し、考えました。
(詳細はページ下部のリンクからご覧いただけます。)
開催報告
まずはじめに、グループでのおしゃべりから。「ジェンダー規範の強化やジェンダー非同調性を貶める風潮などが、演劇界において改善されてきたケース」「稽古場・制作過程・作品の中でジェンダー規範が強く表れる場面」について、思いつくものなどを気軽に共有していきます。
このおしゃべりを通して、演劇創作の当事者としてのジェンダーに結びつく経験を、それぞれが思い出し、かつ共有することができました。
続いて、ジェンダー同調性と非同調性・ジェンダー規範・性の多様性についての基礎的な概念や表現方法について、時間をかけてレクチャーを確認・共有しました。
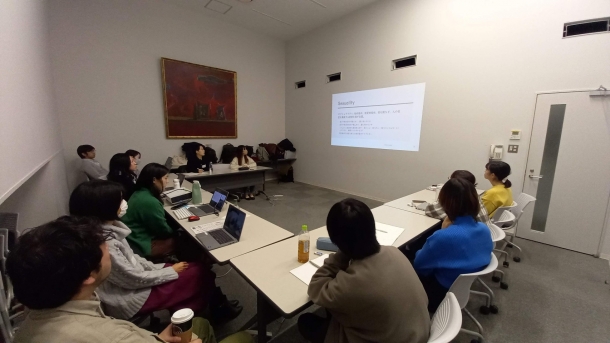
(レクチャーパートの様子)
最後に、もう一度グループでのおしゃべりを行います。そこでは、はじめのおしゃべりで提出された「ケース」「場面」およびレクチャーパートで学んだ内容の三つを総合して、「稽古場・制作過程・作品の安全性を高めるためにできること」についてグループで意見を出し合い、全体で共有していきました。
このパートを通して、演劇の現場でこれから実際にどのように行動できそうか、またはその行動にはどんな難しさがありそうか、といったアイデアを、参加メンバーから発想することができました。
全体を通して、ジェンダー・セクシュアリティに関わる知識面での学びはもちろん、悪い事例だけでなく行動によって改善されてきた事例もあるということ、演劇に作り手として関わる自分たちだからこそそれらに続いて作る現場の安全性を高める行動を取ることができるということへ、気づきを得られました。また、参加者が互いの存在を認識し合い、それぞれの問題意識を共有できたことも、大きな効果だったように思います。
開催を終えて
改めまして、企画段階から開催に至るまで多大なご協力をいただいたGSセンター職員の向坂さん、白戸さんへ、そして当日参加していただいた皆様へ、深く感謝を申し上げます。
どらま館では、演劇でのよりよいコミュニケーションを考えるための企画を引き続き開催していきます。その上で今回のようなジェンダー・セクシュアリティに焦点を当てる機会も継続的に作っていけるようにしたいと考えています。
演劇に関わる多くの方が、少しの間一緒に立ち止まって考え、創作をより豊かにしていけるような機会を拵えていきますので、今後もチェックしてくだされば幸いです。