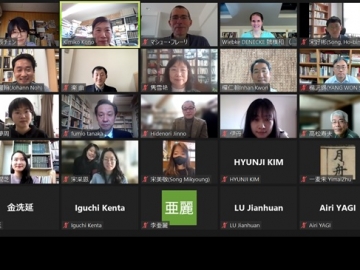2023年3月1日(水)、早稲田大学戸山キャンパス33号館232教室において、第2回国際ワークショップ「東アジア古典研究のグローバル化を目指して―古典翻訳の現在と未来 SECOND INTERNATIONAL WORKSHOP: How to Globalize Premodern East Asian Studies? The Present and Future of the Translation of Classical Literatures」を開催した(一部登壇者のみハイフレックス方式)。

本ワークショップは、昨年度より継続して進行中の『日本「文」学史』(勉誠出版、2015~2019年)の中国語訳プロジェクトを起点として、早稲田大学文学学術院河野貴美子とマサチューセッツ工科大学社会科学芸術人文学部のWiebke Deneckeが企画したものである。ワークショップでは、まず河野貴美子が、ワークショップ開催の背景について、昨年、『日本「文」学史』の中国語訳、韓国語訳、そして英訳についてのワークショップを開催したのに続き、今年のワークショップは、中国語訳や韓国語訳の翻訳作業を通して得られた知見や課題のうえに、古典の現代語訳の問題も加え、さらにはMITを中心として取り組みが進められている東アジア漢文学の英訳プロジェクトについて紹介、報告を行い、東アジアの古典研究のグローバル化のあり方についてのディスカッションを企図するものであることを述べた。続いてMITのWiebke Denecke教授により、東アジアの古典翻訳をサポートする体制や良質な翻訳の不足が憂慮されること、しかしながら将来において新たな文学を生み出していくためにも、翻訳および現代語訳に関する十分な議論が必要である旨、ワークショップ開催の目標について説明がなされた。

ワークショップでは、6つの話題について報告がなされた。
まず報告1は、『日本「文」学史』の中国語訳に携わっている清華大学大学院の徐夢周氏、曾堰杰氏による報告であった。徐氏は、日中の同形語の翻訳方法について、曾氏は固有名詞や学術用語、また引用文の翻訳方法について、翻訳の実践を通して得られた知見について考察し、発表を行った。
また報告2では、『日本「文」学史』の韓国語訳に携わっている高麗大学校の魯耀翰研究教授が、翻訳者の視点からみた当該書物の特徴等について述べた。
次に報告3では、高麗大学校の沈慶昊特勲教授、楊沅錫副教授により、韓国の漢文学の現代語訳の状況や支援体制、および将来の目標についての報告がなされた。具体的には、伝統文化研究会、韓国研究財団、韓国古典翻訳院など、韓国における翻訳事業を推進する機関の取り組みについて、数々のデータに基づき、その成果や課題が詳しく披露された。
報告4では、北京師範大学講師の楽曲氏が、日本漢文学の現代語訳について、これまで全体像が把握しにくかった状況を整理して示し、また今後は網羅的な目録の作成が望まれることを提言した。

また報告5では、早稲田大学総合研究機構日本古典籍研究所招聘研究員の蒋義喬氏が、日本古典文学の中国語訳について、既発表作品がリストアップされ、また、現在中国においては日本をはじめ外国の著作の翻訳を支援する仕組みが十分ではないこと、翻訳に際しては訳者の母語の水準が求められることを述べた。
最後に、報告6では、MITのWiebke Denecke教授が、Oscar TangとAgnes Hsu-Tangからの多額の寄付により永続的に寄付され、今秋に最初の巻を刊行する、東アジアの三千年の漢文学遺産を英訳する漢・英バイリンガル翻訳シリーズHsu-Tang Library of Classical Chinese Literature(徐唐文苑)のビジョンと意義について発表した。この翻訳シリーズは、学術的でありながら読みやすい、文学性のある翻訳を目指し、東アジアの漢文学遺産を、印刷物やオンラインで世界中の読者に届けるための強力なプラットフォームとなることを目指している。
これらの報告を受け、『日本「文」学史』中国語訳プロジェクトを推進している清華大学の雋雪艶教授の講評に続いて、登壇者相互、あるいは会場参加者からの質疑応答が活発に行われた。翻訳に際して、いずれの著作をその対象とするかということ自体に、さまざまな思考が含まれること、古典の有する複雑さを残しつつ翻訳はなされるべきとの指摘など、数々の示唆を共有しつつワークショップは閉じられた。

なお本ワークショップは、早稲田大学総合研究機構日本古典籍研究所、スーパーグローバル大学創成支援事業早稲田大学国際日本学拠点の主催、MIT School of Humanities, Arts, and Social Sciences(マサチューセッツ工科大学社会科学芸術人文学部)、早稲田大学総合人文科学研究センター角田柳作記念国際日本学研究所、科学研究費助成事業(学術研究助成基金助成金)(基盤研究(C)20K00303)の共催により行われた。
(文責:河野貴美子)
参加者感想
韓国漢文という言葉が出ましたが、そういった資料も読んでみたいと思いました。(日本語への影響がより明らかにされるのではないか。)また、Hsu-Tang Library of Classical Chinese Literatureの設立構想は素晴らしいと思いました。そこで、古典翻訳の需要が少ないという問題と、誰が翻訳するのかという問題が提示されました。古典に対する意識を高めるためにはどうしたら良いのか、また、古典翻訳のできる翻訳者の育成などの可能性も考えてみました。 (高橋憲子)
今回のワークショップでは、前回に引き続き、翻訳に携わっている方の様々な視点から見た翻訳の課題を知ることができ、とても勉強になりました。翻訳に際しての同形語や語順の変換や、適切な意訳などの問題、そして文体の流麗な訳本がより多く読まれる現状を通して、訳者には高い目的言語のスキルが問われることを改めて感じました。そして徐唐文苑のように、あえていわゆる「正典」ではなく、パロディー作品を翻訳対象にピックアップしたり、世代を跨って翻訳作業が行われるであろう『資治通鑑』の全訳が計画されたりする一方、研究者の方々からは「翻訳では食べていけない」「翻訳は業績にならない」との声も多く上がっていて、古典翻訳の再評価の必要性を痛感しました。(馮辰鋮)
本日のワークショップでは、まず『日本「文」学史』一書の中国語訳、韓国語訳の作業にまつわる問題点と実践とその具体例が共に取り上げられ、特に日本語の「場」という語をどう的確に訳すか、学術的なテキストを翻訳する時、精確さと表現の豊かさを両立させる工夫について実感しました。また、先生方のご報告で漢字文化圏における機構や取り扱うテクストの現状や改善すべき問題点を知ることができ、「研究者同士のための翻訳」「一般な方向けの翻訳」「文学作品と学術的情報の翻訳」「翻訳者の待遇」など、抽象的な概念から具体的な措置まで伺うことができました。 (シュ イチバク)
イベント概要
- 日時:2023年3月1日(水)9:50~12:40 (JST)
- 会場:早稲田大学戸山キャンパス 33号館 232教室(対面)
- 言語:日本語
- 参加:学生、教員、一般
- 参加費:無料
- 主催:早稲田大宅総合研究機構日本古典籍研究所、スーパーグローバル大学創成支援事業 早稲田大学国際日本学拠点
- 共催:MIT School of Humanities, Arts, and Social Sciences (マサチューセッツ工科大学 社会科学芸術人文学部/早稲田大学総合人文科学研究センター角田柳作記念国際日本学研究所/科学研究費助成事業 (学術研究助成金)(基盤研究(C) 20K00303)