今年度は3名のジョイントアポイントメント教員の他、夏学期には5名の訪問教員による正規授業が行われました。その中のお一人である郡山教授は、内外の複数の大学(東京大学、シカゴ大学、エコール・ポリテクニーク等)で学び、研究活動を行い、そして現在はフランスのエコール・ポリテクニークで教鞭を取られています。郡山教授には2018年度から政治経済学術院において、隔年で「ゲーム理論とその経済学への応用」、「マーケット・デザインとインスティチューショナル・デザイン」の授業を担当して頂いています。今年も多くの学生がこの授業に関心を持ち、より良い社会形成のための制度設計について学習しました。受講生は留学生も多く、これから海外の大学に留学を予定している学生も含まれており、まさにグローバルで多様な学びを実践するクラスです。
郡山教授には昨年(関連記事1)同様インタビューにお答えいただきました。指導の内容や目的について丁寧にご説明頂くだけでなく、ご自身の研究テーマについても語って頂きました。そして、最後にはより良い社会の探求に向けて、本学の学生へのエールも頂きました。
1. 昨年と同様になりますが講義の内容について教えて下さい。(講義の目的、目標達成度、講義内で使用した教材等)
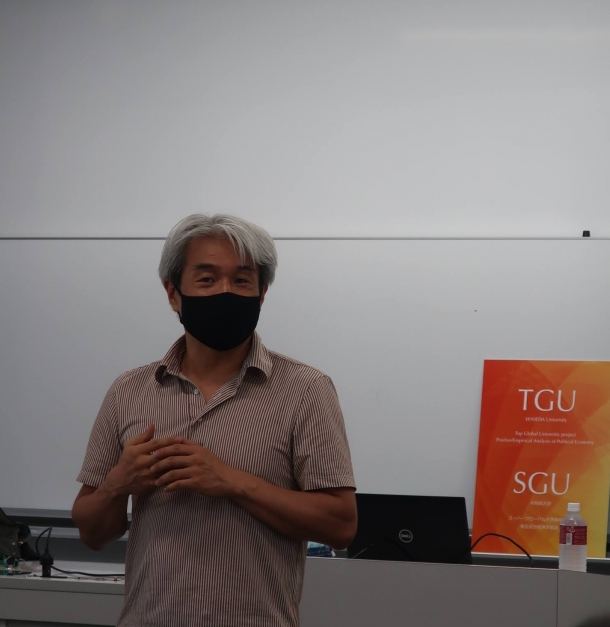 この講義では、マーケット・デザインとインスティチューショナル・デザインについて学びます。マーケット・デザインでは、古典的な市場が使えない場面において、いかにして望ましい財の配分を促すような仕組み(広い意味でのマーケット)を設計するかについて考えます。インスティチューショナル・デザインでは、制度や社会組織だけでなく広くは慣習や法をも指す「institution」を設計する方法について、集団的意思決定のための制度設計理論を用いて研究します。
この講義では、マーケット・デザインとインスティチューショナル・デザインについて学びます。マーケット・デザインでは、古典的な市場が使えない場面において、いかにして望ましい財の配分を促すような仕組み(広い意味でのマーケット)を設計するかについて考えます。インスティチューショナル・デザインでは、制度や社会組織だけでなく広くは慣習や法をも指す「institution」を設計する方法について、集団的意思決定のための制度設計理論を用いて研究します。
マッチング理論においては、金銭による配分ルールが使えない場面を想定します。学校選択制度や臓器移植におけるドナーと患者のマッチングなど、金銭を用いた「市場」が倫理的または法的に存在しえないような場合に、どのような方法で望ましい配分を達成するかについて学びます。またオークション理論においては、希少性が高かったり財の価値そのものが明確でない場合に、いかにして十分な参加者を確保しつつ(「厚い」市場、と言います)望ましい配分を導くのかという問題を考えます。いずれの場合も、メカニズム・デザインの考え方が中心的な役割を果たします。
ここで根本にあるのは、効率性、安定性、公平性、平等性、耐戦略性などの望ましい特性が満たされるために社会のルールをどのように設定するか、という考え方です。結婚市場、住宅配分問題、学校選択制度、臓器移植、多様なオークション制度などの具体例を通して、マーケット・デザインの概念が政治経済や社会的選択理論にどのように適用されるかを学びます。
授業では、具体例を通して議論をすることに重点がおかれます。各受講生はアル・ロス氏の名著「Who gets what and why」の各章を発表することで、具体例とマーケット・デザインの本質について議論することが求められます。講義の最後にはピッチ(短時間でアイデアの要点のみを伝えるプレゼンテーション)を行います。コース中に学んだ概念を用いて、マーケット・デザインの独創的なアイデアに基づいた発表を行います。これらの議論と発表を通して、学生はマーケット・デザインの具体例への応用について、自分の頭で考え工夫をする貴重な機会を持つことになります。
評価では発表とピッチに加えて、授業への積極的な参加に重点がおかれます。すべての学生がクラスでの議論に能動的に参加することが求められます。授業で学んだ概念を繰り返すだけではなく、自分の頭脳を使って反芻し、自分の言葉で表現できることを目指します。その結果、独自のマーケット・デザインの問題に対して学んだ概念を応用できるようになることを目標とします。
2. 入国制限の緩和により今年は外国人学生が早稲田に戻ってきたこともあり、受講学生の背景にも多様性が感じられ、非常に活気のあるクラスであったのではないかと思います。今年のクラスの印象はいかがでしたでしょうか。

・その学生の多様性が授業に与える影響
学生に多様性があることは非常に望ましいことです。世界中から多様な学生が早稲田に集まり、共に学びます。文化的背景や学術的な知識が異なる学生からは、新たな視点や学び方など、多くの点を参考にできるのは言うまでもありません。
とくに私の講義では発表や授業中の発言を促しますので、いかにして議論を展開するか、論点をしぼったり具体例を挙げたりして意見を交換するか、などの方法について互いに学ぶことが多いと思います。上手に行う学生たちと直接会話することによって参考にできる点を知る貴重な機会になると思います。いかにして最も重要なメッセージを抽出し伝えるのか、また時には白熱した議論の合間にちょっとしたジョークを用いることの利点など、なかなか日本では学ぶ機会が少ないスキルについても学ぶ機会になったのではないでしょうか。
それと同時に、多様な背景や考え方を持った学生の間でも、実に多くの共通点があることも学びになったのではないかと思います。見た目や使用言語が異なっても、結局私たちは同じ人間なんだ、同じようなことに喜び悩む学生なんだ、という当然の事実を再確認できるのも、多様性のあるクラスの利点だと思います。

・今年の全般的なクラスの印象・評価
今年の学生は、コロナ禍によって入国制限が厳しい時期に来日したこともあって、日本に物理的に来られたことに満足している学生が多かったように感じました。オンラインでの会議や学術交流の機会が増えた世の中にあって、今回のように多様性に富んだクラスで対面の授業をできたことは非常に喜ばしいものでした。対面でコミュニケーションすることによってしか得られない感覚について、改めてその良さを感じさせてくれるものでした。
そのような利点が目立つ機会であったことのおかげでしょうか、学生たちも非常に強い動機をもって授業に参加してくれたように感じます。あたりまえに教室で授業が受けられるということの喜びをかみしめ、高度に科学的な知識を吸収する幸せを実感できる機会だったのではないかと思います。そのため、例年にも増して活発で学びに貪欲なクラスであった印象を持ちました。

・学生によるピッチの発表の中で個別に印象に残った点、等々
ピッチでは、ベビーシッターと親のマッチング、大都市における渋滞を減らすためのオークション式通行税、DAO(分散型自律組織)、プロ野球のドラフト制度設計など、多彩なテーマで学生が独自のデザインを発表してくれました。時間が限られていたにもかかわらず、多くの労力を費やして真剣に取り組んでくれたと思います。印象に残ったのは、発表が一方的なものではなく、聴衆側の学生からも活発に質問が出て議論が行われたことです。最初は発言を物怖じしていた学生も最終的には意見を述べて、多くのやり取りが行われました。
これこそ、私の「授業デザイン」において目標としている点ですので、それが実際に行われたことをとても嬉しく思います。
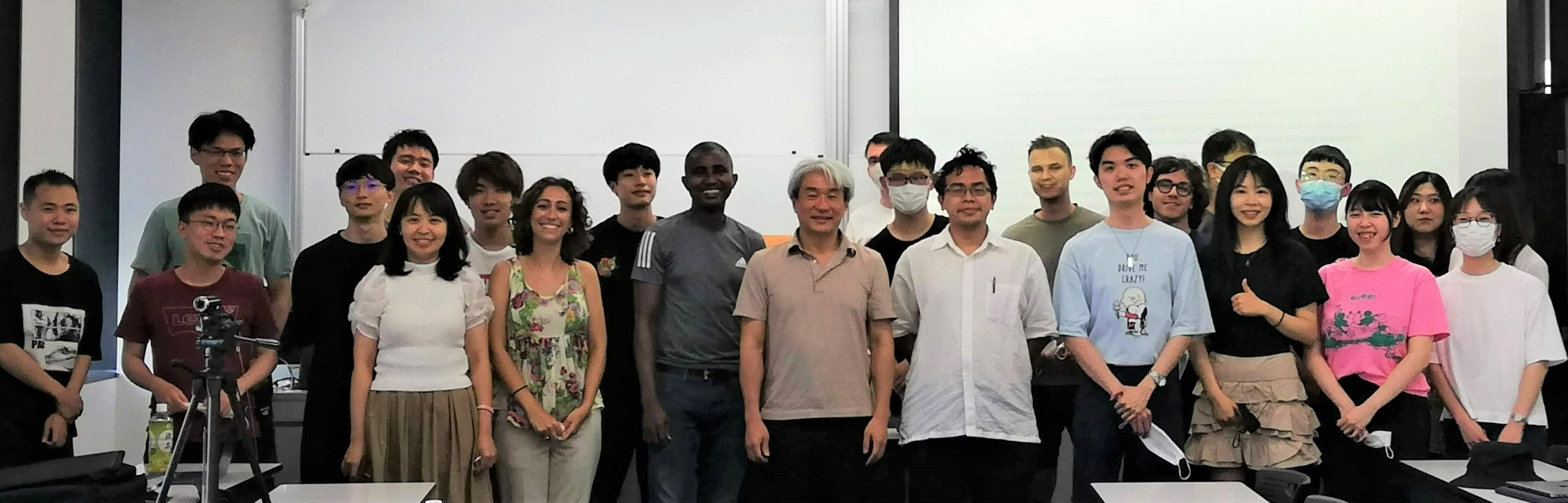
郡山教授(中央)を囲んで集合写真
3. ご自身が探求する研究テーマ、また最近の関心事について教えてください。
インスティチューショナル・デザインは、まさに私の主な研究テーマの一つです。集団的意思決定理論を用いて、望ましい性質をもつ制度設計について研究しています。
この分野では、いくつもの学術領域からの結果や分析方法を駆使します。まず、理論のもとになるのはゲーム理論的分析です。メカニズム・デザインにおいては制度を設計すると、それをもとに各個人がメカニズムに入力するメッセージを選ぶというゲームが定義されます。そのため、ナッシュ均衡を始め非協力ゲーム理論における概念が有用な場面が多くあります。
加えて、理論と人間の持つ行動パターンの間にバイアスがないかを調べる実験経済学、行動経済学を用います。モデルを用いて「合理的な」意思決定者の行動を記述する理論の分析ができたとしても、それが実際に人間の行動と合致しているかどうかを常にチェックする必要があります。そのために、データを用いて理論との整合性を調べ、必要があれば理論を修正します。理論とデータは分析という車の両輪のようなもので、どちらが欠けても車は前に進みません。そのために実験室やフィールドを用いた実験を通してデータを分析することが非常に重要になります。
最近は、協力ゲーム理論に強い関心を持っています。ゲーム理論では非協力ゲームの分析が長く主流になってきましたが、協力ゲームは近年改めて脚光を浴びる機会が増えています。計算機を用いた分析方法の発達に伴って、計算的社会選択理論などの発展にも目覚ましいものがあります。また機械学習における応用に役立つことも大きな要因だと思います。
また、DAO(分散型自律組織)のように新しい技術を用いたinstitutionの設計にも大きな関心があります。集団的意思決定の一部をアルゴリズムに任せてしまうことには潜在的な利点がありそうですが、同時に社会的分配にもたらす構造的な影響については注意深く考察する必要があると考えています。その長期的な影響について研究すべきことが山積していると思っています。
4. この秋には拠点からエコール・ポリテクニークに派遣される博士学生がいます。どのような教育環境で、どのような成果が期待できるとお考えでしょうか。
またエコール・ポリテクニークに限らず、海外の大学に留学する本学の学生に向けてメッセージをお願い致します。
拠点からエコール・ポリテクニークへの訪問が実現したことを大変嬉しく思っています。こちらでは、到着後すぐにセミナー発表を行ってもらい、研究者や博士課程の学生たちと早速交流が始まりました。また学会での発表や研究者との個別会合を通して、多くの経験を積んでくれている様子を目の当たりにしています。英語での発表や日常的な議論を通して、発表技術や論文の進捗に進展があるのはもちろんです。それだけではなく、交流や将来の研究に向けた自信に大きくつながっている様子が伝わってきます。
秋には学会も開催され、早稲田大学の複数の研究者による訪問も実現しました。そんな中で、2ヶ月の訪問が実現しただけではなく、今後もさらなる交流が予定されています。今回の派遣がより広い、早稲田大学とエコール・ポリテクニークとのさらなる学術交流に大きな貢献をしているのは間違いありません。その事実を大変喜ばしく感じています。
コロナ禍で世界は閉塞的な社会の息苦しさを実感しました。今また少しずつではありますが、自由な移動が再開され始めています。世界は大きく、世の中には様々な考え方や生き方をしている人々がいます。世の中には「正解」がないopen questionsがたくさんあります。多角的な視点から学び、自分の意見形成に役立てる。多くの経験を通して、人の実感がともなった考察を行う。そうした態度で研究を行うことによって、「よりよい社会」の探究に少しでも近づいていけるのではないかと考えています。
留学をする早稲田大学の学生には、その貴重な機会を十分に活かし、それぞれの立場で社会に貢献する方法を模索する糧にしてほしいと切に願います。
受講生の声:経済学研究科修士2年 藤岡孝輔
自由闊達な議論の場を郡山先生ご自身が率先して提供くださったことが特徴的でした。留学生が大半を占める本講義において、積極的に議論に参加することは容易ではないものの、その分非常に刺激を受けました。今回のピッチでは、子育て世帯とベビーシッターのマッチングプラットフォームを取り上げました。この発表を通じて得た具体的な知識も勿論有用であると考えていますが、本講義の3大トピックであるmarket design, mechanism design 並びにinstitutional design を学ぶ際に極めて特徴的であった大局的かつ各カテゴリーの違いに焦点を絞るという思考法は今後様々な機会において汎用的に役立つと考えています。
藤岡さんは9月からオランダのアムステルダム大学に留学中です。(関連記事2)









