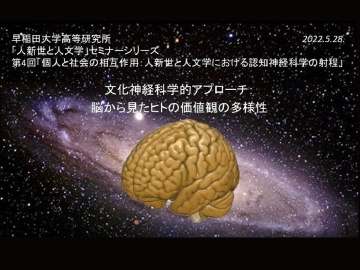本講演会は本学高等研究所研究プロジェクト「人新世と人文学:Humanities in the Anthropocene」セミナーシリーズ第6回公開講演として企画されました。国内外から36名の参加者を得、講演後には活発な議論が行われました。
まず葛西 周氏(早稲田大学高等研究所)が、人新世のフレームワークと接続されうる音・音楽研究の動向について紹介しました。聴覚的に環境の特性や変化を捉えようとする試みについて、サウンドスケープ生態学を提唱するバーニー・クラウスによるサンゴ礁の定点的フィールドレコーディング等を例に説明していただきました。一例として紹介された、魚が多く健康的な環境のサンゴ礁と、サンゴが死滅しかかっている海から聞こえてくる音の違いには驚かされました。目を閉じても見えてくる(聞こえてくる)環境という新たな視点が示されました。また、シェラック盤のような音楽メディアの素材と近代以降の音楽流通との関連や、動植物由来の素材の輸入規制に伴う楽器製作上の課題について、人新世における物質文化の観点へと話題は展開しました。
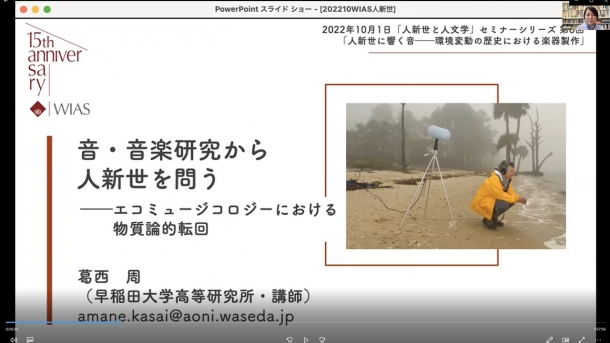
次に、無形文化遺産学・文化財保存技術を専門とする前原恵美氏(東京文化財研究所)をお迎えして、日本の伝統芸能で用いられる楽器の製作技術や材料について、自然環境・社会環境との関連から講じていただきました。一棹の三味線を製作するにも数多くの細かな付属品が必要であり、それぞれの部品の製作には工程ごとに専門家が従事してきた歴史があります。しかし、近年、製作者不足によって分業体制は限界を迎えているとの指摘がなされました。伝統芸能を継承するには原材料と道具の確保だけでなく、保存技術を継承した製作者が存在していること、そして楽器を用いて伝統芸能を実践する技を持つ実演家がいること、その全てが重要であることが、三味線という小さな楽器を通じて切実な問題として浮き彫りとされました。さらに、原材料・道具の安定的確保のためには、製作者だけでなく実演家が協力して新素材や代替素材を長期的に検証することに加え、伝統芸能あるいは伝統文化のジャンルを超えた連携の可能性を探究することに解決の糸口があると未来への展望も示されました。
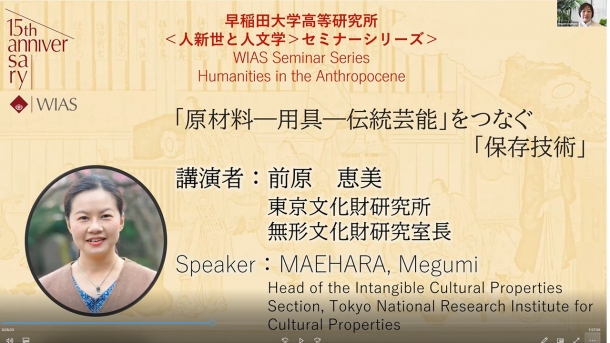
質疑応答では、思想・社会・国家制度といった伝統芸能の需要を喚起する背景についての質問や、海外からの関心や海外での復元・保存活動との連動に関する質問が寄せられました。人新世セミナー第2回講演会で取り上げられた、絵画の技法材料の変遷とも大いに重なるテーマであり、セミナーの回数を重ねることで諸分野の具体的な交差を明らかにすることもできました。
イベント概要
- 日 時:2022年10月1日(土)10:00~12:00
- 会 場:Zoomによるオンライン開催
- プログラム
10:00~10:05 開会挨拶
10:05~10:25 講演「音・音楽研究から人新世を問う――エコミュージコロジーにおける物質論的転回」 葛西 周(早稲田大学高等研究所 講師)
10:25~11:10 講演「「原材料―用具―伝統芸能」をつなぐ「保存技術」」 前原恵美(東京文化財研究所 無形文化財研究室長)
11:15~12:00 質疑応答・討議 - 司会:山本 聡美(早稲田大学高等研究所 副所長/文学学術院 教授)
- 対 象:教員・研究者・大学院生