本講演会は本学高等研究所研究プロジェクト「人新世と人文学:Humanities in the Anthropocene」セミナーシリーズ第4回公開講演として企画され、国内外から20名の参加者を得て、講演後には活発な議論が行われました。今回は2名の講演者にご登壇いただきました。原田宗子氏は認知神経科学を専門とし、岡本悠子氏は発達心理学を専門としておられます。
認知神経科学は、脳から個人の認知・行動を理解することを目的とする研究領域です。特に機能的共鳴画像法(fMRI)は実験室で行う実験科学的手法であり、社会つまり自然や人間の営みという要素を取りこむ人文学的研究手法とは本来疎遠です。しかし、近年、文化が個人差に及ぼす影響を扱う文化神経科学や、社会との相互作用の中で生じる発達を扱う発達神経科学など、脳を介して個人と社会との相互作用を解明しようという試みも増えてきました。そこで、この第4回セミナーでは、個人の脳から見えてくる社会について考察するとともに、人新世を考える上での認知神経科学の射程について取り上げました。
原田氏からは、物理的特徴から見た脳の特異性、自己意識の特徴、異なる文化圏での自己意識の違いに関するfMRI研究が紹介され、文化神経科学が扱う個人差は環境の要因か遺伝の要因か、文化的認知特性の時代による変化、文化的認知特性と言語の関係性について議論がなされました。
岡本氏からは自閉スペクトラム症の高次視覚野の発達の特徴についての事例紹介が行われました。環境の違いが障害に与える影響と、どのような学術的手法で環境と適応を計測できるのかといった論点へと議論を展開しました。

ディスカッションパートでは、イタリア美術史を専門とする桑原夏子氏(早稲田大学高等研究所・講師)より、修得言語の体系の違いによって、子どもの発達過程における認知機能に違いが生じるのか否かとの質問が寄せられました。また、宇宙論を専門とする藤田智弘氏(早稲田大学高等研究所・講師)より、脳で行われる神経伝達活動がそれ自体は物質的特性(原子・分子の集合体としてのふるまい)を示すにもかかわらず、脳が単なる「物質」ではないとどのような側面から言えるのか?という問いが発せられました。いずれも、脳とは何か、人間とは何かという大きなテーマに発展する問いであり、その場で明確な答えが出るものではありませんが、お互いの専門領域を超えてこのような議論の場を持つことができ、大変刺激的な機会となりました。
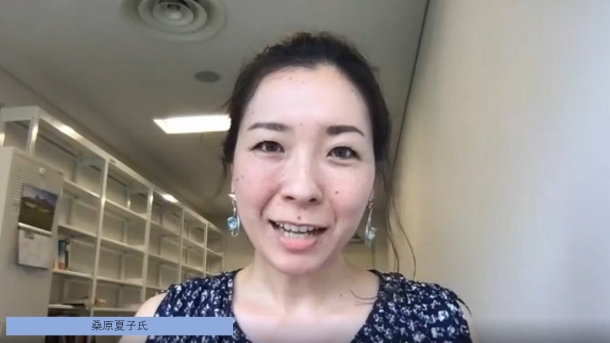

開催概要
テーマ:個人と社会の相互作用: 人新世と人文学における認知神経科学の射程
日 時:2022年5月28日(土)10:00~12:00
会 場:Zoomによるオンライン開催
対 象:教員・研究者・大学院生









