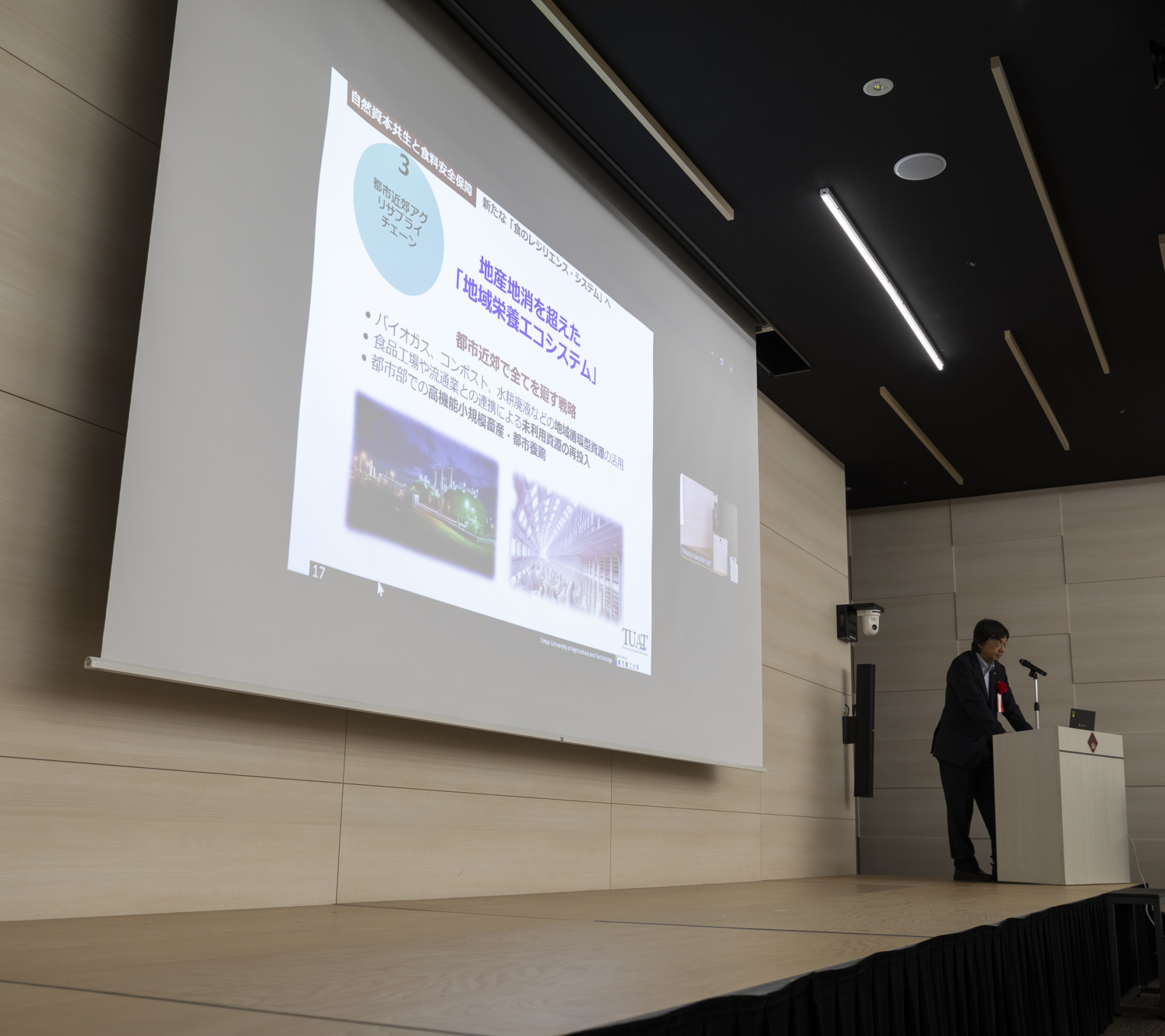- Featured Article
産官学共創コンソーシアムが始動
サスティナブルな未来食の普及に向けた産官学共創コンソーシアムが始動
Fri 18 Jul 25
サスティナブルな未来食の普及に向けた産官学共創コンソーシアムが始動
Fri 18 Jul 25
サスティナブルな未来食の普及に向けた産官学共創コンソーシアムキックオフシンポジウム
2025年4月、「サスティナブルな未来食の普及に向けた産官学共創コンソーシアム」が早稲田大学内に設立されました。本コンソーシアムは、食を取り巻くグローバルな課題に対し、学術的な研究開発を強化し、その成果を社会実装していくことを目指します。6月27日には、コンソーシアムの展望を共有し、議論を深めるべく、キックオフシンポジウムを開催。本記事では、当日のレポートをお届けします。
※各登壇者の発言は、抜粋や要約によるものです。
未来の食の領域に、多様な知見を結集する
早稲田大学が参加する「産業競争⼒懇談会(COCN)」は、国の持続的発展、産業競争⼒の強化、科学技術の推進、イノベーションの創出に関わる政策を提⾔とし取りまとめ、実現を図り活動しています。COCNで取り組まれてきたプロジェクト「フード・サステナビリティ実現に向けたwell-being次世代タンパク質の開発と社会実装」をさらに発展させるべく、2025年4月に早稲田大学内に設立されたのが、「サスティナブルな未来食の普及に向けた産官学共創コンソーシアム」です。
本コンソーシアムは、食のデジタル化産業構想への貢献、宇宙空間における食生活の探求、日本食文化の継承と食の多様化、フードテックのグローバル動向、食の安全保障など、多角的な視点を取り入れながら、未来の食料システム構築に資する研究開発を推進しています。特長は、産官学の連携を重視している点。コンソーシアムの方向性を幅広い関係者に共有することが、今回のキックオフシンポジウムの目的です。
冒頭では早稲田大学の田中愛治総長が、挨拶を述べました。
「2032年に150周年を迎える早稲田大学は、『世界人類に貢献する大学』を目指しています。現在、150周年記念事業を推進しており、研究推進の司令塔『Global Research Center』、教育の司令塔『Global Education Center』、貢献の司令塔『Global Citizenship Center』が連携をしながら、学生や研究者を育成し、世界に開かれた大学に向けた事業にあたっています。“未来の食のあり方”は、世界人類にとって重要な領域の一つです。COCNの尽力のもと、『サスティナブルな未来食の普及に向けた産官学共創コンソーシアム』が設立されたことに、心からの感謝を申し上げます」

早稲田大学 田中愛治総長
次に、コンソーシアムを管轄する「ナノ・ライフ創新研究機構 規範科学総合研究所」で所長を務める竹山春子教授が、設立の経緯を説明しました。
「人口増加や気候変動、健康上の格差など、世界規模の課題において、キーワードとなるのが“食”です。食という領域の重要性は高まっており、多様な知見を結集する必要があります。COCNではこれまで、次世代タンパク質の開発と社会実装に取り組んできました。培われたネットワークは、より広範な課題を解決するプラットフォームへと進化させられるはずです。新たなコンソーシアムでは、サイエンスと社会的ニーズの両輪を考えられる人材の結集、若手研究者や学生が主体的に挑戦できるような人材育成、産学連携による迅速な社会実装などを基軸に、皆さまと意見を交換していきたいと考えています。本日のキックオフが、共創の場の第一歩となることに期待します」

早稲田大学ナノ・ライフ創新研究機構規範科学総合研究所の竹山春子所長
産官学が一体となり、イノベーションを起こす必要性
シンポジウムではつづいて、食領域に関係する各所の来賓より、祝辞が述べられました。文部科学省科 学技術・学術政策局長の井上諭一氏は、地球規模の課題に対するイノベーションの必要性を語ります。
「食は、私たちに欠かせない存在であり、生活を豊かにしてくれるものです。一方、食を取り巻く課題は深刻化しています。世界中の食糧は約1/3が廃棄されているといわれ、多くの人々が肥満でありながら、飢餓で苦しむ人々もいる。また、地球上の哺乳動物は、人間と家畜が約96%(質量ベース)を占め、野生動物はわずか4%という驚異的なデータも報告されています。この分布は窒素や炭素の循環など、地球を貫くメカニズムにも関係しており、生産と消費の観点だけで課題は解決しません。複雑化する食の課題を解決するには、サステナビリティに寄与するイノベーションの創出が必要です。このコンソーシアムに多様な知恵が結集することに、大きく期待します」

文部科学省科学技術・学術政策局長 井上諭一氏
つづいて、農林水産省 農林水産技術会議事務局 研究総務官の信夫隆生氏が登壇。海外の動向を踏まえた、産官学共創の必要性を語りました。
「気候変動に対し、食領域がどのように対応するかは、世界的な課題です。そのアプローチにおいては一刻も早い技術開発が欠かせず、国外では熾烈な開発競争も進んでいます。日本も食や農業分野に関して技術開発への投資を行ってきましたが、その重要性はいっそう高まっていくでしょう。今回の産官学共創コンソーシアムにおいては、さまざまなプレイヤーが参画することに期待します。小さな正解が集まり、一つの大きな正解が育まれれば、日本らしさが生み出され、世界の食糧問題を解決していくと考えています」

農林水産省農林水産技術会議事務局研究総務官 信夫隆生氏
経済産業省からは、イノベーション・環境局長 兼 首席スタートアップ創出推進政策統括調整官の菊川人吾氏が、オンラインから参加。スタートアップやグローバルサウス諸国との共創について語りました。
「COCNから新たなコンソーシアムが発展したことは、緊密に連携している我々にとっても、非常に喜ばしいことでございます。経済産業省では、スタートアップとの共創に注力していますが、食をテーマにテクノロジーを活用していく企業の活躍が目立つようになりました。海外に展開する事例もありますが、特にグローバルサウスと称される地域では、経済的な発展性と社会的課題を内包しているのが特徴です。今年は日本でTICAD(アフリカ開発会議)が開催されるなど、グローバルサウスとの共創が注目される年です。ぜひコンソーシアムの皆さまにも、成果やビジョンを発信していただきたいと思います」

経済産業省イノベーション・環境局長/首席スタートアップ創出推進政策統括調整官 菊川人吾氏
来賓祝辞では最後に、産業競争力懇談会(COCN)実行委員長の斉藤史郎氏が、コンソーシアムへの期待を述べました。
「COCNは、日本の産業競争力向上に資するプロジェクトを、会員である企業や大学が中心となって進めています。2022年にスタートしたテーマの一つである『フード・サステナビリティ実現に向けたwell-being次世代タンパク質の開発と社会実装』は、早稲田大学および島津製作所が強力なリーダーシップのもとで牽引した、COCNの代表なプロジェクトです。日本のエネルギー自給率は15%程度、食糧自給率は38%程度と低い水準にあり、未来食の実装は重要なテーマになるでしょう。今回のコンソーシアムが中心になり、未来の食に対する多様な考え方が広がっていくことに期待します」

一般社団法人産業競争力懇談会(COCN)実行委員長 斉藤史郎氏
フードビジネスイノベーションの使命と課題とは
基調講演では、「産学官連携によるフードビジネスイノベーション」をテーマに、東京農工大学学長の千葉一裕氏が、農学の視点から世界を取り巻く課題を解説しました。
「気候変動や生態系の変化が進む中では、人類は長期的な視点で未来に目を向ける必要があります。目指すべきは『Inclisive Wealth(包括的富)』の追求です。森林破壊や資源枯渇など、『負の外部性』にも着目する産業活動が、今後は主流になるでしょう。世界的な人口増加は都市化を促し、農地の減少、水資源の不足、農業従事者の減少などが加速すると予測されます。また日本は食料や飼料、農業関連の科学技術の多くを輸入に依存しています。輸出を担う農業生産国は、食糧の安定供給や環境保全、先進技術の進化など恩恵が多いです。我が国が意識しない変化にも注視すべきでしょう」

東京農工大学 千葉一裕学長
千葉学長は食を取り巻く課題を共有した上で、産官学で担うべき食の共創圏の再構築について説明します。
「例えば、微生物や植物に由来する肥料・農薬を打ち出していく、地域自給型の種子を導入していくことなど、日本人が共有すべき考えは多いです。そして、都市近郊のアグリサプライチェーン、フードテック×ネイチャーテック基盤の構築も重要化するでしょう。これらは世界に共通するモデルでもあります。我が国が危機を乗り越え、先導していくことはチャンスにもつながります。こうした動きに向けては、先端テクノロジー開発はもちろん、フードビジネスの成長も必要です。しかし、自然資本の定量化不足、技術の社会実装ギャップ、資金循環など、企業が直面する課題も多い。産官学連携によるフードビジネスイノベーションは、これら課題の解消に寄与します。自然資本と人的資本に投資する企業戦略、制度・金融・教育の三位一体の改革、外部性の見える化と収益性の仕組みなど、産官学連携が果たすべき役割も大きいと考えています」

サスティナブルな未来食の普及に向けた展望
つづいて、「サスティナブルな未来食の普及に向けた産官学共創コンソーシアム」の会長を務める早稲田大学の朝日透教授が、コンソーシアムの全体像を説明しました。
「新たに生まれてくる代替タンパク食に対して、『安全・安心・信頼』に基づいた『社会受容性』を高め、継承されてきたわが国の食の伝統や文化を踏まえた新しい食文化を創造する。この理想を掲げ、私たちはCOCNの推進テーマの段階から、約2年間半活動してきました。立ち上げ当初、食という領域を課題する風潮は、現在と比べると小さなものでしたが、現在は多くの企業、大学・研究所のメンバーが集まっています。本コンソーシアムでは、プロジェクト創出、人財育成、人財交流の各部会が、新たな取り組みを進める予定です。人財育成部会、人財交流部会では、企業や学生の皆さまに知見を共有する講座、人的交流を図るワークショップも開催していきます。今後皆さまと未来の食に取り組んでいくことを、楽しみにしております」

コンソーシアム会長 朝日透教授
シンポジウムでは最後に、コンソーシアム副会長を務める島津製作所の岡崎直美氏が閉会挨拶を述べました。
「先日、仕事でインドを訪れました。インドは、伝統的な食文化を守りながらも、バイオ医薬やIT産業が盛んな国です。現地のビジネスパートナーと話をした際、『明日の課題を、今日や昨日のソリューションで解決するのはおかしい』と言われました。私は雷に打たれたような衝撃を受けたのを覚えています。今までの方法論で将来の課題を解決しようとするのではなく、新しいアイデアを出し合い、新たなソリューションを育む方向性が大切なのでしょう。本コンソーシアムは、共創はもちろん、学びにも満ちた場です。より多くの皆さまにご参加いただけることを楽しみにしております」

コンソーシアム副会長 島津製作所 岡崎直美氏