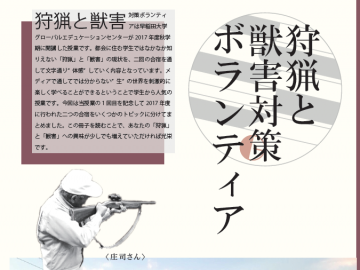Voice_「社会貢献のためのクリエイティブな発想と実践」
| 科目名 | 社会貢献のためのクリエイティブな発想と実践 |
|---|---|
| 担当教員 | 石野 由香里 |
| 履修年度・学期 | 2014年度・春学期 |
庄司知志・教育学部2年
眠くならない授業
この授業は本当に面白かったです。まず眠くならない。なぜなら、自分がこの授業に参加しよう参加しようと自然と入り込んでいってしまうんです。
普段、私たちは色んな人と接します。それは別段仲が良い人でなくとも、電車の中で隣に座る人や、歩いていてすれ違う人、私たちは多くの人と人の間で生活をしています。だからこそ、たまにイラッとしたり、モヤモヤしたりする時がある。
「この人はなんでこういうこと言うんだろう」
「なんでこの人はこんなことするんだろう」
人の一挙手一投足の中にある考え方や気持ちまで、私たちには分からない。
そういった人と人の食い違いは、ちょっと肩がぶつかったり、ちょっとムカつくことを言われたりするような、ほんの些細なコトから、国と国の戦争や民族の紛争といった大きなコトまで広く及んでいるわけです。
私たちは「人と人の関係」に無意識のうちに囚われていることを、この授業で嫌という程見せつけられます。なぜなら、こういった「人と人の食い違い」は私たちの周りで常に起こっていて、私たち自身もこの1秒後に巻き込まれるかもしれない。いや、むしろもう巻き込まれているのかもしれないからです。人の気持ちや行動に、「なぜだろう」「なんとかしたい」と頭を無意識のうちに悩ませてしまうことは、人である以上いつでも何処でも付きまとうものなのでしょう。つまり、「他人事」として切り捨てることがどうしてもできないわけです。だからこそ授業中に、寝る気にも内職する気にもなれないんです。
「相手の立場に実際に立って、相手の動きを真似してみたら?」
では、こういった些細な人間関係から地球規模の人間関係までを、分かりやすく、滞りなく教えてくれるものはなんでしょうか。学問やお金や権力だけでは、うまくいきません。それくらい人間関係を、言い換えると「相手の立場にたつ」という、小学生のころから言われていることを実践するのは、余程難しいことなのでしょう。
「じゃあ体を動かしてみればいいじゃん」
というのが、この授業の面白いところです。どうせ考え込んだって分からない、本を読み漁っていてもたどり着けない。
「それなら相手の立場に実際に立って、相手の動きを真似してみればいいじゃないか」
バカじゃないかと思いませんか?ぼくも最初はそう思いました。「大学に来てやることじゃない、面倒なやつをとっちまったなぁ」と。でもやってみると物凄く難しい。他人の動きをコピーするように動くことは、その人の気持ちや考え方まで意識を配らないと、文字通り体が固まってしまうのです。それから少しづつ、その時の風景や状況、周りにいた人のことまで意識を伸ばして行ってみると、段々体がスムーズになってくる。そしてボンヤリと実感する。
「あの人が、あの時、こういう行動をしたのは、こんな気持ちだったからかもしれない」と。
あなたは、家族や恋人の気持ちを「知っているつもり」に過ぎなかったことに気づく
「悲しい」「嬉しい」そういった一言でまとめられてしまう感情は、人それぞれ感じ方も、感じるタイミングも、表現の仕方も違うわけです。「そんなこと分かってるよ」そういう言葉が心に浮かぶ人もいるでしょう。その気持ちも分かります。僕もそんなことは「人それぞれ」「社会の多様性」「ダイバーシティ」…本やTVでたくさん見てきました。
しかし、体を通して実感することと、頭で文字の意味を理解することは全然違うのです。この授業で体感してみて下さい。
人の心に広がる世界は、本当にバラバラで、決めつけることが出来ない。
もしかしたらあなたは、家族や恋人の気持ちを「知っているつもり」に過ぎなかったことに、この授業で気づいてしまうかもしれません。
柳奈菜・文化構想学部3年
「演劇で社会貢献!?」
私は専攻で演劇について学んでいましたが、演劇自体に対する疑問がありました。ただの娯楽や芸術としての価値以外の演劇の可能性を考える一方で、今自分が学んでいることが何になるのか、漠然とした不安がありました。そのため演劇を目的とするのではなく、演劇をツールにして自らの価値観を問い直すという本講義のテーマに純粋に興味を持ちました。
自分の固定された世界・モノの見方を崩していく授業
実際に自分の興味を持った現場でフィールドワークをして、現場の人に出会い、何か「ひっかかりを覚えた出来事」を演じることは、実際にやってみると本当に大変なことでした。「本人の気持ちになれない!」と何回も感じ、挫折しそうになりながらもフィールドワークやヒアリングを重ねてその人を理解し、自分ではない他人に近づいていく試みの連続です。しかし講義を受けているうちに、人が人を究極的に理解することは不可能かもしれないけれども、この講義では、演劇を通して「自分と違う人間を理解する」という根本的なことに挑戦しているのだと感じました。誰でも自分の世界からしか、ものを見ることはできず、自らの価値観は絶対的な存在です。しかし、この講義では、演じるというよりも代弁しようとすることで、自分の固定された世界を崩していくのです。私はそれによって演じた人物本人になったかのような感覚を得ました。演じる前には「この人はどうしてこういう行動をとるのだろう」と否定的な感情を持っていたはずの人物だったのに、全く異なる目線に立ち、思い知る別の感覚がありました。自分にとってとても重要な他者理解への一歩でした。自分の価値観を身体を使って問い直すことができたのです。この授業の大きな魅力でした。
身体を通して他者を理解することはこの講義でしかできない経験です。また様々なバックグラウンドを持つ他学部、他学年の人たちに刺激を受けて自分の視野を広げられることが、全学オープン科目の最大の魅力です。大学生活の中で、新たな自分を発見できるチャンスが得られるので、ぜひ受講してみてください。
長崎大志・スポーツ科学部3年
フィールドワークと発表シーンの素材集め
この授業では、まず履修者は取り組みたいトピックを選択し、グループを形成します。その後はグループ単位で、フィールドワーク先を決定し、実際にフィールドワークに向かいます。現場では実際に現場の活動に混ぜてもらったり、当事者の方のお話をお聞きしたりして、自分達が演劇にしたい題材・材料を集めます。そして、それを教室に持ち帰り、シーンを作成していきます。シーンができるとそれを実際に演じ、先生や他の班の学生と共有し、他の班の学生だからこその視点から突っ込みをもらい、そのシーンの登場人物への理解を深めていきます。
「なぜ、部屋から出てこないんだ?」~理解できない独居高齢者の気持ち~
実際に私は「人との繋がり」というテーマの下、独居高齢者が全居住者の多くの割合を占める団地にお邪魔しました。そこでは、孤独死や引きこもりがちな高齢者など、普段接点を持つことがないような現実問題に触れることができました。
正直、始めは住民という他者への理解に苦しみました。「なぜ、部屋から出てこないんだ」とか「なぜ、もっとそれぞれの住民が団地に貢献しようとしないんだ」と。分かりませんでした。
だから、半期のうちに何度も足を運び、活動に混ぜてもらい、話を聞こうと自分なりに努力を重ねましたし、他のメンバーや先生と多くの情報を共有しました。それなりの理解が深まったと、その時は思いました。ただ、今振り返るとそれはまだ、やはりどこか表面的で、自分とは切り離した理解だったのではないかとも思っています。
言葉・表情・仕草を再現する=「演じる」ことで、さらに踏み込み、寄り添えた
というのは、上記のような話し合いや現場の状況整理からだけでは得られなかった理解がそのフィールドワーク後の「演じる」という作業をして初めてでき、対象者にさらに踏み込み、寄り添えたと実感をしたからです。それは対象者の置かれる状況・ストーリーに身を置き、発する言葉・表情・仕草等を身をもって再現する=「演じる」ということをしたからではないか、そう思います。
繰り返しになりますが、理解したい他者のバックグラウンドを理解し、演劇という仮想空間ではありますが同じ境遇に身を置き、真似事ではありますが彼ら彼女らが発する言葉を自分も発するという行為はダイレクトに感情や感性に働きかけ、「はっ」とさせられる体験を与えてくれました。
自分を発見し、見つめ直す経験
授業が終わって振り返ると、結局、「なぜ、部屋から出てこないんだ」とか「なぜ、もっとそれぞれの住民が団地に貢献しようとしないんだ」という思考はとっても短絡的であったのではないかと思います。住民の方はそれぞれがそれぞれの思いを持っており、そもそも引きこもりの人が「部屋から出てくること」が正義であると決め付けている自分や、貢献しようとしている住民の方を見落としていた自分を発見し、自分を見つめなおすことにもなりました。
他者を理解しようとすることとは、自分を理解することなのかもしれません。