- 研究科について
- 修士論文
Master's Theses
修士論文
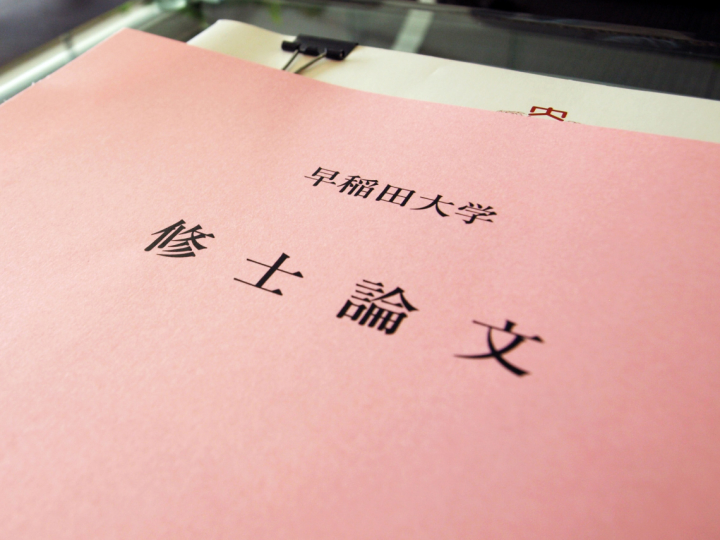
修士論文の審査基準
修士論文の審査では、以下の事項等が評価される。研究内容が本研究科の修士論文としてふさわしい学術的な意義ならびに倫理性、独創性、先進性、有用性等を有していること。修士論文提出者は、研究分野に関連する広範な専門的知識とともに、学術研究倫理※1に関する理解と遵守に基づく高度な研究遂行能力と研究成果の説明能力等を有すること。具体的な審査基準は、次の通りである。
- 研究テーマの適切性:研究テーマが倫理性、独創性、先進性、有用性等の観点から適切に設定され、かつ研究目的が明確で、学術的な意義を有していること。
- 研究遂行能力:学術研究倫理の理解と遵守に基づき、研究計画の立案とその遂行を指導教員等の指導・助言を受けながら、継続して実践していること。
- 情報収集・編集能力:研究テーマに関連する研究動向の把握や文献等の各種資料の調査が十分に行われ、それらを基にした自らの研究の重要性や位置付け、関連研究との相違ならびに関係性が明確にされていること。
- 課題分析能力:研究目的を達成するために採用した手法やその組み合わせが研究テーマの十分な分析に基づいて行われ、合理性かつ説得性を有していること。
- 合理的論述能力:論文全体の構成を含め、内容では一貫性を保持した合理的な論述が展開され、論拠の提示、推論の構築、その上での主張の展開がなされていること。上記により論文の信頼性と説得性を確保するとともに、研究テーマに対応した明解な結論が提示されていること。
- 論文作成能力:論文全体が論理的で明解な文章で記述されており、表紙・概要・目次・章立て・図表・引用・参考文献・付録等に関しての体裁が整っていること。
- 情報発信能力:論文全体の内容を明解かつ端的にプレゼンテーションでき、質疑応答に的確に対応できること。
※1 「学術研究倫理」とは:学生諸君に関連する部分の概要は、以下の通り。
基本的精神・責任
人類の福祉と世界平和への貢献、国際的な研究規範や条約・法律の遵守
基本的姿勢
- 生命・個人の尊厳と基本的人権の尊重
- 国・地域等の文化・習慣・規律等の理解
- 共同研究者の尊重
- 研究協力・支援者への誠実な対応
- 不正行為・同加担行為の禁止
- 研究に関与する学生の不利益の回避
個別項目の例
- 捏造・改ざん・剽窃・盗用等の禁止
- 研究費の不正使用・誤使用の禁止
- アンケート・ヒアリング等におけるインフォームドコンセントの適用
- 同上等 での個人情報の保護
- 資料・データ等の適切な利用と管理
- 機器・薬品等の安全管理、有害廃棄物の適正処理
- 各種ハラスメント(セクシュアル・アカデミック・パワーハラスメントなど)の禁止
- 研究成果の原則公開
- 委託研究等の守秘義務の遵守など
修士論文の審査プロセス
修士論文の審査は、以下の手順で実施される。評価はA+、A、B、CとF(不合格)の5段階で行われる。
- 修士論文履修者は、随時、指導教員の指導・助言を受けつつ研究を遂行し、途中経過を「環境・エネルギー学特別演習 A・B」において年5回、本研究科の教員の前で発表し、質疑に応じる。
- 上記の発表資料については、WasedaMoodle上で『類似度判定』(iParadigms社のTurnitin)のチェックを受ける。
- 当該年度12月(9月入学者は5月)には、同履修者は指導教員を通じて修士論文提出の意志を表明し、本研究科運営委員会の承認をもって修士論文提出者となる。
- 修士論文審査会は、本研究科全教員で構成される。必要と認められるときは、他研究科の教員や客員教員、学外者等を審査会委員とする。
- 審査会は、提出された修士論文ならびにそのプレゼンテーションの内容(質疑応答を含む)を審査する。その際の審査基準は、「修士論文審査基準」を参照のこと。
- 修士論文提出者は、審査会の指摘や助言を反映させた修士論文を最終版として指導教員に提出する
- その他、修士論文概要書および指導教員からの指示がある場合においてweb公開用修論概要、同公開許諾書ならびに修論ポスタを本研究科事務所に提出する。
修士論文の評価は、審査会の助言を受け、指導教員が当該提出者の研究成果に加えて日頃の研究状況や対応姿勢等を勘案して決定し、本研究科運営委員会の判定会議の承認を受ける。
研究指導と修士論文の作成プロセス
修士論文の作成に向けての研究指導は、履修の「研究」の指導教員個々の指導・助言と本研究科教員による講義や共同指導によって行われる。概要は以下の通りである。
- 1年次においては、随時、研究テーマの選択・設定や内容等について履修の「研究」の指導教員(研究対象分野によっては主担当の他に副担当が選任されることがある)の助言・指導を受ける。
- また、「導入学習」においても『研究論文の書き方とプレゼンテーション』等の特別講義や演習において「修士論文審査基準」の達成に関わる指導を受ける。
- 加えて「環境・エネルギー学演習A・B」でも、本研究科教員から「修士論文審査基準」に基づく指導を受ける。
- 上記の科目での提出レポートは、WasedaMoodle上で『類似度判定』のチェックを受ける。
- 1年次中には、指導教員あるいは修士論文の研究指導が予定される教員との連名で、適切な学会に講演あるいは論文等を発表・公表することが、修論文着手条件として求められる(当該年度に翌年度の学会で発表予定等が確定している場合は、上記と同様と見なされる)。
- 1年次3月(9月入学者は8月)の指定期日までに、指導教員の指導・助言に基づき論文題目・内容を決定し、日本語または英語で作成した修士論文計画書を指導教員の承認を得て本研究科事務所に提出する。
- 2年次には、「修士論文」と「環境・エネルギー学特別演習A・B」を履修し、本研究科教員の共同指導による修士論文作成に当たっての指導・助言を受ける。
- 2年次中には1年次と同様に、随時、履修の「研究」の指導教員個々の指導・助言を受け、研究の遂行と論文の作成に取り組む。
