- ニュース
- 【開催報告】日中共同シンポジウム「新技術と法Ⅳ」が開催されました
【開催報告】日中共同シンポジウム「新技術と法Ⅳ」が開催されました

- Posted
- Tue, 10 Dec 2024
日中共同シンポジウム「新技術と法Ⅳ」
主 催:早稲田大学比較法研究所、中国社会科学院法学研究所
共 催:早稲田大学先端技術の法・倫理研究所
日 時:2024年9月5日(木)9:15-18:15
場 所:早稲田大学8号館3階大会議室
参加者:42名
2024年9月5日、早稲田大学比較法研究所と中国社会科学院法学研究所は、シンポジウム「新技術と法Ⅳ」を共同で開催した。
開会の辞

岡田正則教授(早稲田大学比較法研究所所長)
岡田正則所長は、開会にあたり、日中共同シンポジウムの開催に向けた挨拶を述べた。岡田所長は、急速に発展するデジタル技術が私たちの社会や法制度に大きな変革をもたらしている現状に触れ、法学研究者がこれらの課題にどのように対応するかがますます重要になっていると強調した。
また、岡田所長は本シンポジウムが日中両国の法学者にとって、新技術に関する法的課題について知見を共有し、建設的な議論を交わす場となることへの期待を述べた。さらに、岡田所長は国際的な視点で技術と法の調和を目指す議論が、今後の法整備に貢献することを願っていると語り、参加者の積極的な参加と議論を呼びかけて開会の辞とした。
セッション1「訴訟手続・行政手続きにおけるAIの活用」

司会 大橋麻也教授(研究所員、早稲田大学法学学術院)
報告1「日本の民事手続におけるデジタル化の現状と課題(AI活用も含めて)」
内田義厚教授(研究所員、早稲田大学法学学術院)

内田義厚研究所員
内田義厚教授は、日本の民事訴訟手続におけるデジタル化とAI活用の進展について説明した。まず、民事訴訟手続のデジタル化前史として、日本は2004年に民事訴訟法を改正し、オンライン申立てを導入したが、利用は低調で進展が停滞した。2017年の「未来投資戦略2017」により、訴訟記録の電子化、ウェブ会議の導入など「三つのe」を基本方向性とした推進が再開された。その後、全面的なデジタル化を目指して実務運用改革と法改正が進行し、電話会議や電子提出システムが導入され、コロナ禍が普及を加速させた。
続いて、日本の民事司法過程でのAI利用も進展し、データ分析や訴訟支援技術が議論されている。これにはビッグデータ化が不可欠で、裁判情報の大規模な電子化が進む。AI利用にあたっては、予測の信頼性やプライバシー保護の課題が指摘され、慎重な運用が求められる。また、AIが進化しても、最終的な判断は司法専門家が行い、適切な倫理的配慮を担うべきであると強調された。
報告2「中国の刑事事件におけるオンライン訴訟の実践の革新と発展ビジョン」
董坤教授(研究員、中国社会科学院法学研究所訴訟法研究室副主任)

董坤研究員
董坤教授は、中国の刑事事件におけるオンライン訴訟の革新と将来のビジョンについて報告した。
まず概説として、董坤教授はオンライン訴訟が導入された背景には、司法手続の効率化、コスト削減、及び迅速な裁判への社会的要求があると述べた。特に、コロナ禍を契機にオンライン訴訟の活用が急速に進んだことを指摘した。
次に、董坤教授は、全国的な統一プラットフォームの構築や遠隔証拠提出システムの導入により、オンライン訴訟の実施が円滑に進んだことを紹介した。さらに、IT技術の活用により、裁判の透明性が向上し、司法への信頼が強化された事例も挙げた。
続いて、董坤教授は現在の問題点としては、遠隔審理における被告人の権利保護の不足、インターネット環境の格差、及び証拠の真正性に対する懸念があると述べた。また、一部の地域では技術インフラが未整備であり、オンライン訴訟の公平性に影響を与える可能性が指摘されている。
最後に、将来の展望として、董坤教授はAI技術やブロックチェーンの導入によるさらなる手続の効率化が期待されているが、人間の判断の重要性を強調し、技術と司法の調和を図る必要があると強調した。また、法的フレームワークの整備を進め、より公正かつ透明なオンライン訴訟システムを構築することを目指していると述べた。
報告3「行政過程におけるAIと法治主義の危機」
黒川哲志教授(研究所員、早稲田大学社会科学総合学術院)

黒川哲志研究所員
黒川哲志教授は、行政デジタル化がもたらす行政法上の論点と、その影響について報告した。
まず、黒川教授は行政デジタル化に伴う主要な論点として、行政手続の自動化が法治主義の基本原則とどのように調和するかが議論の焦点となっている点を指摘した。具体的には、行政が情報技術を用いることで、効率性の向上と手続の簡素化が進む一方で、法的透明性が損なわれる危険があることに言及した。
次に、黒川教授は法治主義の危機について、AIによる自動的な意思決定が従来の行政権のチェック機能を弱体化させる恐れがあると説明した。AIアルゴリズムの透明性の欠如が、市民に対する説明責任を低下させ、行政権の恣意的運用を招く可能性がある点を強調した。電子政府の導入とデジタル手続法に関しては、行政サービスがより迅速かつ便利に提供される一方、個人情報保護やデータの安全性が課題として浮上していると述べた。また、デジタル化が進む中で、新たな法律や規制の整備が急務であることを指摘した。
続いて、黒川教授はプッシュ型行政の功罪についても触れ、デジタル技術を用いて行政が市民に情報を積極的に提供する利点がある一方で、市民のプライバシー権が侵害されるリスクや、行政の過度な干渉が懸念されると述べた。
最後に、黒川教授は行政によるAI利用の問題点として、AIが偏ったデータに基づいて決定を下す可能性や、AIが不公正な結果を生むリスクを挙げた。こうした問題を解決するためには、AIの運用に関する厳格な規制と、意思決定プロセスへの人間の関与を確保する必要があると強調した。
報告4「公共データの開放と共有に関する法的規制」
席月民氏(研究員、中国社会科学院法学研究所経済法研究室主任)

席月民研究員
席月民氏は、公共データの開放・共有に関する法的課題について報告を行った。
まず、問題提起として、席氏は公共データが新しい生産要素として社会のさまざまな分野に影響を及ぼしていることを指摘しながら、そのデータの開放・共有が、効率的な行政運営や経済成長に寄与する一方で、法的整備の不十分さが課題となっている現状を説明した。
次に、席氏は公共データ開放・共有の基礎分析として、公共データの概念や特性を詳述した。公共データは、政府機関や公共事業体が職務遂行の過程で収集・生成するデータを指し、行政データと公共サービスデータが含まれると定義されている。席氏は、こうしたデータの公開は、透明性や効率性を向上させるが、同時にプライバシー保護やデータセキュリティの課題が伴うことを述べた。
続いて、席氏は中国における公共データ共有の地方立法について説明し、雲南省や福建省などの地方条例がデータ管理に関する具体的な規定を設け、先行的な試行を行っている事例を紹介した。これらの立法は、データの範囲や共有の仕組みを明確化し、公共データの安全な運用を目指しているが、地域ごとの法的整合性に課題が残るとも指摘した。
最後にまとめとして、席氏は公共データの開放と共有を効果的に進めるためには、全国統一の法規制を整備することが重要であると結論づけた。
報告5「デジタル政府建設の進展と展望」
呂艶濱氏(研究員、中国社会科学院法学研究所法治国情調査研究室主任)
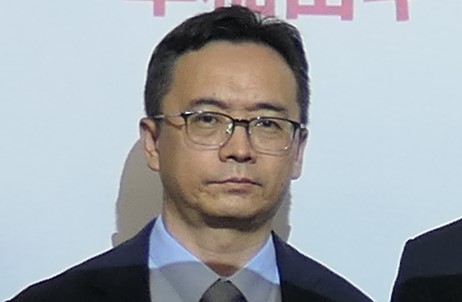
呂艶濱研究員
呂艶濱氏は、中国における法治政府建設に向けたデジタル技術の役割について報告を行った。
まず、呂氏は法治政府建設の基本要件として、法律に基づいた透明かつ公正な行政運営が求められることを強調し、法の支配を実現するためには信頼性と一貫性を持つ行政制度が不可欠であると述べた。
次に、呂氏はデジタル技術による法治政府建設の現状について説明した。中国では、IT技術の進展により、行政手続がオンライン化され、迅速かつ効率的な行政サービスが提供されていることを紹介した。電子政務プラットフォームの構築が進み、データの一元管理や遠隔手続の導入によって、行政の透明性と公正性が高まっている事例を示した。しかし、技術の進歩に伴い、データプライバシーやサイバーセキュリティといった新たな課題も生じていると述べた。
最後に、呂氏はデジタル技術による法治建設の時代的要求として、今後さらに高度な技術を活用することで、法治政府の効率化と公平性を強化する必要性を指摘した。
討論
討論では、セッション1の内容を踏まえて多角的な議論が展開された。まず、公共データ開放に関する法的規制の報告に対して、参加者からは、データ共有によるプライバシー侵害や国家安全保障上の懸念が議論され、規制の枠組みがどの程度まで柔軟であるべきかが問われた。また、行政デジタル化における技術の急速な進展が、伝統的な法治主義にどのような影響を与えるかについても意見が交わされた。AI技術を用いた行政手続に関連しては、アルゴリズムの透明性や説明責任が法的にどう担保されるかが議論の焦点となり、一部の参加者は、人間の判断がどの段階で関与すべきかを再考する必要があると提案した。また、デジタル技術を活用した法治政府建設における時代的要求として、技術導入の効果とリスクのバランスをいかに取るかについても深掘りされた。全体として、報告者と参加者の間で意見交換が活発に行われ、デジタル技術と法的枠組みを調和させるための方策や、今後の課題についての考察が共有された。
セッション2「新技術活用保護と個人情報保護」

司会 呉用教授(中国社会科学院法学執行院長)
報告1「日本の新個人情報保護法とその問題点」
岡田正則教授(早稲田大学比較法研究所所長)

岡田正則所長
岡田正則教授は、日本における個人情報保護制度の発展から現行の法的課題について報告した。
まず、岡田教授は、日本の個人情報保護制度は1980年のOECDプライバシーガイドラインに端を発し、各行政分野で個人情報の管理が進められてきた歴史を説明した。1990年代以降、地方自治体が先行して条例を制定し、全国的に保護制度が整備されていった経緯を紹介した。続いて、法制度の整備として、2003年に個人情報保護関連5法が制定され、2005年に全面施行されたことを説明した。これにより、包括的な個人情報保護制度が整備され、2013年にはマイナンバー法が導入されたと述べた。
その後、岡田教授は、新個人情報保護法の概要に触れ、2021年の改正によって公的部門と私的部門の制度が一本化されたこと、デジタル社会の進展に伴い、個人情報の有用性を考慮しつつ権利保護を強化する内容が含まれていることを説明した。改正の特徴として、個人情報のトレーサビリティや、第三者提供時の透明性確保が強調されている点を指摘した。
続いて、岡田教授は日本の新個人情報保護法には問題点も多いと述べた。特に、オプトアウト規定の曖昧さ、AI技術による個人情報の処理に関する不十分な規制、及び個人情報保護委員会の監督権限の限界が課題として挙げられた。
また、公文書管理法との関連で、岡田教授は、公的機関の個人情報管理における問題も浮き彫りとなっていると指摘した。特に、公文書の適正な管理が行政の透明性に直結することを強調し、個人情報保護と行政文書管理のバランスが重要であると述べた。
結語として、岡田教授は、デジタル技術の進展に伴い、個人情報保護制度のさらなる強化と、持続的な見直しが不可欠であると結論づけた。個人の権利保護と情報の利活用を両立するため、法制度の柔軟な運用が求められていると締めくくった。
報告2「不正競争防止法における個人情報保護の機能と限度」
張浩然氏(中国社会科学院法学研究所知的財産法研究室助理研究員)

張浩然助理研究員
張浩然氏は、不正競争防止法の観点から個人情報保護の機能とその限界について報告した。
まず、問題の提起として、張氏はデジタル社会において個人情報の不正使用が増加し、企業間競争におけるデータの重要性が高まっている現状を指摘した。特に、個人情報の保護が市場競争の健全性にどのように影響を与えるかが大きな課題となっていると述べた。
次に、張氏は個人情報の不正競争に対する保護の実務と、それに関する論争点を説明した。具体的には、企業が顧客データを競争上の優位性として利用するケースが増えており、不正競争防止法を用いた保護の実例が紹介された。しかし、この保護が企業の情報収集活動を過度に制限するリスクもあるため、実務の中で多くの議論が生じていることに言及した。
続いて、張氏は個人情報保護と市場競争の関係の明確化が必要であると強調した。個人情報の保護が市場競争の阻害要因となり得る一方、適切な規制がないと市場の不公平が生まれる可能性があると述べた。このバランスを取ることが、健全な競争環境を維持するために不可欠であると指摘した。
最後に、張氏は不正競争防止法による個人情報の保護とその制限について詳述した。この法律は、個人情報を不正に取得・利用する行為を規制するが、その適用範囲には限界があると述べた。特に、個人情報の商業利用と保護の線引きが曖昧であり、法的な保護が必ずしも完全ではない点が問題視されている。張氏は、今後、法制度のさらなる明確化と調整が必要であると結論づけた。
討論
セッション2の討論では、参加者は、個人情報保護が不正競争防止法と交錯する中で、法制度の統一的なアプローチが求められることを認識しつつ、現行制度の改善に向けた具体的な提案を共有した。全体として、個人情報の保護と市場競争の健全化をどのように両立させるかが討論の中心テーマとなった。
セッション3「メタバース空間におけるリスク管理」
司会 岡田正則教授(早稲田大学比較法研究所所長)
特別講演「リアル3Dアバターを創作するうえでの法的障害への懸念」
森島繁生教授(早稲田大学理工学術院)

森島繁生教授
森島繁生教授は、リアル3Dアバターの制作に関する法的課題について講演を行った。
まず、森島教授は3DスキャナーやAI技術の進展により、本人に酷似したアバターの生成が可能となり、メタバースやバーチャルリアリティ(VR)など多様な分野で活用が期待されている現状を説明した。しかし、これらの技術革新に伴い、肖像権やプライバシー権の侵害、著作権の問題など、法的な懸念が浮上している。特に、本人の許可なくリアル3Dアバターを作成・使用することは、肖像権の侵害に該当する可能性があり、法的リスクが高まると指摘した。
さらに、アバターの商業利用においては、著作権や商標権の問題も生じる可能性がある。例えば、他者のデザインやキャラクターに類似したアバターを制作・販売することは、知的財産権の侵害につながる可能性があるため、注意が求められる。これらの法的課題に対処するためには、技術開発者やユーザーが法的知識を深め、適切な権利処理を行うことが重要であると森島教授は強調した。また、法制度の整備やガイドラインの策定が急務であり、技術と法の両面からのアプローチが必要とされると述べた。
報告1「メタバース空間における財産的損害の概念(知的財産法の観点から)」
上野達弘教授(研究所員、早稲田大学法学学術院)

上野達弘研究所員
上野達弘教授は、メタバース空間における財産的損害について、以下の3つの論点をめぐって、知的財産法の視点から検討を行った。
(論点1:現実世界の街を仮想世界に再現する)
最初に、上野教授は現実世界の街をメタバース内に再現する場合の著作権問題を説明した。具体的には、公開の美術の著作物等の利用がどのように許容されるかが議論されており、現行の権利制限規定が仮想空間でどの程度適用可能かが課題となっている。また、付随対象著作物の利用についても、再現される背景や風景に含まれる著作物が、二次的に利用される場合の法的扱いが曖昧であると指摘した。さらに、仮想空間における商標権問題として、現実世界で登録された商標がメタバース内で無断使用された場合にどのように保護されるかを論じた。最後に、同一性保持権について、建築物や公共の芸術作品が仮想空間で再現される際に、その原型を保つ権利がどのように扱われるかが問題視されていると述べた。
(論点2:現実世界のデザインと仮想世界のアイテム)
次に、上野教授は現実世界のデザインが仮想空間でアイテムとして再現される際の法的課題を取り上げた。仮想空間のアイテム問題として、デザインが著作権や意匠権の保護対象となるかが重要であると指摘し、特に意匠権問題について、仮想空間における独創的なデザインが現行法でどのように守られるべきかを議論した。加えて、不正競争防止法の適用についても説明し、仮想空間での模倣行為が市場の公平性を損なう可能性があると述べた。最後に、仮想空間で使用される商標権問題として、現実の商標が仮想空間内のデジタル製品やサービスに無断で使用された場合の法的対応が未整備である点を指摘した。
(論点3:アバター問題)
最後に、上野教授はアバター問題に関する法的論点を解説した。まず、アバターの著作物性と著作者について、アバターが創作物として認められるか、またその著作者が誰であるかが争点となると述べた。次に、アバターと肖像権に関して、他人の容姿を模倣したアバターが肖像権を侵害するかどうかについて説明した。特に、著名人の容姿を模倣した場合の法的リスクが重要な課題であると指摘した。さらに、アバターとパブリシティ権についても議論し、著名人の名前やイメージが商業的に利用される場合、その使用がどのように規制されるべきかを解説した。
まとめとして、上野教授は、メタバース空間の新たな法的課題に対処するため、知的財産法の再検討が必要であると結論づけた。特に、仮想空間での権利保護を強化するための具体的な法整備が求められると強調した。
報告2「メタバース空間における人身損害の概念(誹謗中傷・ハラスメントとの関連)」
山口斉昭教授(研究所員、早稲田大学法学学術院)

山口斉昭研究所員
山口斉昭教授は、メタバース空間における人身損害の法的課題を整理し、誹謗中傷やハラスメントとの関連について詳述した。
まず、山口教授はメタバース上で生じる人身損害に関する新たな法的課題を整理し、仮想空間における名誉毀損や精神的損害が、現行の法制度でどのように取り扱われているかを説明した。特に、メタバース内でのハラスメント行為は、従来の法律の適用範囲を再検討する必要があると指摘し、新たな法的枠組みが求められる状況を強調した。
続いて、山口教授は2022年に実施された「メタバースでのハラスメント」調査(Nem x Mila)について詳述した。この調査では、多くのユーザーがメタバース内で精神的な被害を経験していることが明らかにされ、特に匿名性が加害行為を助長し、現実の社会的制裁が及びにくいことが問題点として浮上していることを説明した。この調査結果は、法改正の議論を促進するきっかけとなり、メタバース空間における被害者保護の重要性を改めて認識させたと述べた。
さらに、山口教授は関連する裁判例をいくつか紹介し、メタバース内での誹謗中傷やハラスメント行為がどのように法的に扱われているかを解説した。判例では、被害者が精神的苦痛を受けたことを立証することが困難なケースが多く、現行の法制度では完全な保護が提供できていない点が明らかになっていると指摘した。
山口教授は学説の状況についても言及し、メタバース内のハラスメントに対する法的対応が専門家の間で活発に議論されている現状を説明した。特に、仮想空間での人格権保護の重要性が高まりつつあり、一部の研究者は、新たな法的枠組みを導入する必要性を提案していると述べた。
なお、山口教授は、メタバース内の人身損害に対する法的対応を検討し、現行の法制度を補完する形で、新たな法的措置を導入する必要があると主張した。特に、ハラスメント行為に対する抑止効果を高めるための規制や、被害者が救済を求めやすくするための制度設計が求められると述べ、具体的な改善策についても提案した。
結論として、山口教授はメタバース空間における人身損害を適切に法的保護するためには、既存の法制度の改正と新たな規制の導入が急務であると強調した。特に、誹謗中傷やハラスメントに対する法的措置を強化し、被害者の権利を効果的に保護するための包括的なアプローチが必要であると締めくくった。
報告3「メタバース空間における損害と保険」
肥塚肇雄教授(研究所員、早稲田大学法学学術院)

肥塚肇雄研究所員
肥塚肇雄教授は、メタバース空間における損害とそれに対応する保険について報告した。
まず、肥塚教授はメタバース・ワールド(MW)とリアル・ワールド(RW)の関係性について説明した。MWは、現実世界とは異なるが密接に関連し合う空間であり、物理的な制約はないものの、経済活動や社会的な関係がRWに影響を及ぼす場合があると述べた。この関係性を理解することが、MWにおける損害の概念を把握する上で重要であると指摘した。
次に、肥塚教授は損害保険の基本概念について解説した。損害保険とは、偶然の事故によって生じる損害を填補することを目的とする契約であり、RWにおいては財産損害や人身損害をカバーする仕組みが一般的であると説明した。これを踏まえて、MWにおける損害がどのように扱われるかが本報告の中心課題であるとした。
続いて、肥塚教授はMWにおける人身損害について考察した。メタバース空間では、アバターが攻撃されたり精神的な被害を受けたりすることがあるが、これが現行の損害保険制度で保護されるかは未解決の課題であると述べた。肥塚教授は、MWでの被害を補償するための「メタバース損害保険契約」が必要であり、被保険者が受ける精神的苦痛やアバターの損害をどのように保険の対象とするかが課題であると指摘した。
さらに、肥塚教授は「蘇り保険」という新しい概念を提案した。これは、メタバース内での精神的損害を受けた場合に、その慰謝料として支払われる保険である。この保険は、仮想空間でのトラブルによる精神的苦痛を和らげるために設計されており、メタバース空間に特化した保険商品が求められていると強調した。
最後に、肥塚教授はメタバース空間における保険制度の整備が急務であると結論付けた。仮想空間での経済活動や人間関係の拡大に伴い、適切なリスク管理と保険制度の導入が社会全体の安心感を支える鍵となると述べた。また、法的整備と技術的進歩の両面から対応する必要性を強調し、今後の課題と展望について示した。
報告4「深層合成技術の法的ガバナンスに対する中国のアプローチ」
徐玖玖氏(中国社会科学院法学研究所ネットワーク・情報法研究室助理研究員)

徐玖玖助理研究員
徐玖玖氏は、深層合成技術に対する法的ガバナンスの現状と課題について報告を行った。
まず、徐氏は深層合成技術(ディープフェイクなど)の応用範囲と特徴を説明した。これらの技術は、映像や音声を高精度に合成することで、メディア制作やエンターテインメント、さらには教育や医療分野においても利用されている。しかし、深層学習アルゴリズムによる精巧なデータ処理が特徴であり、特に人間の感覚では真偽の判別が困難な点が、技術の特殊性を際立たせていると述べた。
次に、徐氏は深層合成技術がもたらすリスクについて言及した。特に、フェイクニュースの拡散、プライバシー侵害、名誉毀損、サイバー犯罪などが懸念されていると述べた。徐氏は、これらのリスクが社会の信頼性を揺るがし、法的・倫理的な問題を引き起こす可能性があると警告した。
続いて、徐氏は深層合成技術に対する法的ガバナンスの基本的論理について説明した。ガバナンスは、技術の利活用を促進しながらも、濫用を防止するためのバランスを取る必要があると述べた。また、透明性、説明責任、プライバシー保護などの原則が法的枠組みに組み込まれるべきだと指摘した。徐氏は、中国での具体的な法的ガバナンス事例を紹介し、各地方自治体でも独自の法整備が進められていることも示した。
最後に、徐氏は深層合成技術に対する中国のアプローチについて解説した。技術の発展を支援しつつも、そのリスクを管理するための包括的な法規制を構築することが目指されていると述べた。さらに、国際的な連携や技術開発者への教育・啓発活動を重視する姿勢も強調されている。中国のアプローチは、迅速な規制と実効的な監視を組み合わせたものであり、深層合成技術の安全な活用を推進するための模範的な枠組みとして評価されることを期待していると締めくくった。
討論
セッション3の討論では、急速に発展する技術に対応するための法的ガバナンスの必要性と、その実施における具体的な課題について、報告者と参加者の間で活発な意見交換が行われた。討論の中では、法的規制と技術革新のバランスをどう保つかが引き続き重要なテーマとして浮かび上がった。
総括・閉会の辞

謝増毅氏(中国社会科学院法学研究所副所長)
謝増毅副所長は、総括として今回のシンポジウムにおける議論の成果を振り返り、各報告者が提示した新技術に関連する法的課題について、実りある議論が行われたことに感謝の意を述べた。謝副所長は、特に日中両国の法学者がそれぞれの知見を共有し合い、新たな技術がもたらす法的・倫理的課題への対応策を共に考えることができた点を高く評価した。
また、謝副所長は技術の進展がますます加速する中で、法的ガバナンスの在り方を議論する機会が今後さらに重要になると指摘し、本シンポジウムが今後の研究と実践に有益な影響を与えることを確信していると述べた。最後に、謝副所長は参加者全員の貢献に感謝し、引き続き法学の分野で国際的な協力を深めていくことを願いつつ、シンポジウムを閉会した。
(文:杜 雪雯・比較法研究所助手)

