- ニュース
- 【開催報告】シンポジウム「ESG-21世紀における欧州でのビジネスの変貌」が開催されました
【開催報告】シンポジウム「ESG-21世紀における欧州でのビジネスの変貌」が開催されました
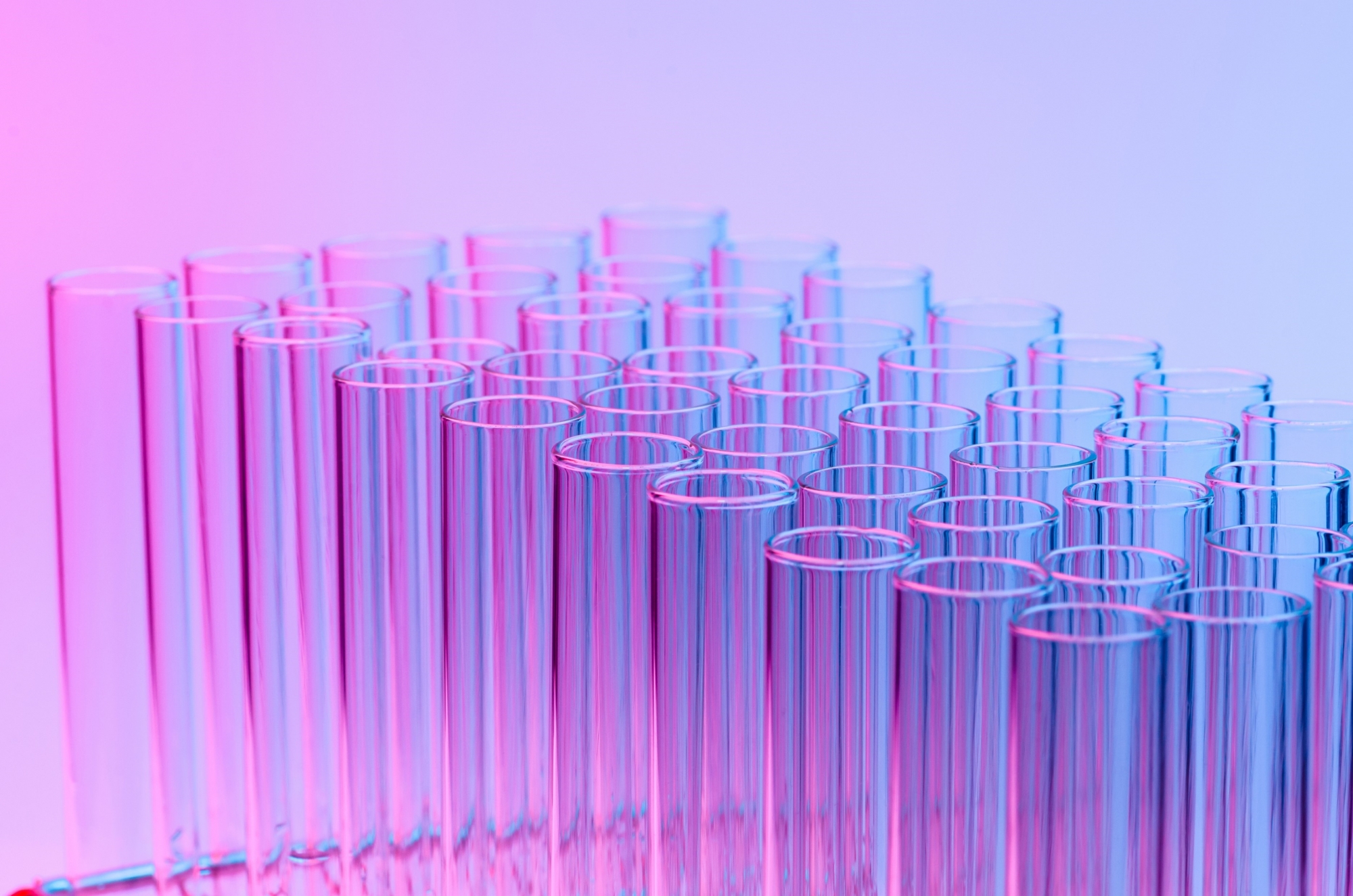
Dates
カレンダーに追加1012
THU 2023- Place
- 早稲田キャンパス8号館303会議室
- Time
- 13:00-16:00
- Posted
- Mon, 23 Oct 2023
シンポジウム「ESG-21世紀における欧州でのビジネスの変貌」
主 催:科学研究費(B)(「現代社会の多様なリスクへの法的対応と民事責任立法提案」(代表大塚直)、科学研究費(A)(「自然の権利の理論と制度-自然と人間の権利の体系化をめざして」)(代表大久保規子 大阪大学大学院法学研究科:研究分担者 大塚直)
共 催:早稲田大学比較法研究所
日 時:2023年10月12日(木)13:00~16:00
場 所:早稲田キャンパス8号館303会議室
世話人:大塚直(早稲田大学法学部教授、早稲田大学比較法研究所研究所員)
参加者:16名(うち学生4名)
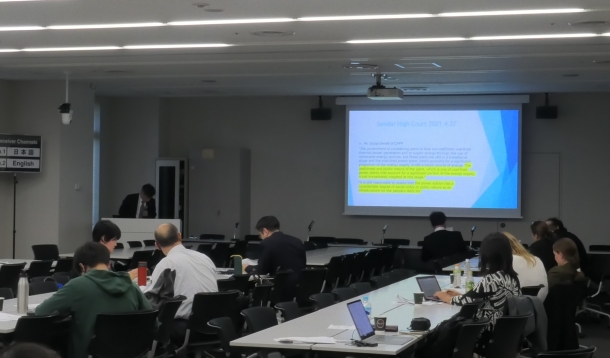
2023年10月12日、早稲田大学にて、シンポジウム「ESG―21世紀における欧州でのビジネスの変貌」が開催されました。このシンポジウムは、特に気候変動対策の観点から環境法政策がドイツ・欧州でどのように変容しているかについてご報告いただくとともに、それを日本の状況と比較検討することを目的として開催されました。最初に、大塚直教授(早稲田大学法学学術院、比較法研究所研究所員)とProf. Marc-Philippe Weller(ハイデルベルク大学)より、開会にあたっての挨拶がなされました。
気候中立性への道程-欧州とドイツの気候規制
Ms. Camilla Seemann(ハイデルベルク大学)
Ms. Seemannは、まず気候中立性という目標を達成する上でドイツが国際法上・EU法上・国内法上どのような義務を負っているかを紹介した上で、現状のドイツ政府の実際の取り組みのみではこの目標の達成は困難であることが明らかになっていると議論されました。そして、気候中立性という目標を達成する上で、公法のみならず私法・会社法の変革が必要であると論じ、その具体的な変革提案として、気候クオータ(Climate Quota)や、「気候中立性」の名称表示の導入、気候中立性への取り組みについて株主が意見を言える仕組みの整備などが提案されました。
気候変動に対する中立性を強制するための戦略的訴訟
Prof. Marc-Philippe Weller(ハイデルベルク大学)
Weller教授は、気候中立性を推進するための手段のひとつである気候訴訟について注目するものでした。報告の中で、世界的に増加している「気候訴訟」の諸事例をいくつかのタイプに分類し、その中でどのような法律・法理論が活用されていたかを明らかにした後、特に不法行為法から派生する気候変動への責任条件について考察されました。
気候規制と訴訟の重要な概念としての因果関係と帰属
Prof. Dr. Chris Thomale(ウィーン大学、ローマトレ大学)
Prof. Dr. Thomaleは、特に気候訴訟の中で、温室効果ガスの排出と気候変動への影響との因果関係が非常にナイーブに扱われているという点を指摘し、これまで裁判所が長い間原則として採用してきた因果性の観念、つまり「but-for」テストを厳密に守った上で因果的責任の所在を判断すべきであると議論されました。
日本における気候民事訴訟
池田直樹教授(関西学院大学)
池田教授は、日本ではまだ比較的新しい現象としての気候変動訴訟について概観した後、日本の法制度が抱える問題点を検討しました。報告の中で、石炭火力発電所によるCO2排出に関する政府処分についての行政訴訟においては、裁判所は行政府に過大な裁量を認め、裁判所による介入の余地がほとんどないという点に問題があると指摘されました。また民事訴訟の方では、裁判所が科学的知見に欠けているため炭素収支の逼迫に関して理解と危機感を欠いていること、また、「クリーンで健康的で持続可能な環境への基本的権利」への注目が欠けていることを指摘し、そのような新しい権利の確立と包括的な制度改革が求められていると議論しました。
パネルディスカッションが行われた後、大塚直教授によって閉会の挨拶がなされました。
(文:松田和樹・比較法研究所助手)

