- ニュース
- 【開催報告】日中シンポジウム「新技術と法Ⅲ」が開催されました
【開催報告】日中シンポジウム「新技術と法Ⅲ」が開催されました

- Posted
- Wed, 09 Nov 2022
日中シンポジウム「新技術と法Ⅲ」
主 催:早稲田大学比較法研究所、中国社会科学院法学研究所
共 催:早稲田大学先端技術の法・倫理研究所
日 時:2022年9月5日(月)9:00-18:00
場 所:Online(Zoom)
参加者:57名
2022年9月5日、早稲田大学比較法研究所と中国社会科学院法学研究所は、オンライン・シンポジウム「新技術と法Ⅲ」を共同で開催いたしました。
このシンポジウムは、2019年9月、2021年9月に両研究所が開催した共同シンポジウム「新技術と法Ⅰ」「新技術と法Ⅱ」につづく第三弾です。前回は、日中の法学者が人工知能や知的財産、金融法、経済法、刑法などを含む非常に幅広い分野に関して、報告・議論いたしました。今回の第三弾では、引き続き日中両国に現在生じている問題への対応について、以下の通り議論しました。
開会の辞
最初に、莫紀宏・中国社会科学院法学研究所所長が開会の辞と挨拶を述べられ、続いて、岡田正則・早稲田大学比較法研究所所長が挨拶をいたしました。その中で、新しいテクノロジーの発達は、私たちの生活に便利さをもたらすと同時に、政府のガバナンスに新たな課題をもたらしていること、そして、今日の研究・議論の成果を教育の場で活かしていくことへの期待が述べられました。
-

- 莫紀宏所長
-
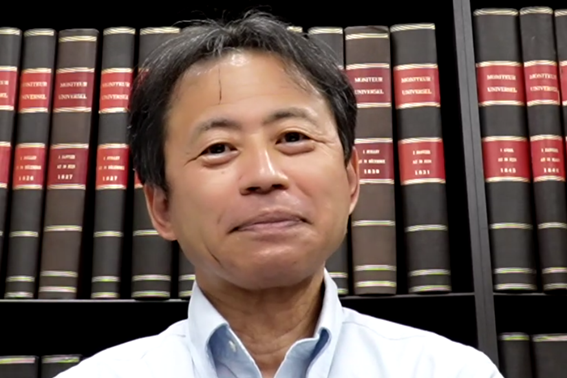
- 岡田正則所長
セッション1「デジタル経済の著作権法規制」

司会 楊延超研究員(中国社会科学院法学研究所科学技術・法研究センター主任)
報告1「日本における著作権制度上の立法課題」
上野達弘教授(研究所員、早稲田大学法学学術院)
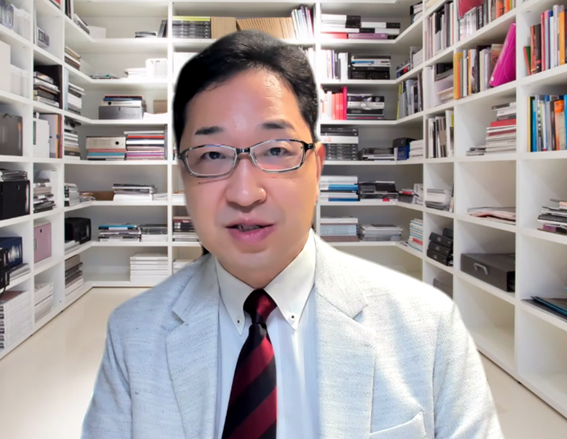
上野達弘研究所員
上野教授は、来年の日本の通常国会で実現される見込みの著作権法改正、とりわけ「簡素で一元的な権利処理方策」について紹介しました。インターネットがさまざまな形でさらなる発展を続けている中、一般の個人であっても、ネット上で入手したコンテンツをもとに二次創作を行い、作成されたコンテンツをまたSNSなどで発信することが一般化しています。しかし、ネット上にありふれている膨大なコンテンツの大部分には著作権や著作隣接権があります。その権利関係が複雑で、権利処理が難しいということになると、コンテンツを利用したさまざまな行為が萎縮する恐れがあります。そのため、コンテンツに関する権利処理を、できるだけ簡便に済ませることができるシステムが求められています。
そこで上野教授は、現在、日本の文化審議会で検討されている「分野横断権利情報データベース」の構築、および、分野を横断する一元的な「窓口組織」による新しい権利処理の仕組みについて紹介しました。
報告2「中国著作権法立法におけるテキストデータマイニング侵害例外規則の構築――中国知網論文査重論争も兼ねて」
管育鷹研究員(中国社会科学院法学研究所知的財産権法室主任)

管育鷹研究員
管研究員は、膨大なテキストやデータリソースを自動的に統計・分析するTDM(Text and Data Mining)技術の利用拡大に注目して、中国におけるTDMによる著作物利用を適切に規律する立法のあり方を検討しました。TDMを行うためには、まずその前提となるデータベースの構築に莫大な資金を投入する必要がありますが、中国における従来の裁判例を見ると、商業的目的をもって他人の作品を大量に複製してデータベースを構築することは、権利侵害として認定されます。他方、諸外国の立法動向を参照する限り、非営利科学研究または教育目的に基づくTDM応用は、広く許される傾向が見られます。
以上に踏まえて、管研究員は、現在の中国でもっとも権威のある学術データベースである「中国知網(CNKI)」をめぐる、最近の著作権と独占論争を紹介しました。CNKIはその学術データベースを構築するために、著者に無断で学術論文をデータベースに収録していると指摘されています。また、CNKIがその学術データベースに基づく剽窃チェックサービスに関しても、その独占的な地位を濫用して、学生や研究機関に対して高額な料金を徴収し、公衆による学術創作活動を制約する疑いがあるという指摘もあります。そこで管研究員は、中国の著作権法において、TDMなどのデジタル技術の発展に応じ、権利侵害の例外規定を構築する必要があると指摘し、その具体的な規則について提言をしました。
コメント 張鵬アシスタント研究員(中国社会科学院法学研究所知的財産権法室)

張研究員は、日中両国の著作権法の現状を比較しつつ、中国における当面の立法課題を、権利制限制度の整備、著作権契約法の構築、および権利処理の簡素化といった三つの課題にまとめました。また、質疑応答において、日本における剽窃チェックサービスの適法性、日本著作権法における情報解析例外規定の導入に際して業界からの反発の有無、「窓口組織」の導入と既存の孤児著作物裁定利用制度との整合性などについて議論がなされました。
セッション2「インターネット医療の法的規制」

司会 李霞副研究員(中国社会科学院法学研究所憲法・行政法研究室副主任)
報告1「中国におけるインターネット医療の法的規制」
周輝副研究員(中国社会科学院法学研究所ネットワーク情報法室副主任)

周輝副研究員
周研究員はまず中国でインターネット医療が非常に発達・普及している状況を説明しました。その中でも周研究員の報告が注目したのは、インターネット病院、即ち、実体病院における初診等を踏まえ、一部の傷病や慢性疾患等のための医療過程の全プロセスをインターネットで提供するものでした。この後、周研究員は、中国のインターネット医療法規制を概観し、現状の法制度の問題点を指摘した上でその解決策を提案しました。現状の問題点としては、第一に、インターネット医療を規制する法の多くが立法レベルではなく規則や規範的文書のレベルに留まっていること、第二に、インターネット医療主体が法的意味での医療施設とされておらずその法的地位が不明確であること、第三に、インターネット医療の特質を踏まえた個人情報保護システムが具体化されていないこと、第四に、特にインターネット病院の経営にIT企業が関与している場合など複数の主体間の法的関係が不明確であること、第五に、現在のところインターネット医療を行政が監督管理するための明確な法的規律や職責区分がなく、国家衛生管理委員会を除いて関連行政部門は既存の職責に基づいて分担してそれを監督しているため、インターネット医療の全プロセスを監督管理する体制が築かれていないことということでした。
周研究員はこれらの問題を解決するために以下のような提案をしました。つまり、オンライン/オフラインのシームレスな監督管理を実効的に確保する制度を創設すること、全国的に統一された管理におけるデジタル化を実現することでインターネット医療独自の優位性をつくること、プラットフォームの責任を強化しプラットフォームにコンプライアンスを徹底させること、医療に関する個人情報を保護・活用する仕組みを整えることで患者のコストを低減させるとともにデータセキュリティを確保すること、そして、金融市場のモニタリングに関する知見を活かしてインターネット医療を監督管理するためのプラットフォームを構築することです。
報告2「日本における遠隔診療規制の経緯について」
山口斉昭教授(研究所員、早稲田大学法学学術院)

山口斉昭研究所員
山口教授は、インターネット医療を含めた日本の遠隔医療への規制の展開を整理した上で、今後インターネット医療を推進する上で留意すべき論点をいくつか列挙しました。山口教授はまず、いわゆる「平成9年通知」に触れ、行政の方針としては、無診療治療等を禁じている医師法20条は直接の対面での医療の提供を基本としており、離島・へき地での医療、病状の安定している慢性期疾患の患者への在宅治療のような場合に例外的に遠隔医療を許容しているとしてきたと述べました。ところが平成30年、インターネット医療を強く推し進めようとする内閣の方針を受けて、厚生労働省は、直接の対面診療の必要性については柔軟に取扱っても直ちに医師法20条に違反しないと示し、遠隔医療を積極的に推進する方向へと政策を転換させたことで、遠隔医療に関する論争は医師法20条の解釈に関するものから、それをいかなる形で推進・規制するかという政策的問題に関するものへと移行することになりました。
この後、特にEDやAGAの治療薬、ピルなどについて、処方来院する必要は一切なしとする医療機関が多数出てきたことが社会的に問題視されたことを受けて、令和元年に厚労省はオンライン診療指針を見直し、改訂したものの、新型コロナウイルスの感染拡大を受けて再びオンライン診療への規制は(時限的・例外的なものという形ではあるものの)緩和されることとなりました。そして令和4年、オンライン診療方針それ自体が改訂されます。この際、医療歴や基礎疾患に関する情報がないまま初診においてオンライン診療が行われることは不適切であり、また、オンライン診療の初診が適さないような傷病があることは医学的にも正しい事実なので、強くオンライン診療を推進しようとする内閣の方針は踏まえつつも、これらの点を重視した形で改訂がなされました。このように山口教授は、遠隔医療・インターネット医療に関する規制の展開を整理した上で、オンライン診療に関する問題と自由診療に固有の問題とを混同しないように留意すべきであることなど、いくつかの論点を指摘しました。
コメント 肥塚肇雄教授(研究所員、早稲田大学法学学術院)

肥塚肇雄研究所員
二つの報告を受けて肥塚教授がコメントを述べました。肥塚教授は、二つの報告の内容に注目し、日中のオンライン医療の規制とそれを取り巻く環境の相違点を整理した後、中にはオンライン診療が適さない場合もあるとしても、特にレントゲンや血液検査などの検査結果に基づいて医療を提供するエビデンス・ベースの医療においてはオンライン/オフラインの差異はあまり問題にならないと説明し、中国やその他の国々を参考にして日本もオンライン医療の活用促進に向けて取り組みを進めるべきであると述べました。
セッション3「インターネット金融と法律」

姚佳研究員
司会 姚佳研究員(中国社会科学院法学研究所『グローバル法学』編集長)
報告1「プログラム化取引の法的規制」
陳潔研究員(中国社会科学院法学研究所商法室主任)

陳潔研究員
陳研究員は、投資家があらかじめ設定した売買ルールをコンピュータにプログラミングして、市場価格の変化に応じて自動的に売買注文をする「プログラム取引」と、その法的規制について検討しました。中国の資本市場には、株式取引において当日の回転取引を許さないこと、取引コストが高いこと、本則市場にマーケットメイク制度が欠けていること、および投資家構成が個人投資家を中心としていることといった四つの特徴が指摘されています。そのため、中国資本市場におけるプログラム取引の発展は、これまで大きく制限されてきました。そうした中、中国におけるプログラム取引の法規制は個々の事件に対処する形で作られてきました。現状では、事前監視、事中監視および事後監視を含むプロセス制御が法規制の主な考え方となっています。
このように、中国は欧米の経験を参照しながら、中国資本市場の特徴も十分に考慮した上で、プログラム取引のリスク防止壁を構築してきたことを、陳研究員は明らかにしました。そこで陳研究員はさらに、法規制の改善策について指摘しました。具体的には、①全体的に監督管理をより精密化にすること、②制度全体の設計を見直すこと、③完備したモニタリング追跡システムを構築すること、④市場間の連動によるリスクを注目することの4点を提言しました。
報告2「日本におけるクラウドファンディングの規制」
黒沼悦郎教授(研究所員、早稲田大学法学学術院)
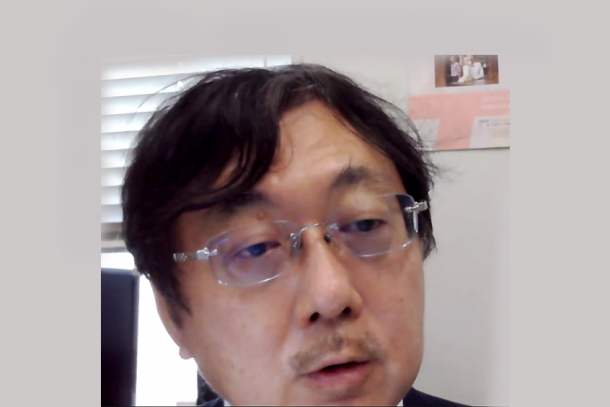
黒沼悦郎研究所員
黒沼教授は、インターネットを通じて企業と個人の間、または個人と個人の間で金銭のやり取りをするクラウドファンディングに着目して、とりわけ株式投資型クラウドファンディングを中心にその特徴と規制の実態について紹介しました。従来では第一種金融商品取引業の登録が必要であった株式投資型のクラウドファンディングですが、ベンチャーキャピタルから資金供給を受ける前の段階にあるスタートアップ企業の資金調達方法として有望であるとして、ベンチャー企業振興のため、2014年の金融商品取引法の改正により、仲介業者が簡易な要件で登録を受けるような制度が創設されました。
株式型クラウドファンディングの特徴に応じた規制が設けられていますが、投資法制として見たとき、黒沼教授は情報開示義務の有無および出資上限額の設置と、投資家の自己責任原則との関係について問題を指摘しました。最後に、黒沼教授は近年のクラウドファンディングに関する紛争事例を紹介・解説しつつ、従来とは異なる規制アプローチを採用したクラウドファンディングの規制の有効性について、さらなる検証が必要であると述べました。
コメント 趙磊研究員(中国社会科学院法学研究所商法室副主任)

趙磊研究員
趙研究員は、陳研究員の報告において言及された「光大烏龍指」事件について補足説明をした上で、中国の資本市場では、とりわけ感情的になりがちな個人投資者が中心となっていることから、プログラム取引が中国の投資市場に与える影響が深刻であると解説しました。また中国においても、2013年から2016年の間にクラウドファンディングが一時期非常に話題になりましたが、政府の規制によってその収益化の余地が制限され、今ではあまり注目されなくなりました。しかし趙研究員は、クラウドファンディングに関する問題はまだ十分に解決されていないままであると指摘しました。
なお、質疑応答において、プログラム取引と民事責任の関係、仲介業者の責任追及、そしてプログラム取引のアルゴリズム登録制度などについて、幅広い議論がされました。
セッション4「プラットフォーム労働者の労働法保護」

司会 謝増毅研究員(中国社会科学院法学研究所副所長)
報告1「プラットフォーム労働者の法的保護――フランスの議論を参考に」
小山敬晴准教授(大分大学経済学部)

小山敬晴准教授
小山准教授は、プラットフォーム労働者の法的保護に関する日本の課題とその解決策を探る上で、フランス法におけるその法的保護の動向を紹介しました。
日本では、実態として使用従属関係があるなら労働法の適用を受けるというのが原則ですが、使用従属関係の有無を判断する際にこれまで重視されてきた基準、即ち時間的・場所的拘束性などが、プラットフォーム事業者とプラットフォーム労働者との関係に見出しにくく、それゆえにその関係には労働法は適用されないとされてきました。現在、UberEatsユニオン団交拒否事案が東京都労働委員会に係属中ですが、今のところ日本ではプラットフォーム労働者の法的保護に関する立法対応や判例などは(労災保険特別加入制度を除き)存在していません。
そこで、日本のこのような無策と言わざるを得ない状況を改善する上で諸外国の法制度を参考にする必要があり、小山准教授はその中でもフランス法の動向を紹介しました。
フランスでは、2020年の破毀院判決が、フランス労働法典上の労働者性に関する伝統的な基準に従ってUber配達員の労働者性を認めました。これは当初、訴訟爆発のような大きな社会的影響をもたらすのではないかとも言われましたが、意外にもそのようなことは起きませんでした。ただ、この判決を受けてフランス政府はプラットフォーム労働者の法的保護のあり方に関する検討を進め、その中でフルーアン報告書が出されました。フルーアン報告書は、プラットフォーム労働者に(プラットフォーム事業者ではなく)就業雇用協同組合との間で労働契約を締結させ、こうすることで社会保障にまつわる保護をプラットフォーム労働者に提供するとともに、プラットフォーム事業者に対する集団法上の権利をプラットフォーム労働者に認めることで、労使対話による両者の対立の解決を促進する仕組みを整えるという案を提言しました。この提言の背景には、2014年の法律で既に作られていた就業雇用協同組合の仕組みへの着目がありました。このようにフランス法では、「労働者か、自営業者か」という単純な二分法に基づく解決を採用せず、独特の仕組みを整えてきました。
報告2 プラットフォーム雇用におけるアルゴリズム管理の論理と規則
王天玉副研究員(中国社会科学院法学研究所社会法室副主任)

王天玉副研究員
王研究員は、プラットフォーム雇用の文脈でアルゴリズムを用いて労働者を管理する仕組みが中国に普及しつつある現状に注目し、そうした管理方法に固有の問題点を析出し、解決策を提言しました。この際、EUやスペインにおける取組みを参照し、中国の法制度の改善にそれを役立てる道を探求されました。
アルゴリズム管理は、プラットフォームの事業者と労働者の需給をマッチングさせる上で重要な役割を果たしています。しかしアルゴリズム管理は、それによって管理される労働者に損害をもたらすこともあります。アルゴリズムを設計する際に考慮ないし予想されていない事柄があったこと、アルゴリズムが濫用されることに伴って、損害がもたらされ得るのです。また、合法的なアルゴリズムが予測不可能な形で、ないし偶発的に、損害をもたらすこともあり得ます。
王研究員は、スペインの判例を参照しつつ、アルゴリズム管理を法的に規制する上で二つの理路があることに注目しました。第一には、インフォームド・コンセント、つまり、プラットフォーム労働者に対するアルゴリズム情報の説明をプラットフォーム事業者に義務付けるというものです。第二には、アルゴリズム管理は労使関係を推定させる要素であるとすることで、アルゴリズムによって管理される労働者を保護するものです。
そして王研究員は、欧州議会・理事会の提言を紹介しました。欧州議会は、インフォームド・コンセントの理路に基づいて、アルゴリズムによって管理される者に重大な法的・経済的影響があったときその者がアルゴリズム事業者に異議申立てをできるような仕組みを整えることを提案しました。また、上の二つの理論を組み合わせるような規制、即ち、アルゴリズムによって管理される者たちが労働者集団のような形で集団的にアルゴリズムについて事業者と交渉することができるような仕組みも提案しました。
コメント 大橋麻也教授(比研幹事、早稲田大学法学学術院)

大橋麻也研究所員
二つの報告を受けて大橋教授がコメントを述べました。大橋教授は、このセッションが、昨年の日中共同シンポジウムにおける「AIと労働法」のセッションを引き継ぐものであり、その際、王研究員より、ドイツでは労働二分法に捕われない形でプラットフォーム労働者の法的保護という問題が解決されていっているという旨の報告があったことに触れ、このようなドイツ法の展開と、今回小山准教授が紹介したようなフランス法の展開との間でどのような差異があると言えるのか、またそのように複雑化される労働法の中でのアルゴリズム管理の位置付けなどについて、コメントをしました。
閉会の辞
四つのセッションを終えた後、閉会のセレモニーが催された。司会は引き続き謝増毅研究員(中国社会科学院法学研究所副所長)が務めた。早稲田大学比較法研究所からは大橋麻也幹事が、中国社会科学院法学研究所からは陳国平副所長が、閉会の辞を述べた(ただし陳副所長の閉会の辞については、謝副所長が代読した)。次回こそは直接の対面での学術的・人的交流がなされることを祈って、閉会した。
(文:周洪騫・比較法研究所助手、松田和樹・比較法研究所助手)

