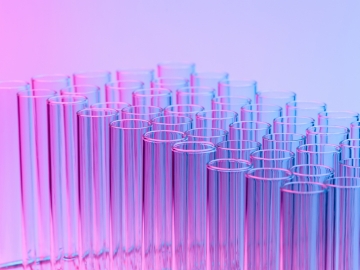=ドイツ連邦憲法裁判所判例における刑罰概念=
【主 催】早稲田大学比較法研究所
【日 時】2025年3月5日(水)15:00-17:30
【場 所】早稲田キャンパス 8号館303大会議室
【使用言語】ドイツ語
【通 訳】中田 己悠(学術振興会特別研究員DC1)
【講演者】ルイス・グレコ(フンボルト大学教授)
【世話人】松澤 伸 (比較法研究所研究所員、早稲田大学法学学術院教授)
参加者:24名(うち学生2名)
【開催概要】
2025年3月5日、早稲田大学比較法研究所において、ルイス・グレコ教授(フンボルト大学)を講師に迎え、「ドイツ連邦憲法裁判所判例における刑罰概念」と題する講演会が開催されました。本講演では、ドイツ基本法における「Strafe(刑罰)」という語の意味内容について、ドイツ連邦憲法裁判所の判例を素材として検討が行われました。とりわけ、同判例における刑罰概念の形成とその変遷を、関心の前提となる認識構造に着目しつつ整理するとともに、それらの理解可能性についても分析が加えられました。

【講演内容】
冒頭においてグレコ教授は、本講演が二つの目的を追求するものであることを明らかにしました。第一に、価値判断を伴うことなく、ドイツ連邦憲法裁判所が数十年にわたって発展させてきた「刑罰(Strafe)」という概念とその解釈を、記述的に把握すること。第二に、記述的観点から離れ、規範的・評価的・批判的な観点から、裁判所の理解における問題点や改善の可能性を指摘すること、という二点です。
この二つの目的に沿って、本講演は三つのステップで構成されました。まず、ドイツ連邦憲法裁判所の判例に共通する認識関心が明確にされ、刑罰概念が特別な制度として扱われており、その適用に際しては厳格な要件が課されることが確認されました。次に、刑罰概念の展開が二つの段階に分けて整理されました。すなわち、第一の定着段階においては、刑罰概念の決定的な特徴が試行錯誤を通じて明確化され、第二の確証段階および深化段階においては、それらの特徴が繰り返されつつ、具体的な結論の基礎として活用されていました。最後に、これらの判例に見られる刑罰概念の理解が妥当なものであるかについて、控えめながらも再構成と評価が試みられました。特に、裁判所の判例に内在する一貫性の欠如や理論的課題に着目し、それらの問題点と今後の発展可能性についても論じられました。

【質疑応答】
質疑応答では、講演の結語で触れられた今後の発展可能性の具体的な意味を問う質問、比例原則の枠組みにおいて刑法上の原則をいかに位置づけるかをめぐる質問、国家論と刑罰論との関係に関する質問など、多岐にわたる内容が寄せられました。これらの質問に対し、グレコ教授は、判例を批判的に読み解くことの重要性、比例原則と責任主義の論理構造の違い、刑罰が国家機能の中で担う特殊な位置づけなどに言及しながら、講演の問題意識とつなげるかたちで丁寧にご回答なさいました。
【文責】杜 雪雯(早稲田大学比較法研究所 助手)
2025.05.08更新