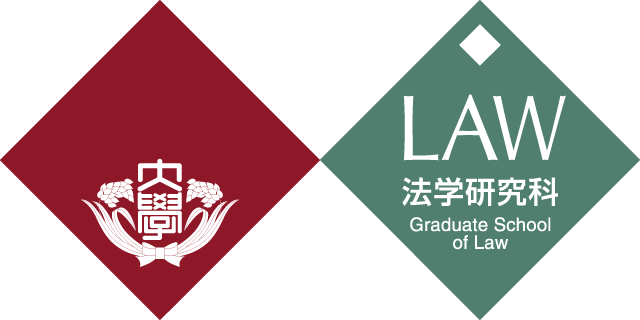- ニュース
- 災害復興支援クリニック、能登半島での活動を報告
災害復興支援クリニック、能登半島での活動を報告

- Posted
- Fri, 28 Nov 2025
早稲⽥⼤学法科⼤学院の「災害復興⽀援クリニック」は、2025年11月9日、早稲田キャンパス27号館にて「能登半島地震被災地⽀援活動報告会」を実施。能登半島地震の発生後における、石川県奥能登地域を中心とした現地での調査・支援活動の内容を報告しました。本記事では、当日のレポートをお届けします。

“実務と理論の架橋”を目指す、災害復興支援クリニックの歩み
2011年の東⽇本⼤震災の発⽣直後、早稲⽥⼤学法科⼤学院の教員17名の有志により「早稲田大学東日本大震災復興支援法務プロジェクト」が発足し、福島県浪江町での活動を開始しました。同プロジェクトは「震災復興支援クリニック」への再編を経て、学⽣・研究者・実務家の有志により、福島県浜通り地域における調査活動を実施してきました。
クリニックはその後、2024年の能登半島地震を受け、被災地における調査・支援活動を行っています。2025年度からは、さまざまな災害に対応する方針のもと、「災害復興支援クリニック」に改称。現地での活動、地域の現状を共有するのが、今回の活動報告会の目的です。現地とオンラインのハイブリット開催となったイベントには、約60名が参加しました。
冒頭では、弁護⼠で法務教育研究センター助⼿を務める尾川佳奈氏により、プロジェクトの目的と背景が説明されました。
「2011年に発足した『東日本大震災復興支援法務プロジェクト』の趣旨は、復興支援に法科大学院が主体的に取り組み、研究者と実務家が創造的な復興支援活動を実践するとともに、そこに学生も可能な限り参加することで、『実務と理論の架橋』という法科大学院の理念を実現することでした。福島県浪江町では、町役場の行動記録に向けた全職員への聞き取り調査、町民に対する被害実態アンケート調査、町による賠償請求の支援などを実施しました」

尾川佳奈さん(法務教育研究センター助手、弁護士)
2016年からは法科大学院の学生が主体的に活動する体制となり、例年10〜30名程度の学生が参加してきた同プロジェクト。能登半島地震をきっかけに、活動拠点を福島から能登に移し、過去の経験を生かした被災地支援を行っています。
「研究会や事前学習、活動内容の検討を行った上で、2024年9月より現地での活動を開始しました。珠洲市、輪島市、能登町、穴水町、七尾市、内灘町などの地域にて、自治体、社会福祉協議会、仮設住宅、事業者など、多くの関係機関を訪問。1年間で総計43名の学生が参加しています」
能登半島における災害復興支援クリニックの支援活動は、二つに大別されます。一つは、質問に対するリサーチ・回答書作成などを通じた、自治体への支援。罹災証明制度、住民クレーム対応、個人情報保護などの質問に対し、学生がリサーチ・回答書をドラフト作成し、教員・弁護士がレビューを行います。
二つ目は、情報や移動手段、司法人材が不足する被災地における、巡回法律相談の「おしゃべりカフェ」です。法に関する相談の心理的ハードルを下げることを目的に、学生が地元の方々と会話することで、現地の課題を発見し、支援につなげてきました。
今回の報告会では、一連の活動に参加した学生が、被災地の現状や活動の成果を共有していきます。
参加学生から共有される、能登半島の状況
法科大学院修了生の横谷純一さんは、能登地域を3回にわたり訪れ、被災住民が語り部となって体験を伝える復興支援ツアーに参加。珠洲市宝立町を中心に、見附島、みなと橋、キリコ倉庫跡などの被災状況と、その後の変化を報告しました。
「初めて珠洲市を訪れたのは2024年9月。震災から半年が経過したにもかかわらず、倒壊家屋がそのまま残されている状況に、言葉が出ませんでした。1年後に珠洲市を再訪した際には、倒壊家屋の撤去や仮設住宅の建設が進んでおり、復興が着実に進んでいると実感。同時に、能登で暮らす人々が不安を抱えながら生活をしていることから、時期に応じた支援の必要性も感じました」

横谷純一さん
つづいて、法科大学院2年生の伊藤寛之さんが、輪島市の現状を報告。輪島朝市や輪島きりこ祭り、天領黒島など、地域文化や建造物の状況が伝えられました。
「平安時代から現代までつづく伝統ある輪島朝市は、地元食材や工芸品が取引される活気ある朝市です。しかし地震を受けて焼失し、現在は特設会場での臨時開催や出張などの形態で継続しています。輪島市は、2024年9月に発生した豪雨の影響も大きく、これら地元文化の復旧・復興に遅れが生じています。人々を支える福祉や教育、産業や文化を復活させることで、朝市や祭りの熱気が戻り、地域が再び活性化する。そうした循環を生み出すことが、能登全体の復興にもつながると感じました」

伊藤寛之さん
交流を通じて把握する、被災地の人々が抱える課題
法科大学院修了生の籠大樹さんからは、「おしゃべりカフェ」の活動について報告されました。
「クリニックでは、学生の調査活動に弁護士が同行するため、訪問先で法律相談を受けることが可能です。しかし実際には、法律相談として募集するとハードルが高まり、参加者が集まらない事態が生じます。課題が法律領域に属すると気づかない被災者も少なくありません。そこで法科大学院生との交流を目的に、課題を一つ一つ発見し、弁護士らの法的支援につなげていくのが、『おしゃべりカフェ』です。支援制度を活用した住まいの再建について知ることができるボードゲームを導入するなど、企画内容も工夫することで、一定の効果を得ることができました」

籠大樹さん
法科大学院3年生の兼板祐太朗さんは、「おしゃべりカフェ」への参加を通じ、「支援制度の認知」に課題を感じたと振り返ります。
「おしゃべりカフェを実施した仮設住宅の集会所は、入居者が普段から交流の場としていることから、学生との話しやすさという点で適切だったと思います。現地での会話を通じ、支援制度の利用状況や理解度には、個人差があることもわかりました。近くに手続きをサポートする人が住んでいる場合は、比較的制度が利用されていますが、そうではない方もたくさんいらっしゃいます。ゲームなどを用いた解説や理解浸透は、そうした課題にアプローチできます」

兼板祐太朗さん
「おしゃべりカフェ」につづき、聞き取り調査の活動報告も行われました。法科大学院3年生の逸見蒼真さんは、和倉温泉の調査(2024年実施)、障害者福祉施設の調査(2025年実施)について報告。復興の状況と、法的課題に関する現地の声を紹介します。
「訪問した障害福祉サービス多機能型事業所では、発災後より自主的に福祉避難所を開設。しかし行政の支援をなかなか得られず、仮設トイレも自費で建てるなどの困難もありました。現在は障害者福祉施設として通常の運営をしていますが、建物の改修や人員不足が課題となっています。この取り組みは、自助・共助が成功した事例である一方、それゆえの疲弊も感じ取られました。局地的な自助・共助の実践をどのように把握し、支援するのかも、今後の重要な課題だと思います」

逸見蒼真さん
法科大学院3年生の西村奈々伽さんは、珠洲市の狼煙町での聞き取り調査について報告。日本財団の支援によって建設された交流スペース「狼煙のみんなの家」を訪問した体験を語りました。
「地元の方々が頻繁に利用する『狼煙のみんなの家』は、倒壊した家屋の瓦の再利用、防災や発電の機能導入など、地元のニーズとデザイナーのアイデアが融合してできた施設です。しかし、イベント開催などにおける若手人材の不足を課題として抱えています。ボランティアの総数が減少していることなどから、まち全体の復興でも若者の力は必要とされており、移住制度なども活用した対策が必要だと感じました」

西村奈々伽さん
能登半島の声を、未来への教訓として生かしていく
報告会では、クリニックに参加した学生より、今後の展望も伝えられました。福島と能登の両方の活動に参加した法科大学院3年生の糸部萌子さんは、両地域の課題の違いに着眼し、法科大学院生の役割について意見を述べました。
「震災から12年経過(訪問当時)した福島は、ふるさとや地域コミュニティの回復、次世代への継続に悩まれている方が多かったのに対し、能登では罹災証明や生活再建制度など手続きに関する情報が不足し、生活の先行きが不透明である方が多かったです。発災からの経過年数によって、被災者の困り事も異なるため、弁護士や法科大学院生が担うべき役割も変わるのだと実感しました。能登においては、複雑な情報をわかりやすく伝えるなど、学生が貢献できることも多いはずです」

糸部萌子さん
伊藤寛之さんは、被災後の生活再建を考える「復興法教育」の重要性について説明するとともに、災害復興支援クリニックの可能性について総括しました。
「活動の柱である『おしゃべりカフェ』では、被災者一人一人の生の声を聞いてきました。それらを整理・抽象化し、未来の被災者に教訓として伝えていくことも重要であるため、今後は復興法教育を第二の柱として取り組んでいきたいです。一気通貫の活動により、復興力のある社会、被災をしても希望を持てる道を歩むことができるのではないでしょうか」


会場の様子
現地活動の経験を、実務家育成にも生かしていく
学生の発表後、質疑応答を経て、報告会は終了。参加者の一人であり、「東日本大震災復興支援法務プロジェクト」の立ち上げに携わった弁護士の日置雅晴氏は、今後における活動の継続に期待を込めます。
「大学院法務研究科(法科大学院)の教授として15年前に関わったプロジェクトが、ここまで継続・発展してきたことを嬉しく思います。原発事故を受けた福島は、過去に経験のない課題が生じ、法学領域の教員の知見を結集させる必要がありました。そして、かつて活動に参加した法科大学院の学生が、弁護士として現地活動を継続しているケースもあります。若手人材の現場経験は有意義であり、今後も世代を超えた支援が続くことに期待します」
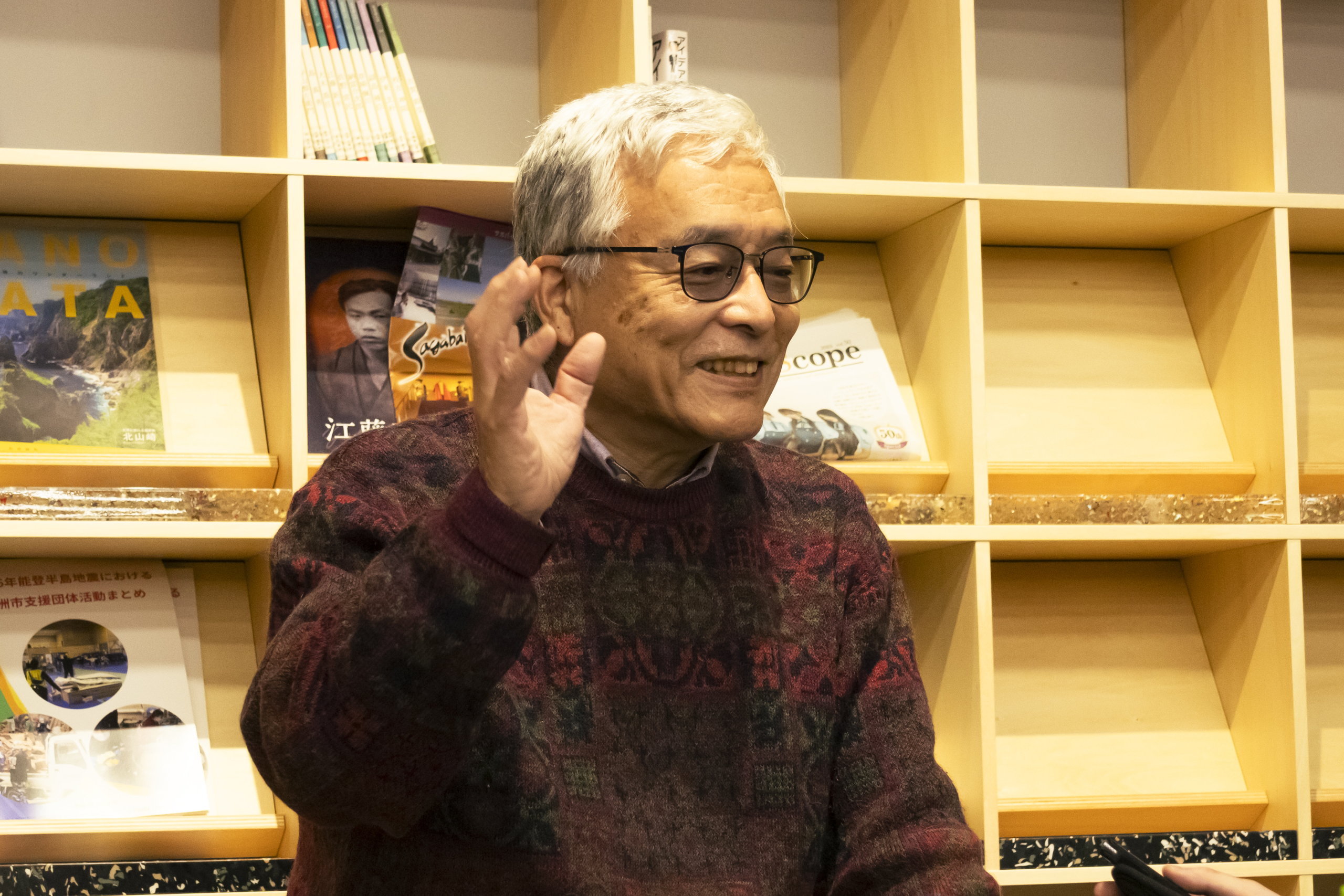
日置雅晴氏
登壇した伊藤寛之さんは、外部を含む参加者に情報を共有できたことに、手応えを感じたようです。
「任意団体であったクリニックが、大学が推進するGlobal Citizenship Centerの活動として認められ、幅広い方々に向けた報告会を開催できたことは、非常に有意義でした。今回は『復興法教育』を提言させていだきましたが、被災者の方々よりいただいた声を未来に生かし、活動の幅を広げていくことが、私たちの使命だと感じます」
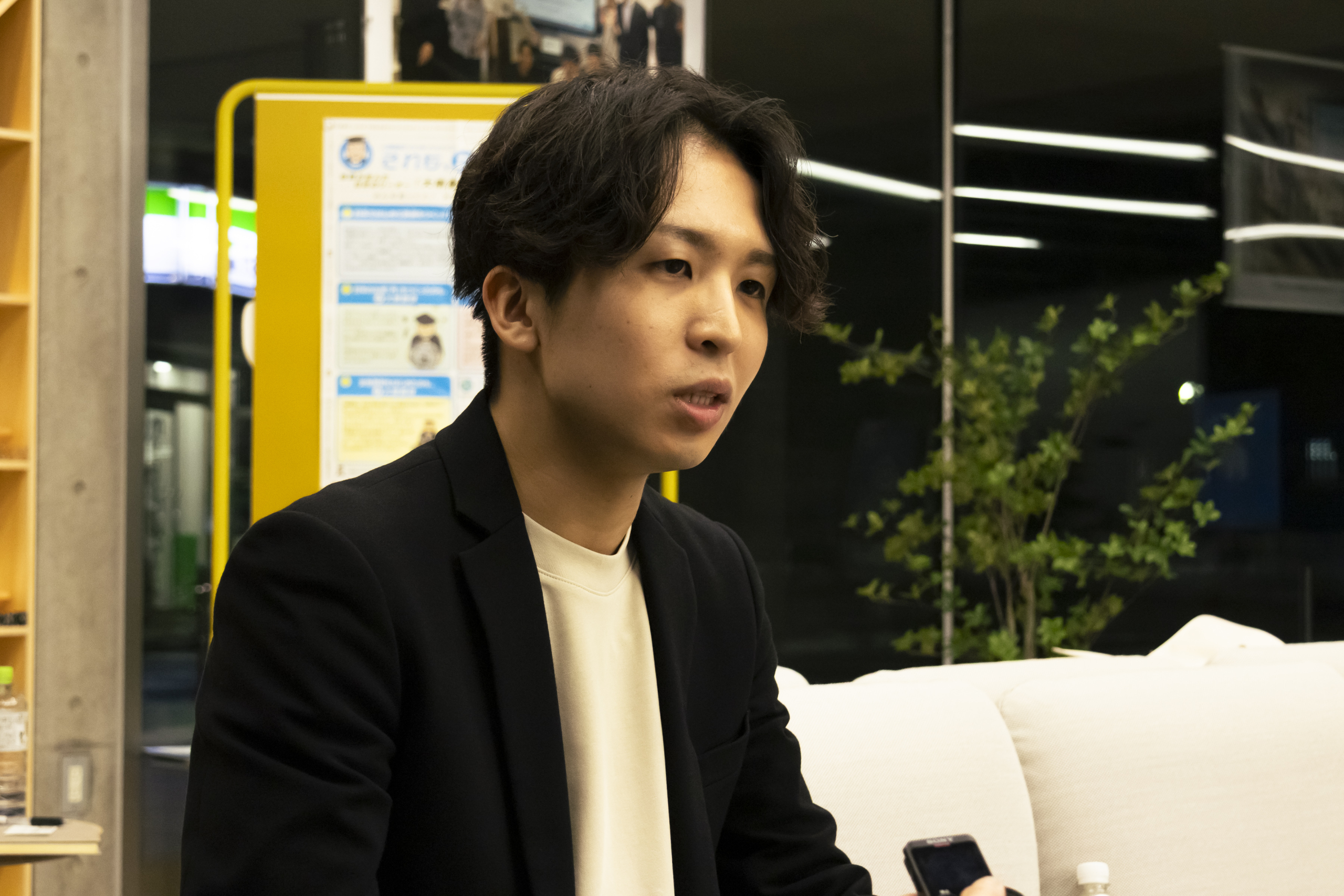
伊藤寛之さん
イベントを企画した尾川佳奈さんは、実務家育成におけるクリニックの意義を改めて感じたと語ります。
「企画・準備から発表まで、学生に主体的に動いてもらうことで、実際の声を届けることを意識しました。私自身も法科大学院時代に福島の活動に参加しており、現在は法務教育研究センター助手の立場から参画しています。将来実務家として活動する学生にとって、被災地の現場で課題を知ることは重要です。今後もクリニックの活動が広がっていくよう、尽力してまいります」

尾川佳奈さん

撮影:GCC Common Room(早稲田キャンパス27号館1階)
【主催】早稲田大学法科大学院
【開催概要】開催案内