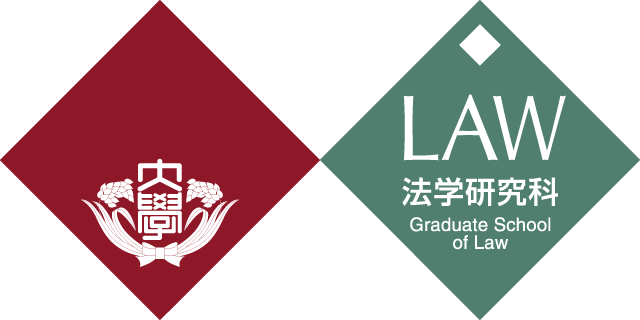- ニュース
- 稲門奨励賞 2024年度受賞者が決定
稲門奨励賞 2024年度受賞者が決定

- Posted
- Fri, 25 Apr 2025
2024年度稲門奨励賞受賞者について
受賞者
・石井 未来氏
活動内容:国際社会を舞台に立法や政策に携わるという法曹としての将来像を描き、これに向けて積極的に多くの国際機関でのエクスターン・インターン活動に挑戦した。
・関 怜禾氏
活動内容:自身のバックグラウンドや留学経験を生かし、留学生の生活向上を図るべくサポートを行う新サークルを設立し、留学生らが継続的なサービスを受けられる態勢を整えた。
・堀江 智仁氏
活動内容:非行少年の更生支援を目的とする「東京少年友の会」において長年にわたり活動を続け、会の活動の維持・継続に大きく貢献した。
- 選考委員所感
在学中の司法試験受験が可能になった影響で、在学生にとっては、司法試験受験前に課外活動に取り組む時間を確保することが、以前よりも難しくなったと考えられる。一方で、司法試験受験後は、より自由で多様な活動に取り組むことが可能となった。当研究科の学生には、司法試験合格のその先を見据え、社会に貢献する活動や専門性を深める取り組みに積極的に挑戦してほしい。
次年度以降も、当研究科の学生から新たな「挑戦する法曹」が生まれることを期待している。
なお、稲門奨励賞の応募に際しては、応募理由書の提出が義務付けられており、審査委員はその内容を確認している。しかし、選考委員会(面接選考)が実施されることを踏まえると、応募者は自身の活動について、本賞の趣旨に沿ったプレゼンテーションができるよう心掛けることが望ましい。
・石井 未来氏 受賞理由
石井氏の活動のうち、特に顕著な実績として挙げられるのは、バージニア大学への留学中及びその前後に、数多くの国内外の機関におけるエクスターン・インターン活動に積極的かつ主体的に参加してきたことである。留学前は、法務省、経済産業省といった国内での機関のみならず、「Save the Children」といったNGOの活動に従事したほか、留学中及び留学後も、世界銀行、ハーグ国際私法会議、国際連合といった国際社会を代表する機関でインターンを行い、人権問題に関して国際社会を舞台に一貫した活動を行ってきた。
石井氏は、「1%でも可能性があるなら挑戦するべき。」をモットーに、自身の興味関心を法科大学院や国内にとどめることなく、世界へ目を向けて熱意をもって活動をしてきた。特に、インターンを行った国際機関の中には、日本人として初めてのインターン生というものもあり、その開拓精神や挑戦への姿勢には、目をみはるものがある。
このような石井氏の活動は、意欲や積極性が認められることはもちろん、自己の目標を的確に見定め、様々な経験を通して、それらを国際社会に還元しながら挑戦してきた成果と認められ、まさに「挑戦する法曹」の在るべき姿といい得るものであるから、奨励賞の受賞にふさわしい活動といえる。
なお、選考においては、石井氏の活動に関して「活動が自分の中で完結しているのではないか。」という意見もあったが、一個人そして法科大学院生としてこれほど国際活動に自発的に「挑戦してきた」経験を持つ者は少なく、今後、将来の国際社会での活躍が大いに期待されることから、次世代への影響力も大きいと考える。このような意欲と挑戦を評価し、奨励賞の受賞にふさわしい活動と認定した。
・関 怜禾氏 受賞理由
関氏の活動のうち、特に顕著な実績として挙げられるのは、在校生と海外ロースクールからの留学生の交流促進を目的とする新サークル「WASEDA GLOBAL EXCHANGE」を設立し、留学生の生活サポートや、留学を希望する在校生の個別サポートを積極的に行ってきた点である。本年度は過去最大規模となる約25名の留学生を受け入れたが、関氏はその対応に中心的な役割を果たし、言語や文化の壁を越えたサポート体制の整備に尽力した点は特筆に値する。
同サークルの活動は、2023年度稲門奨励賞を受賞した金仁浩氏の活動の延長線上にあるものの、関氏は金氏とともに組織化を進め、単なる継続にとどまらず、新たな施策を導入し、活動の発展を図った。特に、ネットワークを活用した留学生との継続的な交流や、留学を希望する在校生に対する情報提供の仕組みを強化した点は、国際的な視野を広げる試みとして高く評価される。また、関氏の活動は、単なる個人の努力にとどまらず、後輩への情報提供や支援の枠組みづくりにも及んでいる。法務研究科において、留学生支援が一過性のものではなく、継続的なものとして確立されるよう取り組んできた姿勢は、今後の国際的な法曹育成にも大きな示唆を与えるものである。
特に、本年度、過去最大の留学生を受け入れた法務研究科にとって、関氏をはじめとする上記サークルの活動は非常に有意義なものであり、同サークルの存在意義は高く認められる。
なお、同サークルは承認団体ではないものの、本奨励賞は、承認団体としての設立そのものを評価するものではない。今後、インターカレッジサークルの設立や、法科大学院間での連携などを模索し、より持続可能な活動へと発展していくことを、選考委員一同期待している。
・堀江 智仁氏 受賞理由
堀江氏は、非行少年の更生に強い関心を持ち、インターネットを含む現代的な少年非行の問題に深く関わりながら、自らワークを立ち上げ、現場で少年と直接関わることで、その認識と感覚を深めていった。特に、2020年に一旦停止していた会の活動を復活させるため、学生を中心に家庭裁判所へ活動再開の打診を行ったことや、「SNSワーク」の実施を学生側から推進し、家庭裁判所や弁護士会との連携を進めている点は、その実践力を高く評価できる。東京少年友の会は既存の団体であり、単にその団体に所属して活動を続けるだけでは評価の対象とはならない。しかし、堀江氏は学部時代から参加していた同団体での活動を法科大学院入学後も継続し、家庭裁判所に赴き、少年と1対1で事例を用いたケースワークを行うなど、積極的な関わりを続けてきた。さらに、「SNSワーク」という新たな試みを提案し、実践したほか、全国付添人経験交流集会にも参加し、発表を行うなど、活動の幅を広げている。このような社会的に意義のある重要な活動を継続して行ってきたことは、十分に評価に値する。
また、堀江氏は、活動の持続性にも重点を置き、月1回の自主研修を通じて少年ボランティアの育成に取り組んでいる。法科大学院内での勧誘活動を通じて、同期を巻き込み、活動の広がりを生み出しており、国内の非行少年の更生支援における新たなモデルとなることが期待される。このような堀江氏の活動は、法務の現場に活かされるだけでなく、社会モデルとしても大きな影響力を持つ。それゆえ、堀江氏の活動は、奨励賞の受賞にふさわしいものである。