- ニュース
- 「モヤモヤからワクワクへ 解放のための学びの実践研究」文学部 矢内琴江准教授(新任教員紹介)
「モヤモヤからワクワクへ 解放のための学びの実践研究」文学部 矢内琴江准教授(新任教員紹介)
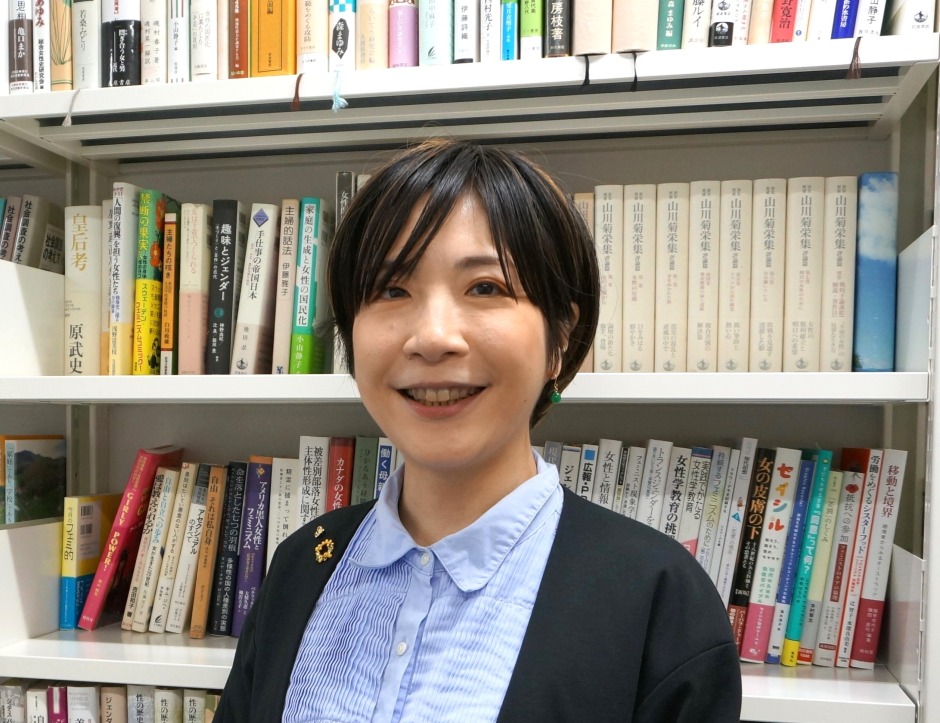
- Posted
- Fri, 13 Jun 2025

自己紹介
みなさん、こんにちは。私が早稲田大学で、皆さんと考えたいことは、3つあります。自分たちの身の周りのこと(学校、部活やサークル、家族、仕事など)で感じてきたモヤモヤが、私たちの社会の中にある性、階級、人種や民族などに基づくさまざまな抑圧とどんなふうにつながっているのか。私たちは、どのようにして抑圧から解放されるのか。そして、そのための学習を、日々の暮らし、仕事、活動、学びの中でどんなふうに創り出すことができるのか。

先住民族の女性たちの作ったコミュニティの一部
私はこれらの問いについて、3つの分野を行き来しながら研究しています。1つ目は社会教育学で、おとなやコミュニティの学習・教育を考える学問です。2つ目はフェミニスト・スタディーズで、ジェンダーをはじめとする様々な社会の抑圧的な関係を変革していく研究です。3つ目はケベック研究、北米で唯一フランス語を公用語とするケベック社会の研究です。ケベックのフェミニスト・アートのギャラリーのスタッフ、民衆教育の実践者たち、先住民族の女性たち、フェミニスト・クリスチャンの女性たちが、自分たちの実践を綴ったものを通して、差別や抑圧を克服していくための学習のあり方を考えています。同時に、私自身も、大学生たちや仲間たちと一緒に学び合う場を作りながら、より良い学び合いの方途を考えています。

ケベックのフェミニズム・アートのギャラリーの中
私自身は高校生の時に、本当は人間の性は多様であるにもかかわらず、学校や社会の中では性別は男女だけが当たり前となっていることに疑問を持ちました。そのため当時、ジェンダーやセクシュアリティについて学ぶことのできるゼミがあった、早稲田大学の第二文学部に入学しました。そこでは、色々なバックグラウンドを持った仲間たちと、とことん話し合う(ケンカも?)経験しました。学部5年生の時、女性たちの朗読会に参加しました。自由に体を動かしたり声を出したりする不思議なワークショップでした。そこでは最初は声や顔に緊張のあった女性が、回を重ねるにつれて、伸びやかな声と柔らかな表情に変わっていく姿を目の当たりにしました。人が解放されるための知は、本の中ではなく、人と人の関わりの中にあるんだ!と感動しました。修士課程に入ってすぐ、偶然インターネットでケベック州の大学でフェミニズムの視点から暴力について議論する1週間の講座があることを知り、思わず参加しました。それからずっとケベックと関わり続けています。日本からはとても遠い場所だけれども、そこで差別や抑圧の問題に取り組む人たちと出会うと、ここで同様の問題に取り組んでいる人たちの姿や思いが重なります。

ケベックの旧市街
さて、早稲田大学では、どんな人たちに出会えて、どんな声を聞けて、どんな風景を一緒に作っていけるのか、胸がワクワクします。
プロフィール
やうち ことえ。早稲田大学第二文学部社会・人間系専修を卒業。修士課程は同大学大学院文学研究科フランス語・フランス文学コース、博士後期課程は同研究科教育学コースに進学し2018年に博士号(文学)を取得。学部生ではフランス・リヨンに、修士課程ではカナダ・ケベック州に留学。ケベックではラヴァル大学のフェミニスト・スタディーズのプログラムで学ぶ。博士課程修了後、2019年から福井大学教職大学院で特命助教として学校の先生や公民館職員の方たちの学習を支援する仕事を、2021年から長崎大学ダイバーシティ推進センターで准教授として、大学の中の女性研究者支援やダイバーシティ推進のための事業をコーディネート。2025年4月より現職。
主な著作:『性差別を克服する実践のコミュニティ—カナダ・ケベック州のフェミニズムに学ぶ』(明石書店、2024年)。ミシュリンヌ・デュモン著・矢内琴江訳『ケベックのフェミニズム—若者たちに語り伝える物語』(春風社、2023年)。
(2025年6月作成)
- 新任教員紹介は、研究紹介・アウトリーチからご覧いただけます。


