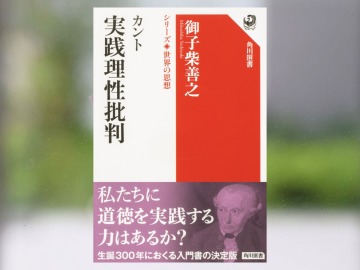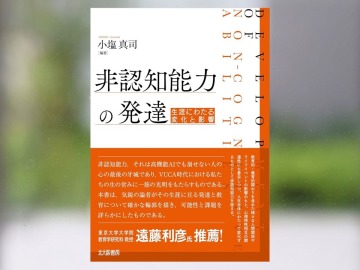なぜ人は国民や民族の名のもとに争うのか
スロヴァキア史やハプスブルク帝国史をはじめとする中・東欧の近世・近代史を研究しています。東欧に関心を持ったのは、高校3年生だった1989年に東欧諸国で起きた体制転換がきっかけでした。その後90年代にはユーゴスラヴィアで内戦が起きるなど、東欧各地で民族紛争が多発しました。遡ると、第一次世界大戦、第二次世界大戦のどちらも東欧から、それも東欧のナショナリズムに起因し始まっています。なぜ人びとは国民や民族の名のもとに争うのか。東欧のナショナリズムの根源を探りたいという思いが、研究の道を進む選択につながりました。
大学院では、スロヴァキアでネイション(国民)がどのように形成されてきたのかを研究し博士論文を執筆しました。スロヴァキアをはじめ東欧の民族は、長らく国家を持たず、近代になってからネイションを作り上げてきた歴史があります。自分たちが何人であるのかという名乗りも定まっていなかったことから、名称を決める作業も必要でした。そのため現在でも国名を巡る論争は根深くあり、ここ10年の間にもグルジアがジョージアに、マケドニアが北マケドニアに国名呼称を変えました。国名論争にとどまらず、複雑に絡み合ったナショナリズムに端を発する紛争や戦争も多く、今次のロシア・ウクライナ戦争もそうです。東欧の一帯が「ヨーロッパの火薬庫」「血の大地」などと呼ばれる理由です。
歴史をたどると、ネイション(国民)という言葉が指すものも、時代により変わってきました。「国民=その国に生まれた人全員」という考え方はここ100年ほどのもので、例えば、中世後期の中・東欧の社会では、身分制議会に参加している貴族だけがネイションでした。つまり、現代のネイションが形づくられてきたプロセスとは、特権身分層に限定されていた国民の枠が、その下の階層の人々へと広がってきたプロセスでもあり、その詳細な過程を明らかにする研究を20年にわたり続けています。またそこから派生し、現地東欧でのアンケートや聞き取り調査を通じて現代の人々のナショナル・アイデンティティの変遷を追う研究も継続しています。

背景や文脈を踏まえ史料を読み解く
国民や国家の意識が形成されていく上ではメディアが大きな役割を果たしました。そのため私の研究の手法としては、当時発行された新聞や雑誌などの史料をつぶさに調べ、分析することが基本になります。これら活字化されている刊行史料だけでなく、当時の人々が書いた日記や手紙といった未刊行史料も含め、ヨーロッパではあらゆる歴史史料が文書館で公的に管理され、誰でもアクセスできます。コロナ禍以降はオンラインで閲覧できる史料が拡充されるなど、遠隔でも史料探索ができる体制が整ってきています。
日記や手紙などの未刊行史料は、現代とは異なる当時の文法で、それも筆記体で書かれているため、解読するには知識と経験が必要です。加えて、その時代の政治や思想、流行していた文化などの背景を理解することも欠かせず、そうした文脈を踏まえて読むことで初めて、言葉の裏にあるものが見えてきます。一方で、史料に記された内容がすべて正しいとは限らないことも、認識する必要があります。例えば政治家の日記であれば、後世に残ることを意識して自身の功績を誇張して書いている場合もあるでしょう。さまざまな角度や距離からテキストを分析することが重要になります。
研究を通して、ときに未知の史料が発見されたり、既存の史料の新しい解釈の仕方が提示されたりして、定説や通説とされてきたものがガラリと変わることがあります。「歴史学」と聞くと、動くことのない事実がそこにあるようにイメージするかもしれませんが、決してそうではないのです。私も過去に、史料分析をもとに本場ヨーロッパの研究者たちとは異なる新たな解釈を提示した経験があり、論文がヨーロッパの学術誌に掲載されたときの喜びはひとしおでした。新たな解釈のきっかけとなった記述は、史料を何百ページ、何千ページと読んだ中のたった1か所です。見つけるまでには途方もない時間と労力を要しますが、定説を覆すような新たな説の提示に自分が関われる可能性があることは、歴史研究の大きな醍醐味といえます。

一次史料を駆使する大学院ならではの探究の魅力
私が所長を務める早稲田大学ナショナリズム・エスニシティ研究所では、定期的にオンラインシンポジウムを開催しています。毎回約500人に上る参加者の中には一般の方も多く、高校生も含まれます。コロナ禍やロシア・ウクライナ戦争を機に、ナショナリズムに対する世の中の関心が高まっていることを実感します。ロシア・ウクライナ戦争を報じるニュース番組ではしばしば、軍事や安全保障の専門家が「今何が起きているか」を解説しています。これに対し、「なぜ起きたのか」を掘り下げて理解するには、歴史をたどり時系列でさまざまな要素の関わりを見ることが不可欠で、歴史学を学ぶ意義はそこにあります。
大学院でさらに深く歴史学を探究する面白さとして第一に挙げたいのは、先ほど触れたように、当時の人々が書いた一次史料から歴史をひも解く研究ができることです。学部の先に大学院の学びを見据えているのであれば、卒業論文のテーマを定める学部3年生ごろから、研究対象の国や地域の言語を学び始めることをおすすめします。早稲田大学では多様な言語科目が提供され、ポーランド語やラテン語も学ぶことができます。開講されていない言語については、外国語学系大学での科目聴講や、文化協会などが開く語学講座を活用する方法もあります。
語学を身につけておくことで、大学院でのスタートダッシュが可能になります。研究を進める上では学内だけにとどまらず、海外留学も含めて積極的に外へ出て、現地の研究者をはじめ多くの人と関わり、いろいろな史料にあたることを大切にしてください。自分で史料を探索し、読み解き、歴史の新たな事実を探り当てていく、このゾクゾクするような探究の楽しさを体感してほしいと思います。
早稲田大学文学学術院教授
中澤 達哉(なかざわ・たつや)

専門は中・東欧近世・近代史、スロヴァキア史、ハプスブルク帝国史、ナショナリズム・スタディーズ。
1971年長野県生まれ。早稲田大学大学院文学研究科史学(西洋史)専攻博士後期課程単位取得退学。博士(文学)。スロヴァキア科学アカデミー歴史学研究所留学後、早稲田大学文学部助手、日本学術振興会特別研究員PD、福井大学教育地域科学部准教授、東海大学文学部准教授などを経て、2018年より現職。この間、スロヴァキア・コメニウス大学哲学部客員教授、英国オックスフォード大学歴史学部附属近代ヨーロッパ史研究センター上席客員研究員を歴任。著書に『近代スロヴァキア国民形成思想史研究―「歴史なき民」の近代国民法人説』(刀水書房、2009年)、共編著『王のいる共和政 : ジャコバン再考』(岩波書店、2022年)など。
(2023年8月作成)