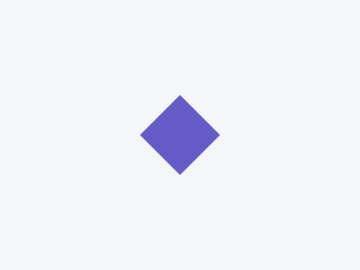(
NPOと連携した孤独・孤立に関する研究にも注力
社会学の中でも特に、ネットワーク論や人間関係論を専門に研究しています。この分野に進んだのは、大学院修士課程での指導教員がネットワーク論の専門家だったことがきっかけです。当時1990年代終わりから2000年代初めにかけては、日本の企業がそれまでの部門・部署ごとの縦割り組織を見直し始めた時期で、博士論文では企業社会における人間関係やネットワーク組織をテーマにしました。
当時はちょうど、日本の社会で「個人」を重視する傾向が強まったときでもあり、それによって人々が人間関係を結びづらくなり、孤独や孤立の問題を伝える報道が増えました。それを機に、孤独・孤立に関する研究に比重を移し、さらに「人のつながりをどう作るのか」という観点から、東京の多摩市をフィールドとする地域コミュニティのあり方についての調査研究や、「友だち」に関する研究にも範囲を広げ、現在に至ります。一般的に社会学の研究者は一つの分野に専念して研究を続けることが多いなかで、私の場合はネットワークや人間関係を軸に、地域、企業、家族、ネット空間も含めて研究テーマが幅広いのが特徴です。
その一つに、子育て世帯を支援するNPOと連携して進めている、子育てと孤独・孤立についての研究があります。現代社会では核家族化や近所づきあいの希薄化により、子育て中の親が孤立しやすい状況にあります。加えて、SNSなどを通して母親友達のキラキラした部分ばかりが目に入り、かえって孤独感を深めたり、自己否定につながったりすることも少なくありません。子育て中の親をサポートするためにNPOが運営するカフェで、利用者への聞き取り調査などを実施し、こうした「居場所」が母親の孤独感や孤立状況にもたらす影響や、より効果的なサポートのあり方などを探っています。研究の結果をまとめた本をNPOの方との共著で2023年中に出版する予定です。

人間関係の悩みの根源を社会学の観点から探る
コミュニケーションの歴史をひも解くと、1970年代に固定電話が過半数の世帯に普及するまで、人々は長らく、身の回りの直接会える範囲の人とだけとやりとりをしていました。90年代に携帯電話が、さらに2000年代にはスマホが急速に普及し、目の前にいない人といつでも気軽に連絡をとることが一般的になり、さらにコロナ禍でオンライン空間が一気に生活の中に入り込みました。直近の20年間で社会が経験してきた変化は非常に急速で激しく、人類史においても特異なものです。この急激な変化は人々の「つながり」にどのような影響を与え得るのか、人間関係は今後どうなっていくのかに私自身は強い関心があり、さらに研究を深めていきたいと考えています。
人間関係で悩みやモヤモヤを抱え、その根源を考えてみたいと思っている人は皆さんの中にも多いのではないでしょうか。その方法として最初に浮かびやすいのが心理学で、相手や自分の心理から人間関係について考えるのも一つのアプローチです。しかし一方で、人間関係のあり方は時代や社会とともに変化しています。かつて、他者と本音で話し合うことや主張をぶつけ合うことで関係性は深まると考えられていたのが、1990年代頃から他者との摩擦や衝突を避ける傾向が表れ、その流れは強まっています。
つまり、人に対して気を遣ってしまう、なかなか相手に踏み込めない、といった現代の人間関係の悩みは、個人の心理というよりも、社会の変化がもたらした側面が強いのです。社会の状況と絡めて考えていくことで、問題の根源や回答、対処法が見つかる可能性があり、それができるのが社会学のアプローチといえます。また、人間関係という非常に身近な問題を研究対象にできることも、学びの面白さにつながるでしょう。

目的に応じ調査方法を適切に選択することが重要に
テクノロジーの進歩により、研究の環境も劇的に変わりました。先行研究の論文を検索し読むこともオンラインで手軽にできるようになり、また、統計ソフトを使うことで調査結果の分析作業も圧倒的に速く楽になりました。複数の変数(項目)間の相互関連を調べるような複雑な分析も、統計ソフトなら1秒で結果が出ます。社会学の研究においてデータ分析の需要は今後も高まるでしょう。一方で、それだけに注力すればよいわけでもありません。質問紙調査をはじめとする量的研究と、聞き取り調査などに代表される質的研究とでは、見えてくるものはそれぞれ異なり、対象が同じであっても質的・量的調査の結果が対照的になる場合も往々にしてあります。どちらかの結果だけを見て結論を下すのではなく、目的に応じて調査方法を適切に選択したり併用したりすることが大切になります。
早稲田大学には、社会学の各専門分野を究めた教員が多数在籍し、国内の大学でも屈指といえる層の厚さです。教員の数が多いということは、常にどこかの研究室で何らかのプロジェクトが進行しているということでもあり、意欲ある学生は研究室の枠を超えてさまざまなプロジェクトに参加する機会を得られます。大学院での研究は特定の分野を深く掘り下げるイメージを持たれがちですが、研究の初期こそ、範囲を狭めずに幅広く見ることが必要です。意外なところに自身の関心を見いだしたり、異なる分野の知見が役立ったりすることも多くあるからです。
研究者を目指す道のりは長期戦になることも多く、相応の覚悟も求められます。しかし長期戦を越えて研究者となった暁には、この立場でしか担えない役割や味わえない醍醐味があると感じます。世の中で主流とされる価値観から距離を置き、立ち止まって考え、「求める結果に最短距離でたどり着くことを良しとする社会で本当にいいのか」「合理性や効率性を追求することは果たして正しいのか」といった問いを投げかけることができる、そんな唯一無二の職業が研究者ではないかと私は思っています。
早稲田大学文学学術院教授
石田 光規(いしだ・みつのり)
 専門はネットワーク論、人間関係論、社会的孤立、地域福祉。
専門はネットワーク論、人間関係論、社会的孤立、地域福祉。
1973年神奈川県生まれ。東京都立大学大学院社会科学研究科社会学専攻博士課程単位取得退学。博士(社会学)。大妻女子大学専任講師・准教授、早稲田大学文化構想学部准教授を経て、2016年より現職。内閣官房「孤独・孤立対策の重点計画に関する有識者会議」メンバー。『孤立の社会学』(勁草書房)、『「人それぞれ」がさみしい ―「やさしく・冷たい」人間関係を考える』(筑摩書房)、『「友だち」から自由になる』(光文社)など著書多数。
(2023年8月作成)