- ニュース
- Let it Roll!(現代文芸コース:有好宏文さん)
Let it Roll!(現代文芸コース:有好宏文さん)
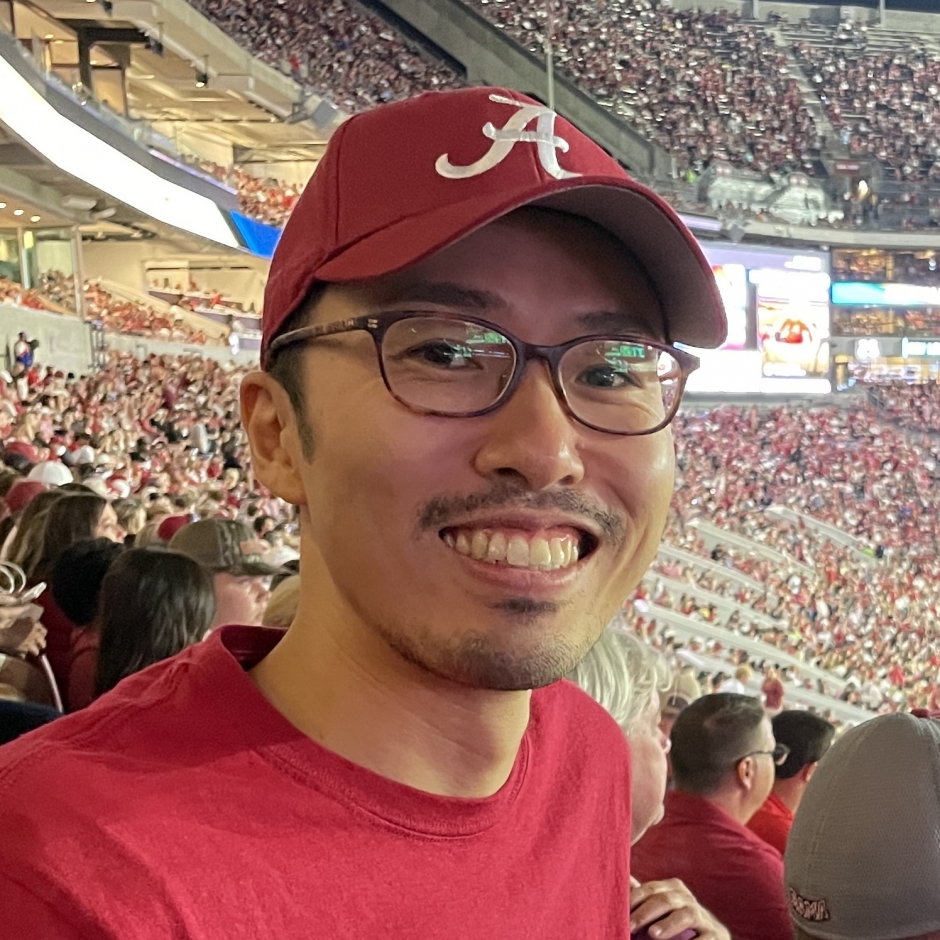
- Posted
- 2022年2月16日(水)
有好宏文さん(アラバマ大学大学院英文科博士課程在学中)
私が現代文芸コースを志望した理由
大学を卒業したあと、文章にかかわる仕事がしたかったので新聞記者になり、配属された香川・兵庫県で事件事故取材のかたわらローカルな地域の話題を担当しました。やりがいのある仕事でしたが、その一方で、海外文学の翻訳をしてみたいという気持ちがだんだん強くなってきました。調べてみると、翻訳を学べる大学院が国内にいくつかあることがわかり、当時教えていらっしゃった翻訳家の青山南教授の翻訳やエッセイのファンだったので、早稲田大学の現代文芸コースを受験しました。アカデミックな文学研究というより、創作や翻訳などを実践的に学べるコースなのも魅力でした。いざ会社を辞めるときにはしばらく悩みましたが、どうしても翻訳をあきらめきれず、挑戦することにしました。
現代文芸コースの雰囲気、教員・学生などとの交流
青山教授のゼミでは英文を緻密に読んで訳す訓練を積んだほか、最新の海外文学・文化事情を追いかける姿勢を先生やほかの学生たちから学びました。松永美穂教授のクラスでは、近年研究がすすむ世界文学論や翻訳学を初めて知りました。いずれの先生も大変親身にご指導くださり、修了してからもなにかとお世話になっています。生涯の師と思う方々に出会えて幸せです。
翻訳ゼミからはプロの翻訳者がたくさん出ていて、今ではともに仕事をしたり励ましあったりする大切な仲間です。また、現代文芸コースでは海外文学・翻訳系の学生だけではなく創作・批評系の学生ともときどき一緒の授業を受けていたので、翻訳者とはまたちがう、創作者たちの視点にふれることができました。
研究(翻訳)にかけた思い
そもそも翻訳に興味を持ったきっかけのひとつは、学部生のときに授業でニコルソン・ベイカーの『中二階』という小説を読んだことです。すっかりファンになり、ベイカーの本をもっと読みたくて未邦訳のU and Iという本のペーパーバックにも挑戦しました。でも、なにやらエキサイティングな本だな、という雰囲気は伝わってきたものの、実力不足で理解しきれないまま本棚の片隅に眠らせていました。早稲田に入り、せっかく翻訳を学ぶのだからと5年ぶりに引っ張り出し、修士2年目の1年間、毎日ひいひい言いながら全訳しました。この翻訳を修士論文の一部として指導教授の先生方に読んでいただき、口頭試問で受けた指摘をいかして修了後に翻訳を練り上げ、出版社に持ち込んで出版することができました。
修了後、留学先の博士課程での生活
修了後はフリーランスで書籍や雑誌の翻訳をしてきましたが、今度はある本のためにアメリカ南部のアラバマ州に住むことにしました。世界恐慌期のアラバマの田舎の貧農の暮らしを描いたルポルタージュ文学で、なにやらすごい本だということは伝わってくるのですが、難解な文体もさることながら、アラバマの土地の雰囲気がいまいちピンと来ず、訳すには現地に行くしかないと思い、留学することにしたわけです。
現在は、アラバマ大学英文科の博士課程に在籍しており、授業にむけて文献を読み、ディスカッションをし、論文を書く、という日々を送っています。翻訳に挑戦しようか迷っていたころには大学院留学など現実味のない絵空事にしか思えませんでしたが、現代文芸コースで学んだことで道が開けました。また、アメリカ大学院の勉強は大変ですが、今のところなんとかついて行けているのも早稲田での学びのおかげだと思います。
ちなみに、アラバマ大学のスクールカラーのクリムゾン(深紅色)は早稲田の臙脂色とそっくりです。アメフトの強豪校として全米に知られており、Roll Tide!という応援フレーズがスタジアム内だけではなく、すれ違いざまとか、別れ際とか、メールの末尾とか、アラバマ中のあらゆる場所で、「がんばって!」「グッドラック!」「じゃあ、またね!」など、いろんな意味をこめて使われています。
Roll Tide!
プロフィール
北海道旭川市出身。京都大学文学部哲学専修卒業後、読売新聞社に入社し、香川・兵庫県で尼崎連続殺人事件などを取材。退社後、早稲田大学大学院文学研究科現代文芸コースに進学し、青山南教授のゼミでアメリカ文学の翻訳を専攻。修士論文ではニコルソン・ベイカーの『U&I』をとりあげ、全訳した。修了後には、訳書の『U&I』(白水社)、メアリ・ノリス『カンマの女王』(柏書房)を出版。現在はフルブライト奨学生として、アラバマ大学大学院英文科博士課程でアメリカ南部の文学・文化を研究している。
- Links
- 先輩紹介ページ

