For Prospective Students
受験生の方へ
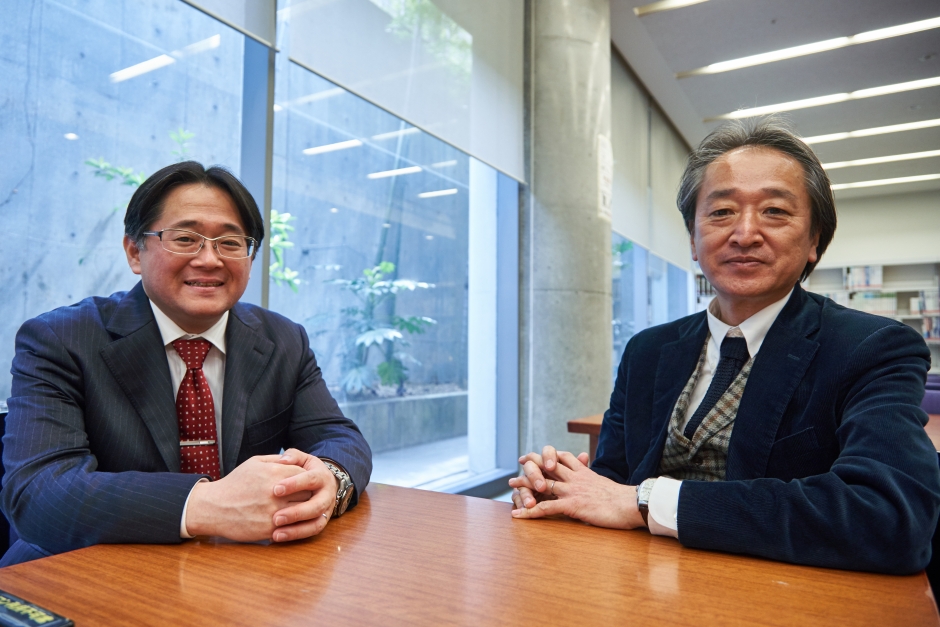

教員免許状の取得を卒業要件としない教育学部
最初に早稲田大学教育学部の特徴を教えてください。
若林教授:大学の教育学部と聞くと、多くの方は「小・中学校、高校などの教員になるための勉強をする学部」と思われるかもしれません。しかし、一口に教育学部と言っても実はそれぞれの大学によって特徴がある上に、その目的から主に「教育学の学修」と「教員養成」という二つのタイプに分けることができます。早稲田大学教育学部には教育学を学べる教育学科があり、同時に各教科の教員養成を目指す5つの学科・専修もあるため、この二つのタイプのどちらにも該当するという点が大きな特徴です。さらには、教員養成にも対応できる組織構成でありながら、教員免許状の取得を卒業要件としないという点は、早稲田大学教育学部ならではの特徴です。
守屋教授:最初は「え?教育学部なのに教職課程が必修じゃないの?」と疑問に思うかもしれません。しかし若林先生がおっしゃるように、ここが早稲田大学教育学部の肝なんです。私は教育学部のOBなのですが、元々教員を目指していたわけではなく、大学では純粋に地球科学、古生物学を学びたいと思っていました。私立大学で地学を学べる大学は意外と少ないので、教員免許を取得せずに専門を深めることもできる早稲田大学教育学部は自然と選択肢の一つになっていました。入学後、当初は民間企業への就職を考えていたのですが、学んでいくうちにこの学問の奥深さと面白さを知ってしまって、気がつけば教員免許も取得しつつ、研究の道に進んでいました(笑)。
若林教授:大学に進学する動機は人それぞれだと思います。教師になりたいと思う人もいるでしょうし、守屋先生のように自分の興味のある学問を深く学びたい人もいます。一方で明確な目的―学びたいことや将来何がしたいか―が決まっていない人もいます。大学は、そういった多様な人たちの“知的好奇心”を満足させる場でありたいと思っています。早稲田大学教育学部には、先ほどの専門を究める6つの学科に加えて、既存の枠組にとらわれず新しい知の創造を目指す複合文化学科もあり、様々な“知的好奇心”のニーズに応えられると思います。
守屋教授:大学の授業では、教わったことを暗記するのではなく、そこから自分なりの考えを導き出し、広げていくことが求められます。自分を広げる上では、専門的な学問を深く学ぶことと同じくらい、専門分野以外の学問やそれを学んでいる人に接することが大切です。その意味でも、幅広い専門分野を持ち、教員をはじめとして多様な進路をとる仲間がいる早稲田大学教育学部では、自分を広げる機会が多いと思います。
若林教授:私は社会学が専門で、他大学から早稲田大学教育学部に来ました。赴任当初は同じ学部に他の専門分野―教育学はもちろん、地学や文学や政治学・数学など―の教員がいるということが珍しかったのを覚えています。しかしすぐにその人材の豊かさに惹き込まれました。なんて贅沢な環境なのだろう、と(笑)。

副専攻が選べる総合科学プログラムとは?
共通科目以外で他の専門分野に触れるというのは、どのようなメリットがあるのでしょうか?
守屋教授:どのような道に進むにしても必要になってくるのは、自分の専門分野とその他の分野を繋ぎ合わせて考えられる知識と柔軟性だと思います。たとえば大地震などの自然災害を考えた時、地球科学では、そもそもの地震の発生メカニズムや津波の規模、被害の大きさなどを考えます。一方で、教育学や心理学では、生徒の安全を考えた普段からの防災教育や、心のケアを考えるかもしれません。
若林教授:そのような場合、社会学では、避難経路の想定や被災地での住民のネットワークづくりを考えます。行政の対応や、外国人に正確な情報を伝えることも大切でしょう。ひとつの事象を自分の専門分野とは違う角度から見る、ということは視野を広げる意味でも深さを増す意味でも非常に意義があります。教育学部では2019年度から副専攻制度である「総合科学プログラム」を開始しました。大学では自分の専門分野を修めて卒業すると学士号が与えられますが、それに加えてこのプログラムの要件を満たすことで、自分の専門分野以外の副専攻を修めた証明としての修了証を得ることができます。
守屋教授:現在は“地球システムコース”と“外国語A発展履修コース”が用意されています。それぞれのコースでは、地球のメカニズムについて本格的に学んだり、英語以外の外国語科目を体系づけて深く学んだりすることができます(一部対象外の学科・専修あり)。それが修了証という形になるのは学生にとっても励みになるでしょうし、専門分野を多く持つ教育学部だからこそ、より活きるプログラムだと思います。

広い意味での「教育者」を輩出
最後に、早稲田大学教育学部を目指す皆さんにメッセージをお願いします。
若林教授:大学での学びが小・中学校、高校での学びと大きく異なるのは、学生が主体的であることだと思います。大学では、決められたコースに沿って「授業を履修する」のではなく、自分が学びたいことを「探しに行く」ことが求められます。
守屋教授:こちらとしては、専門分野という素材、それも活きのいいネタをたくさん用意しているので、ぜひそれを自分でチョイスして美味しい料理を作ってほしいという気持ちです。失敗してもいいのだと思います。それが許されて再挑戦できるのは学生の特権ですし、人と違うことをしても成果を出せば正当に評価してくれるのが大学なのですから。
若林教授:卒業に必要な単位だけでなく、興味・関心がある講義があれば、とにかく一度聞いてほしいし、たとえ履修していない講義の先生であっても、疑問があれば是非それを聞きに行ってほしいですね。自分の専門分野を質問されることは、嬉しいことですから(笑)。
守屋教授:私たちが持っているものを、すべてとは言わないけれど少しでも吸収していってほしい。そして教育学部で学んだことが社会に出たときに何かの役に立ってくれれば嬉しいですね。
若林教授:早稲田大学教育学部では、今まで培って来た基礎学力の上にさらに高度な知識を積み重ねていくことで、広い教養と高い学識、豊かな人間性をもった人材を育成しています。卒業生は、学校教員をはじめとして、社会の様々な場面で指導的な役割を果たすことのできる、広い意味での「教育者」として活躍しています。今後も、早稲田大学教育学部は、そのような「教育者」を一人でも多く育てていける場でありたいと思っています。学部4年間、さらに大学院に進めばそれ以上のおつきあいになりますが、一緒に学べることを楽しみにしています。
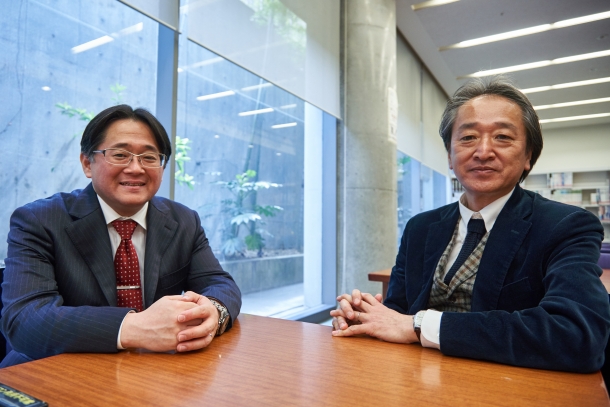
若林 幹夫
社会科公共市民学専修 教授
1986年 東京大学 教養学部 教養学科・相関社会科学分科卒業。1990年 東京大学大学院 社会学研究科 社会学専攻博士課程中退。博士(社会学)。 東京工業大学助手、筑波大学教授等を歴任し、 2005年より現職。2008年にエル・コレヒオ・デ・メヒコ(メキシコ大学院大学)客員教授、2016年より早稲田大学大学院教育学研究科長、2018年より2022年まで早稲田大学教育・総合科学学術院長ならびに同学部長を務める。専門は社会学・都市論・社会的時間-空間論。
守屋 和佳
理学科地球科学専修 教授
1997年 早稲田大学 教育学部 理学科・地学専修卒業。2002年 東京大学 理学系研究科 地球惑星科学専攻博士課程修了。博士(理学)。
日本学術振興会特別研究員(PD)、英国サウサンプトン海洋センター客員研究員、カナダブリティッシュコロンビア大学客員研究員、早稲田大学教育・総合科学学術院助手などを経て、2015年より早稲田大学教育・総合科学学術院准教授。2020年より現職。専門は進化古生物学、古海洋学。「地史学」、「古生物学」、「地史学実験」、「進化古生物学研究」などを担当。
