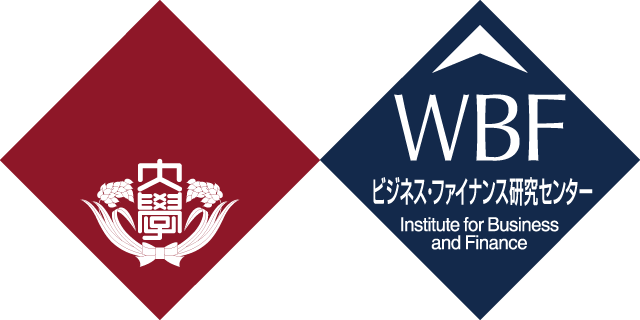- News
- 『サプライチェーンマネジメント中核人材育成講座』でヤマハ発動機株式会社様へ訪問をしました
『サプライチェーンマネジメント中核人材育成講座』でヤマハ発動機株式会社様へ訪問をしました

- Posted
- Mon, 28 Apr 2025
2024年に開講したサプライチェーンマネジメント(以下、SCMという)中核人材育成講座には企業訪問がカリキュラムの1つとして設置されています。
本講座では、参加者3人から4人でグループを作成し、討議を行い、そのグループの中から企業訪問先を選び、事業所や工場などを見学します。今回は、ヤマハ発動機へ訪問したグループの受講生、高橋さんよりヤマハ発動機のSCMと、企業訪問の内容をお聞きしました。
高橋直裕さん:
ヤマハ発動機株式会社
カスタマーエクスペリエンス事業部SCM部在庫供給管理1グループ ご所属

ヤマハ発動機が目指すSCMの姿
当社では、他社との差別化に繋がるValue Driverとしてお客様の体験価値向上を中期経営計画の中で掲げています。
その中でアフターセールス領域における製品のメンテナンスや修理に必要な補給部品のサプライチェーンを担っている当部門においては、「次世代グローバルSCMによる最良の顧客体験の提供」をタグラインとして定め、SCMの変革に取り組んでいます。
次世代とは、お客様の価値観や製品の使われ方の変化に合わせて需要連鎖の方針を見直し、一方でモノづくりや調達および物流の環境変化に合わせて供給連鎖の実現手段を最適化することです。また、グローバルとは新しいクラウドシステムにより連結拠点のデータを集約することで全体と個社のKPIを一元的に管理し、目標とアクションプランの設定をスピーディーに行い、個々の活動を推進するサイクルをグローバルレベルで構築することです。
企業訪問の内容
当社の企業訪問には講座メンバーだけでなく、早稲田大学ビジネススクール教授の長谷川先生および共催企業である株式会社クニエと株式会社NTTデータのコンサルタントの方々にお越しいただきました。当日は、まず午前中に当社からのインプットとしてSCMの説明と物流センターの見学、及び質疑応答を行いました。その後、昼食を挟んで講座メンバーによる課題と打ち手の検討から発表を行い、最後に意見交換、という流れで進行しました。
当社からの説明においては、サプライチェーンの全体戦略、ネットワークデザイン、計画と実行、という講座で学習したフレームワークを使って全体を捉えていただくことを意識しました。
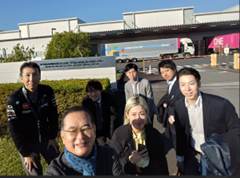
企業訪問を受け入れてどうだったか
自社分析を改めて行う良いきっかけになったと同時に、新中期計画をまとめた直後であったためアクションプランを具体的に考える上での様々ヒントやアイデアをいただくことができました。また、講座メンバーと近い職位のメンバーにも参加してもらったため、他社同クラス人材との会話によって刺激を得ることにもつながりました。
準備には一定の時間を要しましたが、第三者視点での客観的な分析や提案を聞くことにより、自社で設定している課題を再確認することもでき、対価は十分にあったと考えています。

これから企業訪問をする方へメッセージ
学びの内容を踏まえた実践の場となりますが、学んだ内容を全て織込もうとすると纏まりがつかなくなってしまい、ミクロ的な視点になりすぎると手段のブレインストーミングの様になってしまうと思います。そのため経営課題を解決するためのSCM改革をシュミレーションする場と考えて、活用の中心に据えるフレームワークやテンプレートをある程度定めるアプローチをお勧めします。
本講座は、2025年も8月に開講いたします。詳細はこちらをご覧ください。