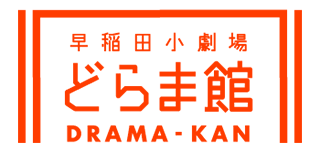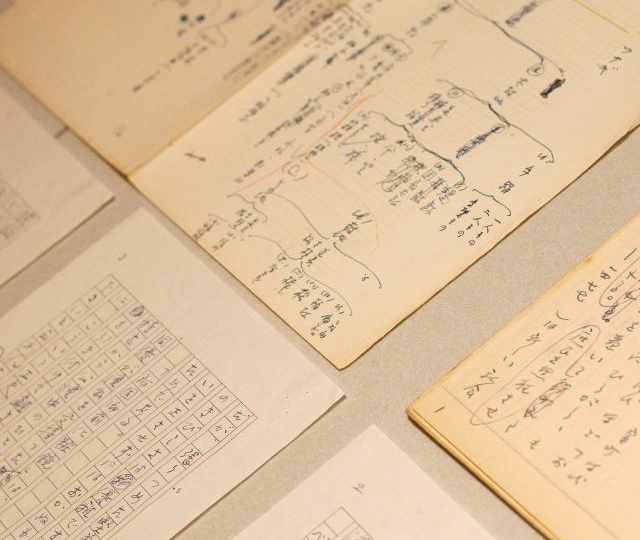2015年4月30日、早稲田キャンパス近くの南門通り商店街にグランドオープンした「早稲田小劇場どらま館」。これまで多くの団体がその舞台を彩ってきました。早稲田演劇の今をお伝えすべく、公演レビューをお届けします。
【早稲田演劇の今】早稲田小劇場どらま館レビューVol. 12
2018年9月14日(金)~10月1日(月)
早稲田小劇場どらま館 × 遊園地再生事業団『14歳の国』
早稲田小劇場どらま館で上演された『14歳の国』は、早稲田大学文学学術院教授である宮沢章夫によって、1998年に初演された作品である。初演時には、温水洋一、モロ師岡をはじめとする男性俳優たちによって演じられたこの作品を20年後に再演するにあたって、宮沢は出演者のほとんどを女優に変更した(当初は全員が女性という計画だったものの、リハーサル中に牛尾千聖が体調不良によって降板。善積元が参加することになった)。しかし、その他の設定や内容が現代風にアレンジされることはなく、いくつかの小さな変更が加わっているだけで、大枠としてはほとんど変わりがない。そこに描かれたのは、携帯電話もインターネットもまだ現在ほど普及していない1990年代後半の風景だった。
この物語は、20年後の観客に対して、どのような意味を持ったのだろうか?
「持ち物検査」が起こす悲劇
作品は、学校のチャイムをモチーフとした曲が流れ、始まる。『14歳の国』の舞台となるのは、ある中学校の教室だ。体育の授業中、5人の教師たちは子どもたちのいない教室に忍び込み、秘密裏に持ち物検査を行う。しかし、意味のない会話ばかりがなされるその持ち物検査は一向に進まず、いつもジャージであることを指摘された教師1(谷川清美)が「学校にいるときのジャージと家にいるときのジャージは違う」と主張したり、美術部の部員数が何人かを確認し合ったりする。無意味な会話ばかりが続きながらも、持ち物検査に参加していない教師の影におびえ、コソコソと様子をうかがっていると、おもむろに教師4(大場みなみ)がつぶやく。

左から、教師4と教師3
「間違ったことはしてませんよ」
彼らの振る舞いからは、「教師」という権威は微塵(みじん)も感じられない。生真面目で、実直な風情がありながらも、くだらない話ばかりを続けるその姿は、どこか現実感が希薄だ。そして、「間違ったことはしてない」と主張しながらも人影におびえ、ひっそりと息を潜めるその様子は、あまりにも愚かだ。結局、この愚か者たちは、体育の授業が終わったことによって、持ち物検査をしに来たにも関わらず、ほとんど何もしないまま教室を後にする。
1場から1週間後という設定の2場になっても、教師たちは同じようにこっそりと持ち物検査を繰り返す。風によって割れてしまった花瓶をあたふたとごまかそうとしたり、生徒の机の上にカッターで掘られた「SATAKE SHINE」という文字が、サタケという名前の教師2(善積元)に対する「死ね」という意味なのか、それとも「輝け」という意味なのかを話し合ったりするシーンの無意味さなどは1場と同様だが、異なるのが、生徒の持ち物からさまざまな物が発見されていくこと。生徒の机からは少年法が記された紙片や、他の女子生徒の机からはデートクラブの番号が発見され、だんだんと不穏な空気が漂う。そして、教師たちは「ぼくは今14歳です。そろそろ聖名をいただくための聖なる儀式『アングリ』を行なう決意をしなくてはなりません」というメモを発見し、観客は、それが「酒鬼薔薇聖斗(さかきばらせいと)事件」(神戸連続児童殺傷事件、1997年)を想起させるものであることを知る。彼らは、それに動揺しながらも「遊びですよ」と、その事実に対して目を背けた。
(写真左)持ち物検査をする教師たち。教師1(中央)はいつもジャージ姿
(写真右)教師5(右)の言葉に耳を傾ける教師たち
だが、さらに物語は続く。教師5(踊り子あり)による「先生が欲しかったのはこれでしょう」という言葉とともに、生徒の机からはナイフが発見され、持ち物検査の理由が明らかにされる。そのナイフを握った教師3(笠木泉)は、ほとんど訳も分からずに教師2を刺す。まるで、当時流行した「キレる世代」(※)たちのように、そこには動機の分からない殺人だけが残った……。
(※)1982年前後に生まれた世代のこと。2000年前後に相次いで発生した凶行を起こした犯人たちがその世代に多いことからそう呼ばれた。
「内部崩壊」が起こった1990年代
宮沢は、今回の『14歳の国』で配布されたパンフレットにおいて次のように記している。
「これがいま理解されるのか不安になったのは――それは再演の稽古を進めるあいだに気がついたことだが――、1997年の、神戸のニュータウンで14歳の少年が犯した凄惨(せいさん)な事件や、その翌年、社会問題になったバタフライナイフを使った殺傷事件の生々しさがこの20年でよくわからなくなっていることだ。
(中略)事件をそのまま扱っているわけではないとはいえ、背景にはそれがあり、間接的に語っている。初演時にはそれがすぐに理解された。ナイフの重さがドラマを作動させる力になっていると」
では、20年前に理解された「ナイフの重さ」とは何だったのか? あらためて、当時のことを振り返りながら考えてみよう。
批評家の大澤聡が「1990年代の日本社会を語る際には、必ず『1995年』以前/以後で議論されます」(『1990年代論』河出書房新社)と語るように、阪神・淡路大震災やオウム真理教事件が発生し、Windows95が発売、『新世紀エヴァンゲリオン』が放送され、インフレ率がマイナスを記録した1995年は、歴史的な転換点として参照されることも多い。
しかし、それはあくまでも未来から振り返った視点であり、当時、人々がそのような時代の意味や変化を察知していたかといえば、とても怪しい。恐らく、ほとんどの人間は1995年という転換点に気付かずに、対応することができていなかった。1997年に「酒鬼薔薇聖斗事件」が起こってもなお、だ。
児童を殺害、遺体を切断し、その首を中学校の校門に置くという凄惨(せいさん)極まりないその行為だけでなく、メディアに犯行声明を送りつけた「酒鬼薔薇聖斗」を自称する人物が14歳の少年であったことは日本中に衝撃を与えた。さらに人々を驚がくさせたのは、例えば1989年に同じく日本を震撼(しんかん)させた未成年による事件「綾瀬女子高生コンクリート詰め殺人事件」が、いわゆる「不良」たちによる犯行だったのに対して、少年Aと呼ばれたその犯人は決して素行の悪い生徒ではなかったことだ。そして、犯行声明文で「透明な存在」と自称する彼に、少なくない子どもたちが「シンパシー」とも表現できる感情を抱いた。
その後、中学生たちの間でナイフを持つことが流行する。1998年1月、栃木県黒磯市(※)で中学1年生が遅刻を叱られたことにより「カッとなって」女性教師を刺殺した事件が起きると、ナイフという凶器の存在が一気に社会において前景化。朝日新聞の報道によれば、栃木県栃木市のある中学校では430人の生徒のうち、43人がナイフを持っていると回答したという。そして、何よりも重要なのが、教師たちは、生徒の間にナイフが流行していることを黒磯市の事件が起きるまで何も知らなかったことだ(朝日新聞1998年2月6日)。
(※)2005年1月1日に那須郡西那須野町、塩原町と新設合併して那須塩原市となり廃止。
つまり「14歳の国」の変化に、大人たちは全く気付いていなかった。
いや、彼らは何かが変化していることには気付いていたのかもしれない。しかし、何が起こっているのかはさっぱり分からなかった。劇作家の別役実は、当時の状況について、2000年に刊行された宮崎学との共著『17歳のバタフライナイフ』(三一書房労働組合)においてこのように書き綴(つづ)っている。
「本書は、1997年の、いわゆる『酒鬼薔薇事件』から99年の『音羽殺人事件』までを扱っているが、それに引き続いて発生した『17歳少年たちの事件』を含めて、ある『大いなる変化』というものを感じ取らざるを得ないであろう。(中略)『表面的な』というよりは『内面的な』と言ってもいいものであり、我々の社会を社会たらしめていたものは何ものか、基本的なものが静かに内部崩壊しつつある、といった類のものであろうと私は考える」
そんな「内部崩壊」は、大人たち以上に敏感な中学生の間では自明のことだった。大人たちは、ナイフのブームの原因を「テレビゲームの影響」や「ドラマの影響」と分析して14歳の国を理解したつもりになっていたが、中学生本人が「何かあった時のため」(朝日新聞1998年2月3日)、「自己防衛のため」「護身用」(朝日新聞1998年3月17日)と回答している意味に向き合うことはなかった。平和なこの国においてナイフが必要な「何か」などほとんどあるはずがない。彼らが自衛しなければならなかったのは、時代の「内部崩壊」からだったのではないか。
「大人」である根拠が失われた世界
また、宮沢はナイフの持つ意味と同時に、この作品を「身体」についての作品であると述べている。
「この作品を書こうとしたいちばんの理由は、当時新聞で短い記事を読んだことだ。中学校の教師が体育の時間に生徒の持ち物検査をしていたという。社会問題になっていたナイフを探していたのだろうか。正しいことをしているつもりだが、ほんとうは間違っている。じつはそのことを教師たちはよく知っていた。その『からだ』に興味を持った。中途半端な『からだ』だ。切ない『からだ』だ。そして、とても『悲しいからだ』である」(14歳の国 当日パンフレット)
一体「悲しいからだ」とはどういう意味だろう?
教師とは、「大人」として生徒たちを正しい道へと指導するという役割を与えられた存在であり、彼らの振る舞いは「正義」に依拠している。しかし、その寄って立つべき「正義」は「1995年以降」に崩れていった。『14歳の国』で描かれる彼らは、「内部崩壊」によって、大人であることの根拠を失いつつある存在だ。
「1995年以前」の「大人」の態度とは、例えばこのようなものだった。1998年、当時の文部大臣・町村信孝は、ナイフを持つ子どもたちに対して次のような「緊急アピール」を表明した。
私は、いま、全国の子どもたちに訴える。
最近、君たちの仲間によるナイフを使った事件が続いている。
人を傷つけること、まして命を奪うことは、絶対に許されない。
命を奪われた人たちは、二度と帰ってはこない。
亡くなった人たちや傷ついた人たちのお父さん、お母さんや家族の悲しみがどんなに深いものなのか、それを知ってほしい。
そこで、君たちに訴える。
ナイフを持ち歩くのはもうやめよう。
(文部科学省Webサイト「青少年によるナイフ等を使用した事件に関する文部大臣緊急アピールについて」より)
ここに前提とされているのは、「大人」としての威厳を保ちながら「子ども」を教育するという態度であった。だが、恐らくこの声明は、全く意味をなさなかっただろうと想像される。中学生がナイフを持ったとき、「14歳の国」は建国された。それによって、「大人/子ども」という対立軸は失効し、大人という役割は相対化されてしまったのだ。
この意味は、2006年、いじめ自殺が社会問題と化した時代に出された同じ文部科学大臣・伊吹文明(当時)による緊急アピールと比較するとよりはっきりとするだろう。『未来のある君たちへ』と題された声明は、同じ年代の子どもたち向けられたものであるにも関わらず、その文体を著しく違えている。
弱いたちばの友だちや同級生をいじめるのは、はずかしいこと。
仲間といっしょに友だちをいじめるのは、ひきょうなこと。
君たちもいじめられるたちばになることもあるんだよ。後になって、なぜあんなはずかしいことをしたのだろう、ばかだったなあと思うより、今、やっているいじめをすぐにやめよう。
(文部科学省Webサイト「文部科学大臣からのお願い『未来のある君たちへ』」より)
2006年には、すでに文部科学大臣ですらも「大人」という役を演じられなくなってしまった。「14歳の国」は、わずか8年の間にその国境を固く閉ざし、人々はその国に語りかける言葉を失った。だから、一国の大臣ですらも、奇妙なポエムまがいの言葉を使うしかなかったのだろう。
1998年に『14歳の国』に描かれた教師たちは、まさにその中間の時期に立っていた人々だ。「大人」の象徴である教師という役を演じながらも、それが意味をなしていない半端さの中にいた。ここに描かれる教師たちは、「間違ったことはしていない」とつぶやきながら、ただ教師という役を空転させるほかなかった。その身ぶりはひどく滑稽(こっけい)だ。けれども、その渦中にいる彼らにはどうしようもなかった。だからこそ、それは「悲しい」。
ナイフが落ちる音の重さ
その後、東日本大震災やそれに伴う原発事故といった時代の転換点を経ながらも、1990年代に起こり始めた内部崩壊はとどまることがなかった。『1990年代論』(河出書房)における鼎談(ていだん)で、批評家・東浩紀が次のように語っているのはとても示唆的だ。
「日本社会が道を誤ったとすれば、やはり90年代なんだと思います。よく言われるように、例えば少子化問題にしても、90年代に手当すべきことは誰もがわかっていた。にもかかわらず、なにもやらなかった。当時は日本人全体がバーチャルな世界に生きていて、リアルな問題への直面を避け続けていたように感じます」(『1990年代論』)
酒鬼薔薇聖斗が記した犯行声明文を書き写したとおぼしきメモを発見しても、教師4が「遊びですよ」と即座に目を背けたように、教師たちは、まさに「リアルな問題への直面を避け続け」た。その背後には「14歳の国」に対するおびえがあり、「1995年以降」に対するおびえがある。
劇のクライマックスにおいて、教師3は教師2をナイフで刺す。
教師2が苦痛にもがくでもなく、ただ「そうそう、そうだよ。そうするんだよ」と発話することは、彼らの虚(うつ)ろな身体を強調する。そして、それとは対象的に、教師3が落としたナイフの音は、「ゴトッ」というひどく重い音を残す。その音は、当時の社会がナイフに対して感じていた重さだったのだろうか? それとも、「14歳の国」の重さだったのだろうか? 「1995年以降」の重さだったのだろうか?
ただ一つ言えるのは、当時、その重さの意味から、ほとんど誰もが目を背けていたということだ。
そして2018年、20年後を生きる観客の耳に、もう一度1998年のナイフが落ちる音が響いてきた。
(かもめマシーン主宰 演出家・劇作家・フリーライター 萩原 雄太)
1983年生まれ。早稲田大学在学中より演劇活動を開始。愛知県文化振興事業団が主催する『第13回AAF戯曲賞』、『利賀演劇人コンクール2016』優秀演出家賞、『浅草キッド「本業」読書感想文コンクール』優秀賞受賞。かもめマシーンの作品のほか、手塚夏子『私的解剖実験6 虚像からの旅立ち』にはパフォーマーとして出演。http://www.kamomemachine.com/
関連リンク
【早稲田大学の文化事業全体を支える寄付制度「早稲田文化募金」ご支援のお願い 】
早稲田大学は「早稲田小劇場どらま館」を早稲田演劇振興の拠点の一つと位置付け、早稲田演劇の伝統を継承・発展させ、優れた演劇文化を発信し、教育を通して時代を担う演劇人を多数育成することを目指しています。「早稲田小劇場どらま館」を含む、「文化の潮」が渦巻く早稲田からの強い発信と、燦然(さんぜん)と輝く早稲田の文化を未来の世代へ受け継ぐべく、皆さまのお力添え、温かいご支援を心よりお願い申し上げます。なお、皆さまからのご寄付は、学生のため、演劇教育に資する目的のために使用いたします。
「早稲田文化募金」Webサイト