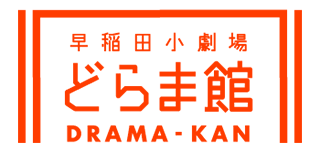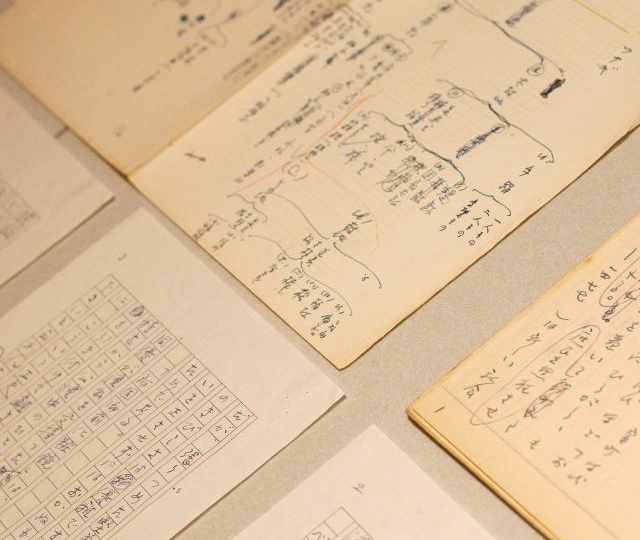シアターオリンピックス観劇レビュー
ラ・ザランダ『すべては夜のなか』
今年9月、富山県南砺市利賀村で行われた国際演劇祭「シアターオリンピックス」に観客として参加した3人の学生たち。早稲田ウィークリーで掲載されたレポート・座談会とともに、どらま館ホームページでは、彼らが見た作品のレビューを掲載します。
劇団24区に所属し、早稲田小劇場どらま館学生スタッフとしても活躍している浜田誠太郎さんが執筆したのは、スペインの劇団「ラ・ザランダ」によって、合掌造りの劇場・新利賀山房にて上演された『すべては夜のなか』についてのレビュー。ホームレスの男たちによる「ごっこ遊び」を描いたこの不条理劇について、浜田さんはその「物乞い」のシーンに焦点を当てて、レビューを執筆しました。

盛り上がりに「水を差す」コメディ
「物乞い」としてのパフォーマンス
すべては茶番である。
防護服を着て現れた3人のホームレスは空港からどこへも出発できず、ただただ荷物を運んでは降ろし、降ろしては運んでいる。2人の先輩ホームレスたちは、スーツを着たおそらく新入りの男を連れて下水を通り、路上に立つ。すると、彼らは物乞いをし始め、その新入りに対して物乞いの指導をはじめた。そして、だんだんと先輩ホームレスによるその指導がエスカレートしていくと、いつしか、彼らの振る舞いはリア王戴冠の場面へと発展。舞台の最後には、それほど多くない、そしておそらく高価でもない小道具たちだけが「夜のなか」に残されたのだった。
1978年に創設された演劇集団ラ・ザランダによる『すべては夜のなか』の上演を要約すればこのような話になるだろう。その内容は他愛のないものであるが、ホームレスのちょっとした仕草や癖、カートやストレッチャーといった小道具類を様々なものに見立てて場面を少しずつズラしていくその軽妙さに魅せられた。
そして、俳優による細部の巧みな技術もさることながら、上演全体の大きな仕掛けも興味深い。先輩ホームレスは新入りに「もっとこうだ!」と物乞いのコツを伝えていき、「物乞い」という「パフォーマンス」を指導。それが3人で『リア王』を演じるまでに変化していくと、そこにはホームレスが「王」になるというバカバカしさともの悲しさ――非常にまっとうな道化のあり方だろう――が溢れてきた。
では、この作品においては、どこから「物乞い」だったのだろうか? 先輩ホームレスたちの「物乞い」の指導は、彼らのそれまでの行動を対象化し、舞台上の行為を一種の劇中劇のようなものに変える。一般的に、劇中劇を描く場合「台本を確認する」「段取りを打ち合わせる」「演出家が舞台上に現れて始まりの合図を出す」など、その「始まり」を示すことが多い。しかし『すべては夜のなか』では、「物乞い」という劇中劇の「始まり」が明示されていないことから、舞台上で行われてきたすべての行為に対して「(物乞いとして)わざとやっていた」と解釈することが可能になってしまうのだ。
当然、この作品は、最初からずっとパフォーマンスだ。しかし、観客は卓越した演技や小道具の使い方によって、勝手に「何かおもしろい物語が進行している」と思い込み、すべてパフォーマンスであり、「嘘」であるということを忘れてしまう。いや、「忘れている」というよりも「(知っているが)忘れたことにしている」のだ。先輩ホームレスたちの「物乞いの指導」は、そんな演劇の本質の一側面を浮かび上がらせていった。
さらに、この作品の興味深いところは、「すべてはパフォーマンスである」と同時に「すべては物乞いである」という可能性をも示唆したこと。ホームレスに限らず、あるいは舞台上のパフォーマーに限らず、すべては「対価を得る」という「物乞い」のために行われる。そのことも、わたしたち「観客」は「忘れている」。そして、リア王のシーンまでが挿入されることによって「王」すなわち「権力」の振る舞いまでもがパフォーマンスとなり、「物乞い」と変わらないと気付かされる。『すべては夜のなか』は「権力」を対象化し、笑いへと変えている。

「盛り上がり」の影にある排除
劇場に足を運び、お金を払い、上演を鑑賞するとき、いつもぼくは「なぜここに来て、何を見るのか」を考えてしまう。これは悪い癖のようなものかもしれない。本当は、来たいから劇場に来て、見たい舞台を見て「わーすごい」となればそれで十分なはずだ。それでいいじゃないか。盛り上がれるヤツらと盛り上がれることこそが最高じゃないか。
しかし、本当にそうなんだろうか、と、ひとり俯(うつむ)いてしまう。
演劇は、複数の人間が集まってはじめて動き出す。その集まる方法のひとつとして「盛り上がり」みたいなものは当然ある。むしろ、ほとんどそれしかないといっても過言ではないかもしれない。だから大抵、その「盛り上がり」に水を差すような表現は、その集まり自体を否定するものとして捉えられ、無視される。そうしなければ、「集まる」ことができず、散り散りになってしまうのだ。一方で「盛り上がり」は、いろんなことを覆い隠し、排除し、影に葬り去ってしまうこともある。きっと「盛り上がり」だけを求め続ける限り、この排除は「忘れられる」ことだろう。
『すべては夜のなか』は軽妙な俳優が魅せるコメディだ。しかしこれは、観客と一緒に盛り上がることを目的とした「お笑い」ではない。むしろ、この舞台は「これはただのパフォーマンスですよ」「ただの物乞いですよ」と水を差し、場が「さめる」ようなことを求めている。それにも関わらず、そんなさめた舞台はなんだか笑えるし、そんなさめた舞台をぼくは笑いたい。この舞台を通じて「コメディ」とは、そしてそれを演じる「道化」とは、実はひどくさめたものなのかもしれないとはじめて実感させられた。きっと、こういうコメディや道化がもっと身近にもいれば、社会はもっと明るくなるんじゃないかと思う。
すべては茶番である。
浜田 誠太郎(はまだ・せいたろう)
劇団24区では脚本・演出・俳優を担当。2019年2月、学生会館で上演した「どうしようもないほど巨大な力に対して、ちっぽけな私たちができることは何か、それを見つける物語」という『大怪獣』の演出を手掛けた。2019年10月から早稲田小劇場どらま館学生スタッフ。