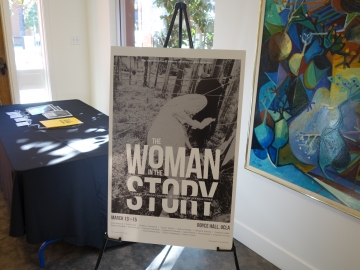2022年6月1日、国際日本学拠点では、訪問教員であるDr. Christina Laffinの講演会「自然、文学、気候変動-「危機感」からではなく自然から学ぶ日本文学 – Teaching about/with/through nature and Japanese literature」を、対面・Zoom Meetingのハイブリッド方式で開催しました。対面では早稲田大学の学部生・院生および教職員が24名、オンラインでは外部の学術機関や一般の方々などが29名、合計53名の参加者を得て開催されました。
講演では、世界が直面している気候変動への取り組みや、気候変動に対して前近代文学の研究の観点からは何ができるのか、そしてそれをどのように教えるべきかに焦点が当てられました。そして気候変動に対して持つ「危機感」自体が間違っているのではないか、という問いから講演はスタートしました。
まず前半では、ブリティッシュ・コロンビア州で発生している気候変動の影響による自然災害とそれを巡る環境運動、そしてその問題が論じられました。ブリティッシュ・コロンビア大学(以下UBC)の学生たちのさまざまな政府へのアピールや、保有林の放出などを求める大学への働きかけなど、活発に展開されている環境運動が紹介されました。そもそもUBCが先住民マスキアム族の土地に建てられているため、逆に大学側もこうした学生の環境運動を公的にバックアップし、むしろ宣伝にも利用している向きがあることが指摘されました。
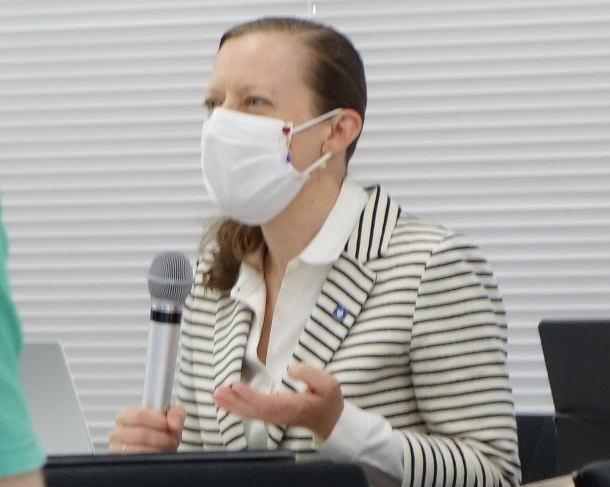 しかし、ラフィン氏は、ミシガン大学のカイル・ホワイト氏の論文「危機認識論に反して」を紹介しながら、危機感を煽って気候変動の問題に取り組むことには問題があるのではないか、と問いかけます。ホワイト氏は先住民族ポタワトミの出身であり、ネイティブアメリカン研究を専門とする文化人類学者ですが、この論文のなかで「前例のない、緊急事態」といった語りによって「危機感」を煽り、それによる植民地化が正当化されてきた事実を指摘し、批判しました。ではどのような方向で気候変動を巡る問題に対応すべきか。ラフィン氏は、ホワイト氏の意見に基づいて、問題解決型Solution-Oriented -Actionsではなく、協調co-ordinationが重要であることを示唆しました。つまり、1)moral bond道徳・倫理やモラルによる絆、2)kinship 友情との間での協調が唯一の方法である、というホワイト氏の結論を提示しました。
しかし、ラフィン氏は、ミシガン大学のカイル・ホワイト氏の論文「危機認識論に反して」を紹介しながら、危機感を煽って気候変動の問題に取り組むことには問題があるのではないか、と問いかけます。ホワイト氏は先住民族ポタワトミの出身であり、ネイティブアメリカン研究を専門とする文化人類学者ですが、この論文のなかで「前例のない、緊急事態」といった語りによって「危機感」を煽り、それによる植民地化が正当化されてきた事実を指摘し、批判しました。ではどのような方向で気候変動を巡る問題に対応すべきか。ラフィン氏は、ホワイト氏の意見に基づいて、問題解決型Solution-Oriented -Actionsではなく、協調co-ordinationが重要であることを示唆しました。つまり、1)moral bond道徳・倫理やモラルによる絆、2)kinship 友情との間での協調が唯一の方法である、というホワイト氏の結論を提示しました。
後半では、文学研究、特に前近代日本文学において、こうした気候変動の問題をどのように表現したらよいかという方向へと話題がうつります。まず日本近代文学の研究では、70年代より英米を中心にエコクリティシズムや環境人文学という観点から研究は進んでいるものの、なかなか拡がってはいない状況であることが指摘されました。それらの研究では石牟礼道子氏や伊藤比呂美氏の文学、ポスト311文学に代表される災害文学などが扱われています。
ハルオ・シラネ氏に代表されるような、明治期の日本文学における自然描写を議論した研究もあります。それでは前近代文学において、自然や気候変動について議論する場合どのようなやり方があるのか、具体的には大学においてどのような授業展開が可能なのかについて議論するために、これまでのラフィン氏の授業実践が示されました。日記文学をより深く理解するためには身体的感覚的な経験を積むことが重要であると考え、たとえばUBC内にある新渡戸稲造記念公園を歩いて自然を体験させ気づいた点を書かせる、「月見」を実際にさせてみて感想を書かせるという工夫が紹介されました。さらにオーディエンスに対して、これらの授業に対するコメントや新たな授業アイデアが求められました。

コメンテーターの山本聡美教授(日本中世絵画史)は、まず、気候変動が人の営みにどのように作用するか、あるいは気候変動が人の営みのふるまいをどう変えていくのか、人文学に何ができるのかというテーマで、ご自身が本学高等研究所で「人新世と人文学」セミナーを実施してきた経緯について説明しました。つぎに、特に今回の講演で取り上げられたハルオ・シラネ氏の「二次的自然」という解釈に言及しました。本来荒々しい自然を「飼いならした自然」として文学・絵画などの芸術で表現することによって、人びとがそれを受け入れていく、これこそが芸術の「虚構」の力であり、そこに人文学の果たしうる役割があるのではないか、と論じました。
質疑応答の場面では、参加者の教員および大学院生から、前近代文学における気候変動へのアプローチについて、具体的な提案や意見が寄せられました。和歌の研究から環境活動家になった研究者の例も出され、文学と自然、環境の問題が密接につながっていることが共有されました。
最後に司会の河野貴美子教授は、次のようにコメントしました。
「中国での厳しい自然のなかで漢詩が生まれ、それを日本が受容して詩歌が生まれていく過程を考えると、周辺の漢字文化圏の地域が文学のなかでどのように自然を受容し言語化して来たのかということと比較すれば、日本文学の自然受容の特徴がみえるのではないか。人類史的なスパンで、人間が自然にどう対峙してどう記録してきたのかということを広くみることによって、私たちが今何をすべきかがわかる。文学は言葉であり、科学にはできない文学の力があるので、人類史的なスパンからのふりかえりによって、文学や詩歌の力を発掘できるのではないか。」
ラフィン氏や山本教授からも、このコメントへの共感が示され、会は閉会となりました。
開催詳細
- 日時:2022年6月1日(水)16 :30 – 18:00 (JST)
- 会場:早稲田大学戸山キャンパス 33号館3階第1会議室 ・ Zoom Meetingハイブリッ
- 講師:Dr. Christina Laffin
- 司会:河野 貴美子(文学学術院教授)
- コメンテーター:山本 聡美(文学学術院教授)
- 使用言語:日本語
- 参加対象:学生/教員/一般
- 参加費:無料