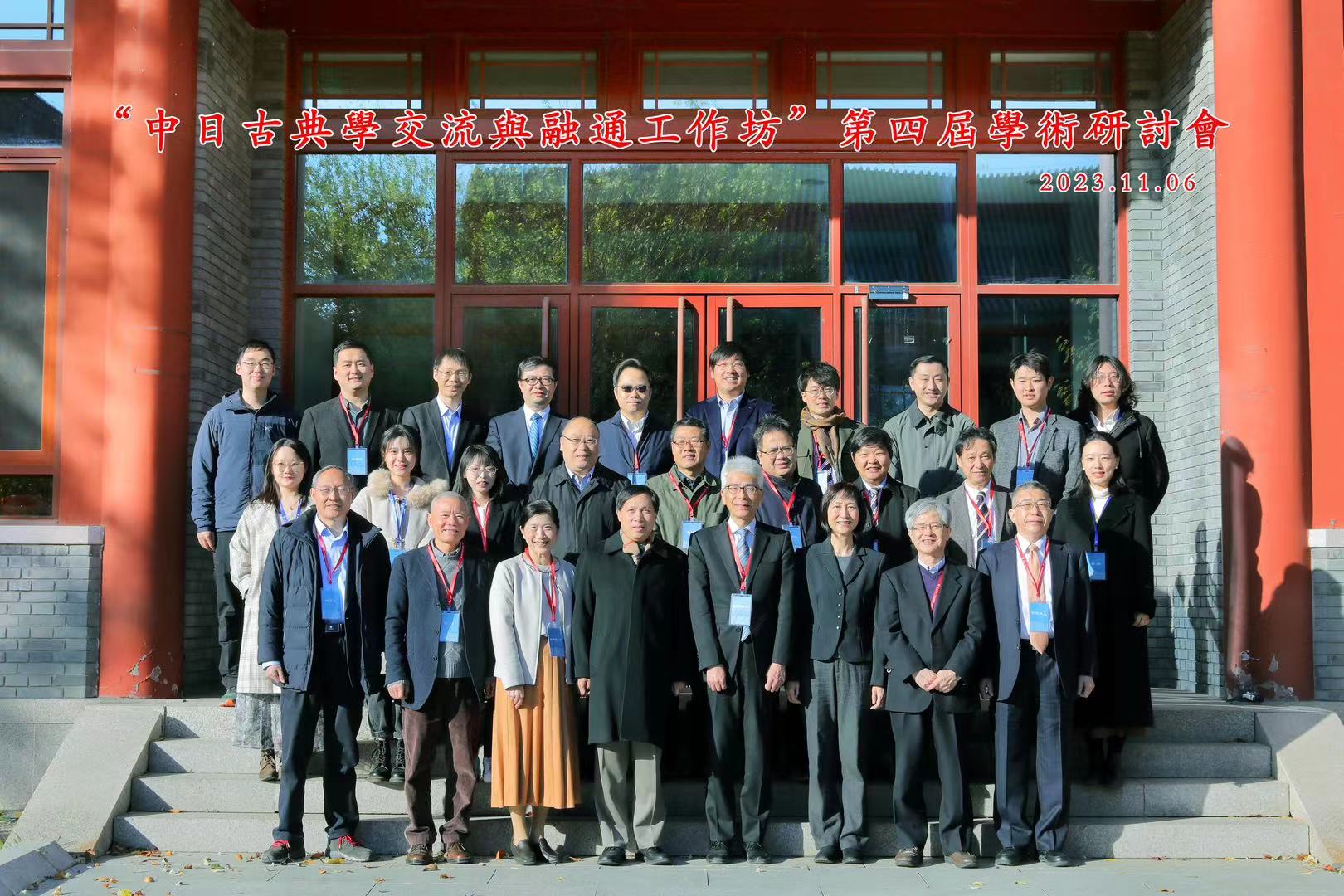2023年11月6日、7日の2日間にわたり、北京大学にて第四回中日古典学ワークショップ「中日古典学交流与融通工作坊”第四届学術研討会」を開催しました。本ワークショップは、第一回は2018年11月に早稲田大学で、第二回は2019年11月に北京大学で、そしてコロナ禍を経て第三回は2022年11月にオンライン(早稲田大学担当)にて行ってきたものですが、今回は4年ぶりに対面とオンラインのハイフレックス形式での開催が実現しました。

このワークショップは、中国と日本が長い歴史の中で共有してきた古典学と古典籍について、中国における中国古典学研究者と日本における日本古典学研究者との学術交流のプラットホームを作り、相互の研究方法、研究対象、研究動向などについて情報交換を行い、新たな研究の開拓、構築をはかろうとするものです。ワークショップは、毎回、古典学にかかわる具体的なテーマを設定して開催しており、今回は「「文」と「集」」(中日古代“文”“集”観念及相互関係)をテーマとして合計19名による発表が行われました。また、本ワークショップは、両校の大学院生による青年論壇の枠を設け、次世代の研究者による研究発表と相互交流の場となることをも期すもので、青年論壇ではあわせて8名の発表が行われました。
 2日間のワークショップを通して、歴代の「集」がいかなる材料を用いて、いかなる編纂方針のもと生み出されてきたのか、またそこにいかなる意図が含まれ、いかなる価値観を形成してきたのかなど、「集」というものの存在についてきわめて多角的、そして本質的な問題が提出されました。また、中国古典文献における「集」とその他の「経・史・子」との関係や、その枠組み、分類の変遷などについて、古代から近現代にいたるまで通史的な見通しからの問題提起もありました。また、「文」という概念の含意、「文」の型や機能について、「集」とのかかわりから考察し、その意味を浮かび上がらせようとする試みも示されました。さらには、一つの顕著な傾向として、中国側の発表において、日本に所蔵される古典籍資料や日本で刊刻された和刻本を考察に用いるものが多いことがあげられます。古典学研究をめぐって、中日共同で議論することの重要性が再確認されるとともに、相互にとってのさまざまな「発見」の契機となるワークショップとなりました。
2日間のワークショップを通して、歴代の「集」がいかなる材料を用いて、いかなる編纂方針のもと生み出されてきたのか、またそこにいかなる意図が含まれ、いかなる価値観を形成してきたのかなど、「集」というものの存在についてきわめて多角的、そして本質的な問題が提出されました。また、中国古典文献における「集」とその他の「経・史・子」との関係や、その枠組み、分類の変遷などについて、古代から近現代にいたるまで通史的な見通しからの問題提起もありました。また、「文」という概念の含意、「文」の型や機能について、「集」とのかかわりから考察し、その意味を浮かび上がらせようとする試みも示されました。さらには、一つの顕著な傾向として、中国側の発表において、日本に所蔵される古典籍資料や日本で刊刻された和刻本を考察に用いるものが多いことがあげられます。古典学研究をめぐって、中日共同で議論することの重要性が再確認されるとともに、相互にとってのさまざまな「発見」の契機となるワークショップとなりました。
そして今回のワークショップの成果として特筆すべきは、青年論壇です。発表はいずれも、博士論文の執筆に向けて取り組んでいる具体的な材料や研究の骨格について、効果的なパワーポイント資料を用いながら簡潔明瞭になされ、参加者相互にとって大いに刺激となるものでした。青年論壇においては、中日それぞれの教員からの多数の助言もあり、参加した学生にとっては少なからぬ収穫が得られる時間となりました。
これまでのワークショップの成果として、中国語版論集の第一巻目は2022年に刊行され、日本語版論集もまもなく刊行される予定です。そして第三回、第四回のワークショップの成果論集もまた、中日両言語にて刊行される予定です。また、続く第五回のワークショップは、2024年11月に早稲田大学にて「「文」と「図像」」をテーマとして開催する予定です。
今回のワークショップのもう一つの重要な点として、北京大学、早稲田大学のみならず、国内外の他大学からも多数の教員の参加、発表があったこと、また中国他大学の学生も会場を訪れ、ワークショップに参加したことがあげられます。今後、この中日古典学ワークショップが、関係の領域の研究者、学生の一つの核となり、ネットワークを築き拡げる基地の役割を果たしていくことが期待されます。
本ワークショップは、北京大学中国語言文学系、早稲田大学総合研究機構日本古典籍研究所、スーパーグローバル大学創成支援事業 早稲田大学国際日本学拠点の主催、早稲田大学総合人文科学研究センター角田柳作記念国際日本学研究所、JSPS科研費基盤研究(C)(20K00303)の共催、早稲田大学総合研究機構の後援で開催されました。