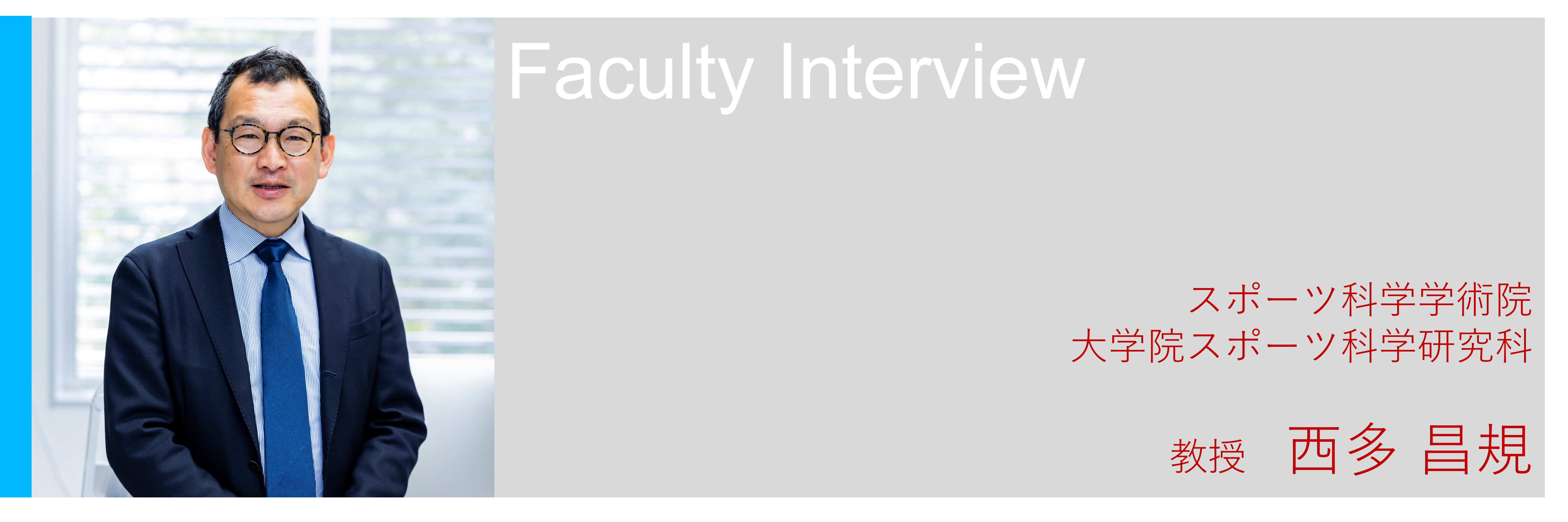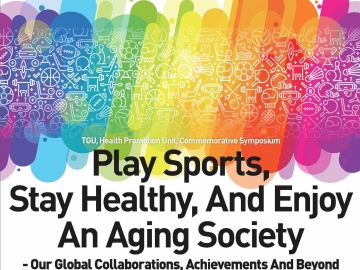睡眠・スポーツ・メンタルヘルスの関連性を明らかにし、ウェルビーイングの実現へ
スポーツパフォーマンスへの睡眠の影響
睡眠や体内リズムと身体運動、スポーツとの関連性を解明していくのが当研究室のテーマです。適度な運動と十分な睡眠が健康に良いのは言うまでもありませんが、それだけに留まらない長期的な影響や関係を科学的に追求します。アスリートのパフォーマンス向上や、一般の人々の健康増進、ウェルビーイングに役立つ研究に重きを置いています。
近年では、特に睡眠がスポーツパフォーマンスに与える影響について考察を深めてきました。例えば、適度な仮眠によってサッカー選手の首振り動作やゴルフ選手のパッティングが向上すること、学生アスリートの朝練習は睡眠障害につながりやすいことなどが、研究結果では明らかになっています。従来、スポーツ研究では運動生理学や栄養学、トレーニング科学などが中心であり、睡眠は「何もしていない時間」として見過ごされてきました。しかし今日、その重要性への認識は高まっています。
アスリートのメンタルヘルスを支えていく
睡眠科学は国際的にも研究対象として認められてきていますが、そこにメンタルヘルスとスポーツを組み合わせた研究は世界でも非常に少なく、当研究室の特徴になっています。 現在は、アスリートのメンタルヘルスに着目した研究を進行中です。結果を出すことへの極度なプレッシャーや、過度な指導・トレーニングの負担、SNSなどで受ける誹謗中傷、怪我による予期せぬ休養など、アスリートが直面する壁はさまざま考えられます。それに対し、どのような精神面のサポートが求められているかを探っていきます。
現在は、アスリートのメンタルヘルスに着目した研究を進行中です。結果を出すことへの極度なプレッシャーや、過度な指導・トレーニングの負担、SNSなどで受ける誹謗中傷、怪我による予期せぬ休養など、アスリートが直面する壁はさまざま考えられます。それに対し、どのような精神面のサポートが求められているかを探っていきます。
また、産学共同研究にも積極的に取り組んでいます。株式会社Yogiboと協働し、ビーズソファでの睡眠が筋肉や心拍、自律神経機能に与える影響を明らかにした研究はその一例です。現在は、株式会社TENTIALとともにリカバリーウェア「BAKUNE」を用いた研究を進めており、輻射熱を利用した特殊な繊維が疲労軽減にもたらす効果を検証しています。睡眠に関わる企業とは多くの交流があり、共同研究をきっかけにそれらの企業への就職活動を検討する学生もいます。
自国の視点と日本での学びを融合させる
スポーツ科学学術院では、研究の発表媒体は基本的に英語であり、海外の学会への参加機会も少なくありません。スーパーグローバル大学創成支援事業の拠点として、海外の提携大学とも連携を深めています。
第一線での研究を目指す上で、英語論文を書く能力は必須といえ、指導において重視する点です。言語の壁は翻訳ツールの発展によって薄れてきても、英語へのアウトプットを前提に、母国語で論旨を組み立てる力は将来にわたって必要とされ続けます。
 スポーツ科学学術院にはすでに多くの留学生が在籍しますが、さらに多様な視点を得るためにも、さまざまな国からの入学者を期待しています。英語での研究活動をベースとしながらも、心の機微に触れる調査では、日本語でのコミュニケーションの方が馴染みやすいこともあります。日本語学習にも興味を持ち、異文化を経験する貴重な機会として捉える方には、より実りの多い環境となるでしょう。自国の視点と日本での学びを融合させ、新たな化学反応を生み出していってほしいと考えています。
スポーツ科学学術院にはすでに多くの留学生が在籍しますが、さらに多様な視点を得るためにも、さまざまな国からの入学者を期待しています。英語での研究活動をベースとしながらも、心の機微に触れる調査では、日本語でのコミュニケーションの方が馴染みやすいこともあります。日本語学習にも興味を持ち、異文化を経験する貴重な機会として捉える方には、より実りの多い環境となるでしょう。自国の視点と日本での学びを融合させ、新たな化学反応を生み出していってほしいと考えています。