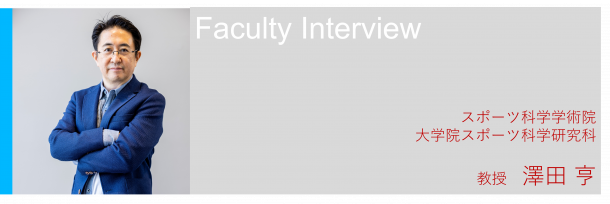
スポーツ疫学研究により身体活動を普及・促進し、人々の幸せと健康に貢献
身体活動の価値を科学的に明らかにする
私たちの研究室では「スポーツ疫学」を専門としています。疫学とは、ヒト集団の問題や課題を改善するためのエビデンスを、科学的な比較を通して提供する実践的な学問です。「どちらの方法がどのくらい効果的か」を明らかにし、いち早く課題解決の方法を見出していきます。
そしてスポーツ疫学では、スポーツや身体活動に関わる課題に疫学的手法で取り組みます。これまで当研究室では身体活動や体力と健康の関係をテーマとした比較研究を多く行い、身体活動レベルが高い人ほど、糖尿病やがんにかかりにくいことなどを明らかにしてきました。
並行して、身体活動や体力がBrain Health(幸福感、健康関連QOLなど)や感覚器(聴力、視力など)に及ぼす影響についての研究も進めています。高い心肺体力が保たれていると、難聴や緑内障になりにくいことが確認されており、それは認知機能の維持の観点からも大きな意義を持ちます。
分野を横断したチーム型プロジェクト研究
現在、私たちが注力しているのが、スポーツの観戦や応援が観戦者や応援者(ファン)の幸福感や健康に及ぼす影響についての研究です。スポーツは「する」「みる」「支える」といった活動の側面があり、今まで「する」スポーツへの研究は進んできましたが、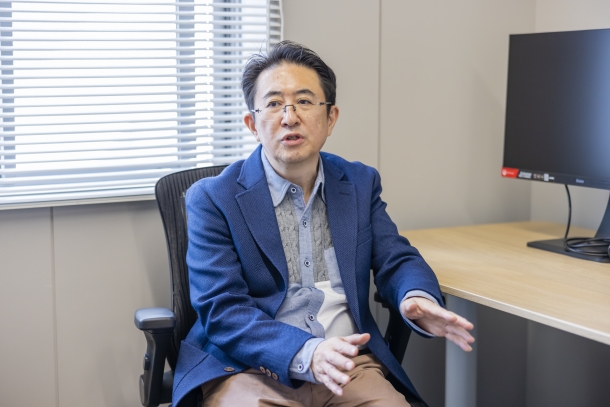 残り2つは未開拓となっていました。熱烈なスポーツファンとスポーツに興味を持たない人では、長期的な心身の健康に受ける影響にどのような違いがあるか、「みる」「支える」スポーツへの問いに答えを出していきます。
残り2つは未開拓となっていました。熱烈なスポーツファンとスポーツに興味を持たない人では、長期的な心身の健康に受ける影響にどのような違いがあるか、「みる」「支える」スポーツへの問いに答えを出していきます。
またスポーツ科学学術院では、「スポーツファンの精神的・身体的健康度およびQOLを明らかにする総合的スポーツ科学研究」というチーム型プロジェクト研究を実施しています。これは、スポーツ疫学だけでなく、スポーツ文化、スポーツマネジメント、精神保健、スポーツ医学、行動科学など、多様な分野の研究者が協働し、「みる」スポーツの多面的な価値を追求するものです。こうした高次元なチーム研究が実現するのは、各分野を代表する研究者が集まった早稲田大学スポーツ科学学術院ならではといえるでしょう。当研究室からは、国内外出身の大学院生も積極的に参加し、インターネット調査やデータ分析などで活躍しています。
高い「公衆衛生マインド」を持って
学生とは半年に一度に面談を行い、「自発性」と「希望」を重視した個別指導を行っています。特に重視するのは、卒業後の希望する進路に合致する能力を身につけていくための支援です。疫学は実務的な学問であり、企業や自治体に就職したり、国政に関わる上でも、培った手法を応用しやすいのがメリットです。私自身が27年間民間企業に籍を置いてきましたので、その経験を活かした実践的なリテラシー養成にも力を注いでいます。また、さまざまな企業との共同研究を行い、米国ハーバード大学・サウスカロライナ大学などの海外研究者とも連携する中、コミュニケーション能力の向上も欠かせません。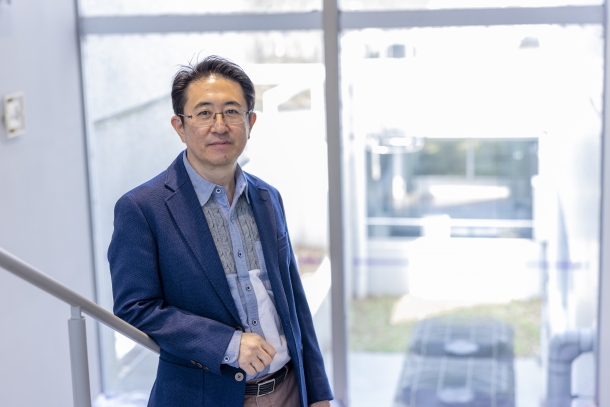
当研究室で共有するミッションは、「身体活動疫学研究による社会への貢献」です。スポーツ疫学は、地域・集団の健康に尽くす「公衆衛生(Public Health )マインド」が高い人こそが活躍できる学問といえます。スポーツを通じて人々の幸せや健康に貢献するための研究に、一緒に取り組んでいきましょう。









