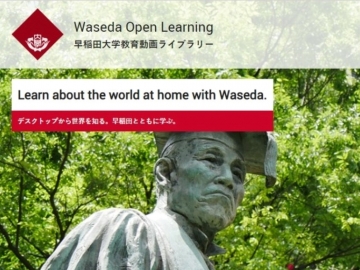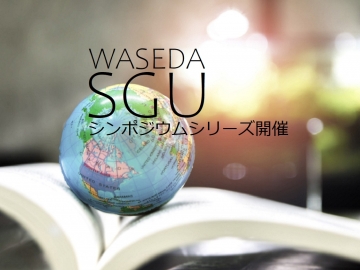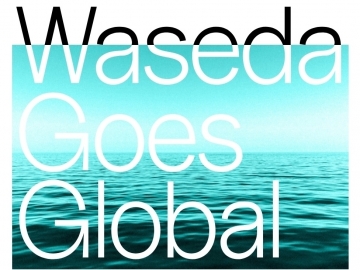日時
2018年2月5日(月)16:00~17:30
会場
19号館315号室
タイトル
「国際関係学における文化人類学的視点-世界情勢と貧困をどう語るのか-」
講演者
ラルフ・ペットマン博士 (一橋大学)
アデレード大学にて政治・歴史学を専攻、ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス(LSE)にてPh.D.(国際関係学)を取得。メルボルン大学教授、学習院大学客員教授等を歴任し、現在は一橋大学にて教鞭を執る。主な担当科目は、国際関係学および国際政治学。オーストラリア人権委員会、オーストラリア国際開発援助局、オーストラリア放送局を始めとする実務家としての職務経験も有する。近著に、Here Comes Everyone: anthropology and world affairs (World Scientific Publishing Company, 2017); Psychopathology and World Politics (World Scientific Publishing Company, 2012); World Politics: an analytical overview (World Scientific Publishing Company, 2010); Intending the World: a phenomenology of international affairs (Melbourne University Press, 2008)がある。
コメンテーター
勝間 靖(早稲田大学大学院アジア太平洋研究科 教授)
概要
国際関係学においては、世界情勢から一定の距離を置き、客観的に事象を分析するトップダウンの視点が主流である。このような視点は、国際政治の有様やメカニズムを説明するには効果的であり、ミレニアム開発目標(MDGs)や持続可能な開発目標(SDGs)といった世界規模の政策策定をも可能にしてきた。しかしながら、当該視点には、代替的な考え方や、異なった視点によって可能となる研究の手法や結果には十分に焦点が当てられないという点に限界がある。
一方、文化人類学においては、ボトムアップの視点が主流である。コミュニティに参加し、身近な立場から人々の声に耳を傾けることにより、MDGsやSDGsに関する学びを得ることができる。こうした視点は、本質的な関心事に影響し、動態的社会統計や災害、精神性といった「オラリティ」に光を当てるのである。
本セミナーでは、貧困と開発の事例を中心に上述の点を考察する。また、対象の人々に語りかける文化人類学者の方針が、バングラデシュ、ブータン、インドのケララ州、オーストラリア原住民の事例において、どの程度有効であったかを紹介する。
言語
英語
対象
学生・教職員・一般
参加費
無料
お問い合わせ先
早稲田大学 スーパーグローバル大学創成支援 グローバルアジア研究拠点
Email: [email protected]
ウェブサイト:https://www.waseda.jp/inst/sgu/unit/global-asia-studies/