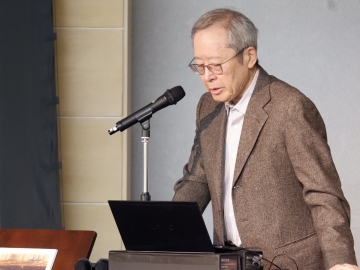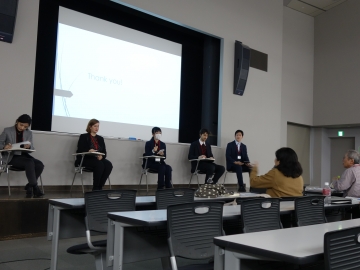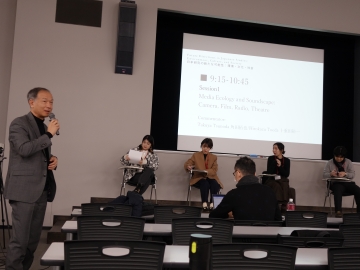2024年1月12日・13日の2日間にかけて国際日本学拠点のコア・パートナーであるコロンビア大学との共催で、公開セミナー「Future Directions in Japanese Studies: Environment, Culture, and Society 日本研究の新たな可能性:環境・文化・社会」と大学院生を参加者とするワークショップを実施した。なお本イベントは、早稲田大学高等研究所「人新世と人文学」セミナーシリーズと総合人文科学研究センター「環境人文学」セミナーシリーズと共同開催した。
- ハルオ・シラネ教授(コロンビア大学)
- 大西 健夫教授(岐阜大学)
国際日本学拠点では、これまでにもコロンビア大学とのパートナーシップを通じて、その時々の学術的動向を見据えた研究・教育プログラムを実施してきた。今回はスーパーグローバル大学創成支援事業の最終年度にあたり、将来の日本学研究において重要なテーマとなることが見込まれる「環境」というテーマを軸に、文化、社会と広い射程で、大学院生の研究に広がりをもたらすことを意図したセミナーとワークショップを企画した。
初日に、環境人文学研究の第一人者であるシラネ・ハルオ教授、また地球環境学を水と土の循環の観点から研究しておられる大西健夫教授の両氏に、人文科学および自然科学それぞれの分野からの基調講演をしていただいた。両氏の講演を通じて、水と土という我々の生存環境の基盤を形成する物質が、一方の文学、文化、芸術といった人間の文化的営みといかなる相互作用を形成してきたかについて考える端緒が開かれた。

左から鈴木 登美教授 (コロンビア大学)
角田 拓也助教授 (コロンビア大学)
その後のラウンドテーブルでは、コロンビア大学の鈴木登美教授と角田拓也助教授より各々の専門である近代文学とメディアスタディーズの観点からのコメントが寄せられると同時に、コロンビア大学と本校の大学院生3名、入倉 友紀(近代日本映画論)、山吉 頌平(宗教文学)、ペナー ダニエル(日本近代文学)が登壇し、各々の研究分野からのコメントや質問を投げかけた。大隈記念小講堂を用いて対面とオンラインのハイブリッド形式で実施し、会場からも多くの質問やコメントが寄せられた。
2日目に実施した大学院生ワークショップは、博士後期課程の大学院生が各自の研究の独自性や今後の方向性について発表を行い、それに対して両校教員がコメントすることにより、院生の研究を推進するのみならず、院生と教員全体のディスカッションを展開した。特に、大学院生世代の領域横断的な論点や分析方法の広がりが顕著であり、文字通りこれからの日本文学・文化研究のあり方を探る機会となった。
1月12日Zoom録画はこちらからご覧ください。
1月13日概要集はこちら
イベント概要
- 日時:講演会:2024年1月12日(金)10:00-13:00 (JST)、
ワークショップ1月13日⁽土)9:00-17:50 - 参加:学生、教員、一般
- 使用言語:英語・日本語
- 開催方式:対面/オンラインのハイブリッド開催 (1月13日は対面のみ)
- 主催:スーパーグローバル大学創成支援事業 早稲田大学国際日本学拠点/総合人文科学研究センター角田柳作記念国際日本学研究所/早稲田大学高等研究所