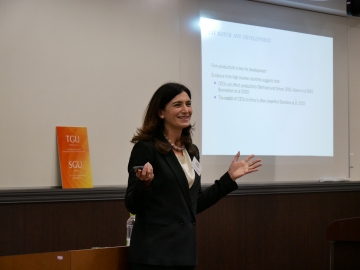早稲田大学スーパーグローバル大学創成支援事業 実証政治経済学拠点、組織経済実証研究所では、経済産業研究所共催のもと、ハーバードビジネススクールのRaffaela Sadun教授を基調講演者としてお招きし、2023年11月22日早稲田大学日本橋キャンパスにて国際カンファレンスを実施しました。総勢37名(うち大学院生14名)の参加者が集い、経営者や経営チームをテーマとした実証研究の報告と活発な議論がなされました。

全体風景
参加レポートをいただきましたので、ご紹介いたします。
高橋孝平(早稲田大学政治経済学術院助手および大学院経済学研究科博士課程)/ 大湾秀雄(早稲田大学政治経済学術院教授)
本コンファレンス内では、まず日本側の研究者4名による研究報告があった。Kongphop Wongkaew氏(早稲田大学)は、“CEO age, firm exit, and zombification amidst the COVID-19 pandemic”というタイトルで、コロナ禍によって企業のゾンビ化(実質的に経営が破綻しかけているのにもかかわらず金融支援等により生き永らえている状態)、企業退出、CEO交代が増えたか、という研究を報告した。ゾンビ企業は増加したが、コロナ禍の影響はCEOの年齢に依存しており、若いCEOが経営する企業では長期負債が増え、年配のCEOが経営する企業では退出やCEOの交代が加速したことを実証した。都市部と地方の違いに大きな関心が寄せられた。
次に報告を行った山野井順一准教授(早稲田大学)は、“Heterogeneity of Risk and Time Preferences among Founders, Successors, and Non-CEOs ”というタイトルで、創業者は、経営継承者や従業員と比べて時間選好やリスク選好がどう違うか、それらの特性は企業行動をどの程度説明できるかについて報告を行った。約1800人のCEOと約500人のCEO以外の個人を対象とするサーベイに基づく分析によって、創業者CEOは事業を継承したCEOや一般従業員と比べて、リスクに対する耐性が強く、かつ時間割引率が高いが、それだけでは創業者と経営継承者との違いは説明できないことも明らかにした。有限混合モデルを使った手法に高い関心が寄せられた。
3番目に報告した明日山陽子氏(JETRO)は、中間管理職のスキルの違いが部下の業績と定着や自身の処遇に与える影響について、企業内人事データを使用した研究結果を報告した。ラインマネジャーとしての業績で昇進が決まる昇進制度とシニアマネジャーに必要なコンピテンシー評価で決まる昇進制度の優劣の条件を明らかにすることで、ピーターの法則(人は無能になるまで昇進する:業績ベースの昇進による非効率な業務配置)はある条件の下で避けることが出来ることを、実際の実例を持って示した。因果関係を証明する手法の改善等について活発な議論があった。
4番目に報告に立った久保克行教授(早稲田大学)からは、CEOのマネジメントスキルが企業業績に与える影響を検証した結果が報告された。東証一部上場企業のプロフィール情報から就任前の経営経験を測り、他企業や子会社でのマネジメント経験を持たないCEOから持つCEOへの変化が企業業績に正の影響を与えることを示した。にもかかわらず、就任前に子会社等での経営経験を持たないCEOが6割超もおり改善傾向が見られないことは驚きをもって受け止められた。
Sadun教授はいずれの報告においても積極的にフィードバックを返し、特に前提となる知識の確認や今後の分析に関する提案も数多く、報告者だけではなくオーディエンスの内容理解にも深くつながった。

Sadun先生から報告者への発言
最後のSadun教授による基調講演では、企業特性とCEOの行動タイプの適合度合いが生産性に与える影響について、42か国4,500製造業企業から収集したCEOの時間の使い方に関するデータを用いた分析結果が紹介された。
Sadun教授自身の先行研究(Bandiera, Prat, Hansen, and Sadun 2020)に基づく手法に関心が集まった。まずCEOをタスク管理を重視する「マネージャータイプ」と、組織的な方向性を作り出す「リーダータイプ」に分類する。次に先行研究で用いたデータを中心に先進7か国の訓練データを用いてどういう特性の企業でリーダータイプのCEOが着任しているか予測モデルを構築する。続いて予測モデルを用いてリーダータイプ(マネジャータイプ)を必要とする企業に実際にリーダータイプ(マネジャータイプ)のCEOが就任しているかを確認することで、CEOと企業のマッチング度合を把握している。その結果、CEOタイプと企業のミスマッチがその国のGDPに負に相関していることが明らかになった。本研究はリーダータイプ、マネージャータイプのどちらが良いかという議論ではなく、企業とのミスマッチに焦点が当てられているところが興味深い。生産性改善のためには、企業の事業特性の理解とそれとマッチした人材を獲得できるガバナンスが重要であることを理解することができた。
- Sadun先生ご講演
- 質疑応答
本コンファレンスでは経営者や経営チームについて研究されている研究者が一堂に会することで知的交流を図る有意義なものであった。また、大学院生にとっても第一線の研究者の最新の研究・潮流を肌で感じることができる貴重な機会となった。
- 講演者全員
- Sadun先生