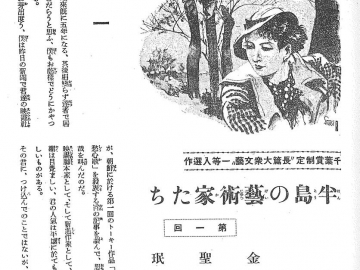国際日本学拠点では、2022年7月21日に訪問教員Dr. Christina Yi (University of British Columbia)の講演会”Intersecting Diasporic Literatures: On Jini’s Puzzle and Pachinko”を開催しました。
 イ氏の講演は、崔実『ジニのパズル』(2016年)、ミン・ジン・リー『パチンコ』(2017年)の翻訳やテレビドラマ化を取り上げ、さらに普段個々に語られる「ディアスポラの物語」の交錯に焦点を当てることで、そこから浮かび上がってくる世界的な力関係を問い直すことを目的としました。
イ氏の講演は、崔実『ジニのパズル』(2016年)、ミン・ジン・リー『パチンコ』(2017年)の翻訳やテレビドラマ化を取り上げ、さらに普段個々に語られる「ディアスポラの物語」の交錯に焦点を当てることで、そこから浮かび上がってくる世界的な力関係を問い直すことを目的としました。
まず、イ氏は英語では単純な地名・国籍として捉えられる「Korea」又は「Korean」という単語を日本語に訳す時、独特な意味合いがある選択肢から、選ばなければならないということを指摘しました。
日本語には植民地時代に使われた「朝鮮」と、戦後から普及した「韓国」、「北朝鮮」の違いがあり、また、「朝鮮人」・「韓国人」・「朝鮮籍」・「コリアン」はそれぞれ異なる意味を持ちます。その違いは、単なる翻訳の選択肢の問題だけではなく、日米両国で公的記憶から排除された(日米)帝国主義と冷戦政治の歴史を翻訳することをも意味するのです。
 『ジニのパズル』では、北朝鮮は主人公にとって、アメリカで自己発見の旅を展開するために拒絶しなければならない不可知の場所として描かれます。その一方で、アメリカは具体的な意味を持ち、特に「ハワイ」という空間は特別な役割を果たしています。主人公にとってハワイにいた時に最もつらかったのは、現地の人からは観光客扱いされ、観光客からは地元の人として扱われることでした。一方、オレゴン州では主人公の人種は全く問題にされません。逆説的に見えるかもしれませんが、それはハワイにおける人種関係が、アメリカ型多文化主義の土台になる自然化された「白人性」の存在を明らかにするからだ、とイ氏は説明しました。
『ジニのパズル』では、北朝鮮は主人公にとって、アメリカで自己発見の旅を展開するために拒絶しなければならない不可知の場所として描かれます。その一方で、アメリカは具体的な意味を持ち、特に「ハワイ」という空間は特別な役割を果たしています。主人公にとってハワイにいた時に最もつらかったのは、現地の人からは観光客扱いされ、観光客からは地元の人として扱われることでした。一方、オレゴン州では主人公の人種は全く問題にされません。逆説的に見えるかもしれませんが、それはハワイにおける人種関係が、アメリカ型多文化主義の土台になる自然化された「白人性」の存在を明らかにするからだ、とイ氏は説明しました。
『パチンコ』も、アメリカでは優れた「移民文学」として評価されました。しかしイ氏は、その捉え方は小説の内容を実際に植民地化された国の人々の歴史的経験から切り離された物語として評価されていることを示しました。その上で、イ氏は、これらの指摘は「Misreading/間違った捉え方」を批判するのではなく、「西洋」を「普遍的なメッセージ」にし、「非西洋」を「限定されたメッセージ」にする構造的状況を考え直すためのものだと主張しました。誰の経験が「透明」・「翻訳可能」と思われ、誰の経験が「不透明」・「翻訳不可能」と思われるかという問題は、いつも「不平等な力関係の上で行われ」、歴史的状況に強く影響されたプロセスとなるからです。


学部生、大学院生、一般の方を合わせ34名が参加する、非常に有益な講演会となりました。講演のあと質疑応答が設けられ、予定時間をオーバーするほどの活発な討論が行われました。
開催詳細
- 日時:2022年7月21日(木曜日)16:30 – 18:00 (JST)
- 会場:早稲田大学戸山キャンパス36号館581教室
- 講師: Dr. Christina Yi (早稲田大学訪問准教授、Associate Professor, University of British Columbia)
- 使用言語:英語(通訳なし)
- 参加:学生/教員/一般
- 参加費:無料