しっかりと思考すれば自ずとしっかりした文章が書けるはずだ、と私たちは考えがちです。だから、まずは思考を練ってそれから考えたことを言葉で表現しよう、と思うものです。しかし、逆の見方があります。しっかりと言葉を使う人は、しっかりと思考することができるという見方です。私たちは言葉を使って思考をするので、言葉を使いこなせる範囲内でしか思考をすることができないのです。
「学術的文章の作成」授業は、この見方を前提としています。言葉の使い方を鍛えることによって、思考そのものが鍛えられるのです。しっかりした文章を書いて、はじめて緻密な思考をしたことになるのです。したがって、この授業で文章作成の技術を学ぶことにより、レポートや論文は、「書き方」がよくなるばかりでなく「内容」そのものもよくなるはずです。
学術的な文章は、意味を最も厳密に伝えようとする種類の文章です。学術的な文章に盛り込まれる内容は、抽象的であったり複雑であったりします。多くの人の声も盛り込まれます。そのような内容を、書き手は意図した通りに読み手に伝えようとします。
ですから、学術的な文章を書く力がついた人は、社会に出た後で、どのような機能的な文章も容易く書けるようになるはずです。学術的な文章の作成に必要とされる技能は、社会で使われるすべての機能的な文章の基礎となります。
この授業は、オンデマンド方式です。eラーニングプラットフォームシステム「Waseda Moodle」を使って配信されます。履修者は、家庭やキャンパスのパソコンから授業を視聴します。「Waseda Moodle」での視聴は24時間可能です。本授業は、全7回7週間で、1週ごとに新しい回が視聴できます。1回分の授業は約60分間です。いったん配信された授業は、授業期間内であれば繰り返し視聴することができます。
毎回、400字から600字の文章を書く宿題が課されます。この課題文章は、コメントと評価点がつけられて一人ひとりの履修者に返送されます。コメントと評価点をつけるのは、専門的な訓練を受け、さらに厳しい審査に合格した指導員です。指導員は、学内の修士課程、博士課程に在籍する大学院生です。
[第1回]文を整える
[第2回]課題作成の留意点(剽窃を防ぐ)、語句を明確に使う
[第3回]全体を構成する
[第4回]論点を整理する
[第5回]参考文献を示す
[第6回]引用をする1
[第7回]引用をする2
「学術的文章の作成」は、全7回のフル・オンデマンド型の授業です。毎週一つの技術を取り上げ、その週に学んだ技術を使って400字から600字の文章を書くことが課題として出されます。提出した課題文章には、各クラス担当の指導員からの個別にフィードバック(コメントと評価)がされます。
| Step01.講義コンテンツの視聴 |
|---|
| 自宅や学内のパソコンを通して、「学術的文章の作成」を視聴します。
チェック! |
| ↓ |
| Step02.「今週の課題」 |
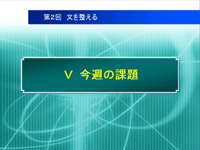 講義コンテンツの最後に課題(400字~600字)が出されます。 講義コンテンツの最後に課題(400字~600字)が出されます。 |
| ↓ |
| Step03.「課題の作成」 |
| 課題は、Microsoft Wordで作成します。詳しくは、「パソコン環境」を確認してください。 |
| ↓ |
| Step04.「課題の送信」 |
| Waseda Moodleを通じて、クラスを担当する指導員に課題を送信します。 |
| ↓ |
| Step05.「課題を受信した指導員が採点」 |
| 指導員は、課題が届くと、採点し、コメントをつけてくれます。また、よく書けている文章は、「模範文章例」として選ばれ、名前等を伏せて各クラスで公開されます。 |
| ↓ |
| Step06.「フィードバックの受信」 |
| 課題の提出締め切り日から六日以内に、指導員からのコメントが入った文章が届きます。指導員からのフィードバックは毎週確認し、次からの課題文章に活かしていきましょう。 |
「学術的文章の作成」は、春クォーター、夏クォーター、秋クォーター、冬クォーターの年4回開講されています。
科目登録期間、登録方法は、グローバル・エデュケーション・センターホームページで確認してください。
毎回の授業後に課題を出します。提出された課題の合計点で評価をします。
オンデマンド授業「学術的文章の作成」を受講するためには、「Waseda Moodle」の動作が検証されているブラウザを使用する必要があります。
※以下のURLから検証済環境を御確認下さい。
https://www.waseda.jp/navi/services/system/sys_requirements.html#section1-8
レポート課題の提出画面に、専用のフォームを用意していますので、必ずこれをダウンロードして文章を作成、提出してください。
下記URLより、ダウンロードしてください。
オンデマンドコンテンツが視聴できない、Wordファイルでの課題の提出がうまく出来ないなど、Waseda MoodleやPCの使い方に関する質問があるときには、下記の「Waseda Moodle利用マニュアル」を参照してください。そのうえで、解決できない場合にはITセンターヘルプデスクや早稲田ポータルオフィスに問い合わせをしてください。