- ニュース
- 【開催報告】2024年度第1回スタディセミナー「国際刑事司法の30年:冷戦後の制度的発展と残された課題」が開催されました
【開催報告】2024年度第1回スタディセミナー「国際刑事司法の30年:冷戦後の制度的発展と残された課題」が開催されました

Dates
カレンダーに追加0711
THU 2024- Place
- オンライン
- Time
- 17:00-18:30
- Posted
- Wed, 17 Jul 2024
比研スタディセミナー「国際刑事司法の30年:冷戦後の制度的発展と残された課題」
主 催:早稲田大学比較法研究所
日 時:2024年7月11日(木)17:00-18:30
場 所:オンライン(Zoom)
講 師:小阪真也(比較法研究所助教)
参加者:15名(うち学生7名)
2024年7月11日(木)、2024年度第1回スタディセミナーが開催されました。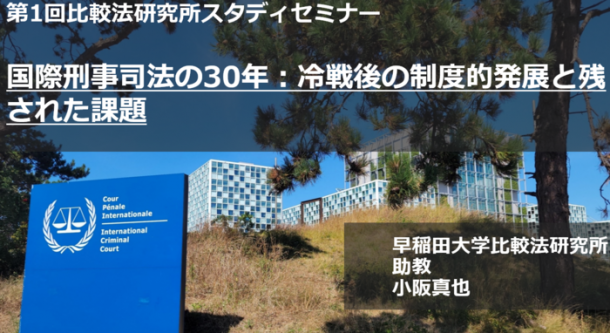 今回のテーマは「国際刑事司法の30年:冷戦後の制度的発展と残された課題」でした。講師は早稲田大学比較法研究所の小阪真也助教が務め、司会は早稲田大学法学学術院の大橋麻也教授が務めました。
今回のテーマは「国際刑事司法の30年:冷戦後の制度的発展と残された課題」でした。講師は早稲田大学比較法研究所の小阪真也助教が務め、司会は早稲田大学法学学術院の大橋麻也教授が務めました。
報告ではまず、冷戦後の国際刑事司法の発展について、法と組織に焦点を当てて説明を行いました。法に関しては1993年の旧ユーゴスラヴィア国際刑事法廷(ICTY)の設立を皮切りに世界各地で設立されてきた国際刑事法廷における適用法規において、国際刑事法上の重大犯罪とされるジェノサイドなどの中核犯罪を裁くための法整備が類似した形で行われたことが指摘されました。また、国内においては日本のように国際刑事裁判所(ICC)と協力するための法を制定する国々や、カナダやアルゼンチンのように特別法を設置して中核犯罪を訴追する体制を整える国々などの類型について説明が行われ、アルゼンチンの例を挙げて国内での中核犯罪訴追の実例が紹介されました。
また、組織の発展経緯に関して、1993年に活動を開始したICTY以降、世界各国に国際刑事法廷が設立されていく経緯が説明されました。報告では特にICC規程が2002年に発効して以降、2024年現在までの予算や人員規模などを含めた組織の発展経緯が説明されるとともに、ICTYやルワンダ国際刑事法廷(ICTR)などの閉廷した法廷における「遺産」の形成に向けた近年の取り組みも説明されました。
次に過去30年間で国際刑事司法において果たされなかった課題として、在任中の行政府の長の国際刑事法廷における有罪判決が挙げられ、ICTYからICCに至るまで、大統領や首相に該当する人物の在任中に逮捕状は発行されつつも、実際に審理を受けて有罪判決が出されている事例は、該当する人物が退任し政治的な権力を失った後であることが散見されると述べられました。本課題は2023年のロシア大統領ならびに2024年のイスラエル首相などに対するICCによる訴追においても課題となるものであり、報告ではその要因として、特にICCに関してはICC規程第1条に定められた「補完性の原則」の理念に基づき常に各国の刑事管轄権に優越し司法介入を徹底する形で組織が形成されているわけではないことや、ICC規程第87条の協力を締約国に求める制度が必ずしも実効的に機能していないことなどが指摘されました。
報告の最後部では国際刑事司法に関する研究方法についても紹介され、各国際刑事法廷の法規・判例を探すための方法や、法廷の活動地において現地調査を行うための方法などについて説明が行われました。その後の質疑応答では、ジェノサイド条約などの国際条約と各国際刑事法廷の適用法規の関係、冷戦後に世界各地に国際刑事法廷が設立されたことの意義、国際刑事裁判所の審理プロセスなどが議題として挙げられ、議論が行われました。
(文:小阪真也・比較法研究所助教)

