- ニュース
- 【開催報告】2023年度第2回スタディセミナー「著作権集中管理制度の比較法的検討―近時の発展方向を焦点に―」が開催されました
【開催報告】2023年度第2回スタディセミナー「著作権集中管理制度の比較法的検討―近時の発展方向を焦点に―」が開催されました

Dates
カレンダーに追加1214
THU 2023- Posted
- Wed, 13 Mar 2024
2023年度第2回 比較法研究所スタディセミナー
「著作権集中管理制度の比較法的検討―近時の発展方向を焦点に―」
日 時 2023年12月14日(木)
17時00分~18時30分(Zoomによる開催)
主 催 早稲田大学比較法研究所
講 師:譚天陽(早稲田大学比較法研究所助教)
コメンテーター:森綾香(早稲田大学法学部助手)
参加者:27人(うち学生15名程度)
2023年12月14日(木)、2023年度第2回スタディセミナーが開催されました。今回のテーマは「著作権集中管理制度の比較法的検討―近時の発展方向を焦点に―」でした。講師は早稲田大学比較法研究所の譚天陽助教が務め、コメンテーターは早稲田大学法学部の森綾香助手が務めました。司会は早稲田大学法学学術院の大橋麻也教授が務めました。
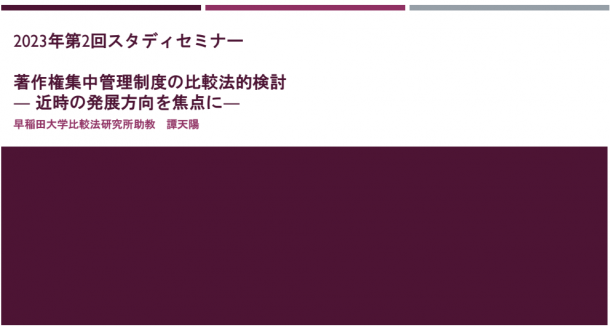
冒頭では、司会の大橋教授が講師とコメンテーターの経歴を簡単に紹介しました。報告の最初において、譚助教はまず、著作物の利用をめぐる現状と問題点を説明し、デジタル時代における様々な場面で生じ得る問題を説明しました。その後、報告のテーマとなる著作権集中管理制度の定義とその役割について紹介し、拡大集中許諾という制度が北欧発祥の一種特殊な著作権集中管理であり、それがデジタル時代における著作物の利用問題を一定程度解決できる可能性があると説明しました。
次に、譚助教は、著作権集中管理制度の起源、すなわち、1850年頃にフランスで誕生し、後に世界各国に普遍してきたこと、それから著作権集中管理制度の発展、主に日本と中国での設立経緯、また、著作権集中管理制度の現状を紹介しました。特に、中国では、著作権集中管理団体が初めて設立されたのは1990年頃であり、これは、中国の現行著作権法が制定・公布された時期と重なると指摘しました。
そして、譚助教は拡大集中許諾の起源について説明した後、それがEUないし主要加盟国ではどのように扱われているのかについて、2019年デジタル単一市場指令の前と後という2つの時期に分けて紹介しました。その後、アジアの日本と中国では、拡大集中許諾がどのように議論されているかについて説明しました。特に中国では、2011年頃から始まった第三回著作権法改正の作業において、日本よりも本格的に拡大集中許諾を法制度の一部として取り入れようとする動きがみられましたが、学界、実務界及び権利者の間では導入に対して賛否両論があったとの指摘がなされました。
報告の最後では、譚助教が拡大集中許諾がもたらす様々なリスクを説明し、同制度の導入が必ずしも著作物の利用問題を解決できる良い手段とは限らないと指摘した上、著作権集中管理制度のあり方について検討しました。そして、大学院生及び留学生向けに、大学院での学習・研究の方法について、自分の経験を踏まえて説明しました。
報告終了後、コメンテーターの森助手は、譚助教の報告をまとめた上、拡大集中許諾の問題点についてコメントをしました。特に、拡大集中許諾の位置づけ、権利制限規定との関係性、契約相対効原則との摩擦と解決策、それから同制度が仮に導入されてもなお問題点が残ると指摘しました。
質疑応答の段階では、研究者及び大学院生から、拡大集中許諾の法的根拠、独占禁止法関連の注意点、そして論文の執筆にあたる心得などが話題となりました。活発な議論の後、セミナーは和やかな雰囲気で終わりました。

