- ニュース
- 【開催報告】公開講演会「中国農地制度の三次元的検証」が開催されました
【開催報告】公開講演会「中国農地制度の三次元的検証」が開催されました
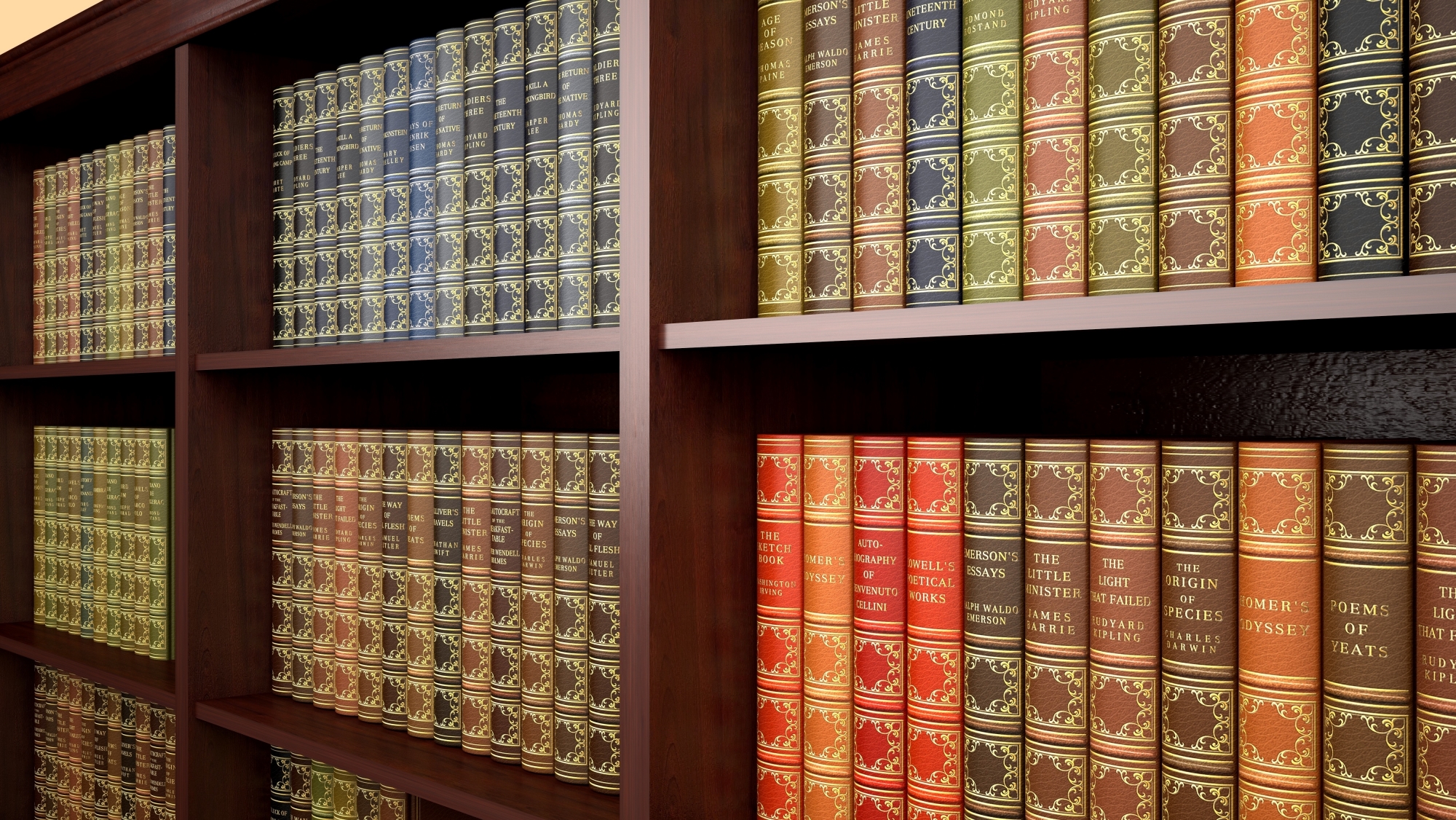
Dates
カレンダーに追加1017
TUE 2023- Posted
- Mon, 04 Dec 2023
公開講演会「中国農地制度の三次元的検証」
主 催:早稲田大学比較法研究所
共 催:早稲田大学法学部
日 時:2023年10月17日(火)17:00~19:00
場 所:早稲田大学26号館B104 多目的講義室
言 語:中国語(通訳あり)
講演者:倫海波 中国燕山大学文法学院副教授
通訳:文元春(早稲田大学法学学術院教授、比較法研究所研究所員)
世話人:楜澤能生(早稲田大学法学学術院教授、比較法研究所研究所員)
参加者:16人(うち学生8人)
2023年10月17日(火)に早稲田大学で公開講演会「中国農地制度の三次元的検証」が開催された。本講演において、倫海波氏(中国燕山大学文法学院副教授)は、中国の農地制度について、3つの観点から論じた。本講演の元となる研究内容は、楜澤能生氏(早稲田大学法学学術院教授)、文元春氏(早稲田大学法学学術院教授)および倫海波氏の共同研究によるものである。

倫海波氏の講演に先立ち、講演会世話人である楜澤能生氏から、中国農地制度を3つの次元から検証するという言葉の意味につき、財産権としての農地、生産要素としての農地および地域資源としての農地という3つの観点から中国の農地制度を論じるという意味であるとの説明があった。
倫海波氏は、以上の3つの観点から、中国における農地制度を以下の通り説明した。まず、財産権としての農地について、中国現行の農地制度は、土地所有権、土地請負経営権および土地経営権という「三権分置」を基にして構築されており、伝統的な民法における「所有権―物権―債権」という構造とほぼ同じであるが、中国の農地制度が土地請負経営権を中心としているところは、多くの国が所有権を中心としているところとは異なっていると指摘する。
続いて、倫海波氏は家族請負を中心として説明を展開した。中国の農地所有権には、国家所有と農民集団所有の2種類があり、所有権の運用面ではそれぞれ、国務院(中央人民政府)、各集団経済組織または村民委員会・村民小組による「代表制」を採用している。また、農民集団所有から国家所有へと変更される場合は、「譲渡」とはいえず、実際には公法上の収用制度の範疇にある。。この点について、本来であれば、農民集団の分割と合併は、私法上の土地所有権の変動を中心とする方式によって行わなければならないが、実際上、公法的な形式が採られ、農地所有権の変動は公権力運用の必然的な結果となっていると指摘する。

次に、生産要素としての農地について、倫海波氏は、地力の向上と零細化問題の解決、農地仲介プラットフォームの確立、資金調達の円滑化および遊休農地問題という4つの点から論じた。例えば、地力を向上するには、公法上の土地改良助成メカニズムを強化する必要があるとし、零細化問題の解決については、既存の権利構造を尊重することを前提に、土地請負経営権者の同意を通じて、権利者間の土地利用関係を調整することが必要であると指摘する。また、農地仲介プラットフォームについては、農村土地経営権移転サービスセンターなどの設立が提唱された。
そして、地域資源としての農地について、倫海波氏は、これは、個々の農民が協力する必要性および歴史的に発展してきた地域差に由来するものであると述べる。集団土地の運用モデルは、「家族請負経営を基礎とし、統一と分散を結合させた二重の経営体制」と概括されるが、長年の慣行は「分散」を中心として行われ、「統一」の側面は意識的または無意識的に無視されてきた。この「統一」を実現する方法には、①所有権を出発点として、所有権を代表して行使する集団経済組織や村民委員会が主導するもの、➁土地請負経営権を出発点として、土地請負経営権者が「協同の合意」に基づいて推進するもの、③公権力を出発点として、公的介入を強化するもの、の3つがあるとする。

最後に、倫海波氏は、次のように結論を述べた。まず、財産権としての農地について言えば、農地の三権分置は、所有権―物権―債権という法的論理を合理化したが、権利の内容に実質的な変化はない。所有権を希薄化し、請負権を安定化させ、経営権を移転するという道は、中国の現実に即したものであり、今後の農地制度の改善の基本方向となるべきものである。また、生産要素としての農地については、農地の移転に基づく農地の利用効率の発揮に注意を払うべきである。そして、地域資源としての農地については、土地請負経営権を出発点として、公権力に支えられた権利者間の協力の合意を通じて、「統一」の構築を促進すべきである。
(文:譚天陽・比較法研究所助教)

