- ニュース
- 【開催報告】2023年度第1回スタディセミナー「生殖補助医療およびヒト胚研究に対する法規制のあり方 -日英の比較から-」が開催されました
【開催報告】2023年度第1回スタディセミナー「生殖補助医療およびヒト胚研究に対する法規制のあり方 -日英の比較から-」が開催されました
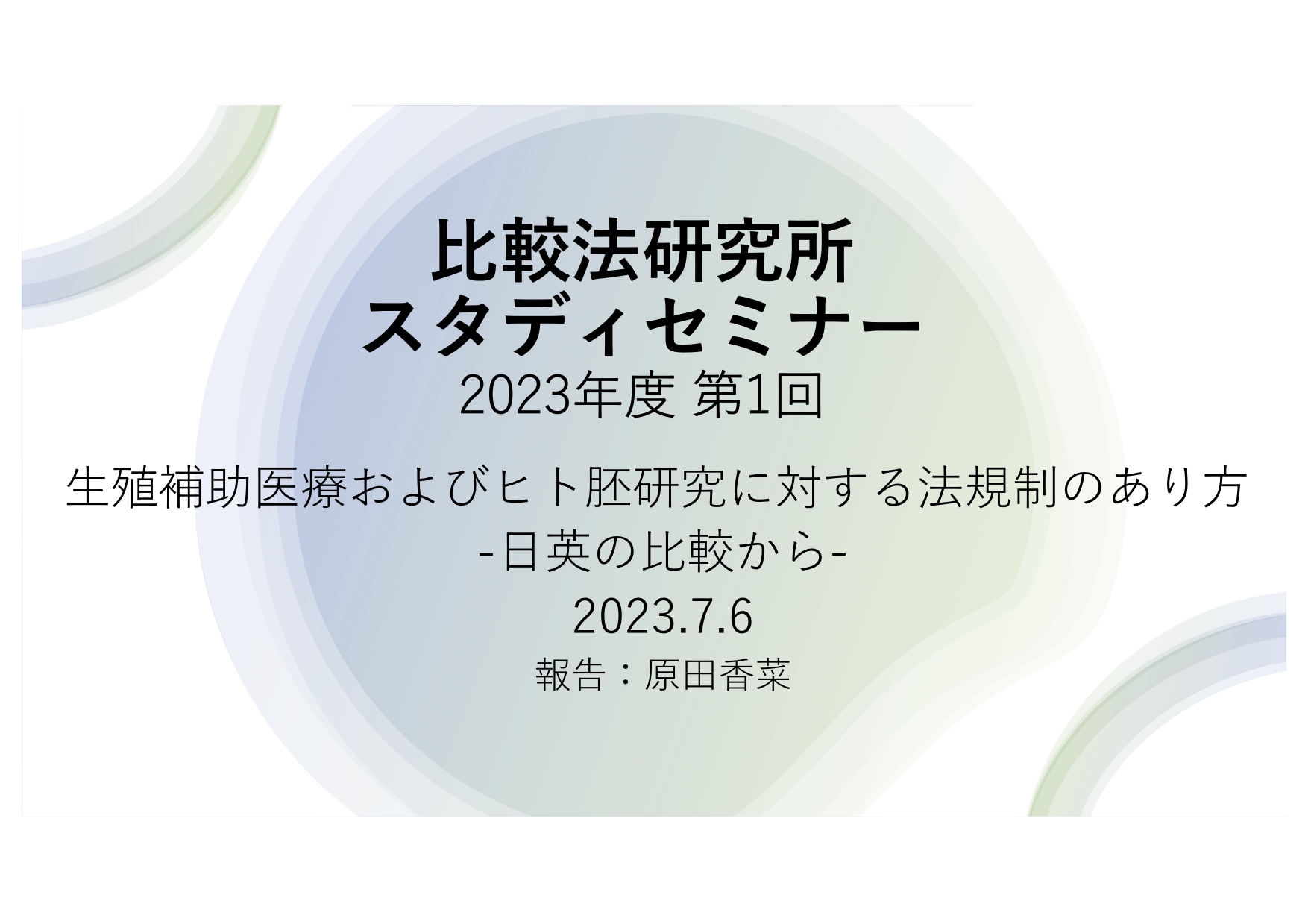
Dates
カレンダーに追加0706
THU 2023- Place
- オンライン
- Time
- 17:00-18:30
- Posted
- Mon, 09 Oct 2023
比研スタディセミナー「生殖補助医療およびヒト胚研究に対する法規制のあり方 -日英の比較から-」
主 催:早稲田大学比較法研究所
日 時:2023年7月6日(木)17:00-18:30
場 所:オンライン(Zoom)
講 師:原田香菜(法学学術院講師)
参加者:54名(うち学生47名)
2023年7月6日、2023年度第1回比研スタディセミナーを開催しました。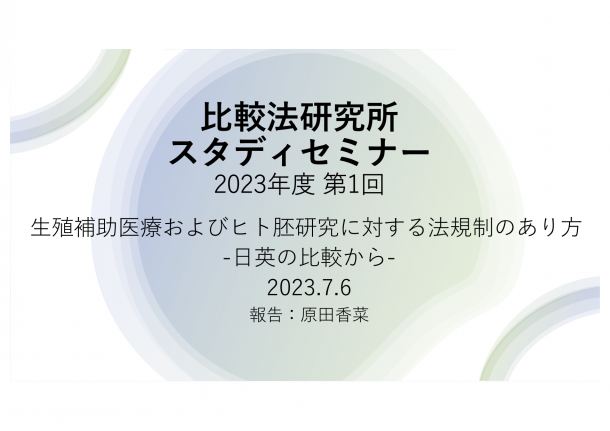 講師は、民事法学・家族法学・医事法を専門に研究している本学法学学術院講師・原田香菜先生が務め、特に高度生殖補助医療およびヒト胚研究に関する法規制のありようについてご講義いただきました。
講師は、民事法学・家族法学・医事法を専門に研究している本学法学学術院講師・原田香菜先生が務め、特に高度生殖補助医療およびヒト胚研究に関する法規制のありようについてご講義いただきました。
日本でも生殖補助医療の利用は年々増加しており、2020年には14人に1人の新生児が体外受精により、そのうち9割以上が凍結融解胚移植(FET)を経て出生しています。こうした増加に伴って、生殖補助医療を受けることに同意した時点から長期間経た後に胚移植が行われる場合にかつての同意はどのように扱われるべきか、また医療機関が胚・配偶子を保管している間に起きた問題や紛争をどのように解決すべきかについて、判断の拠り所となる法制度が一層必要とされている状況にあると、原田講師は述べました。
また、ヒト胚研究に用いられる研究試料の提供元は、生殖補助医療目的で作成されたヒト胚です。ここでも、同意を含めた提供側の視点が尊重される必要があることに加え、同意取得のありようについて、法的拠り所を確立する必要があります。
ところが日本では、ヒト胚研究の規制については、対象となる胚の種類および研究目的ごとに複数の指針が並立している状況にあり、また、生殖補助医療の実施については日産婦による会告・「見解」が指標とされ、法的行為規範は存在していません。そこで原田講師は、生殖補助医療とヒト胚研究を横断する制定法を持つ英国の様子や、ヒト胚の取扱いに関する国際的な動向を見ることで、日本への示唆を引き出そうと考えられました。
英国では、Human Fertilization and Embryology Act 1990, 2008という一連の法律によって、研究や生殖補助医療において用いられるヒト胚・配偶子の取扱いが一体的に定義・規制されています。上の法は、ヒト胚を用いる研究と生殖補助医療の実施についてライセンス認可制度を樹立するものであり、その制度運用のためにヒト受精・胚研究認可庁の設置を要請するものです。この庁は、不妊治療やその実施医療機関、配偶子・胚提供について無償かつ明確、公平な情報を提供する役割も担っており、英国の認可を受けた医療機関で行われる全ての治療に関するデータを収集・検証しています。
日本においては、2006年に最高裁が、夫の死後に夫の精子を用いた体外受精により子を懐胎・出生した場合の死後認知の問題について扱っており、この問題は立法的解決を必要とするという姿勢を示したものの、いまだに立法の整備はなされていません。また医療機関による凍結胚の紛失や毀損をめぐる裁判上の紛争も起きています。原田講師は、英国では既に類似の問題について扱った判例が出ており、HFE法改正を含めた立法での解決も積み重ねられていると指摘されました。この上で、日本においても、ヒト胚・配偶子の法的位置づけと保護のありようを立法において明確化すべきときはとうに来ており、またそのためにヒト胚・配偶子を用いる研究と生殖補助医療の実施を規律する公的機関の設置が必要とされていると議論されました。
講義後の質疑応答においては、ヒト胚研究や生殖補助医療の実施の規制を職能団体に委ねることの限界や、「自然生殖」とそうでない生殖との境界線はどこに引かれるのかといった問題について、議論がなされました。
(文:松田和樹・比較法研究所助手)

